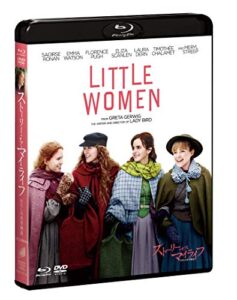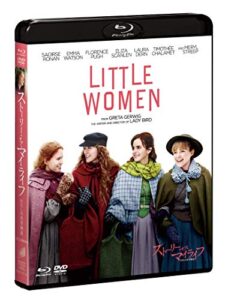「セカイ系」とは何なのか、たとえば「SF小説」とはどう違っているのか?
その問いから始めて、『エヴァ』や『ガンダム』から『攻殻機動隊』、あるいは『進撃の巨人』といった傑作アニメに共通する「ワールドビルディング」という方法論を見ていきたい。
- 【「セカイ系」は「SF」の一種なのか?】
- 【セカイ系と「SF的リアリティ」の欠落。】
- 【SF小説は「ミクロ」が弱い。】
- 【ここが違う! 「SF小説」と「セカイ系」の落差。】
- 【ライトノベルも文学も。】
- 【「キャラ」と「キャラクター」の両立。】
- 【ライトノベルは「キャラ」中心。】
- 【『天冥の標』のキャラクター描写。】
- 【「世界の秘密」を探る物語が流行する?】
- 【物語への興味が「個人の内面」から「世界の秘密」へ移っている?】
- 【『ガンダム』の魅力は「世界」にあり。】
- 【「小世界」と「大世界」は補い合う。】
- 【「世界」とは「生きたひとりのキャラクター」。】
- 【「ワールドビルディング」という方法論。】
- 【オタク第一世代の方法論。】
- 【ただの「パッチワーク」ではない。】
- 【「世界」とはその作家の「魂の風景」である。】
- 【映画『ドラゴンクエスト』はなぜ酷評されたか。】
- 【お願い】
- 【電子書籍などの情報】
- 【おまけ】
【「セカイ系」は「SF」の一種なのか?】
どうにも検索しても出典が見あたらないのだが、東浩紀から「セカイ系」の定義、「主人公(ぼく)とヒロイン(きみ)を中心とした小さな関係性(「きみとぼく」)の問題が、具体的な中間項を挟むことなく、「世界の危機」「この世の終わり」などといった抽象的な大問題に直結する作品群のこと」を聞いた大森望が、「それならSFはみんなあてはまるじゃん!」みたいなことを話した、という記述をどこかで読んだことがある。
一読してなるほど、と苦笑してしまうような話である。たしかにそうかもしれない。
SF小説の名作とされるものは、むろん例外はいくらでもあるにせよ、『2001年宇宙の旅』であれ、『ディアスポラ』であれ、『果しなき流れの果に』であれ、『グラン・ヴァカンス』であれ、ここでいう「具体的な中間項」の描写にページを割かない。一気に宇宙の果てまで跳躍する。その良し悪しはともかく、SFにはたしかにそういうところがある。
ちなみに、Wikipediaによると、「具体的な中間項」とは、「国家や国際機関、社会やそれに関わる人々」を指している。つまり、東の定義によれば、セカイ系とは「小さく個人的な関係が、一気に世界的な大問題に直結する作品」を指していることになる。
大森による(らしい)指摘は、それはべつだんセカイ系とされている作品の専売特許でもないだろう、ということだろう。
しかし、どうだろうか。広くセカイ系の代表作と見られる作品、『ほしのこえ』や『最終兵器彼女』などを見ていると、やはり従来のSFとはどこか違っているようにも感じられる。具体的にどこがどう違うのか、少し考えてみよう。
【セカイ系と「SF的リアリティ」の欠落。】
まず、思いつくのはセカイ系作品のSF的な意味でのリアリティの欠如である。ぼくはよく庵野秀明監督の『トップをねらえ!』と新海誠監督の『ほしのこえ』を比較して考えるのだが、前者にはたしかにあった「SF的にリアリティを増進させようとする態度」が後者には決定的に欠けていると感じる。
もちろん、前者も後者も、あらゆる意味で荒唐無稽な物語であることは同様である。いわゆる「メカ(ロボット)」と「美少女」をそのままに描いたどこまでも非現実的なストーリー。
あえていうなら前者には存在するある種の含羞のようなものが、後者にはほとんど感じ取れないかもしれないという違いはあるが、前者が後者に比べて特段にリアルであるとはとてもいえそうにない。
しかし、SF的な意味でいうのなら、やはり前者にはある種の配慮があり、後者にはそれがないのだ。つまり、『トップをねらえ!』はまだウソはウソとして、それでも一貫性のある虚構を成り立たせようという努力が見られるが、『ほしのこえ』は虚構の虚構性を意図的に前面化している、ということになる。
だからこそ、『トップをねらえ!』では一応の疑似科学設定がほどこされているのに対し、『ほしのこえ』では制服を着たまま銀河のかなたまで行ってしまうし、何光年離れようと携帯電話が通じるのだ。
おそらく、新海はそこでたとえば「ワープ通信機能を備えた特殊な携帯電話なのだ」などといった設定を付け加えることを蛇足だと考えたのだろう。
新海にとって重要なのはセンチメンタルなラブストーリーを美しく描きだすことであり、設定の科学的/疑似科学的一貫性などどうでも良いことだったのだと思われる。
【SF小説は「ミクロ」が弱い。】
このようにSFはSF的首尾一貫性にこだわるが、セカイ系は特別こだわらない、という違いはあるように見える。『最終兵器彼女』でも、なぜ一般人の少女が世界最強の最終兵器になってしまったのか、そこに合理的な説明は一切ない。
ただ、これも「強いていうなら」というだけの差であって、いわゆるハードSFとは違う系統のSF小説には、その種の科学設定にほとんどこだわらない作品もいくらでも見られることもほんとうだ。
そういう意味では、SFとセカイ系のより大きな違いとしては、SF小説では一般にセカイ系において「きみとぼく」に相当する部分の比重が小さいことが挙げられるだろう。
これは「近景(別所実)」とか「想像界(ジャック・ラカン)」といった語に対応させて語られる部分であるが、ぼくは経済学的に「ミクロ」と呼びたい。つまり、個人と個人の関係性の領域である。
SFでは個人的なミクロ描写にあまり力を入れないのだ。あくまで一般論であって例外はいくらでもあるには違いないが、SFでフォーカスされるのは、未知の新技術とか、世界の革新とか、宇宙から襲来する異星人とか、そういった「抽象的な大問題」、つまり「マクロ」である。
だから、先ほど述べた『2001年宇宙の旅』も、『果しない流れの果に…』も、名作であることは間違いないが、登場人物の名前などひとりも憶えていない。
これはぼくが特殊なのではなく、クラークやイーガンの天才は認めても、その作品に出て来る人物の名前を正確に記憶している人など、ほとんどいないのではないだろうか。そういうものなのだ。
【ここが違う! 「SF小説」と「セカイ系」の落差。】
つまり、SFとセカイ系では、SFでは「マクロ(抽象的な大問題)」に注力される一方で「ミクロ(きみとぼく)」の描写が弱く、セカイ系では「ミクロ」が丹念に描き込まれるものの、「マクロ」はかなり抽象的になるという落差があるわけである。
繰り返すが、これはあくまでざっくりと見たときにそうなるということであって、そうではない作品も無数に見つかるだろう。
しかし、ジャンルとはそもそも明確に定義不可能なものであり、そういうふうに雑駁に語るしかない。
そして、もうひとついえることは、SFもセカイ系も「具体的な中間項(国家や社会)」の描写は弱いということである。大森望の言葉はその意味では的確だ。
たとえば「地球連邦」や「銀河帝国」の出て来るSFは数多くても、それらを複雑巧緻かつリアリティ豊かに描きだすことに作品は少ないだろう。
例によってそこに力を注いだ作品もないわけではないが、SFの主流はやはり「中間項」とか「中間領域」と呼ばれる部分よりも、「マクロ(遠景とも、現実界とも呼ばれる)」といわれるところを描くことにある。
なぜなら、そういった「中間項」を描写することは、べつだんSFでなくてもできるからである。それに対し、「世界の命運」とか「宇宙の危機」といったマクロな主題をあつかった作品は、ほとんどそれだけでどこかしらSF的になってしまうのだ。
【ライトノベルも文学も。】
もちろん、それぞれ「ミクロ」や「中間項(ここではミクロ、マクロという呼称に合わせてミドルと呼ぶことにしたい)」を描きだすことに集中している作品もある。
たとえばラブコメライトノベルなどはほとんど「ミクロ」しか描いていないだろうし、私小説に端を発する「自然主義文学」由来の「いわゆる文学作品」もそうだろう。「社会派」と呼ばれる作品では社会の描写が中心となる。
両者はかけ離れているように思われるかもしれないが、それはその作品が「記号的個性(キャラ)」を描こうとしているか、それとも「複雑な内面、あるいは近代的自我(キャラクター)」を描こうとしているかという差があるだけのことである。
主人公の身近な関係性だけを描いているという意味では、電撃小説大賞受賞作も芥川賞受賞作もそれほど変わりはない。
ちなみに、「キャラ」と「キャラクター」という呼び方はややこしいようだが、伊藤剛『テヅカ・イズ・デッド』を参照した笠井潔『探偵小説と記号的人物』から流用している。
簡単に要約するなら、前者はある人物の「記号のようにわかりやすい個性の輪郭」のようなものであり、後者はその人物の「個人の欲求と社会規範のあいだで、ときに悩み苦しみ、ときに悶え哀しみながら自分自身について考える心理」のことだ。
もちろん、ほとんどの作中人物(キャラクター)はこの「キャラ」と「キャラクター」の両方を備えていることだろう。かれらを指して「キャラ」的であるとか、「キャラクター」的であるというのは程度問題である。
【「キャラ」と「キャラクター」の両立。】
この意味での「キャラ」と「キャラクター」の描写をある程度ハイレベルに兼備した作品に、栗本薫の『グイン・サーガ』であるとか、田中芳樹の『銀河英雄伝説』であるとか、京極夏彦の『妖怪シリーズ』であるとかがあるだろう。
あるいは、ジョージ・R・R・マーティンの『氷と炎の歌』でも良い。これらの作品の登場人物はかなり高い水準で「記号的個性」と「近代的内面」を両立している。
たとえば、田中芳樹の人物造形の最高傑作ともいうべき『銀英伝』の主人公ヤン・ウェンリーは、「紅茶好き」、「酒好き」、「天才軍人」、「私生活ではなまけ者」といったきわめてわかりやすく記号的な個性を備えているが、それらをすべて足し合わせてもそれだけではヤンにはならないだろう。
物語のなかでときに悩み、ときに苦しみ、状況に対応していくその内面描写がヤンをヤンたらしめているのだ。とはいえ、ヤンはやはりただ「リアルな人間」とだけいうにはあまりにも記号的/個性的である。
ヤンではなくヴァラキアのイシュトヴァーンでも、榎木津礼次郎でもそうだろう。ある種の捉えやすさ、わかりやすさと、実在感(むろん、虚構としての実在感)が併存していることが、かれらをして、忘れられないキャラクターにしている。
そして、もしかれらの「キャラ=記号的個性」が弱ければ、読者は読後にはあっさりとかれらの名前を忘れ去ってしまっていたことだろう。
【ライトノベルは「キャラ」中心。】
これらに対して、傑作とされるライトノベルのキャラクターは、さらにもっと「キャラ」寄りである。涼宮ハルヒも、キリトも、それなりに苦悩はするが、読者はべつだんかれらのそういうところに惹かれているわけではない、という気がする。
つまりはイラストとセットで描きだされるその「記号的個性」こそが圧倒的主眼なのだ。
ライトノベルは、その後継であるネット小説も含め、最も「近代リアリズム文学」から遠ざかった作品群といえる。
もっとも、「近代リアリズム文学」がほんとうに「リアリズム」であり、「近代的自我」を描けていたかというと、それはかぎりなく怪しい。
ようするに文学とは文字=記号の羅列以上のものではないのだから、文学とは一種の「仮想現実装置」ではありえても、「生々しい現実をそのままに描く」ことなどできるはずもないのである。
それが「生身の人間を描けている」と認識されるのは、そういう一種の幻想が成立した時代があったということ以上ではないだろう。ここら辺は、大塚英二の文学論に対する東浩紀の『ゲーム的リアリズムの誕生』などを踏まえて考えるとなかなか面白そうだ。
ぼくは特にサブカルチャー批評に深い興味があるわけではないからかるく流すが、関心がある方はぜひ追いかけてみてほしい。
【『天冥の標』のキャラクター描写。】
ぼくはいま、小川一水の『天冥の標』シリーズを読み耽っているのだが、メジャーなライトノベルと比べると、かなり登場人物の「キャラ」が弱い、と感じる。
小川はSF作家としては相当に「ミクロ」も描きこなせる作家だとは思うが、それでも、その「キャラ」はどうしても一定の限界の範囲内に収まっている印象を受けるのである。
つまりはこれがSF小説が広く受け入れられない理由だ。日本SFは、それこそ小川の作品を初めとして、質的にはいま、何度目かの黄金時代を迎えているといわれているのだが、それでもメジャーにヒットした作品はほとんどない。
人はあくまでも「ミクロ」のキャラクターにこそ注目する。ハリウッド脚本術などでくどいほど語られていることだが、ミクロレベルのキャラクターが魅力的で好感が持てる性格でないと、大抵の人は物語に興味を示さない。
マクロレベルの描写がどんなに優れていても、そこに好きになれる人物がいなければ、読者はそもそもその作品を読もうとは思わないのだ。
しかし、中国ではいま、SF小説がブームで、大傑作といわれる『三体』を初めとする数多い小説がベストセラーになっているという。
じっさい、中国のAmazonを見に行くと、『ハイペリオン』とか『ファウンデーション』の中国語版らしいタイトルが見つかる。
これはおそらく、中国ではいま、大衆が「マクロな未来」の行く末に興味を抱く時代が来ているのだろう。日本でもアメリカでもかつてあった現象だ。
【「世界の秘密」を探る物語が流行する?】
日本で大ヒットした『進撃の巨人』は、「ミクロ、ミドル、マクロ」の三領域を制覇した印象がある。
また、『エヴァ』の頃は「中間項」に興味を示していなかった様子の庵野秀明も、『シン・ゴジラ』以降、急速にその描写を強め、『シン・エヴァンゲリヲン劇場版:||』ではやはり三領域を描き切ったように見える。
セカイ系が流行った頃から、確実に時代は変わっている。また、現在はミクロの物語ではなく「世界の意味の解明」が主眼となる作品が広く受ける、としている指摘も見受けられる。
1975年生まれのイギリスの女性作家、ゼイディー・スミスが語ったという言葉があります。
「誰かがなにかについてどう感じたのかというようなことを伝えるのは、もはや書き手の仕事ではなくなった。いまの書き手の仕事は、世界がどう動いているのかを伝えることだ」(『Present Shock』Douglas Rushkoff、2013より。未邦訳)
これは村上春樹さんの文学もそうですね。『1Q84』も『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』も、わたしたちの日常の薄皮を一枚はいだ裏側に、世界の構造が見えてくるような物語を描いている。
さらには『進撃の巨人』や『エヴァンゲリオン』も、同じような物語が描かれています。1995年のテレビアニメから今年『シン・エヴァンゲリオン劇場版』にいたるまで、シンジくんは成長はしません。しかし一枚一枚皮をはぐように、世界の構造がどうなっているのかが見えてくる。
登場人物の物語ではなく、世界の意味の解明と提示が主題となっているのです。
もし世界が、その構造をつくるコンピュータのOSのようなものと、その上で動くアプリのようなもので成り立っているとしましょう。従来の「物語」は、アプリがつくる起承転結と成長の物語です。でもOSには、始まりも終わりもありません。OSは、「そこにある意味とは何か」「これからどうなるのか」「どこから現れてきたのか」などを聞かない。ただそこに存在しているだけです。
21世紀のわたしたちが知りたいのは、OSがどのように管理され、どのようなルールで運用され、どのような構造を持っているのかを知りたい。世界の奥底へと降りていき、奥底で駆動しているOSをつぶさに観察して世界の原理を探求したい。
わたしたちの求める物語への熱情は、そう変容している。
しかし、どうだろう。ぼくはそのようなマクロ重視の作品が流行する傾向があるとしても、あくまで入り口はミクロの人物描写であると考える。それは一時的な流行としては変わることがあっても、基本的には相当に普遍性の高い事実ではないだろうか。
一般に人間は人間をこそ好む。社会や、「世界」といったものの描写を受けつけるのはその次になる。
【物語への興味が「個人の内面」から「世界の秘密」へ移っている?】
ここでいう「世界」とは、単に物語の背景となっている設定を指すわけでもなければ、主人公たちが活躍するその舞台の描写を指しているわけでもない。その両者が一体となり、初めて物語の「世界」を形づくっている、と考える。
とりあえずここでは便宜的に、前者を「大世界」、後者を「小世界」と呼んで区別しておこう。
たとえば『機動戦士ガンダム』でいうなら、「宇宙世紀0079年、人々は宇宙に舞台を移し、モビルスーツを呼ばれる兵器を開発して、終わらない戦争を続けていた」というのが「大世界」、具体的な軍事基地なりスペースコロニーなりが「小世界」にあたる。
そのいずれも『ガンダム』の「世界」を形成するためには欠かせないものである。
『ガンダム』という作品が魅力的なのは、ひとつにはこの「世界」が独創的で個性的だからだろう。
もちろん、視聴者はそこで繰り広げられるアムロ・レイだのシャア・アズナブルだのの冒険やら陰謀やらをこそ楽しんでいるわけなのだが、背景となる「世界」にオリジナリティがなければ『ガンダム』はここまでヒットしなかったこともたしかだろう。
そして、個々のキャラクターがいなくなったあとも、最新作『閃光のハサウェイ』に至るまで『ガンダム』シリーズが続いているのは、もっとこの「世界」のことを知りたい、この「世界」にひたっていたいという欲望が視聴者にあるからに他ならない。
【『ガンダム』の魅力は「世界」にあり。】
つまり、『ガンダム』シリーズにおいて最も魅力的で不可欠なキャラクター、それはアムロでもなければシャアでもなく、ガンダムやザクが宇宙を舞台に戦い合う、その「世界」だということである。
このオリジナルな「世界」は富野由悠季監督がほとんど独力で作り上げたものだとされているが、そのことはかれの特別な才能を語って余りあるだろう。
漆黒の宇宙空間ではてしない戦闘を繰りひろげる無数の人型のロボット。そのまわりに浮かぶ、いくつもの円形をしたスペースコロニー。戦いのなかで超感覚に覚醒してゆく「ニュータイプ」や「強化人間」たち。
これは日本伝統のロボットアニメと、舶来の『スター・ウォーズ』や『2001年宇宙の旅』の折衷ではあるが、それでも『ガンダム』のまえにこのような「世界」を提示した作品はなかった。
いま、ロボットアニメの歴史を振り返るぼくたちにとって、『ガンダム』という作品がそのなかで圧倒的に独創的に思われるのは、その「世界」に独創性があるということなのだ。
今日なお『ガンダム』が不世出の名作として知られているのは、当時のアニメとしては別格なほど、時間的にも空間的にも考え抜かれたこの「世界」があったからだと思われる。
この「世界」のことを、大塚英二に倣って「大きな物語」と呼ぶこともできるだろう。
【「小世界」と「大世界」は補い合う。】
くり返すが、この「世界」は主人公たちがそこで躍動する物語のじっさいの舞台である「小世界」と、時間的、空間的設定としての「大世界」に分かれる。
このうち、じっさいに映像のなかで視覚的に確認できるものは「小世界」のほうであり、「大世界」はあくまで抽象的な概念として存在しているに過ぎない。しかし、いくつもの「小世界」に統一感を与えているのは「大世界」である。
士郎正宗原作、押井守監督の『攻殻機動隊』を思い浮かべてみよう。この映画で「小世界」にあたるのはあきらかに香港からイメージを持って来たと思われる近未来日本のサイバーパンク・シティだ。
「攻殻機動隊」こと公安九課のリーダーである草薙素子や相棒のバトーの冒険はそこから出ることはない。だが、その「小世界」を成り立たせているのは、「過去に第三次非核大戦と、第四次核大戦があり、そこで義体技術という名のサイボーグ・テクノロジーが飛躍的に進歩した」という時間的な設定、つまり「大世界」である。
いい換えるなら、『攻殻機動隊』の混沌とした「小世界」は「大世界」の制約のなかで作られていて、そこから逸脱することはない。突然、設定的にありえない出来事が次々と起こったりしたらまさに興醒めでしかないわけだ。
その意味で、「小世界」と「大世界」は補完しあっており、ふたつそろって「世界」を構成しているといえる。
【「世界」とは「生きたひとりのキャラクター」。】
こういったひとつの「世界」は、単に書き割りの設定であるのみならず、まさに人間のキャラクターに匹敵するほど「生々しい」ものでなければならない。
そこには、「世界とはこのような場所である」、あるいは「このようであるべきである」という作家の認識と主張が込められているといえるだろう。
たとえば、『エヴァンゲリオン』シリーズの「世界」が謎めいているのは監督である庵野秀明がそのように世界を捉えているからだろうし、『進撃の巨人』世界が過酷なのは、まさに作家がそういうふうに世界を受け止めているその証左に他ならない。
ここでいう「世界」とはまさにひとつの思想、哲学、あるいは「世界観」の象徴であり、その意味で「生きたひとりのキャラクターである」ということができる。そして、それだけにひとつの「世界」を作り出すことは魅力的なキャラクターを生み出すことと同様、むずかしいことなのだ。
佐々木俊尚さんが記している記事からもわかるように、近年の日本のアニメ界隈やハリウッド映画業界では、ことにこの「世界」を描写することに力が注がれるようになってきている。
もちろん、最も重要なのはキャラクターのドラマであり、それがなければ観客は映画を見てはくれない。しかし、その「世界」が十分に活き活きとしていて魅力的であるのなら、多少ドラマが弱くても映画が成立してしまうこともたしかなのだ。
【「ワールドビルディング」という方法論。】
そのような「世界」構築の方法論は、ハリウッドでは「ワールドビルディング」と呼ばれているという。それについて書かれた具体的な記事を引用してみよう。
特に北米の映画業界で言われていることですが、いまの映像業界では「ワールドビルディング」という手法がメインになってきています。
これまでは、古典的映画が遵守していた「ひとつの作品で起承転結をはっきりつけ、観客に効率よく物語を見せる」というメソッドが長らく主流でした。しかし、70年代以降のハリウッドで隆盛してきたメディア・コングロマリット、メディアミックスのような流れがそれまでの撮影所システムの衰退と入れ替わるように発展し、作品がヒットした際にすばやく連作が出せるように、あらかじめ大域的に世界観を設定しておき、その中に適度に「謎」を読み込める「余白」を散りばめる、というスタイルが広がってきたんです。例えば、いまのハリウッドでのワールドビルディングの代表的なコンテンツが、3月1日に日本公開される『ブラック・パンサー』も含まれる、「マーベル・シネマティック・ユニバース」(マーベル映画)です。
このような「ワールドビルディング」の方法論は映画史的には『スター・ウォーズ』に始まるとされているが、その『スター・ウォーズ』は連続テレビドラマに影響を受けているようだ。
あらかじめ個々の人物や「小世界」を内包する「大世界」を作り上げておいて、そのなかでドラマを展開する、というやりかた。
【オタク第一世代の方法論。】
この「ワールドビルディング」の方法論においてどういうことが起こるかというと、個々の物語、あるいは作品を語るだけではその作家の創作の全体像を語ったことにはならない、といった事態である。また、同じ記事から引用しておこう。
ただ、ひとつ言えるのはワールドビルディングというコンセプトの話にも繋がりますが、第一にひとつの作品、画面が、それだけで完結してクオリティや作り手の創造性を評価できるという考え方や、第二に映画なりアニメなり、あるいはスクリーンなりテレビ画面なりといったひとつのジャンルやデバイスに特化した批評基軸が有効性を持たなくなってきているということです。やはりJ.J.エイブラムスを例に取るなら、彼は黒澤明やジョン・フォードのような創造性というより、二次創作的というか、オタク的な感覚で映画をつくっている印象があり、それをかつての大文字の巨匠と同じように論じてしまうと、その本質、面白さというものを見誤ってしまうでしょう。それは庵野秀明さんの『シン・ゴジラ』にも同じことが言えます。
これは、庵野秀明監督や『エヴァ』について考えたことがある人にとっては、ほとんど自明のことだろう。「オタク第一世代」と呼ばれる庵野監督は、いつもかれが好きな作品のパズルのように組み合わせて作品を作っている印象がある。
しかし、それでは、庵野さんが生み出した『エヴァ』の「世界」はどこまでも模造品に留まっているのだろうか?
【ただの「パッチワーク」ではない。】
『エヴァ』の世界(「小世界」と「大世界」のいずれも)が、ある意味で『マジンガーZ』や『ウルトラマン』、『宇宙戦艦ヤマト』といった過去の名作のパッチワークから成り立っていることはつとに知られていて、もはやなかば常識となっている。
これは『ガンダム』の「世界」が『スター・ウォーズ』の影響下にあることと同じで、皮相的には「既存の作品の物まねでしかない」ということもできる。
「人類補完計画」や「裏死海文書」といった不思議な、なぞめいた言葉から構成されるその「大世界」は、圧倒的なセンスのよさによって魅力的にはなっているものの、本質的には「どこかから借りてきたような」ものだともいえるわけだ。
しかし、それでも、『エヴァ』の世界は圧倒的に輝きを放っている。なぜなら、そこには「作家の実感」が、いい換えるなら「魂」が篭もっているから。
『エヴァ』の世界がかぎりなく怖ろしく、いくつもの深遠な「謎」に満ちていて、しかも主人公たちに対してまったく優しくないのは、作家がそう世界を捉えているからだと先に述べた。
それは、単に「設定ではそうなっている」という次元を超えて、象徴的な意味で作家にとっての「この世界の真実」を表しているのだ。それが、「世界に血が通っている」ということ。
「世界」の構築において重要なのは、単に設定上のつじつまが合っているからということだけではなく、それがきちんと「作家の内面の心象風景」を表現できているかということなのである。『進撃の巨人』でも同じことだろう。
【「世界」とはその作家の「魂の風景」である。】
『進撃の巨人』の「世界」は、なぜあそこまで人間に対し残酷なのか。それは、描き手が「この世界は残酷な場所だ」と感じているからに他ならない。それが「時代の気分」にマッチしたからこそ、『進撃の巨人』は破格のヒットになったのだろう。
きわめて政治的(ポリティカル)といわれる『進撃の巨人』の物語だが、その背景にあるのは作者の「世界観」である。それが、「壁に囲まれた都市」という「小世界」、「なぜ巨人たちが都市の外に徘徊しているのか」という「大世界」を作っている。
そして、読者はそこに「たしかに、この世界ってこういう残酷な、だけど美しい場所だよな」と共感し、物語に夢中になるのだ。
つまり、物語のなかの「世界」とは、その作家にとって「この世界はどういう場所であり、またあるべきであるか」という、その「実感」と「理想」が篭もったものなのであり、逆にいうならそこにその作家の「魂」が篭もっていなければ、いくら緻密に考え抜かれていても意味がないといえる。
『エヴァ』にしろ、『進撃の巨人』にしろ、その「ワールドビルディング」の独創性はずば抜けている。それはただ「細部までよく考え抜かれている」という次元のことではなく、「その作家にとってのこの世界の真実の形」を表現できているということなのである。
【映画『ドラゴンクエスト』はなぜ酷評されたか。】
同じことが『ONE PIECE』でも『HUNTER×HUNTER』でも『十二国記』でも『獣の奏者』でもいえるだろう。それらの「世界」は、すべて作家の「世界観」に沿ってデザインされている。
あるいは、そういった「異世界」を舞台としているわけではない『よつばと!』や、『ALLWAYS 三丁目の夕日』といった作品にしても、作家の「世界はこうであってほしい、こうであるべき」という価値観を象徴しているところに魅力があるのだと思う。
これらの作品の「小世界」はいかにもリアルなこの世界そのものというふうに見えるが、じっさいにはそうではなく、やはり作家の願望なり理想を反映したものなのである。
最近公開された映画『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』が多数の観客から非常な酷評を浴びたのは、この「世界」の虚構性を暴いたそのシナリオに理由があるだろう。
いつまでもその「世界」にひたっていたいと願う観客にとって、そういった「楽屋落ち」的な結末はきわめて重大なタブーに触れるものなのだ。
ほんとうに佐々木さんがいうように物語を楽しむ観客の興味が「個人」から「世界」へ映っているのかどうかは微妙なところだが、少なくともいまやいかに「魂の風景」としての「世界」を作り込めるかに作品の成功がかかっている、とはいえそうである。
まあ、まさに書き割りの「世界」を使い回している「なろう系」みたいな例もあるのだけれど。ここら辺のことは、「なろう」のことを考えるときにまた新たに考えてみたい。
【お願い】
この記事をお読みいただきありがとうございます。
少しでも面白かったと思われましたら、![]() やTwitterでシェア
やTwitterでシェア
をしていただければ幸いです。ひとりでも多くの方に読んでいただきたいと思っています。
また、現在、記事を書くことができる媒体を求めています。
この記事や他の記事を読んでぼくに何か書かせたいと思われた方はお仕事の依頼をお願いします。いまならまだ時間があるのでお引き受けできます。
プロフィールに記載のメールアドレスか、または↑のお問い合わせフォーム、あるいはTwitterのダイレクトメッセージでご連絡ください。
簡易なポートフォリオも作ってみました。こちらも参考になさっていただければ。
【電子書籍などの情報】
この記事とは何の関係もありませんが、いま、宮崎駿監督の新作映画について解説した記事をまとめた電子書籍が発売中です。Kindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければご一読いただければ。
また、オタク文化の宗教性について考える『ヲタスピ(上)(下)』も発売しました。第一章部分はここで無料で読めますので、面白かったら買ってみてください。
その他の電子書籍もKindle Unlimitedで無料で読めるのでもし良ければご一読いただければ。
『ファンタジーは女性をどう描いてきたか』はファンタジー小説や漫画において女性たちがどのように描写されてきたのかを巡る論考をはじめ、多数の記事を収録した一冊。
『「萌え」はほんとうに性差別なのか? アニメ/マンガ/ノベルのなかのセンス・オブ・ジェンダー』は一部フェミニストによる「萌え文化」批判に対抗し、それを擁護する可能性を模索した本。
『Simple is the worst』はあまりにも単純すぎる言論が左右いずれからも飛び出す現状にうんざりしている人に贈る、複雑なものごとを現実的に捉えることのススメ。
『小説家になろうの風景』はあなどられがちな超巨大サイト「小説家になろう」の「野蛮な」魅力に肉迫した内容。レビューの評価はとても高いです。
Kindle Unlimitedに未加入の方は良ければ下のバナーからご加入ください。これだけではなく、ぼくの電子書籍は「すべて」Kindle Unlimitedに加入すれば無料で読むことができます。初回は30日間無料です。
ちなみに、Kindle Unlimitedに登録された本は「kindle unlimited検索」から検索することができます。めちゃくちゃ便利。
【おまけ】
さらに、世にも図々しいことに「Amazonほしい物リスト」を公開したので、もし良ければ投げ銭がわりにご利用ください。
それから、18禁の裏サイト「Something Orange Adult」がひっそり公開しています。男性向けから乙女向け、凌辱から純愛、百合からボーイズ・ラブまであつかうヘンタイ的なサイトにしたいと思っていますので、お好きな方はどうぞ。
でわでわ。




















![GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 [Blu-ray] GHOST IN THE SHELL/攻殻機動隊 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51zQhaRZOLL._SL500_.jpg)