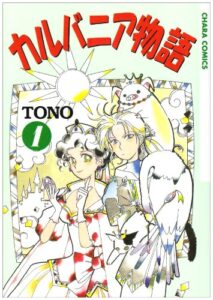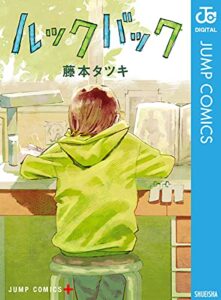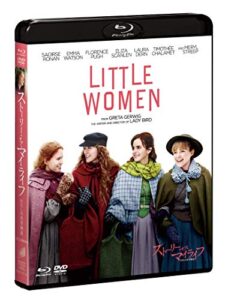映画『ゴジラ-1.0』(以下『マイナスワン』)を批判する動画を見ました。
非常に面白い。
ある種の政治的観点からこの映画を批判する意見は当然、出て来ると思っていました。
単なる難癖に過ぎないような批判は無数にあるけれど、この動画はきわめてロジカルだし、非常に説得力がある感じ。
そしてその上で、まったく共感できない(笑)。
この動画は主に映画の「リアリティ」と「人間ドラマ」について批判しているのですが、物凄く丹念に批判されているにもかかわらず、ほとんど納得がいかない。
ほんとうに作品の本質が理解されていない、何ひとつ伝わっていないんだなあといっそ感心するくらい。
そしてまた、山崎貴という監督はほんとうに舐められている、あなどられているんだということもあらためて感じますね。
小説でもマンガでもそうだけれど、カルト的に「とがった」作家に比べ、一見して「わかりやすい」エンターテインメントを展開する娯楽作家は、一段下に見られる傾向があります。
現実には大衆向けにエンターテインメントを書くことにはそれなりの才能や技術が要求されるわけなのだけれど、それはめったに理解されず、高く評価されない。
「お涙ちょうだい」のウェットな映画を作ってヒットさせるなんて、だれにでもできるだろうとみなされるわけです。
その際、同じようにウェットでも全然ヒットしていない作品が無数にあることは都合よく無視されるのですね。
『シン・ゴジラ』はたしかにいわゆる「人間ドラマ」とされる部分を徹底してカットして怪獣映画を一流のポリティカル・スリラーに仕立て、絶賛を浴びた天才的な傑作でした。
しかし、だからといって『シン・ゴジラ』的なやりかたが「正解」というわけではなく、唯一の方法論でもないのは当然です。
庵野監督に庵野監督の個性があるように山崎監督の作家性もまた尊重されてしかるべき。ぼくはそう思いますが、わかりやすい「ように見える」話の作り手はどうしても適切な評価を得られないようですね。
最初に結論を書いてしまうと、『マイナスワン』を「リアリティがない」と「酷評」するこの動画で理解されていないように思える前提は、『マイナスワン』は1947年を描いてはいるものの、あくまで2023年のテーマとコンセプトを持った映画なのだということです。
この映画の「リアリティ」とはまさに2023年における「リアリティ」なのであって、作中で主人公たちが示す「団結心や使命感」にもこの時代なりの理由がある。
まさにいまの時代固有のテーマとして、共同体の「団結」が選択されているのであって、賞賛するにせよ、非難するにせよ、そこを見なければ何を見たことにもならないでしょう。
動画のなかでは「感動げなストーリー」と語られていますが、実際には思想的な意味でも相当に練られた脚本だと感じています。
それが、たとえ批判するにせよ、そもそも認識されていないのは、山崎はどうせ何も考えていないだろう、ただウェットなストーリーで感動げにまとめることしか能のない奴だろう、自分が鋭く見抜いた真実には何も気付いていないだろう、という見下しがあるせいではないでしょうか。
山崎監督はこういう人たちから「やめちまえ」などとののしられながら、つねに一流のプロフェッショナルとして限られた予算と納期のなかで最良の作品を生み出してきたのだと思うと、ぼくはとてもリスペクトします。
大人が仕事をするってそういうことですよね。
この動画のなかでは「怪獣映画の限界」が語られていますが、現実に『マイナスワン』はめちゃくちゃにヒットしているわけで、ぼくとしてはこの点も納得いかないですね。
興行的なペースとしては『シン・ゴジラ』を上回るくらいで、それはやはりこの作品が「時代を捉えた」ことを意味しているのだと思います。
実写映画としてはきわめて稀有なことで、『シン・ゴジラ』ですら成し遂げられなかった、興収100億円という数字にすら到達するかもしれません。
もちろん興行的な成功が即座に作品的な成功を意味するわけではありませんが、少なくとも単に「感動げなストーリー」さえ準備すれば容易に到達できるという数字ではないでしょう。
そして、「怪獣映画」はもう複雑化した現代社会を捉えられないのではないかという視点は面白いけれど、そもそもゴジラはあくまで特定の「社会問題」の象徴ではないと考えるべきだと思います。
むしろ、そういった複雑な問題を含んだ社会の全体そのもの吹き飛ばしてしまいかねない超社会的な脅威の象徴がゴジラなのです。
それが初代『ゴジラ』の時代においては原爆だったし、『シン・ゴジラ』においては震災だったし、『-1.0』においては再来する戦争そのものだったということになる。
『シン・ゴジラ』がそうだったように『マイナスワン』もこれからさまざまに論じられていくことでしょうが、せめてこの種の大衆蔑視的な「あなどり」なしに正面から語られてほしいものだと切に思います。
話を戻すと、思想的な意味では、類似した批判は『シン・ゴジラ』に対してもありました。
左翼的な、戦後民主主義的な描写――即ち権力は悪であり、「団結」もまた悪であり、そこに対する批判を抜きにして政治を語ることはできないのだ、といったある意味では素朴ともいえるかもしれない理念にもとづく描き、それに対しいわば一条の亀裂を生んだのが『シン・ゴジラ』だったのでした。
そこで描かれていたのは国家という「公(パブリック)」に屈託なく(と見えるまま)奉仕する官僚たちの姿だったからです。
じっさい、左派リベラルの立場に立つ(と思われる)藤田直哉さんは『シン・ゴジラ論』のなかで、『シン・ゴジラ』初見のとき、その映像に圧倒されながらも感じ取った疑問についてこのように書いています。
この映画にはほんとうに喜んで良いのか?
日本政府と自衛隊が勝つ映画に拍手を送るのはどうなんだろう?
重工業、製造業が強かった時代の日本をあまりにロマンチックに描いていないか?
危機に際して「一体感」を集団が持つ、過労死しそうな環境で働くこの映画の現実の労働に対する効果はどうなんだろう?
カタルシスを感じさせるこの映画のスペクタクルは、実際の震災の犠牲者や被害者に対する共感を失わせる効果がないか?
「日本政府と自衛隊が勝つ映画」という語句は非常に象徴的です。
『シン・ゴジラ』はつまり直観的に戦後はずっと抑圧され軽蔑されてきた「右翼的な態度」に一歩踏み込む作品として受け取られたのでしょう。
そもそも、最近のポップカルチャーのウルトラヒット作には、若者の「右傾化」傾向を示していると受け取られる作品が少なくありません。
それは『進撃の巨人』に始まり、『鬼滅の刃』、そして『すずめの戸締まり』と続きました。
これらの傑作は現代という時代の「右傾化」を示す作品として見られ、左派的な論客からさまざまに批判されました。
しかし、同時にこういった作品たちを生み出した時代背景については詳細に考えていかなければなりません。
右翼的な「公共善への奉仕」と左翼的な「個人の生の称揚」はときとして矛盾し、対立するわけですが、わが日本の場合、太平洋戦争という大きな曲がり角(はっきりいってしまえば大失敗)を経ている結果、「公共善の奉仕」という価値観はつねに疑問視されてきており、それがエンターテインメントにも表れています。
もっとも、じつは「公(パブリック)」と「私(プライベート)」の対立というテーマは戦前、いやもっとずっと昔から日本の物語において語られてきたものでした。
ただし、そこでは「公」の価値が圧倒的だった。
たとえば、歌舞伎や人形浄瑠璃で有名な『菅原伝授手習鑑』というお話があります。
この話のなかに良く「寺子屋」と呼ばれて切り取られる人気の一部分があるのですが、そこでは主君の血筋を守るためにわが子を犠牲にする親が出て来ます。
現代の価値観からすると理解しがたいほどの内容ながら、あくまで「美談」として描かれているのです。
また、『伽羅先代萩』という作品もあって、そこでは、やはり忠義のために毒見役の子供が死亡します。
他にも類例はあるでしょうが、そこにあるものはようするに滅私奉公の美学です。
滅私奉公――「公(おおやけ)」を奉るために「私(わたくし)」を滅する。
その「忠義」の姿勢はある種、個人の我欲を超越した理想的なものとして受け取られ、しかし一方でそこにどうしても消し切れない「私」の情に対する哀憐の切なさがただよい、見る者の涙を誘うわけです。
しかし、それはあくまで江戸時代の価値観。これが戦後になると状況は逆転して、「私」の価値がどんどん向上していくことになります。
この「私」のいのちこそが最も価値の高いものなのであって、迂闊に「公」に取り込まれるとろくなことはない、という考え方です。いわば「滅公奉私」といっても良いかもしれません。
たとえば友人のLDさんから教えてもらった『ガメラ対宇宙怪獣バイラス』(1968年)という作品があって、いまでもAmazonで見れるんですけれど、この映画のなかでは宇宙人の人質となったたったふたりの子供の命を救うために地球は全面降伏するそうです(笑)。
いや、思わず「(笑)」とつけてしまったけれど、これはマジメな話で、いかにも子供だましな筋立てとはいえ、その頃の思想的背景ではそれなりのリアリティを感じさせる表現だったと思うのです。
ダッカの日航機ハイジャック事件において、当時の福田首相が「人の命は地球よりも重い」という言葉とともに「超法規的措置」を実施したのはそれから9年後の1977年のことです。
この言葉そのものもじっさいにはそれより前にこの言葉は人口に膾炙していたともいいますが、まあ、ともかくこの表現が広く一般に知らしめられたのはこのときだったのではないでしょうか。
いずれにしろ、こういった個人の生命を至上の価値とみなす価値観は、現実にどの程度実行に移されるかはともかく、この時代には一般的なものだったのでしょう。
その「私」の価値の高騰が行き着くところまで行き着いたのが、他ならぬ『新世紀エヴァンゲリオン』でした。
この作品の主人公・碇シンジは初めは「逃げちゃダメだ」と呟きながら何とか人類のために戦いますが、最終的には立ち上がる気力を失い、「エヴァに乗る」ことができなくなってしまいます。
滅私奉公どころではありません。パブリックの価値が決定的に信じられなくなってしまったのだということもできるでしょう。
で、いたって当然ながら最終的に世界は滅び去ってしまう。
シンジとアスカのふたりが、それでもなお、「人類補完計画」から抜け出してきた結末は未来にほのかな希望を感じさせるものだと見ることもできますが、世界が滅んでしまっているのだからやはり大きな問題が残されていました。
ひたすらに「私」を追求するセカイ系的な価値観がある種の袋小路に達したといっても良いでしょう。
もちろん、そこに至るまでには『ザンボット3』やら『ガンダム』やら何やらいろいろとあるわけですが、まあ、そこまで語っているとさらに長くなるので今回はカットします。
とにかく、そこでは「ヒーローの大衆への自己犠牲的な奉仕」がもはや成り立たなくなってしまっている状況が赤裸々に描き抜かれていました。
自己犠牲、うつくしい言葉ではありますが、90年代中葉のリアリティではもはやありえないことだったのでしょう。
石原慎太郎は『男の業の物語』というエッセイ集のなかで、三島由紀夫と対談したときのエピソードを紹介しています。
男にとっても最も大切なものはなにか、という問いに対し三島と石原両者が出した答えが奇しくも「自己犠牲」だったということです。
石原慎太郎に対しては他者に「自己犠牲」を強いる一方で自分はどれほど大衆に奉仕したのか怪しいところが多々あるわけですが、まあ、こういう「男性的」な美学を称揚する作家が「太陽の季節」とか「完全な遊戯」のようなニヒリズムの世界に至ることは良くわかる。
ぼくは良く山田風太郎の最高傑作『魔界転生』を例に上げますが「男の子の物語」が徹底されたとき、たどり着くところは「虚無」なのではないでしょうか。
それはともかく、先に例を挙げた作品でいうと、『鬼滅の刃』もやっぱり自己犠牲の美学を描いている一面があるといって良いでしょう。
まさにだから右傾化しているとか全体主義的などといわれてしまうのだけれど、一方でいまなおそういう「滅私奉公のロマンティシズム」というのはやっぱりあることを証明した作品だったといっても良いと思います。
あるいは見方を変えるならそれもまた「感動げなストーリー」に過ぎないといわれるかもしれませんが、どんなに左翼的な視点からそれに対する批判があるとしても、歴史的な大ヒット作であることは揺るぎません。
また、その戦後民主主義的な価値観が根本から揺らいでいるのが現代という時代だと思うのです。
印象的なのはウクライナ戦争における左派著名人たちの徹底的な「反戦」言動です。
戦争反対というと「良いこと」のようですが、そこにはあからさまな思想的頽落が見て取れました。
典型的なのがたとえば上野千鶴子さんによる「停戦」を求める言動だったでしょう。
「権力」と「団結」を徹底的に否定的に見る思想はこのようなあい路に至ってしまったわけです。
そして、こういう時代においては古典的な「滅私奉公」的な価値観とともに「男の子の物語」が形を変えて復活する。
戦後、左派はフェミニズム思想とともにそのような右翼的なマッチョイズムを批判してきました。たとえば、大江健三郎の初期作品に「セヴンティーン」と「政治少年死す」という短編があります。
戦後文学の代表作とすらいわれながら何十年も「封印」されていたといういわくつきの小説なのですが、これは偶然にも三島由紀夫の「最も三島らしい」代表作「憂国」と同じ年に発表されているということです。
しかし、内容的には三島的、あるいは右翼的な「男の子のロマンティシズム」に冷や水をかける物語であると見ることもできる。
何しろ自涜(オナニー)をやめられない17歳の少年がテロリストになっていく話で、最終的にかれが自殺するときも「精液の匂いがした」と描写されているのですから、おまえら「七生報国」がどうとかかっこいいことをいっているけれど、ようはただ天皇をオカズにしてオナニーしているだけじゃん、と受け取ることも可能なのです。
まさにそうだからこそ、右翼からの大批判を受け「封印」されることになってしまったわけですが、しかし、「憂国」と並んで名作であることは揺るぎません。
ちなみにこれは余談の余談になるものの、自慰(オナニー)という行為はポルノグラフィとともに男性性を語るとき、無視できないウェイトを持っていると思います。
射精という行為をどう捉えるかはいろいろな論点があるでしょう。たとえば『感じない男』や『非モテの品格』といった本ではそれはネガティヴに捉えられ、「自傷行為」とまで呼ばれます。
で、男性のオナニーというとぼくが思い出すのがやはり『エヴァンゲリオン』です。
小谷真理『聖母エヴァンゲリオン』を引くまでもなく、碇シンジが「ポジトロン・ライフル」を発射して使徒を撃退する「ヤシマ作戦」の展開はあきらかに射精のアナロジーでした。
シンジは日本中に注目されながらのその「公開射精」によって明確に「男性性」を確立するわけです。
それは日本エンターテインメント史上最高の「気持ちいい射精」といっても良いでしょう。
しかし、それが最終的に「なさけない去勢」にたどり着いてしまうことはご存知の通りです。
その流れは『エヴァ』のエンターテインメントとして極限のカタルシスがとんでもないアンチ・クライマックスへ向かう流れそのものです。
『エヴァ』は勃起と射精という男の子の生理を両面的に描き抜いたという意味でも傑作であるといえるかもしれません。
さて、『マイナスワン』もそういった先行作品からの流れにのっとっているわけですが、この作品には少なくともひとつ、大きな議論を呼ぶポイントがあります。
はっきりとゴジラへの「特攻」を描いているところです。あきらかに山崎監督の代表作のひとつ、『永遠の0』から来る描写と思われます。
それだけに、結局のところ、ここで、かれは「特攻」を美化してしまっているに過ぎないという批判はあって当然ではあるでしょう。
しかし、問題はそう単純ではありません。『マイナスワン』の主人公はまさに碇シンジ的に「特攻」や「自己犠牲」から逃げつづけた末に「特攻」に回帰しているからです。
これは「そうはいってもやっぱり特攻しかない!」というシンプルな話ではなく、「どのような条件でなら「公」への奉仕としての自己犠牲が成り立つか」考え抜いた末の結論がそれだったということなのだと思います。
右翼的な自己犠牲観念と左翼的な平和主義理念がここではある種の折衝を試みられている。まさに時代が要請したテーマというしかありません。
ここら辺のことについては、「アズキアライアカデミア」の配信で語られたことです。何時間もあって長いのですが、良ければ見てみてください。面白いはず。
全体への奉仕とか自己犠牲なんてばかげている、しかし「だれかが貧乏くじを引かなければならない」、そうでなければ国家は、あるいは世界は滅び去ってしまうし、そのとき、個人の権利もまた何も保証されない。
いま、あらためてぼくたちが世界状況から突きつけられているシビアな現実をまえに、新たな「公の価値」を見いだすためにはどうすれば良いか、それが『マイナスワン』が追求したテーマだと思います。
山崎監督は、『ドラえもん』、『寄生獣』、『ルパン三世』などの著名作の映画化を次々に手がけていることもあって、たとえば天才肌の庵野監督などと比べたときに、一見して凡庸な作家性の持ち主と受け取られてしまうかもしれません。
なまじ映画について一家言ある「シネフィル」であればあるほど、かれの業績を正当に評価することができない一面があると思う。
ですが、今回の『マイナスワン』ではっきりと(わかる人には)わかるように、一流のクリエイターです。
作家や作品への批判は自由ではあるものの、かれがしばしば今回のように(ぼくから見れば)不当な低評価を受けているところを見ると、そもそも作家を正当に評価できない批評者の存在意義とは何なのか、と疑問に思えてしまう。
あるいは山崎監督本人はそういった世評を歯牙にもかけないかもしれませんが、ぼくはかれは問題作とされる『ドラゴンクエスト ユア・ストーリー』なども含めて、「コスプレショー」ではない「一本の映画作品」として見るべきマンガの映像化作品を生み出しつづけている稀有な作家だと認識しているので、ちょっと気分が悪く感じます。
むしろ自分自身をある種の「マニア」として認識している人ほど、大衆を魅了するかれの真価がわからない。そういう意味ではかれの作品にはある種のリトマス試験紙としての一面があるかもしれません。
だれにでも理解できるわかりやすい作品を作っている「ように見える」からこそ、わからない人にはわからなくなってしまう。
山崎貴とはそういう作家であり、かれの物語はつねにぼくたちに問いかけているのだと思うのです。
あなたは、ほんとうに映画を「観る」ことができる人ですか、と。
【お願い】
この記事をお読みいただきありがとうございます。
少しでも面白かったと思われましたら、![]() やTwitterでシェア
やTwitterでシェア
をしていただければ幸いです。
また、YouTubeチャンネルの「アズキアライアカデミア」で月一回、配信を行っています。こちらもチャンネル登録していただくと配信の際、通知が行きます。
合わせてよろしくお願いします。
オタク文化の宗教性について考える電子書籍『ヲタスピ(上)(下)』を発売しました。第一章部分はここで無料で読めますので、面白かったら買ってみてください。
その他、以下すべての電子書籍はKindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければそちらでもご一読いただければ。


![『ゴジラ』4Kリマスター 4K Ultra HD [Blu-ray] 『ゴジラ』4Kリマスター 4K Ultra HD [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51SSy09DfiL._SL500_.jpg)























![ルパン三世 THE FIRST[Blu-ray豪華版(ブレッソン・ダイアリーエディション)] ルパン三世 THE FIRST[Blu-ray豪華版(ブレッソン・ダイアリーエディション)]](https://m.media-amazon.com/images/I/518jWQjnq+L._SL500_.jpg)