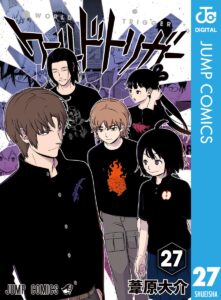それは、どこかで「聖なるもの」と繋がっているのか? それともまったく無関係な「俗なる文化」に過ぎないのか? 考えてみよう。
序文
以前、「なぜ、ただのアニメやゲームが人を救うのか、宗教的に説明するよ。」という記事を書きました。
なぜかはよくわかりませんが、かなり広く拡散され、非常に賛否両論を巻き起こしたようです。
で、これがこの「Somehing Orange」でも最も長い記事で、無料公開部分だけでも2万文字以上あるんですね。
通常のブログ記事ではまずめったに見ないくらいの長さといっても良いのと思うのですが、問題はじつはその無料公開部分は全体の八分の一であるに過ぎず、じっさいの原稿は18万文字もあるということです。ひええ。
そう、ぼくはだれが読むかもわからない、というかおそらくほとんどだれも読まないであろう原稿をひとり黙々と18文字も書いたんですね。
バカじゃないかと思うかもしれませんが、あなただけにそのほんとうのところを教えましょう。バカなんです。バカだから計算ができないんですね。困ったものです。
その後、この原稿は電子書籍『ヲタスピ(上)(下)』としてKindle Storeで発表しました。しかし、いまのところ、その上下巻で合計6冊くらいしか売れていません(笑)。
各巻につき3冊くらいということです。信じられるでしょうか? 18万文字も書いたんですよ。それが3冊ずつしか売れないなんて!
時給がいくらになっているか計算したくもありません。というか、必要だった資料代などを計算に入れるとはっきりとマイナスでしょう。
もう、何もかもイヤになったので、全文を無料で公開しちゃうことにしました。お金にならないのはしかたないとして、せめてだれかに読んでもらったほうが良い供養になるだろうということです。
はてなブログって一記事何文字くらい投稿できるんですかね? もし、一度に投稿できる文字数を超えてしまったら分けてアップしますが、まあとにかく無料で全文です。
こう書くと、お金を払って買ったその数人の人たちはどうなるんだと思われるかもしれませんが、大丈夫、Amazonで売っている電子書籍のほうには追加で何か原稿を用意しておきます。それで損はないはずです。
まあ、もし、ブログで18万文字を読むのは苦しいと思われた方がいらっしゃったら、ぜひ、電子書籍をお買い求めください。1冊500円、2冊で1000円です。
なお、Kindle Unlimitedで読むこともできて、そのばあい、お金はかかりません。無料です。
これだけではなく、ぼくの電子書籍は「すべて」Kindle Unlimitedに加入すれば無料で読むことができます。初回は30日間無料です。
ちなみに、Kindle Unlimitedに登録された本は「kindle unlimited検索」から検索することができます。めちゃくちゃ便利。
ちなみに、この原稿はいままでぼくがアニメやゲームからしばしば感じ取ってきた「崇高な感動」を言語化するために書いたものです。
いわゆるサブカルチャー批評と呼ばれる本はたくさんありますが、それらのいずれとも違うアプローチになっていると思います。ただ、以下のような本を参照しました。
【参考文献】
『不可能性の時代』
『人類にとって「推し」とは何なのか、イケメン俳優オタクの僕が本気出して考えてみた』
『サイファ覚醒せよ!』
『きわきわ 「痛み」をめぐる物語』
『気流の鳴る音』
『パンセ』
『宗教と日本人』
『ケルトの水脈』
『ケルト復興』
『ヨーロッパ異教史』
『グラストンベリーの女神たち』
『母権制』
『魔女の世界史』
『鏡リュウジの魔女入門』
『聖魔女術 スパイラル・ダンス 大いなる女神宗教の復活』
『サイコマジック』
『時間とテクノロジー』
『中二病取扱説明書』
『神は妄想である』
『神は妄想か?』
『正統とは何か』
『霊と金 スピリチュアル・ビジネスの構造』
『前田敦子はキリストを超えた』
『オタク文化と宗教の臨界 情報・消費・場所をめぐる宗教社会学的研究』
『ポップカルチャーマジック』
『ポップ・スピリチュアリティ』
『宗教なき時代を生きるために』
『デカルトからベイトソンへ』
『アイドルについて葛藤しながら考えてみた』
『エロティシズム』
『ツァラトゥストラ』
『童貞としての宮沢賢治』
『アルティメット・エクスタシー』
『性と芸術』
『「スピリチュアル」はなぜ流行るのか』
『あなたを陰謀論者にする言葉』
『宗教と性』
『ゴシックハート』
『ゴシックスピリット』
『見えない世界の物語 超越性とファンタジー』
『天使の王国』
『魔法少女はなぜ変身するのか』
『オウムからの帰還』
『共時性の深層』
『聖と俗』
『「推し」の科学』
『サピエンス全史』
『実存的貧困とはなにか』
『利他とは何か』
『贈与論』
『精神世界のゆくえ』
『世界が変わる現代物理学』
『奇蹟を求めて』
『動物化するポストモダン』
『聖母エヴァンゲリオン』
『無痛文明論』
『私はどこから来て、どこへ行くのか』
『現代宗教とスピリチュアリティ』
【参考作品】
『新世紀エヴァンゲリオン』
『その着せ替え人形は恋をする』
『魔法少女まどか☆マギカ』
『ハリー・ポッター』
『ホドロフスキーのDUNE』
『ナルニア国ものがたり』
『スター・ウォーズ』
『英霊の聲』
『Kanon』
『AIR』
『CLANNAD』
『Angel Beats!』
『SWAN SONG』
『輪るピングドラム』
『銀河鉄道の夜』
『プラネテス』
『愛人[AI-REN]』
『くつしたをかくせ!』
『楽園の泉』
『海底牧場』
『幼年期の終り』
『神狩り』
『百億の昼と千億の夜』
『アイの物語』
『サーラの冒険』
『ソラリス』
『天の声』
『九尾の猫』
『十日間の不思議』
『ふたたび赤い悪夢』
『夏と冬の奏鳴曲』
『Fate/Zero』
『魔法少女まどか☆マギカ』
『タコピーの原罪』
『チェンソーマン』
『リコリス・リコイル』
『Gunslinger girl』
『天気の子』
『カラマーゾフの兄弟』
『風の十二方位』
『PSYCHO-PASS』
『ジョーカー』
『僕の地球を守って』
『伊集院大介の新冒険』
『ライト・ノベル』
『ハチミツとクローバー』
『攻殻機動隊』
『春と修羅』
『金子みすゞ詩集』
『ママの推しは教祖様』
『2001年宇宙の旅』
さらにはネットの記事もいくつも参考にしています。
ぼくの書くものの常で情緒的で論旨が怪しいところはあると思いますが、一方でそれなりのオリジナリティも感じられるのではないでしょうか?
ちょっとでも気になる方はぜひ、読んでみてください。ぼくがいままで書いてきたもののなかで、最も労力がかかっていることは間違いありません。
よろしくお願いします。
序章
いま、この本を読まれているあなたにはだれか熱く応援している「推し」がいるでしょうか。そして、その「推し」とのあいだに、何か神聖ともいいたいような絆を感じたことはあるでしょうか。
本書『ヲタスピ』上下巻は、そのサブタイトルからわかる通り、オタク文化の「スピリチュアル」な一面について綴った本です。そういうわけで、推しに「聖なるもの」を見いだしたことがある人は、まさに本書の想定読者なのです。
ただ、あるいはもしかしたらスピリチュアルという言葉を使うと、ただそれだけで怪しいとかいかがわしいと思われてしまうかもしれません。
しかし、スピリチュアルとは本来、かなり価値中立的な言葉で、特定の文化とひもづいているわけではないのです。たとえば、医療業界でもしばしば「スピリチュアルケア」、「スピリチュアルペイン」といった概念が使用されています。
この場合の「スピリチュアル」は「霊性」とか「たましい」などと翻訳されるのですが、明確な対応日本語は存在しません。日本語ではきわめて捉えにくい概念なのです。
つまり、江原啓之的な世界ばかりがスピリチュアルではないということ。それはスピリチュアルの全体ではなく一部であり、それもかなりねじ曲がった一部なのです。
本書ではそういった意味での「スピリチュアル」も扱いますが、それ以外の意味での「スピリチュアル」についても記述します。
本書でいうところの「スピリチュアル」とは、何らかの超自然的な存在にふれたときの感触を意味するものと思ってほしいです。いかにもあいまいですが、そのようにしか定義できません。
また、「スピリチュアルペイン」とは、死をまえにした人が抱く、自分の存在がひき裂かれるような痛み、苦しみを意味しています。
広い意味での「スピリチュアルペイン」は本書上下巻を通したテーマであるといって良いでしょう。本書はオタク文化がそういった「存在の痛み」をどう癒やすかについて記したつもりです。
オタク文化の宗教性、あるいはオタク文化と宗教の親和性については、すでに宗教学のほうでも話題になっていて、専門的な本が何冊か出ています。
もちろん、本書はそれらの本のような学術的な内容ではなく、あくまで軽快に、楽しく、そしてなるべくわかりやすくオタク文化と聖なるものの親和性について語ってみました。
電子書籍として発表された本書がひとりでも多くの読者に届くことを祈っています。
ちなみに本書はまったく専門的な内容ではありませんが、一応は先行する宗教学の概念を引用する場合もあります。たとえば、20世紀最大といわれる天才的な宗教学者ミルチャ・エリアーデ。
わたしはエリアーデが好きで、十分に理解できているとはいえないかもしれないにしろ、昔から何か惹かれるものを感じてきました。
本書は一部で、そのエリアーデの宗教学が前提となっているところがあります。
たとえば、エリアーデは人間の宗教存在としての一面を捉え、宗教的人間(ホモ・レリギオスス)と呼びました。
そして、どれほど世俗化が進み、人々が宗教から離れていっても、完全にホモ・レリギオススの本質が変わってしまうことはないとしたのです。
わたしはそのエリアーデの言葉に共感します。科学がどれほど進んだとしても、人の本質が「宗教的」である以上、宗教がなくなることも「スピリチュアル」が語られなくなることもないと思うのです。
しかし、これはいまから本書全体を通して語っていくことなのですが、伝統宗教のリアリティはここ最近、社会発展のなかで急速に薄らいでいます。
「宗教的なるもの」に対する需要こそ大きくあるにもかかわらず、伝統宗教が必ずしもそれを提供できていない現実があるように思われるわけです。
そこで、広義の「スピリチュアリティ」の文化が興隆します。いま、一般に「スピリチュアル」といえば、まさに江原啓之に代表されるような奇異な文化を意味することでしょう。
このような文化は学術的には「新霊性文化」と呼ばれます。本書はこの新霊性文化について書いた本ではありませんが、それに接近する領域を扱っているので、本文中でいくらか触れています。
「スピリチュアル」に興味があって、そういうものをたくさん知っているというタイプの人もご一読いただければ幸いです。
人間が人間である限り、「聖なるもの」への渇仰、「宗教的なもの」への欲望はなくならないでしょう。
かつて、素朴な科学と進歩への信奉が大きな夢を見せたこともあったように思いますが、すでにその季節は去って久しい。わたしたちの時代は、リオタールのいう「大きな物語」をなくして半世紀も経っている、そういう時代です。
たくさんの人々が「たましい」のレベルで飢え、自分の孤独を癒やしてくれる「何か」を求めています。
その「何か」を、たとえば恋愛や家族に見いだせた人はそれで良いでしょう。うまくすれば、十分に幸福で満たされた人生を送れるものと思われます。
しかし、「たましい」が何かより高次の、形而上的ともいえるようなものを求める人もあるのです。そのような人にとって、重要なのはスピリチュアルな充足であり、単なる肉体的な欲望の満足だけでは足りません。
しかし、いまの時代、いったいこの「たましいの飢え」をどう満たせば良いでしょう?
あやしげなカルト宗教団体などに入ってしまえばただ搾取されて終わることはわかりきっているし、そうかといってふつうであたりまえの業界はあなたの「スピリチュアリティ」を満たしてはくれないことでしょう。
本書は、ひとりのオタクとして、いわゆる「推し」を持つことで、その「スピリチュアリティ」が満たされることがあると語っていきます。
タイトルの『ヲタスピ』とは、だいたいそのような含意です。
ところで、エリア―デの造語にヒエロファニーという言葉があります。聖体示現などと翻訳されるもので、ブリタニア国際大百科事典によると、このような意味です。
「聖なるものの現れ。聖体示現,聖化現象,神聖顕現などとも訳される。ギリシア語の神聖 hierosと現れる phainomaiから成る合成語。宗教学者 M.エリアーデが,諸宗教の現象形態を説明するために用いた基本的概念の一つ。宗教現象を非合理的側面からばかりでなく,その全体において,また進化論的評価の観点とは異なる立場からとらえようとするエリアーデの方法的態度を示した概念といえる。聖なるものの顕現を意味すると同時に,直接的には知覚できない聖なるものが表わされる媒体をもさす。たとえば,天,空,太陽,月,地,石,動植物,寺院,神殿,観念,道徳律,神話,儀礼,象徴,神,人など。したがって,ヒエロファニーには,実在と非実在,聖と俗の逆説的合一が認められる。」
これだけではわかりづらいかもしれませんが、つまり、何らかの「聖なるもの」が地上においてあらわれるときの物体を示しているわけです。
それは単なる実在する物体であり、同時に非実在の神聖さそのものです。
本書では、この「ヒエロファニー」という言葉が何度も出てくるはずなので、ここで意味を憶えておいてほしいと思います。
さあ、語りはじめましょう。猥雑を究めるオタクたちの文化と、地上を超えて遥か天上にまで達する聖なるもの――その両者をひとつのものとみなすことはむずかしいかもしれませんが、本書を読み終わる頃には、納得がいっているものと信じています。
本書はその意味で、あなたの「たましい」の冒険の書です。
第一章「オタク・スピリチュアリティとは何か?」
話をしているときに
同じ景色を見ているときに
悩み励まし合うときに
懐かしさを憶える人がいる
今日出逢ったばかりでも
感じる事さえある時
信じられるんだ僕らが
生まれ変わることを 槇原敬之「THE CODE~暗号~」
①「オタク文化と宗教のアフィニティ」
たとえば、そう、何気なく眺めていた報道番組で、何の罪もない子供が亡くなる事件が放送されていたとき。ふと、何ともいえず哀しく、薄ら寒い気持ちにならないでしょうか。
その子は大人から虐待を受けていたのかもしれませんし、純粋に不幸な事故で落命しただけかもしれません。いずれにしろ、かれ/彼女は、一見して平和で安全なこの社会に開いた「虚無の穴」へ墜落してしまったのです。
「虚無」は社会の至るところに穴を開けています。そのとき、あなたも、その報道を通しその深淵をほんの少しのぞき込んだといって良いでしょう。
戦慄の体験。
とはいえ、あなたはあまり長い間その記憶を引きずらないに違いありません。
その出来事はきわめて痛ましいけれど、あくまで見知らぬ子供のことに過ぎませんし、いつまでも気にかけるには人生はあまりに忙しないこともたしか。ひとまずは、そういえるでしょう。
しかし、もしそれが遠いどこかのことではなく、自分自身の息子や娘、あるいは少なくとも良く知っている子供のことであったら?
そのとき、あなたは「虚無」に魅入られ、その無窮の「落とし穴」をのぞくことをやめられなくなるかもしれません。
その穴は限りなく暗く深く、じっとその深みを眺めていると、快適で豊饒なこの社会の一切の「意味」や「意義」がまるで無価値に思われて来るのです。
「虚無」と向き合うとはそういうこと。そして、もしかしたら、人はそのようなときこそ「生きる意味」を求め宗教に誘われるのかもしれません。
宗教。
現代日本において、その評判は必ずしもかんばしくありません。ちょうどいま、元首相銃撃暗殺事件に関連しある宗教団体が問題視されています。
宗教とはただひたすらに怪しく、うさん臭く、おぞましい、理不尽で蒙昧な教義の集積であるに過ぎない。
そのような「偏見」を抱いている人すら少なくないでしょう。また、それが完全に間違えているともいえないのです。
そのためか、どうか、世界的にも宗教人口は減少の一途をたどっています。
しばしば「日本人は無宗教だ」といわれますが、それは海外、特に欧米の国々は日本とは違ってキリスト教の長い伝統があり、いまでも信仰を集めているという前提があっての話でしょう。
それなのに、じっさいにはそのキリスト教の伝統も大きく揺らいでいるのです。
そうはいっても減っているのはキリスト教人口だけで、たとえばイスラムの信徒などは増加しているのではないかという人もあることでしょう。
しかし、近年はイスラム教人口が多数を占めるアラブですら宗教人口は減少しつづけているともいいます。
あたりまえのことかもしれません。
キリスト教にしろ、仏教にしろ、あるいは相対的に新しいイスラムにしても、1000年から2000年以上もまえに構築された教理です。
現代社会に合致していませんし、常識的な科学技術とも矛盾します。いったんその教義に疑問を抱いてしまえば、いつまでも無心に信じつづけることができなくとも不思議ではありません。
しかし、だからといって、これから先、宗教の蒙昧は晴れ、ひたすらに輝かしい科学と理性の時代がやって来るのかというと、その展望を信じることはできません。
どれほど科学が万能を究めようと「虚無の穴」は空虚に開きつづけるに違いないのです。人類社会はここ何百年も経済的に豊かになりつづけていますが、格差は開くばかりですし、不条理なこともなくなるようには思われません。
つまり、たしかにわたしたちは狭義の宗教を必要としなくなりつつあるものの、一方で「宗教的なるもの」の需要は絶えないのです。
それなら、いったい何が伝統宗教に代わりその需要を満たすのか。現代日本を無心に眺めてみましょう。
たとえば「スピリチュアル」はどうでしょうか。「スピリチュアル」とは天使や精霊、宇宙人など超自然的な存在を前提とした文化で「オカルト」と隣接しつつ微妙に異なっています。
暗く怪しい「オカルト」に対し「スピリチュアル」は一見あかるいのです。
もっとも、非科学的な文化には違いありませんから、人によっては宗教と同じくらいうさんくさく捉えているでしょう。
わたしも頭から信じ込むわけではありませんが、そういった「非科学的」な価値を一概に否定し切ってしまう気にもなれません。
科学を信頼してはいますが、それが「虚無」に対し答えを用意していないことも知っているからです。
人は生まれるまえにどのような存在だったのか? 死んでしまったらどうなるのか? なぜ他のだれかではなく「この自分」が苦しまなければならないのか?
そういった「究極の問い」に科学は答えてくれません。それは科学の不備ではなく、ただその役割ではないのです。
もちろん「スピリチュアル」がその「問い」に対し、どれほど深い答えを用意しているわけでもないでしょう。だが、とりあえず一時の慰めにはなります。
それはこの世の摂理そのものでもある「虚無の落とし穴」をふさいでしまうことはできないにせよ、一とき、目を逸らすことを助けてはくれるのです。
あるいは「自己啓発」。
自分自身を改善し成長させてきびしい競争社会を生き抜いていこうとする自己啓発の精神は、いまや広く社会的に普及し、いわゆる自己啓発書はしばしばベストセラーとなります。
自己啓発にばかり熱心な人たちは「意識高い系」と揶揄されることもありますが、それも自己啓発がどこか宗教と近いことに理由があるのでしょう。
そして、もうひとつ、わたしが宗教とアフィニティ(親和性)を持つものとして取り上げたいのが、いわゆるオタクの文化です。
マンガ、アニメ、アイドル、ボーカロイド、Vtuberなど、現代社会において、広い意味でのオタク文化は「スピリチュアル」や「自己啓発」以上に多くの人を支えています。
それは一般的には単なる娯楽、エンターテインメント、ポップカルチャーの一種に過ぎないとみなされています。
しかし、ひとりのオタクとしていうなら、オタク文化にはたしかに「宗教的なるもの」がある。
一見すると猥雑で享楽的に見える文化ですが、それぞれのファンは何らかの「感動」を通じファンになっているのですし、ときには作品を通して「聖なるもの」を感じ取っています。
数年前、日本女子大学で「オタクにとって聖なるものとは何か」というワークショップが開かれました。
未見なのでその内容はわかりませんが、担当者のブログに中身の一端が残されています。
現代日本のオタク文化のなかに、宗教的なものを見出すのはたやすい。オタクたち自身、いくらか自嘲気味に「ネタとして」、しかし内心ではかなりの真剣さをもって「ベタに」、みずからの行動や世界観を宗教用語であらわすことがある。その行動様式もまた、自覚的であろうとなかろうと、しばしば「まるで宗教のようだ」。例えば、原始宗教を思いおこさせる奇天烈な衣装、古代の崇拝(カルト)とみまがう踊りや礼拝、集団の祈りのごとき形式化された絶唱など。オタク文化を彩る作品群(マンガ、アニメ、ゲーム、ラノベなど)にも、宗教的な表象が満ちあふれている。伝統宗教の場や象徴がそっくりそのまま採用されていることもあれば、元の文脈から引きはがされた有形無形の断片が作品に意味をあたえていることもある。また、オタク作品群につねにあらわれる超常的で霊的な存在や力は、「宗教」という固い表現になじまず、むしろ、「オカルト」「スピリチュアル」「俗信」といった表現の方がしっくりくることも多い。制作者と作品とオタクとが、こうした世界観において「何か」を交換しあい、多彩な文化をきずきあげているのだ。めくるめく伝統と霊性のオタク現象――これをまえに、宗教研究には、重大な問いが突きつけられる。オタク文化はどうしてこうも宗教に「類似している」のだろうか。「共有されるなにか」があってこその類似のはずだが、それはなにか。はたして、オタク文化とは伝統的な宗教と「同じなにか」なのだろうか。それは「偶像崇拝」「多神教」「異教」と何が異なるのだろうか。あるいはまた、「宗教」という言葉をさけて、「スピリチュアル」「霊的」「俗信的」「空想的」などの言葉を使えば、それはうまく説明されるのだろうか。」
この「問い」に対し、宗教学の研究者ではないわたしは的確な答えを用意することはできそうにありません。ただ、この問題に「オタクの側から」意見を述べることはできます。本書はそういう性格の本です。
それでは、語りはじめましょう。混沌としたオタク文化のなかに神聖なる何かを探しだすのです。
②「アイロニカルに没入する」
前項でオタクと宗教のアフィニティについて書きました。
しかし、あきらかにオタクと宗教は同一の概念ではありません。
あるいは同一の何かを根底に有しているかもしれませんが、オタク的なるものと宗教的なるものは、一方で酷似しているとしても、他方ではやはりかけ離れているのです。
それでは、具体的にどこが違うのでしょうか。
ひとつには、宗教が熱烈に「信じる」ものであるのに対し、オタク文化にはどうしようもなくアイロニーがともなう点です。
この場合のアイロニーとは「表面の意味とは逆の意味が裏にこめられている用法」を意味し、皮肉とか反語と訳されます。
つまり、表面的には「嫌い」な態度を取りながら、じつは「好き」、あるいはその逆といったことが端的なアイロニーです。
オタクたちのオタク文化に対する態度には、広くシニカルでアイロニカルな姿勢が見て取れます。
オタクはオタク文化を「好き」だからオタクなのですが、それにもかかわらず、オタク的なものが「嫌い」であるかのような言動を好みます。
いい換えるなら、表面的にはあたかもその文化から距離を取って、皮肉に眺めているかのような態度を維持しつつ、深層ではそこに没入している、それがオタクの自文化に対する態度です。
大澤真幸はこういった姿勢を「アイロニカルな没入」と説明しています。「シニカルなコミットメント」と同じ意味だとか。
大澤は書いています。
オタクは、現実をも虚構と本質的には異ならない意味的な構築物と見なすような、アイロニカルな相対主義者である。オタクは、意識のレベルでは、虚構の対象に対して、このようにアイロニカルな距離を保ちながら、反対に、行動のレベルでは、その同じ対象に徹底して没入してもいる、こうした意識と行動の間の逆立が、またオタクを特徴づける。
「アイロニー(ネタをともなう相対主義)」と「没入(ベタなコミットメント)」が平然と両立するところがオタク文化の特色なのです。
それでは、オタクはなぜ「アイロニカルな没入」に走るのか。オタク文化が一般に「幼稚」で「危険」だと非難を受けているから、自己防衛のため、斜にかまえた態度を崩さないだけのことなのでしょうか。
そういう側面はあるでしょう。オタクがオタク的なものに対ししばしば皮肉と冷笑を向けるのは、自分自身の行為の問題性を意識的にせよ無意識にせよ実感し、アイロニーとして処理することで安全な次元に留めようとする意思を抱いているからです。
つまり「アイロニーである限り安全だ」という意識がある。
しかし、じっさいにはまったくそうではありません。たとえ「アイロニカルな没入」であっても、没入には違いないのであって、そこには没入に付きまとう危険が必然にともないます。
オウム真理教はその典型でしょう。「オタク宗教」といわれたオウムは、ときに「笑える」ほど過剰で滑稽な一面を持っていました。
オウムの失笑せざるを得ない側面だけを見た人は、まさかそれが国内史上最大最悪の宗教テロを巻き起こすとは想像だにしなかったに違いありません。
ですが、現実にオウムは地下鉄サリン事件を起こしたのです。
つまりは、いくらアイロニーによって自分自身を防衛しようとしても、あくまで「没入」している以上、そのディフェンスは成立しないのです。
「自分はアイロニカルに対象に接しているから安全だ」という考えかたはその実、まったくの錯覚でしかありません。
そういう意味で、オタクはアイロニーの時代を象徴します。
かつて竹熊健太郎は「オタク密教(ネタとしてオタク文化を愛好するオタク)」と「オタク顕教(ベタにオタク文化を好むオタク)」という言葉を用い、オタクのアイロニーを表現していました。
そこには竹熊なりの複雑な考察があるのですが、重要なのは「自分はアイロニカルに対象から距離を保っているから大丈夫」としていた「密教」的な態度のオタクたちが、その後しばしばトラブルやスキャンダルを起こし、まったく「大丈夫」ではないことをさらしてしまったことです。
その意味で、オウム真理教事件に学ばなかったオタクは多かったといえるでしょう。
本来であれば、地下鉄サリン事件が起き、『新世紀エヴァンゲリオン』が放送された1995年の時点で、アイロニカルな態度への過度の依存は棄却されていてしかるべきだったのです。
ですが、少なくないオタクは「アイロニーである限り安全だ」と信じつづけた。その結果、オタクのなかで「ベタ」と「ネタ」は分離していきます。
とはいえ、大澤が上記引用の内容を記したのは2006年に過ぎません。現時点でそれから17年が経ち、オタクは完全に一般人化しています。
もはや、オタクは特殊な人種というより、若者集団そのものの属性のひとつでしかありません。
それにつれ、オタクの「アイロニー」も変わってきました。端的にいってしまえば、オタクたちの「アイロニカルな没入」は「ただの没入」へ向かっています。
もちろん、ひと口にオタクといっても色々な人たちがおり、あいかわらず斜にかまえた態度を崩さないまま対象に「没入」している者も見受けられるわけですが、オタク全体を俯瞰して見てみると、もはや少数派に過ぎないでしょう。
その「希薄化するアイロニー」を最も端的に示しているものがオタクたちが好んで使う宗教的な語彙です。
いつ頃からなのか、オタクたちが使うジャーゴン(俗語)にやたらと宗教的なものが目立つようになりました。
「神絵師」や「神作家」、「神作品」、「聖地巡礼」、「布教」、「祭壇」、「生誕祭」、そしてあっさり「萌え」に代わって普及した「尊い」。
これらの用語はもともと伝統宗教で使われていたものだが、いつからかオタクたちが自らの行為の真剣さを強調するため使うようになりました。
いまでは、序章に書いたように、専門の宗教学者ですらこういったオタクの「宗教性」に注目しています。
インターネット上でオタクたちはあたかも既存宗教を意図して模倣しているかのように振る舞います。それはかつては考えられなかったほど「ベタ」な崇拝の姿勢です。
もちろん、ここにもまだ「あえてそういう語彙を使ってみせる」アイロニーはただよっているでしょう。
ただの作家やイラストレーターを、いかにその技量が優れているとしても、「神」と呼ぶことはあまりに「大袈裟」で「過剰」であり、それ故に「アイロニカル」です。
オタクが愛する者の「生誕祭」を祝い、自分なりの「祭壇」をネットに上げるとき、そこには「自分の過剰さを見てほしい」といった、照れ隠しの心理が働いています。
自分の過剰さを意識しているからこそ「ネタ」として有効なのであって、オタクは自分の「やりすぎ」をジョークとして楽しむ余裕を備えているのです。
やはりオタクとアイロニーは切り離せません。
しかし、オタクのそういったアイロニカルな性格は時とともに薄れ、最近ヒットしたオタクネタマンガ『その着せ替え人形は恋をする』では、好きなキャラクターの誕生日を「ベタ」かつ熱狂的に祝う少女がきわめて肯定的に描かれています。
もちろん、そこには第三者の冷めたまなざしが付随してはいますが、それにしてもこうした「ベタな」オタクの姿はかつては「痛い」ものとして批判的に描写されるのが常でした。
時代は変わったのです。むしろ、その実態は、オタクが自分の感動をいい表そうとしたとき、それを可能にするものが宗教的なボキャブラリーしかなかったということなのではないでしょうか。
その昔、オタクといえば「萌え」と切り離せませんでした。いまでもそのように認識している人は少なくないでしょう。ですが、いまでは「萌え」を使用するオタクはほとんど見かけません。そのかわり、現代では「尊い」が使われます。「推しが尊すぎて無理」というふうに。
「萌え」には、それこそアイロニカルで複雑な自嘲がありました。ですが、「尊い」は無邪気に讃嘆を表しているに過ぎません。そこにも「わざと尊いといってみせる」アイロニーがかすかにただよってはいるにしろ、「萌え」に比べればその側面は後退しています。
もちろん、オタクが「推し」に対する冷静な現実認識を喪失したわけではありません。
オタクは、それが「二次オタ(アニメなどの二次元作品を好むオタク)」であれ「ドルオタ(アイドルオタク)」であれ、あいかわらず対象との距離感を現実的に把握しているます「現実と虚構を混同している」オタクはほとんど架空の存在といえます。
オタクは自分が「没入」している対象が虚構であったり、はるか遠いものであることをだれよりも良くわかっています。ただ、現代のオタクはその上でアイロニーに依存して自分の行為の安全性を担保しようとすることをやめたのです。
素朴で危険な態度でしょうか。
ですが、「アイロニカルな没入」が実質的に何ら安全性を意味してはいなかったことを思うなら、その姿勢はむしろ健全であるかもしれません。
もちろん、そこには虚構に対し深く没入しすぎる危険性は残っています。しかし、『その着せ替え人形は恋をする』を見ればわかるように、現代では「虚構への没入」は相当に好意的に受け止められるようになっているのです。
いかにも逆説的なことですが、この不透明さと流動性を強めた、たしかなものが何もない社会において、他ならぬ対象への没入性、即ち「好きという気持ち」こそが、船を港に留めるイカリのように人を現実にコミットメントさせてくれるからです。
くり返します。
時代は変わりました。
オタクであることはいまやいたって現実的なサバイバルの方法論なのです。
むしろ、オタクでないこと、つまり何も没入するものを持たないことは、いまとなっては危険なまでに不安定な生き方に見えます。
状況は次のステージへと進んだのです。
③「オタク・スピリチュアリティ」
本書はオタク文化のスピリチュアルな一面を示す一冊です。
しかし、最初に書いたように、宗教とかスピリチュアルに対しネガティヴな印象を持っている方は多いでしょう。
その種の文化を象徴する「天使」、「心霊」、「占い」、「奇跡」、「パワースポット」、「パワーストーン」といった言葉を並べてみるだけでそういった「匂い」がただよってくるかのよう。
ですが、そのうさんくささにもかかわらず、いまだにスピリチュアルな文化が流行していることは、人がこういった文化と関係を断てない事実を示しています。
第一項で書いたように「宗教」そのものは世界的にその勢力を減衰させています。ですが、「宗教的なるもの」への需要と関心はいまだに強いものがあります。
いい換えるなら「宗教的なるもの」を求めながら宗教を信じることはできない人々がたくさんいるわけです。そういう人たちは、あるいはスピリチュアルにハマり、あるいは自己啓発を信じ、そしてあるいはオタクになります。
もちろん、たかがスピ、たかが自己啓発、たかがオタク、そういってしまえばそれまでではあります。
「この世の真理とは何ぞや?」といった哲学的難問に頭を悩ませる人たちに、これらの文化が答えをくれるわけではありません。
ジャーナリストの佐々木俊尚は「特集 どこの国でも「宗教離れ」が進み、自己啓発に乗っ取られていく ~~私たちはいま「救い」や「癒やし」をどこで得られるのだろうか」と題したネット上の記事で、このように書いています。
「わたしはしばらく前に、曹洞宗の僧侶の藤田一照さんと何度か対談の機会をいただいたことがありました。この中で今も心に残っている会話があります。わたしが「いまは自己啓発とか、さらにはスピリチュアルのようなものが出てきて、宗教の代わりになってしまっている感じがします。日本の仏教が葬式仏教になってしまった結果、そちらに走る人が増えるのはしかたない部分もあると思うのですが、では宗教と自己啓発の根本的な違いってなんでしょうか?」わたしのこのぶしつけな質問に対して、一照さんはこうお答えになったのです。「多くの人生の悩みは、自己啓発本とかセミナーでも解決するのかもしれません。でもそういうものだけではどうしても最後まで解決しない悩みがあります。『なぜ自分は生きているのか』『なぜ人は死ぬのか』といった悩みです。これらにこたえるのが、宗教なんです
「なぜ自分は生きているのか」、「なぜ人は死ぬのか」、こういった「究極の問い」を、ここでは慣例にしたがって「ビッグ・クエスチョン」と呼ぶことにしましょう。
一照は宗教とはそういった「ビッグ・クエスチョン」に答えるものだといっているわけです。
しかし、そうなら、逆にいえばそのような「ビッグ・クエスチョン」に答えているものは、一見して宗教には見えなくても、単なるスピリチュアルとか自己啓発に留まらない次元に達しているともいえるのではないでしょうか。
そもそも「ビッグ・クエスチョン」に答えるとはどのようなことなのでしょう?
いうまでもなく、この「大いなる問い」に対する「真の答え」は不定です。それは万能を究めるかに見える科学ですら究極的には答えが出せない性質の問いなのです。
だから、さまざまな宗教もほんとうの意味で「ビッグ・クエスチョン」に答えているわけではありません。
いってしまえば、宗教は「ビッグ・クエスチョン」に対し天国とか地獄とか、神とか仏とか、救世主とか聖母といった「物語(ナラティヴ)」を提供しているだけです。
それらのナラティヴの信憑性に関する疑惑をいったん棄却し「ただ信じる」場合に限り、宗教は人を救ってくれます。
ただ、ここに微妙な点が残ります。一照は「これらにこたえる」といっている。この「こたえる」をわたしは簡単に「答える」と理解したわけですが、そうではなく「応える」なのかもしれません。
もしそうなら、宗教もまた「答え」を用意しているわけではないことを認めた上で、それでもなお「応える」ことが大切なのだといっているとも受け取れます。
もしこの解釈が正しいなら、オタク的な作品も「ビッグ・クエスチョン」に「答える」ことはできないまでも「応えて」いることはありそうです。
美少女ライブもSFアニメも、基本的にはエンターテインメントであり、人生の難問に答える/応えることを第一義とはしていません。
ですが、もしこの本を読まれているあなたがある程度ディープなオタクなら、何らかの「作品」に触れ、こうした「答えのない問い」に答えをもらったように思ったことがあるのではないでしょうか。
それが映画なのか、音楽なのか、それともマンガやアニメやライブなのかはわかりませんが、そのいずれであるにせよ、あなたは「宗教的な体験」をしたわけです。
伝統宗教が衰退しつづける現代社会においては、稀有な経験でしょう。
たしかに、それらは、哲学的に緻密な言説や、「天国はある」とか「死後はこうなる」といった物語を提供したわけではないはずです。
ですが、それらは「なぜ自分は生きているのか」と悩むわたしたちに対し、懸命に生きるとはどういうことなのか示してくれます。
そういう一例を通じ「生きることの意味と無意味」を「実感」した人間こそが、最も熱烈な意味でのオタクになります。
そもそも「なぜ自分は生きているのか」という「問い」に直面したわたしたちが求めている答えとは、単なるロジカルなストーリーではないはずです。
何より大切なのは「自分はこのためにこそ生きているのだ」と心から納得できることであり、たとえ死後どうなるのかはわからないにせよ、いま、この瞬間、ここを生きていると強く感じられることでしょう。
その意味で、個々の作品はオタクにとって「ビッグ・クエスチョン」の「答え(アンサー)」ないし「応え(レスポンス)」になりえます。
あるいはそのメッセージそのものは、一見して陳腐な、たとえば「愛こそすべて」といったものだったりもすることでしょう。
しかし、それでもそこに凄まじい強度を感じ取ったなら、それは「生きていく理由」になりえます。
もしオタクが幸福な人種だといえるとしたら、それはかれらが言葉ではなく体験を通して「ビッグ・クエスチョン」の答えをもらっているからに違いありません。
そういった強度を生むひと握りの人間のことを「天才」と呼びます。現代のオタク的語彙をもちいるなら「神」。
この不安定な時代、「宗教的なもの」を求める若者は少なくありません。
しかし、数十年前ならそういう人間が頼っていたような宗教だの文学だの思想だの哲学だのは、かれらにとってリアリティがなく、自分自身の人生とかけ離れているように感じられます。
だから、かれらは子供の頃から延々と親しんでいたポップカルチャーにこそ「答え」を求めます。そして、幸運な場合には「応え」を得ます。
そのような「宗教的なオタク体験」、いい換えるなら「オタク・スピリチュアリティ」を通して「信者」ともいうべき最も熱烈なオタクは生まれるのです。
いうまでもなく、世の中には「宗教的なもの」を必要としない人もいます。そういう人たちはたとえば自由恋愛や、仕事に没頭することなどで人生を豊かにできるでしょう。
いわゆる「リア充」的な生き方です。そういった「世俗的な」生き方で満足できる人はすれば良いと思います。ですが、気質的により神秘的なものを求めずにはいられない人もまたあるのです。
その昔なら宗教の門を叩いていたような人たち。
現代においてはそういう人たちはポップカルチャーに「答え」を求め、見いだし、そしてそこで飢え、かつえ、求めていた「救いと癒やし」を手に入れます。
そこから救われ、癒やされた者どうしの「つながり」も生まれるでしょう。
「救済」と「癒やし」、それに「コミュニティ」という宗教の役割はこうしてポップカルチャーに代替されるのです。
「寄る辺なさ」に苦しむ多くの人がそのようにして救われたことでしょう。素直に、素晴らしいことだと思います。
④「ありとあらゆる善きものの象徴にして集合」
オタク文化に「推し」という語彙が登場したのはいつのことでしょうか。初めはアイドルオタクの間で使われていた言葉でしょうが、いまではもっと広い層で使用されています。
辞書的な意味での「推す」とは「人や事物を、ある地位・身分にふさわしいものとして、他に薦める。推薦する」ことですが、オタクにとってはそれ以上の意味を持ちます。
自分の全身全霊をもってその人物を支える、応援する、それが「推す」。
かつて、一般的にオタクのそういう感情は恋愛感情の変形と見られていました。ですが、いまでは必ずしもそれだけではないことが広く認知されるようになりました。
もちろん、いまでも「推し」に熱烈に恋をするオタクもいます。いわゆる「ガチ恋」です。そういう恋心は、まず絶対に報われないわけですが、まさにそうだからこそ純度が高い。
そういった「ガチ恋」オタクは、一般社会で広く見られる感情の変形として受け止められるわけで、ある意味で理解しやすい一面もあるでしょう。
しかし、まったく見返りがないように見える「推し活」は、そういった説明だけで理解し切れるものではありません。
いったい推しとは何なのでしょうか。
横川良明『人類にとって「推し」とは何なのか、イケメン俳優オタクの僕が本気出して考えてみた』では「推し」は「恋人」より「神」に近い存在であると切々と語られています。
あまりに宗教的な言説であることから、一読しての納得はむずかしいのですが、その文章から伝わって来る熱量は単なる韜晦とみなすことを許しません。
紛れもなくこの人は推しを「神」とみなしているのだと切実に感じさせるものがあります。
それにしても、なぜ一個人をそこまで崇拝し「信仰」さえするのか、疑問は残ります。いったいそこに何があるのでしょうか。
横川の本を読んでいると、かれが推しを単なる一個人として見ているわけではないことが伝わって来ます。
かれにとって、推しとは、一個人を超えて、この世のありとあらゆる「善きもの」の象徴なのです。あるいは少なくとも、あらゆる「善きもの」が投影されているはずです。
かれは推しに美貌や演技力だけではなく、人格も求め、その期待が裏切られることを怖れます。
常識的に考えれば、彼ら、彼女たちは、ただ見栄えが綺麗なだけのふつうの人間に過ぎず、「神」ではありえません。
ですが、横川にとっては、推しはどこまでも善良で、気高く、誇り高く、美しい、理想の存在なのです。
もちろん、こういった期待は現実と乖離しているでしょう。
いってしまえば、かれが推すイケメン俳優はかれの理想に合致するよう演技しているに過ぎず、理想的な人格のもち主であるとは考えづらい。
あるいはそれがアニメやゲームのキャラクターなら「超絶美形にして大天才」といった、現実にはまずありえない属性を兼ね備えているかもしれませんが、それでも「神」とはいいがたいでしょう。
横川にそのような認識がないわけではありません。
しかし、それでもかれは推しにありとあらゆる善きものを投影しつづけるのです。まさに信仰といいたくなるような姿勢です。
つまりはオタクの推しへの感情は、単なる恋慕を超え、信仰と化している場合が見られるわけです。
だからといって、即座に推し活を宗教と見ることはあまりに安易な結論でしょう。真の宗教は「ビッグ・クエスチョン」に対する答えを備えていることを思い出してみましょう。
いったい美少女アイドルやイケメン俳優、萌えキャラクターが「ビッグ・クエスチョン」に対し答えを持っているでしょうか。
もちろん「否」でしょう。
しかし、前に語ったように、推しは「ビッグ・クエスチョン」に「答える」ことはできなくても「応える」ことはできます。
それでは意味がないでしょうか。ですが、既存の伝統宗教もこの生と死に関する「ビッグ・クエスチョン」に真摯に答えているとはいいがたいのではないでしょうか。
宗教は「人は死んだらどうなるのか?」といった問いに対し、たとえば「天国へ行く」といった答えを用意します。しかし、それは客観的な事実ではなく、いってしまえばひとつのナラティヴに過ぎません。
たとえばキリスト教を例として見てみてみましょう。キリスト教徒は聖書のナラティヴを事実として認めることを求められます。
そもそもイエス・キリスト自身にしてからが実在したのかすらわからない人物なのですが、ほとんどのキリスト教徒はイエスの実在を疑わないでしょう。
そして、聖書はさらに膨大なナラティヴを綴っています。イエスがどう行動し、どのような言動を残したかに始まり、使徒たちの行状に至るまで、克明に「記録」されているのです。
「ビッグ・クエスチョン」に対する明確なアンサー。
しかし、それはあくまで「物語」に過ぎないこともたしかです。
聖書の描写は、完全な虚構ではないにせよ、しばしば現代科学と矛盾します。
それでも、信徒はそのナラティヴを現実として信じなければなければならないのです。それで初めて信徒は「救われる」。
イエスの事績はともかく、エデンの園や黙示録といったことがらはあまりに神話的で、現代においては信じがたいものです。
ですが、キリスト教はそういったナラティヴの累積の上に成り立つ宗教なのであって、その「物語」を捨て去ってしまえば信仰もまた残りません。つまり、信仰とは「物語を生きる」ことであるのです。
一方でオタクはどうか。
いうまでもなくオタクもまた「物語」を愛します。
横川のようなイケメン俳優オタクもそうですが、いわゆる「二次オタ」はさらにわかりやすく物語を愛好しています。
ですが、宗教者が宗教の「物語」を現実として信じるのに対し、オタクにとって「物語」はあくまで虚構です。
宗教者が物語を生きているのに対し、オタクは虚構が虚構であることを前提にして楽しむに留まっているともいえます。
ここにオタクの「アイロニカルな没入」の根源がある。オタクは自分が楽しんでいるものがフィクションであることをだれよりもよく知っています。
だからこそ、オタクの態度はアイロニーを帯びるのです。しかし、それでもオタクは対象に「没入」します。
オタクの「物語」に対する態度がわかる一例として、たとえばボーカロイドが挙げられるでしょう。
コンピューターで音声を合成するソフトのことです。「ボカロ」として親しまれているそれらのソフトは、それぞれキャラクターの名前が付けられています。その最も有名な例が初音ミクです。
いまとなっては初音ミクの「歌」は膨大な量があり、名曲とされるものも数多く存在します。
それでは、コンピューターの合成音声に過ぎない初音ミクの「歌声」が、実在する人間の歌にも増して情緒に訴えかけるのはなぜでしょうか。
それは、まさに「初音ミクが歌っている」というナラティヴが背景にあるからではないでしょうか。
もちろん、初音ミクの「歌」を聴く者は、そのような人物が実在しないことを知っています。
初音ミクは純粋な虚構であり、さらにいうならほとんど設定らしい設定すらありません。
ただその名前と、キャラクターデザインと、身長などのわずかな情報があるだけ。それでも、オタクは初音ミクの「歌」を聴くとき、「初音ミクが歌っている」というナラティヴを感じ取ります。
この二重性にオタクの本質があるのです。オタクは、たしかにある意味では「宗教的なもの」を信じ熱狂します。
ですが、その一方でオタクは虚構の虚構性を理解しています。
初音ミクの歌声に涙しながら、一方では単なるコンピューターの合成音声だとわかっているように。
ここに、伝統宗教とオタクの決定的な落差があります。宗教者がナラティヴを現実のものとして認識しているのに対し、オタクはその虚構性を理解しているわけです。
ただ、それならオタクがその虚構を冷ややかに相対化しているかといえば、そうではありません。
オタクは虚構を虚構として知りながらそれに熱狂します。そこに「この世のありとあらゆる善きもの」の集合、あるいは「聖なるもの」をすら視るのです。
このような姿勢は、伝統宗教の信徒にとっては理解しがたいものでしょう。かれらは「信じるか、信じないか」という問題に対し「信じる」ことを選びます。
ある意味、その態度はシンプルです。それに対し、オタクは同じ問いに「信じないが、信じる」と答えるわけです。そこにはアイロニカルなねじれがあります。
このねじれを理解せずにオタクを理解することはできません。
宗教者が虚構を現実として生きる人たちだとすれば、オタクとは、虚構を虚構のままで生きる人間のことなのです。
⑤「世界の秘密と始原の暗号」
オタクにとって、推しとはこの世界の「ありとあらゆる善きもの」の象徴であり集合である、ひとまず、そう定義することにしましょう。
ひとり、推しの歌声に耳を澄ますとき、心がどこか遠い「たましいのふるさと」にとどくように思う。
映画館で推しの死闘を見守るとき、「生きること」のあまりに重い意味が言葉ではなく実感として体得できる。
そういうふうに思う人は少なくないでしょう。
そう、オタクは推しを通じて「聖なるもの」を垣間見ます。その意味で推しは地上における神聖さの顕現であり、より濃密な別世界に通じる扉です。
すなわちヒエロファニー。
重要なのは、推しがじっさいにそのような聖なる存在であるかどうかではありません。
そもそも聖なる存在とは客観的に計測可能なものではないからです。大切なのは推しに聖性を「投射」可能かどうかなのです。
「投射」とは最新の認知心理学「プロジェクション・サイエンス」の用語で、この本のずっと後のほうで解説しますが、いまは詳細を省いておきましょう。
ともかく、オタクにとっては、自分が推しに何を見出だせるかが真に重大なわけです。
オタクはそれが生身の人間だったり架空のキャラクターだったりすることを十分に承知していてもなお、推しに「聖なるもの」を見るのです。
オタクの姿勢が「アイロニカルな没入」と称されるゆえん。この聖なる何かを、社会学者の宮台真司は「端的なもの」と表現します。
宮台は『サイファ覚醒せよ!』のなかで、社会システム理論でいう「サイファ(暗号)」という概念を提唱しています。これは「世界の底が抜けている」、つまり世界に「未規定性」が残ることを「翻訳して無害化する」ための表象です。典型的には「神」。
この世界には解けようはずもない「暗号」があり、その「暗号」を解けたことにして無害化したものが「サイファ」なのです。
宮台は語っています。
長くなりますが、重要な個所なので引用しましょう。
「世界」とは奇妙なものです。ありとあらゆるものの全体を「世界」というわけです。ところが、人間は言葉を使って思考するけれど、ありとあらゆるもの全体が「世界」だとして、「世界」はどうしてあるのだろう、「世界」の外は何なのだろうというふうに考えちゃうんですね。〝「世界」はなぜ……〟とか〝「世界」の外は……〟という問いを突き詰めて考えると、必ずパラドックスに陥るからです。
多くの「社会」では、「世界」は神が創ったとするジェネシス(創世神話)を持ちます。ありとあらゆるもの全体を神が創ったと考えるわけです。さて、神は「世界」のどこにいるのか。もちろん「世界」の中にいたら、「世界」を創ることはできません。かと言って「世界」の外にいるとすれば、ありとあらゆるものの全体が「世界」なのだから、神を含めて「世界」だというしかなくなるし、神が「世界」の外だと言い張ると、「世界」の外にある存在をどうして僕たちが認識できるのかという問題が生じます。神は「世界」の中にいると言っても外にいるとイッテモ、背理になるわけです。
実は、こうした「世界」概念をめぐる背理は、キリスト教のスコラ神学において既にはっきりと意識されています。その意味で「世界」概念をめぐる背理という観念自体は、キリスト教に由来する概念です。そのキリスト教的な「世界」概念をベースに立ち上がったのが近代科学ですから、どのような個別科学も、それを突き詰めることで、必ず「世界」概念をめぐる背理に突き当たる構造になっています。
不完全性定理で知られる数学者ゲーデルは、すべての命題の真偽が数学的に証明できると予想するヒルベルトに対抗する形で、この「世界」概念をめぐる背理を証明しようとしました。その結果、「世界」を無矛盾な形式論理で完全に覆えないということが証明されてしまったわけです。これが誰でもその名前くらいは知っている「ゲーデルの不完全性定理」です。アインシュタインをはじめ多くの物理学者にも大きな影響を与えました。ちなみにゲーデル自身は、自分のやった証明を凌駕しうるような「神の存在証明」をしようとして、晩年には気が狂ってしまった。
「世界」はそもそも人間の論理によって完全に定義することができないというのです。
わたしたちは科学を信頼するあまり、いつかはそれがこの「世界」の全貌をあきらかにする日が来るのではないかと考えがちです。
しかし、宮台の主張によれば、その日は永遠に来ません。それこそロジカルに考えるなら「世界」にはどうしても「未規定性」が残ってしまうし、その「未規定性」を覆い隠すために「神」のような「サイファ」が求められるからです。
人は世界の未規定性を覆うサイファ、すなわち神なるものを見るとき、そこに聖なるものを感じ取ります。宗教学者ルードルフ・オットーが語るところの「ヌミノーゼ」でしょうか。
宮台によれば「端的なもの」は「世界の根源的な未規定性」に対する志向性を持つかぎり、必然的に出逢ってしまうものです。
僕は九四年の『制服少女たちの選択』、九五年の『終わりなき日常を生きろ』という二冊の本で、宗教を「前提を欠いた偶然性を馴致する装置」、分かりやすくかみ砕けば「端的なものを、無害なものとして受け入れ可能にする仕組み」であると定義しました。すなわち、宗教とは、たとえば近代科学を徹底的に押し詰めることで露わになるような――もちろん別の仕方でも露わになりうるような――「世界の根源的な未規定性」を、いわばバーチャルに覆い隠すために、無害なものへと加工する社会的メカニズムです。だからこそ、社会システム理論の立場から見ると宗教は不滅であらざるを得ないのです。
ただ、あとあと話したいことの絡みもあるので、一つだけ注釈をつけておきましょう。僕たちが「世界の根源的な未規定性」に向かい合ってしまうのは、トタリテート(全体性)への希求を持つからです。つまり全体を知ろうとするオリエンテーション(志向性)を有するからです。たとえば、論理を使って言語や思考を制御しようとすれば、それこそ論理て必然的に、その人は全体性への志向を帯びることになります。全体性への志向をもつと、必ず「世界」二は「端的なもの(たち)」が見つかります。つまり皺が生じるわけです。
「端的なもの」は、忘れるか、受け入れるしかありません。受け入れる場合には、無害なものへと加工して受け入れるんです。そこに宗教性が巣くう。実際には、無害化に向けた加工は、「神」概念のような「世界」の内と外に同時に属しうる「特異点」の導入によって図られます。そのことも後で述べるとして、いま述べたロジックを逆にたどれば、全体性や包括性への志向を放棄し、あるいは、「端的なもの」との出会いを次々に忘れてしまうことができれば、僕たちは宗教性から自由でいられます。
しかしその結果、僕たちの「世界」との関わりは、モザイク状に断片化することになります。もちろんそのように生きている人たちを、比較的容易に見出すことができます。しかし、それは僕たちが「皆」そのように生きられる「はず」だということではありません。
つまり、人は思考において全体性を志向する限り、「端的なもの」を受け入れるか、あるいはそれを忘却するか二者択一を強いられるわけです。
忘却すればモザイク状に断片化した「世界」との関わりしか持てません。そして、受け入れるためには何らかの意味で宗教的な態度が不可欠になります。
もちろん、それはたとえばキリスト教のナラティヴをそのままに受け入れるというようなことではありません。
しかし、ともかく何らかの形で「サイファ」を受け入れることなしには、人は「世界」を全体的に受け止めることができないのです。
⑥「推しを通して聖なるものを垣間見る」
この『サイファ覚醒せよ!』を受けて、マンガ研究家の藤本由香里は『きわきわ 「痛み」をめぐる物語』の最終章を書いています。
その文章で、宮台の師にあたる見田宗介の『気流の鳴る音』や田口ランディの小説『コンセント』を引きながら、藤本はある種、「スピリチュアルな」論考を展開します。
宮台がいうところの「世界の未規定性」とは、つまり、この世界で起こっている諸々の出来事は、一見するとごくたしかそうに思えるにもかかわらず、その実、ほんとうにそれが確実であることはだれにも証明できないことを意味します。
しかし、藤本によれば、そのように世界が未規定であるからといって、それがまったく「底が抜けている」とはいえないというのです。
否、純粋に論理的には「底は抜けている」。つまり、だれにもロジックだけでこの世界の実相を説明し切ることはできません。
それは恐ろしいことです。何らかの「サイファ」、つまり「神」のような概念を用意するのでなければ、人は世界を無限に疑いつづけるしかないとうことだからです。
ですが、ここで藤本は、人が次の行動を決定するとき、論理的には不確定な世界に対し何らかの「見当」をつけていると語ります。
つまり、純粋に論理だけで考えるなら、世界はどんな姿にも変わりえます。わたしたちは「世界の姿がこうである」という絶対に確実な答えを手に入れられません。
どれほど科学的な探求をくり返しても、どこかで神の指さきがすべてを操っているかもしれないように。
しかし、それでも「おそらくこうだろう」と「見当」をつけて「賭ける」ことはできるし、人間はじっさいにそうしているのです。
なるほど、宮台のいうように「世界の底は抜けている」かもしれませんが、それでもなお、わたしたちは「おそらく世界はこうなっているのだだろう」という「見当」をつけつづけることはできるということ。
藤本はパスカルの『パンセ』から言葉を引いています。
神はある、あるいは神はない。しかしどちらの側へわれわれは傾こうか。理性はここでは何事も決定することはできない。……表が出るかそれとも裏が出る。君はどちらに賭けるか……勝つかどうかは不確実であるなどといってもなんの役にも立たない。……賭けをする人はすべて、勝つ不確実さのために確実を賭ける……。
神があるのかないのか、人間の理性では決して決定できない。それはまさに宮台がいう「世界の未規定性」を覆う暗号そのもの、サイファだからです。
ですが、だからといってすべてを「何もわからない」といって終わらせることが最善ではありません。
疑いの余地は永遠に残るとしても、限りなく「見当」の精度を上げて、どこかで「勝つ不確実さのために確実を賭ける」。たとえば科学とはそういう営みのはずです。
何千回、何万回、実験と確認をくり返しても、科学は原理的に「絶対」にはとどかない。それでも、科学者は「おそらく世界はこうなっている」という「見当」の精度をしだいに上げていく。
そして、どこかの時点で「信じる賭け」に出るのです。
世界は美しいかもしれない。醜いかもしれない。神はいるかもしれない。いないかもしれない。
「理性はここでは何事も決定することはできない」。
それでも、なお、わたしたちは世界に美しくあってほしいと望み、神聖なるものを「信じる」。
それはたしかに厳密に論理的な行為ではないでしょう。なぜならそれは「そうであってほしい」という「祈り」に過ぎないからです。ですが、藤本は書いています。
「私たちの「祈り」が届く一点がある」と。
それはわたしたちがそこへ向かって「賭ける」、つまり主観をジャンプさせる一点です。そして、彼女はそれを「私の北極星」と呼んできたと告白します。
その北極星とはつまり、この世の「神聖さ」の道標です。人は何か「神聖なもの」に触れたと感じたとき、その向こうに「北極星」を見ているのです。
その「北極星」が具体的に何であるかは人それぞれ異なっているのが当然でしょう。
ある人にとってはバッハの旋律かもしれないし、またある人にとってはラファエロの聖母子像かもしれない。
藤本にとって、それは不世出の天才舞踏家シルビィ・ギエムの踊りだといいます。
彼女は書いています。
ところで、暗闇の中でまんじりともせず「世界は波動でできている」という考えと向き合っていたとき、「異次元が洩れ」、そこから吹きあがって来る風に精神が吹きさらわれそうになっていたとき、私は自分の正気を保つために「自分にとっての神聖なもの」の記憶を必死でたぐりよせていた。その中で、イメージや感覚ではなく、具体的に私が「信じられる」もの、神聖さの指標として浮かび上がってきたもの、それがシルビィ・ギエムの踊り(バレエ)であった。
萩尾望都『青い鳥』の中に「なにもかもなくしても 希望がなくても 世界が不条理でも 舞台だけは楽しかった……舞台にだけは青い鳥が住んでた」という一節があるが、ギエムの踊りはまさにそれを彷彿とさせる。
彼女が足を上げる、すると私たちはその向こうに、一瞬だけ永遠が揺らめくのをみる。彼女の腕が微妙に動く、その瞬間、自明であったはずのこの世界に裂け目ができ、私たちはその向こうに、もう一つ、別の次元の世界が揺らめくのを見る。それは不思議な感覚である。これは本当にこの世で起こっていることなのだろうか……?
なるほど、ギエムであれば、そのような「神聖さ」を感じさせても不思議ではない、そういうふうに思えて来ます。
しかし、世の中にはギエムの他にもさまざまに「神聖な」作家がいて、作品があります。
たしかに不世出の天才バレリーナは「〈神聖さ〉のイデア」を表すためにふさわしいと思われますが、同じことはアニメでもマンガでもいえるでしょう。
わたしたちはある人物や作品を通じ「神の世界」を視ます。そしてここまで来てしまえば、その人物なり作品を「推し」と呼んでも不自然には感じません。
推しとは「ありとあらゆる善きもの」の象徴であり、また集合だといいました。この不たしかな世界で信じられるもの。藤本にとってはギエムがそういう「推し」なのでしょう。
それでは、あなたにとっては何でしょうか?
そのような存在と出逢ったことはない人もいるでしょう。そういう人は「底が抜けた」世界の未規定性に対し不安定であるといえます。
なぜなら、ただ理性だけではその不たしかさに対して何もいえないのですから。
わたしたちはどこかで理性的な「無限の疑い」を捨て、主観的に飛躍する必要があります。
そのとき、いったいどこへ向かってジャンプすれば良いのか。それを指し示すものこそが、あなたにとっての「北極星」であり、いい方を変えるなら「推し」なのです。
いわば推しとは別世界へ通じた聖なる回路、ヒエロファニーなのであって、人の形をしていても、人ではありません。
シルビィ・ギエムの一挙手一投足の向こうに「彼岸」が見えるように。
あまりに大仰な表現でしょうか。ですが、じっさいに多くの人が、ポップカルチャーの傑作名作を通じて、かろうじてこの世界につなぎ留められています。
たかが音楽、たかが演劇、たかがアニメ、たかがマンガ――そうさげすむ人たちはいつまでもいなくなりはしないでしょう。
しかし、一方でその「たかが」によって救われる人もいなくならないのです。それがカルチャーの価値。
藤本はいいます。
「それこそが「サイファ」であり、他のどんなものにも侵されない「〈神聖さ〉のイデア」、わたしの北極星なのだと思うのである」と。
しかし、どうでしょう? じっさいのところ、ほんとうにアイドルグループの歌声や、他愛ないアニメの数々がそれほどの力を持ちえるのでしょうか?
「〈神聖さ〉のイデア」を胸に抱きつづけることは大切。ですが、それにふさわしいものはもっとクラシックな名作であり、芸術的な傑作なのであって、猥雑なポップカルチャーなどではないのではないでしょうか。
おそらく、世間一般的にはそのような解釈がまかり通るでしょう。ですが、その「たかがマンガ」にしても、「たかがアニメ」にしても、「たかがアイドル」にしても、見かけよりずっと深い世界を隠しもっているのです。
それが単に楽しく、享楽的なだけの文化なら、多くのファンを集めはしても、そこまで熱狂する人はあらわれないでしょう。
やはり、そこには「猥雑さ」を含み、なおかつそれを超えた何かがあるのです。
たしかに、並大抵の凡作は「サイファ」でも「〈神聖さ〉のイデア」でもありえないことでしょう。
藤本の言葉によれば、その人物なり作品が「神聖さ」を示すためには「天上のもの」である必要があります。
一般的なポップカルチャーで、遥かな天上を指し示すような名作になどめったに出逢えるものではありません。
ただ、その作品の客観的、一般的な評価は問題ではないのです。あくまで重要なのは、あなたやわたしといった個人がそこに何を感じ取るか。
人が神聖なものを「視た」とき、それは人生を照らす北極星、つまり「光の道しるべ」となります。
その道しるべを得たとき、初めて人は有象無象の「スピリチュアルなるもの」に対する本質的な抵抗力を手に入れます。
なぜなら、そういった有象無象はそのスピリチュアリティのクオリティにおいて「道しるべ」に及ばないから。
ポップカルチャーのなかに「光の道しるべ」を手に入れること。それが即ち「オタク・スピリチュアリティ」です。
第二章「非合理性の誘惑」
躓いて笑う日も涙の乾杯も
命込めて目指す
やがて同じ場所で眠る
他人だけの不思議を 星野源「不思議」
①「スピリチュアル文化の歴史と現状」
第一章では、人がオタク文化のなかに「聖なるもの」を垣間見る理由について説明し、上質のスピリチュアリティを発見する重要性を解説しました。
それにしても、なぜ人はスピリチュアルなものに惹かれるのでしょう? それは一見して非合理的だし、直接に現世利益をもたらしてくれるわけでもありません。
たしかにスピリチュアル文化の現場では「わたしを信じればお金が儲かる」という主張も時々見つかりますが、じっさいに効果があるとは信じられません。儲かるのはそれを信じた人から搾取した当人だけです。
いや、その信じがたい主張を信じるからこそ超自然的な文化を求めるのかもしれませんが、いずれにせよ、単純にお金を儲けたいだけならスピリチュアルに頼る必然性は薄いでしょう。
そこにはあきらかに現世を超えた形而上的な観念に対するあこがれがあります。
しかし、ほんとうにスピリチュアル文化はその憧憬を満足させてくれるのでしょうか。
この節では、少しオタク文化の話題から離れて、学術的には「新霊性文化」ともいわれるスピリチュアル文化の歴史と現状について語っておきたいと思います。
日本でスピリチュアル、あるいは「精神世界」などと呼ばれる文化は、海外では「ニューエイジ」として知られています。
これはヘレナ・P・ブラヴァッキー夫人によって創設された神智学の大きな影響を受け、占星術的な意味での「新時代の文明」を目指す一連のムーヴメントで、1960年代あたりから発展しつづけています。
教皇庁の調査によると「ニューエイジ」とは元々、薔薇十字団などによって使用された言葉であるといいます。
『アクエリアンエイジ』というトレーディングカードゲームがありますが、このタイトルはニューエイジの重要概念「水瓶座(アクエリアス)の時代」を借用しています。
また、モバイルゲームをたしなむオタクなら、たとえスピリチュアルにくわしくなくても、ヘレナ・ブラヴァッキーという名前に聞き覚えがあるのではないでしょうか。
そう、彼女はTYPE-MOON制作の大人気ソーシャルゲーム『Fate/Grand Order』に過去の偉人の「英霊」として登場するのです(エレナ・ブラヴァッキー名義)。
『FGO』では直接に神智学のくわしい記述があるわけではありませんし、エレナは史実とほとんど関係ないようにも見えるのですが、それでもきわめて好意的な描写といって良いと思います。
あるいは『Fate』シリーズの魔術描写自体、神智学の遠い影響を受けているのかもしれません。
それはともかく、60年代末からのカウンターカルチャー(対抗文化)の流れのなかでニューエイジは完全に花開きました。
その内実は瞑想、チャネリング、占星術、気功、自然食、セラピーなどまさに多様ですが、重要なのはそこに近代的な科学文明への懐疑と反発がひそんでいたことです。
ニューエイジの歴史における最初の大きな出来事として、ニューヨーク州ウッドストックで開かれた「ウッドストックフェスティバル」とミュージカル「ヘアー」があります。
両者とも音楽史のなかで特筆すべき重要な出来事ですが、当時のアメリカの若者たちは反体制を掲げ「新しい時代」を探し求めていったのです。
こういったカウンターカルチャーの空虚な実態を描写した面白く興味深い本としてジョセフ・ヒースの『反逆の神話 「反体制」はカネになる』があります。
そういう「反逆の神話」の一部として、反近代、反文明があり、スピリチュアルな文化が求められていったわけです。
ニューエイジは、自己啓発とも無縁ではありません。たとえば「自己啓発セミナー」として知られるヒューマン・ポテンシャル運動もニューエイジの流れのなかにあります。
かつて『新世紀エヴァンゲリオン』最終回の描写が自己啓発セミナーの亜流に過ぎないと批判を受けたことがありましたが、ある意味ではニューエイジの遠い余波が『エヴァ』まで続いているといえなくはないでしょう。
こういったニューエイジ運動は、日本に輸入されて「精神世界」として流行することになりました。宗教学者の島薗進によると、初めて「精神世界」という言葉が使用されたのは1977年のこと。
また、日本で「スピリチュアル」とか「スピリチュアリティ」といった言葉が使われるようになったのは1990年代後半のことです。主に医療、それも死生学の分野での使用です。
現在でも、医学界では医療用語として「スピリチュアルケア」とか「スピリチュアルペイン」といった言葉が使用されています。
それらの概念も「霊性」と翻訳されますし、宗教的な一面を持ってはいますが、ニューエイジや精神世界と直接に関係しているわけではありません。
そして「スピリチュアル」という言葉がより広く注目されるようになったのは2000年代に入ってからです。
江原啓之による「スピリチュアル・カウンセリング」というパフォーマンスが話題を集め、またその名前を冠した本がベストセラーになったことが契機でした。
江原の「スピリチュアル・カウンセリング」は人気テレビ番組『オーラの泉』でも取り上げられ、高い視聴率を稼ぎ出しました。
現在、「スピリチュアル」が心霊的なものと関連づけて語られているのは、江原の影響が大きいでしょう。オウム事件から十数年を経て、霊的な現象はまたも平然とテレビで扱われるようになったわけです。
オウムやその他の「カルト」を批判し攻撃しておきながら、一方でスピリチュアルな文化に近づいていくマスメディアの態度を軽薄と批判することは可能でしょう。
ですが、ようするに需要があるから供給があるのであって、江原の人気はあの凄惨な地下鉄サリン事件を経てなお、この種の需要が残りつづけたことを示しています。
その後、霊的な現象はいくらか硬い印象の「精神世界」より、「スピリチュアル」という言葉で語られるようになります。
それまで、こういったジャンルには恐怖体験的な暗さがぬぐい切れずありましたが、江原以降、非常に明るい印象になりました。
もちろん、その結果として、深い知識のない若者がスピリチュアルという言葉に惹かれ、全国各地であたりまえのように開かれている「ホリスティック」とか「ヒーリング」を掲げたイベントに出向き、結果として詐欺集団やカルト宗教の網にひっかかることも起こったでしょう。
スピリチュアル文化のその明るさには功罪があります。
さて、先ほどから「スピリチュアル」という形容詞を「スピリチュアリティ」と同様の名詞として使用していますが、これは現代日本で慣例的に使用されている言葉遣いです。
あるいは違和感がある方もいらっしゃるかもしれませんが、本書ではこの使い方を貫きます。ご容認ください。
ともかく、こういった歴史をたどって、現在のスピリチュアル文化の良くいえば多彩な、悪くいうなら雑多な現状があります。
試しにAmazonで「スピリチュアル」と入れて検索してみると、じつに膨大な本やアイテムが発見されます。
宗教が衰えているといわれる現代社会でも、なお、スピリチュアルは人気を集め、開花しつづけているようです。
良いことなのか悪いことなのはわかりませんが、そういったスピリチュアルなものを求める心理にはそれなりの社会背景があります。
そこにはある種の「霊的なものに対する飢え」すらあるでしょう。そして、本書でいうところの「オタク・スピリチュアリティ」を求める心も、そういった心理と背景を同じくしています。
根はひとつなのです。
「精神世界」についてオタク的なことについても触れておきましょう。山折哲雄監修『宗教の事典』によれば、一部のアニメやマンガ、つまり『北斗の拳』、『AKIRA』、『風の谷のナウシカ』といった作品も、当時、若者たちにスピリチュアルな影響をあたえたといいます。
もちろん、これらの作品はあくまでフィクションとして書かれたものであり、また大方はフィクションとして認識され消化されたわけですが、それでも隠然たる影響はあったでしょう。
その頃、時代はまだ「ノストラダムスの大予言」の1999年を迎えておらず、またオウム真理教による地下鉄サリン事件も起こっていませんでした。
マンガを読んだ結果としてオカルティックだったりスピリチュアルだったりする物事に惹かれる若者たちはいま以上に多かったものと思われます。
また、逆に初めからスピリチュアルなものを求めてこういった作品にのめり込んだ者も少なくなかったことでしょう。
つまりは、オタク文化とスピリチュアル文化は異質ではあるが、ときに接近しながら歴史を紡いでいっているのです。
それはいまなおそうです。最近、オタクのあいだでも「スピる」という言葉がなかば自虐的に使用されています
。それは、オタク文化とスピリチュアル文化がまったく縁遠いものであるとは限らないという、ひとつの根拠になることでしょう。
②「オタク文化のなかのスピリチュアルな表象」
次に、こういったスピリチュアルな文化が現代のオタク文化のなかにどのように取り込まれて行っているか見てみましょう。
『FGO』や『アクエリアンエイジ』についてはすでに触れました。このほかにも、オタク文化にはニューエイジの影響を受けた作品や「宗教的なもの」が花盛りです。
単なる作中の小道具として使っている場合もあれば、まさに深遠な宗教的テーマを感じさせるものもあります。
たとえば、最近はネット小説の世界で「異世界転生もの」や「聖女もの」が流行しています。
これらの作品では、おそらく明確に自覚はされていないでしょうが「転生」や「聖女」といった宗教的概念が流用されているわけです。
もちろん、それらは単に物語を進めるために都合の良い素材として扱われているに過ぎず、宗教的な一面があるとはいいがたいでしょう。
しかし、もう少し本質的な意味で「宗教的」といいたいような作品もあります。
渡辺聡『なぜ宗教はなくならないのか ポストモダンと宗教社会学 』では『機動戦士ガンダム』、『新世紀エヴァンゲリオン』、『ONE PIECE』などの作品の作品に宗教性を見ています。
「ニュータイプ」という神秘現象が出て来る『ガンダム』や、露骨に宗教的なモティーフが多用される『エヴァ』はともかく、『ONE PIECE』は意外かもしれません。
しかし、渡辺が「空島編」を取り上げた文章によると、『ONE PIECE』のなかで「敵である神」は、「現代の若者たちが直面している非人間的な管理社会」を象徴しています。
そして、この物語のなかでそのような宗教を打破できるものは「人間味を持つ主人公たちの正しい信念」だけなのです。
渡辺は書きます。
『ワンピース』は現時点ではまだ完結していないから、ここで詳しく書評するのは時期尚早であると思うが、それにしてもその物語は、社会全体が「官僚化」してしまい、人々の個人的なニーズに応えられなくなっていることへの怒りを表しているように見える。この物語の中で重要な存在となってきている「海軍」は、人々の幸せを踏みにじる悪として描かれており、それに対する徹底的な不信感が一貫して作品の中に流れている。当然のことながら、物語の中で主人公たちは反体制側に属している。話を現実世界に戻せば、なぜイスラム教という宗教が人びとを惹きつけ成長し続けているのかという理由も、抑圧されている人たちがグローバル化した管理社会に対して反発し、仲間に対する温かさに惹かれるという貴族の問題と関係づけながら考えることもできるのである。例えば、それはイラク戦争に従軍した黒人兵士がイスラム教に改宗したなどという事例の中に見出すこととができる。
ひとりの『ONE PIECE』の愛読者として、この意見にはうなずくところもありますが、一方で違和を感じないこともありません。
『ONE PIECE』の読者ならご存知の通り、この作品における「海軍」は必ずしも「人々の幸せを踏みにじる悪」としてのみ描写されているわけではないからです。
たしかに主人公のルフィたちは「反体制側」に属していますが、だからといって単純に「反体制こそが正義で、官僚制は悪だ」とされているわけではありません。
また、ひとりのオタクとしてわたしは『ONE PIECE』のこのような構造がエンターテインメントの長い試行錯誤の歴史の末に生まれてきたこともわかっています。
『ONE PIECE』の「反官僚主義的」な描写は、たしかに一面で暴力的に過ぎるかもしれませんが、しかし、一方では効果的であります。
もしこのような展開を避けたなら、それこそポストモダン的な相対主義の地獄のなかで何ひとつ決断できなくなるかもしれないのです。
その話はともかく、この例のように、その気になれば既存のマンガやアニメには宗教的、あるいは反宗教的なテーマが数多く見つかります。
宗教学者の内藤理恵子は『新しい教養としてのポップカルチャー』のなかで『ドラゴンボール』を宗教と自己啓発の文脈に位置づけています。
『ドラゴンボール』のどこが自己啓発かと疑問に思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、この場合の『ドラゴンボール』はそのスケールが爆発的にインフレーションしていった後半ではなく、主人公の孫悟空が亀仙人のもと修行する前半です。
亀仙人は「武道を学ぶことによって心身ともに健康となりそれによって生まれた余裕で人生をおもしろおかしくはりきって過ごす」、「いっしょうけんめい修行して人生を楽しくくらす」というモットーを掲げています。これが自己啓発的だというのです。
牽強付会に思われるかもしれません。しかし、現代の自己啓発本の少なくないものに『ドラゴンボール』の影が揺曳していることはたしかです。
自己にリミットを設定せず、無限に成長しつづけるように見える『ドラゴンボール』の世界観は自己啓発と相性が良いのです。
また、このような見方に疑問を感じられる方も『鬼滅の刃』の儒教性については納得がいくのではないでしょうか。
同書のなかで内藤は『鬼滅の刃』について、神話学の研究者である植朗子の『鬼滅夜話』、浄土真宗本願寺派の僧侶・松崎智海の『「鬼滅の刃」で学ぶはじめての仏教』といった本の名前を挙げながら、「もはや民間信仰?」と語っています。
80年代には「自己啓発の役割」「気晴らし」を担ったマンガが、2020年代には、そのエンタメ性をリバイバルしつつ、オタクカルチャーが一般化したことによって、その役割を拡大し、ついには民間信仰のようなものにまで発展したのです。
『鬼滅の刃』は日本映画史上空前にして、おそらく絶後になるだろう大ヒット作ですが、そこに人を惹きつける「宗教的なもの」を見て取ることは謬見とはいえないでしょう。
『鬼滅の刃』に見られる自己犠牲精神、私を滅し公に使える美学は、ときにファシズム的との批判を受けるにせよ、良くも悪くも個人主義的になってしまった社会で、わたしたちを強く惹きつけます。
それは少し見方を変えれば宗教的ともいえます。
このようにマンガ・アニメ、あるいはゲームにも「宗教的なもの」は散見されます。
また、オタク文化にはいわゆるオカルト的な表象もたくさん見つかります。たとえば「魔術」。
男性であれ女性であれ、オタクなら先述の『Fate』シリーズや『とある魔術の禁書目録』など、何らかの形で魔術が主眼となる作品に一度は触れたことがあるのではないでしょうか。
前節ではスピリチュアルがその明るいイメージによって普及したことを記しましたが、一方でもっと暗いもの、魂の深淵に宿る何かを示すような描写に対する需要もあって、そのため、魔術的なものが求められているわけです。
70年代から80年代にかけてのオカルト・ブームの残滓といっても良いでしょう。
魔術がオタク文化のなかのどのように扱われているのかについては第四章で再度触れます。
ともかく、オタク文化においては、スピリチュアルな、あるいはオカルティックな表現があたりまえのようにいくらでも見つかるのです。
この宗教性に幻惑されると、そういった個所ばかりを発見しつづけて「オタクは宗教だ!」と叫ぶことになるのでしょうが、本書ではもう少し深くこの主題を探究していきたいと思います。
オタク文化がしばしばニューエイジに酷似して見えることは事実です。
ですが、それは単に伝統宗教からさまざまな意匠を借用しているというレベルに留まるものではなく、あるいはそのテーマが宗教的な域に達しているだけですらなく、オタクはほんとうの意味で「宗教的なもの」を求め、「宗教的な生きかた」を望んでいるという話をしたいのです。
それは、オタク文化を単に「性」と「快」の文化と見る見方をする人たちから見れば、意外な、あるいは不快ですらある見方でしょう。
ですが、オタク当事者にとってはいままでわたしが話して来た内容はある程度の納得がいくものなのではないでしょうか。
オタクは、自宅の一室で、あるいは映画館で、コンサートホールで、推しにヒエロファニーを視ます。宗教的人間(ホモ・レリギオスス)としての聖なる体験です。
それを具体的に言語化できる人ばかりではないでしょうが、とにかくオタクの宗教的情熱は偽りのないものなのです。わたしはその由来をなるべく的確に言葉にしたい。
③「人はなぜ非合理的なものを求めるのか」
ここまで、オタク文化のスピリチュアルな一面について語ってきました。
科学合理主義が骨身に染みている人のなかには、こういった文化を取るに足らないもの、ばかばかしいものに過ぎないと却下してしまう方もあるかもしれません。
じっさい、スピリチュアルな文化がすべて高尚だったり崇高だったりするわけではありません。むしろ、その反対のものが膨大に存在するのが実態です。
科学的であったり合理的であったりすることを誇りに思う人から見れば、こういった世界は世にも愚かしい信心と迷信の世界と思われてもしかたないでしょう。
特にいわゆる「スピ本」は、ただそのタイトルを眺めただけでも、非現実的な誇大妄想としか思われないものが少なくありません。大天使ミカエルとか宇宙人バシャールとか、常識的には信じがたい世界です。
ただ、それはそれで、わたしたちのこの世界を説明しようとするひとつの「世界観」を形成しています。
あたりまえの価値観ではなかなか受け入れられない話ではありますが、主流の科学とはまた異なるかたちでひとつのナラティヴを成しているのです。
わたしは基本的には科学の成果を信頼する立場に立ちます。何といっても、科学には間違いを検証するためのシステムが備わっているからです。
科学においては、ひとつの事実は、単に権威や受賞によって正しいと認められるわけではなく、幾度もの実験によるファクトチェックを経て、初めて認知されます。
あるいはそのファクトチェック自体が怪しく、批判の余地を残す分野もあるでしょうが、それでもスピリチュアルと比べるとその実証性は格段に違うはずです。
だから、わたしは科学を「信じ」ます。
一方で、第一章で「世界の未規定性」について語ったように、帰納的に事実を集め検証する科学の方法論では「絶対」はありえません。
いま、事実とされていることもいつかどこかで覆される可能性は皆無ではないのです。
それでも、科学の方法論は信頼に値します。否、むしろ、ひとつの事実を何度となく覆し、より精密に検証していこうとするそのダイナミズムこそが科学なのでしょう。
科学は必ずしも世界について明確な真理を示してくれるわけではありません。ですが、それはより正確な世界像を求めて動的に探索しつづけるのです。その素晴らしさ。
しかし、それでは、この世のおおよそのことは科学を頼りにしていれば解決するのでしょうか。
人生の数々の問題に悩む人々は、じっさいのところ、科学の方法論を理解するだけの知性と合理性に欠けているだけなのでしょうか。そうではないでしょう。
そもそも、この世はほんとうにすべて合理的にできているのでしょうか。
もちろん、近代科学の成果をまさに宗教のように信奉する立場に立てば、世界に不思議なこともないし、理不尽なことも何ひとつないことになります。
すべてがひとつの精妙な時計仕掛けのように計算通りに動いているわけです。
つまりは、本来はこの世に不思議などなく、謎と不思議を生み出しているのはただ人の無知だということになる。
それは一面で正しい見解かもしれません。わたしたちがいま、どんなに巧みなマジシャンの手品を見ても魔法だと思い込んだりしないのは、そこに「種も仕掛けもある」ことを予想するからです。
つまり、単に自分たちの無知ゆえに不思議に見えるのであって、じっさいにはそこには不思議は存在しないと認識しているわけです。
そしてじっさい、マジシャンたちは本物の魔法使いなどではなく、そこには何らかのトリックがある。
わたしたちが不思議だと感じるあらゆることに同じことがいえるでしょう。
自然科学の世界では、どんなに壮大な謎も、いってしまえば単に自然が仕掛けたトリックに嵌まっているだけであって、もし人間が十分に賢ければ、そこに謎など存在しなくなると考えることと思います。
そう考えていくと、どんなに不思議だったり、不条理に思われることも、ただ認識の不備からそう思われるだけだという結論が出ます。
しかし、同時に、人が決して無知や誤謬から逃れられないことも事実です。もしはるか高みから地上のすべてを見下ろす「神の視点」に立つことができれば、この世のすべての出来事を深く納得して受け入れることも可能かもしれません。
ところが、ひとたび「地を這う蟻の視点」に立つとき、世界はまったく違う姿を見せます。
一匹の蟻にとって、世界はどこまでも未知と困難と理不尽に満ちています。神の目で見ればこの世に未知はないわけですが、蟻にとってはまったく違います。
次の瞬間に何が起こるのか、蟻にはまったくわからないし、たとえ「合理的に」起こった出来事であっても納得がいかないことがしばしばです。
蟻にはものごとがいかにして起こるか理路を把握しきることはとても不可能なのです。
そして、人はやはり神より蟻に近い状態で生きています。
たしかに、サイエンスの目は神の視座に近いところにあるでしょう。それは大宇宙の神秘をも解き明かしますし、人間を苦しめる病理のメカニズムも鋭く解明できます。
科学の恩恵によって人は蟻の身分から脱して神に近づきました。
ですが、それでも、科学は、なぜ「このわたし」が苦しまなければならないのか、その究極の理由を説明し切れません。
たとえばあなたが難病にかかったとしたら、科学は確率の問題だと冷たく告げるでしょう。
科学の論理では、それはまったく正しいアンサーです。しかし、じっさいに生き、苦しんでいる人間はなかなかそういった答えでは納得し切れません。
べつのだれかでも良かったはずなのに、他ならぬ「このわたし」がその苦しみを受けなければならない理由は何か、人は求めつづけずにはいられないのです。
ビッグ・クエスチョン。
科学とは再現性によって成り立つ学問だとされています。
ある人が見出だした事実を、他の人が再現して確認することができる、それが科学の客観性を成立させているのだと。
ですが、ある個人の人生に再現性などなく、すべてただ一回きりです。
故に、科学は、たとえ「神の視点」に近いほど高みに立つことができるとしても、一匹の蟻を救えません。神の目から見た答えは蟻を納得させられないのです。
だから人はどこまでも悩みます。いったいなぜこの自分がこうした運命を甘受しなければならないのか。その答えを求めて哲学書や文学書を開く人もあるでしょう。それらは、ある程度は問いに答えてくれるかもしれません。
偉大な碩学や詩人は、人生についての素晴らしい洞察を教えてくれるでしょうし、そこに純粋な合理性で割り切れない人間心理に対する共感も見いだせることでしょう。
たとえばプラトンやシェイクスピアを読むとき、わたしたちはそこに不変の人間の姿を見、心なぐさめられます。とはいえ、やはり倫理学でも抒情詩でも解き明かせない人生の謎は残るのです。
「なぜこのわたしだけがこれほど苦しまなければならないのか」。
「なぜ世界はこれほど理不尽にねじ曲がっているのか」。
いったんそう考えはじめたらその思考迷路から抜け出すことは困難です。そしてそのようなときにこそ、人は活路を求めて宗教の門を叩きます。
何か辛い目に遭ったとき、苦しい出来事を経験したとき、たとえば「すべては神の御心」なのだと信じられれば、それで何もかも癒やされることはないとしても、少しは納得がいくからです。
そのようにして宗教は数知れない人々に救済をほどこしてきました。その、人生の圧倒的な無意味さに強靭な意味をあたえる機能の偉大さはどれほど強調しても足りません。
仮にすべての宗教がまったくでたらめな妄想に過ぎないと認めるとしても、その妄想によって救われた人たちはたしかに存在するわけなのです。
しかし、長い年月を経て、大きく変化した社会をまえに、伝統宗教のリアリティは弱くなっています。
もはやアダムとイヴが楽園を追放されて人類の祖先になりましたといったナラティヴが中世ほどのリアリティを持たないことは必然でしょう。
そこで、人はスピリチュアルを求めることになります。
それは「神の視点」で見るとき、いかにも非合理です。ですが、伝統宗教と同じく、「蟻の視点」で見たなら苦しい人生に癒やしと救いをもたらしてくれることもあるのです。
わたしはマクロな問題に対しては科学的合理性で答えを出していくことを支持しますが、一方でミクロな人生の問題に対しては、たとえば星占いなどで決めてしまうことをあざ笑うつもりはありません。
人の心に「聖なるもの」を求める働きがあるかぎり、そういったスピリチュアルな文化は絶えないでしょうし、じっさいに心の支えになることもあるからです。
そもそも純粋に合理的な人間がありえるとして、その人が幸福だとは限らないでしょう。人間がどれほど合理的に行動したとしても、人生のほうは合理的に進むとは限らないのです。
その意味で、何らかのスピリチュアルな支えが必要な人は少なくないでしょう。ただ、スピリチュアル市場にならぶ「商品」の質は玉石混交です。
そこで何かしらの「道しるべ」が必要になります。二流三流のスピリチュアリティに騙されないためにこそ、自分のなかに何らかの「神聖なもの」の道標がなければならないわけです。
④「人類は宗教を離脱するのか」
ここまで書いた来たようなスピリチュアルな文化には当然、大きな批判があります。
じっさい、それらは詐欺や、そこまで行かないとしてもダーティーなビジネスの温床になっている一面があるでしょう。
また、ひとつスピリチュアルのみならず、宗教全体を批判する人もあります。
かつてアメリカで宗教批判の中心と目されていたのが「新しい無神論の四騎士」と呼ばれた四人の論客です。
いうまでもなく聖書黙示録の四騎士から採用された異名ですが、かれらは神への信仰に終わりをもたらすべくあらわれた騎士と目されたのです。
そのなかでも日本で知名度が高いのは『神は妄想である』で知られるリチャード・ドーキンスでしょう。
ドーキンスはまた『利己的な遺伝子』でも高名であり、世界的にその名を知られている人物です。
かれはこの本のなかで徹底して宗教を攻撃しています。その態度は冷笑的かつ攻撃的で、いったい宗教に何の恨みがあるのかと思えてしまうほど。
とはいえ、その、どこまでも徹底して「科学的」に宗教を否定する態度には反論できないと感じた人も少なくないに違いありません。
しかし、ドーキンスの思想や行動には根強い批判があるのです。それは単に伝統宗教から発せられているにとどまりません。
たとえばフェミニストはドーキンスの男性中心的な態度にいらだちを隠しませんでした。
ドーキンスは理性を至上の価値とみなしながら、じっさいにはわかりやすく性差別的な態度を取りつづけました。
より具体的には、男性を理性的と捉え、女性を感情的な生き物だと考えるという、それこそ「非理性的」な思想がその背景にあることが指摘されています。
また、ドーキンスはしばしばイスラム教を強く攻撃しますが、それもまた明確な根拠のないイスラモフォビアであり、本来、政治に理由があるにもかかわらず宗教を原因視する態度を崩さないことも批判されています。
理性を重視するドーキンスの姿勢は、見かけほど理性的なものではないのです。
たしかに、理性と科学を尊重することそのものは素晴らしいでしょう。しかし、口先で理性的であれということと、じっさいに理性的に振る舞うことは異なります。
ドーキンスを初めとする「無神論の騎士」たちのマッチョな論理が批判を浴びるのは、決して頑迷な宗教論者が非理性的に文句をいっているだけのことではありません。
じっさい、ドーキンスの論理展開は強引で、科学的でも理性的でもないことを指摘する人もいます。
『神は妄想である』のロジックを批判した一冊に、A・E・マクグラス及びJ・C・マクグラス『神は妄想か?』があります。
科学者でありキリスト教徒である著者がドーキンスの説を批判的に検証した本で、ドーキンスがどのように議論を誘導しているか、ていねいに検証しています。
マクダラスはキリスト教徒としての立場から「宗教の幼稚さ」、「非合理性」を指摘するドーキンスのほうにこそ非合理性があることを検証します。
マクダラスによれば、神なるもの、宗教的なものを批判するドーキンスの態度は多くの誤謬を犯しているのです。
ドーキンスは宗教を否定したいあまり、恣意的に証拠を持ち出して攻撃することをためらわないようになっているといいます。
このマクダラスの意見は単に古い宗教的な人間が最新の科学に対し無謀な勝負を挑んでいるだけでしょうか。そうは思いません。なぜなら、マクダラスもまた科学の言葉をもちいドーキンスを批判しているからです。
マクダラスはひとりの敬虔な宗教者ですが、同時に科学の効果を信じてもいます。
かれは『神は妄想である』の内容がとうてい「合理的」とはいいがたいと主張するのですが、それは科学的な理由に依っているのです。
マクダラスによれば、科学を賛美するドーキンスこそが、科学的とはいいがたい態度によって無神論を「信じ込んでいる」に過ぎません。
これはひとりドーキンスのみならず「新しい無神論」そのものに対する効果的な反撃といえるでしょう。
あきらかにドーキンスを初めとする多くの無神論者たちはただ「神を信じない」ことを選ぶだけではなく「信じたくない」と考えているからです。
それは無神論の立場こそが知的であり、理性的であるという「信念」に留まりません。
信仰を持っている人たちは自分たちのような「目覚めた人間」に比べ、より幼稚で非理性的であるという傲慢な考えかたにまで至っています。
まるで一部の宗教の原理主義者のように頑迷な「信仰」ではないでしょうか。
そういった信念を持つことは自由ではあります。しかし、その信念もまた一種の信仰に過ぎないという自覚は持つべきでしょう。
自分たちの信仰だけは特別に客観的かつ論理的なのだという意見は、マクダラスが書いているように根拠がありません。
また、ドーキンスは宗教が一般に非倫理的なものであると攻撃していますが、マクダラスは聖書の「善きサマリア人」の喩えなどを持ち出して反論しています
わたしはマクダラスのほうが冷静で「科学的」な議論を展開していると感じます。
宗教とは、人の想像力の結晶です。宗教の物語では往々にして太古に神が人を生み出したとされていますが、むろん真実は異なります。
人こそが、神を生み出したのです。そして、人はみずから生み出した神によって導かれてきました。神なるものは人の生き方の指針となったのです。
「おてんとうさまが見ている」といういい方がありますが、どこかで神さまが見ているという意識は人を善なる方向へ導きます。
もちろん、それですぐに人の心根が善良になるはずもありませんし、じっさいにそうはなりませんでした。ですが、少なくともそれは宗教の持つ善なる側面ではあります。
宗教がなくなることは「おてんとうさまなど見ているはずもない」という世界観で生きることです。
それでも人は善良さを失うことはないでしょう。しかし、必然的に不安定な一面を抱え込まざるを得ません。
それは現代社会を見ていればわかることではないでしょうか。
結局のところ、いつか人類は宗教を離脱するのでしょうか?
もちろん、完全に宗教が喪われることはないでしょう。ですが、この先の時代、いまよりもっと宗教文化がリアリティを喪失していくことは間違いありません。
一朝一夕にすべてが変わっていくわけではないにしろ、宗教の影響力は低下していくことでしょう。
しかし、ここまで縷々述べてきたように、「宗教的なもの」が消失してしまうことはありません。
したがって、わたしたちは「宗教的なもの」への想いを抱えたまま、「宗教なき時代」を生きていかなければならないことになります。
それは宗教が倫理や生きかたの指針を示してくれない時代です。
宗教がなくても倫理は問題なく働くと思われるかもしれません。
しかし、ドストエフスキーが「もし神が存在しないなら、すべては許される」と書いたように、宗教がないということは「絶対的な指針」が存在しないということです。
わたしたちはいわば羅針盤を失った船に喩えられます。現代社会という荒海で、何らかの「神なるもの」を求めたくなるのは必然ではないでしょうか。
そういった時代性を背景に、オタク的な推し文化が繁栄を究めていることもまた、ある種の必然と思われます。
推し活とは、しばしば失われた「絶対」をそこに見いだそうとする儚い努力なのです。
オタクはしばしば「善きもの」の指針を推しに求めます。いい換えるなら、推しを基準に「何が善いことなのか」判断するともいえるでしょう。
それは長く困難の多い人生において、人を善い方向へ導いてくれると思います。
もちろん、絶対的な指針などなくても人は生きていけます。
しかし、「人はパンのみにて生きるに非ず」。「ただ生きているだけ」の人生で、人はどうしても空虚感を抱え込むことになるのです。
いったい何のために生きているのか。自分が生きていることに何の意味があるのか。そういった、答えの出ない問いを抱えることもしばしばでしょう。
そのような「実存的空虚」の解決はむずかしいものがあります。簡単なロジックで解き明かせる問題ではないからです。
ある人は恋愛に解を求めるでしょう。またある人は仕事に夢中になるかもしれません。その虚ろな胸をいかにして埋めるか、人はさまざまに試行錯誤します。
そしてまたある人は、エンターテインメントに、ポップカルチャーに「神なるもの」を見いだします。
そのとき、人は熱狂的なオタクになる。「オタク・スピリチュアリティ」とはそういうことです。
ポップなオタク文化は、猥雑と享楽、そして快楽を求めるポルノ的な文化に過ぎないように見えるかもしれません。ですが、それが猥雑であればこそ、その混沌のなかで人は神聖なものを求めるのです。
泥沼に可憐な花が咲くように。
⑤「この世に不思議は残されているのか」
じっさいにそうなるかどうかはともかく、このまま科学進歩と経済発展が続いていけば、宗教のような非理性的な教義はいつか消滅すると考える人は少なくないでしょう。
社会学ではそういった考え方を「世俗化理論」と呼びます。
いまを去ること100年以上前に、そのような反宗教的な言説に真っ向から反対したのが、作家であり詩人であり、敬虔なクリスチャンであったG・K・チェスタトンです。
シャーロック・ホームズと並ぶ名探偵ブラウン神父の生みの親として知られるチェスタトンは、その代表的な小説作品も含め、「逆説」の名手として知られています。かれはしばしば、常識をくつがえす逆転した論理で真実を指し示しました。
ただ、チェスタトンの逆説とは、単に奇を衒ってみせることではありません。むしろその反対です。チェスタトンにとって、逆説とは「あたりまえのこと」とみなされるようになってしまった真実の価値をあきらかにするための方法論でした。
かれは一貫して「正統」の立場に立ち、科学による精神の堕落を批判します。その逆説はきわめて強烈です。
チェスタトンの「正統」と「逆説」の思想についてよくわかるのが、最近、文庫化された『正統とは何か』です。
ここでチェスタトンは宗教の立場から科学を批判しています。キリスト教の伝統に乗っ取り、進化論を信じなかったというチェスタトンは、いまではいかにも無知な人物に見えるかもしれません。
しかし、かれの科学批判は、非常に本質的です。『正統とは何か』を読んでいると、むしろ科学を批判するチェスタトンのほうこそが科学精神の体現者に思われて来るくらい。
かれが批判しているのは、じつは科学そのものではありません。
この世に満ち満ちたさまざまな「不思議」をまえに驚嘆することを忘れ、何もかも「あたりまえのつまらないもの」と看過してしまう「堕落した科学精神」こそが主な批判対称なのです。
チェスタトンは不思議と魔法を擁護し「堕落した科学精神」を攻撃します。
ところで、詩人の金子みすゞに、「不思議」と題する有名な詩があります。こんな内容です。
私は不思議でたまらない、
黒い雲からふる雨が、
銀に光っていることが。
私は不思議でたまらない、
青い桑の葉たべている、
蚕が白くなることが。 私は不思議でたまらない、
たれもいじらぬ夕顔が、
ひとりでぱらりと開くのが。 私は不思議でたまらない、
誰にきいても笑ってて、
あたりまえだと、いうことが。
チェスタトンが一貫して擁護するのは、この「誰にきいても笑ってて、/あたりまえだと、いうこと」を「不思議でたまらない」と感じる精神です。
そもそも、不思議とは何でしょう。先述したように、それはようするに、人間の無知から来ている感覚なのではないでしょうか。
ゆえに、常識的に考えれば、神の視点から見ればこの世に不思議などないという答えが出て来ます。
ですが、チェスタトンによれば、ほかならぬ神こそが、だれよりも最も世界の不思議に驚嘆しているものなのです。
太陽が毎日昇り、降りるのはなぜか? チェスタトンは答えます。それは神が無垢な子供のように太陽の昇降に驚きを感じている証拠なのだと。
かれの考えかたでは「あたりまえ」とされるものごとは、じつはちっともあたりまえではありません。
「黒い雲からふる雨が、/銀に光っていること」ことや、「青い桑の葉たべている、蚕が白くなること」や、「たれもいじらぬ夕顔が、/ひとりでぱらりと開く」ことが、ほんとうはまったくあたりまえではなく、とても「不思議」なことであるように。
チェスタトンは「平凡」や「あたりまえ」とされ、その価値を見過ごされていることごとについて注意を喚起します。
平凡なことは非凡なことよりも価値がある。いや、平凡なことのほうが非凡なことよりもよほど非凡なのである。人間そのもののほうが個々の人間よりはるかにわれわれの精神を引き起こす。権力や知力や芸術や、あるいは文明というものの脅威よりも、人間性そのもの奇蹟のほうが常に力強くわれわれの心を打つはずである。あるがままの、二本脚のただの人間のほうが、どんな音楽よりも感動で心を揺すり、どんなカリカチュアよりも驚きで心を躍らせるはずなのだ。死そのもののほうが、餓死よりもっと悲劇的であり、ただ鼻を持っていることのほうが、巨大なカギ鼻を持っているよりもっと喜劇的なのだ。
こういった考えかたこそがチェスタトン一流の「逆説」であるわけですが、それはつまり「堕落した科学精神」への痛烈な批判であると同時に「真の科学精神」の擁護でもあるといって良いでしょう。
「黒い雲からふる雨が、銀に光っていること」といった、一見、「あたりまえ」とされることを「不思議」と感じ、「いったいなぜなのだろう?」と解き明かしていったことこそが本来の科学だからです。
問題は、そうやって解き明かした結果、「不思議」だったはずのものは「あたりまえ」になるということ。
科学はそうやってどんどん新しい「不思議」を求め「あたりまえ」の領域を増やしていくのですが、その結果、生まれるものは「何も不思議なことなどない」というすこぶる退屈な世界なのではないでしょうか。
いや、最先端の研究者たちは、あいかわらず巨大な「不思議」に挑戦しつづけることができるかもしれませんが、大多数の一般人は「何も不思議なことなどない。すべてはあたりまえのことばかり」という世界観に安住することになります。
あるいは、それが「大人」なのかもしれませんが、その世界観はどうしようもなく退屈です。
チェスタトンの立場はまったく異ります。かれによれば、この世は「不思議」に満ちていて、「あたりまえ」のことなど何もないのです。
では、なぜ卵は鳥になり果実は秋に落ちるのか、その答は、なぜシンデレラの鼠が馬になり、彼女のきらびやかな衣装が十二時に落ちるのか、その答えとまったく同じである。魔法だからである。「法則」ではない。われわれにはその普遍的なきまりなど理解できないからである。必然ではない。なるほど実際には必ず起きるだろうと当てにはできるが、しかし絶対に起こらねばならぬという保証はまったくないからである。
このような論理展開を、つまらない屁理屈、科学に対する侮辱だと感じるでしょうか。わたしにいわせれば、このような考えかたこそ真に科学的です。
科学に「絶対」はありません。科学は帰納法的にさまざまな事実を集め、そこに一貫した「法則」を見いだしはします。
しかし、それは「絶対」の真理などではありえません。その事実が科学の根幹にあります。
つまり、世界のすべては「魔法」なのであって「絶対の法則」などありえないとすることもまた科学的態度なのです。
科学が「法則」と呼んでいるものは、その実、不思議な不思議な魔法である。その事実を忘却することこそが科学を退屈にします。科学の堕落です。
人は幼い頃、だれもが現実世界のひとつひとつに驚きます。幼い子供によっては、ただ川に流れていることでも大いなる脅威です。
しかし、歳を経るとその驚きをふたたび感じるために「ファンタジー」を必要とします。
つまり、すべてのファンタジーはリアリズムのワンダーを思い起こさせるために存在しているのです。そして、科学もまたそういうファンタジーのひとつなのです。
わたしなりにチェスタトンの言葉を理解するとそういうことになります。
かの『ナルニア国ものがたり』の作家ルイスはチェスタトンの影響を受け、また『スター・ウォーズ』の構成はその『ナルニア』を反映しているといいます。チェスタトンの影響は、その「正統」の精神とともに、いまなお生きているのです。
さて、『スター・ウォーズ』といえば、国勢調査で自分の宗教を「ジェダイ」と回答する動きが話題になったことがありました。
ご存知のことと思いますが「ジェダイ」とは『スター・ウォーズ』のなかで「フォース」を使いこなす善の側の騎士たちを指します。つまり「ジェダイ教」というべき新たな宗教が生まれたと考えることができるのです。
そうはいっても、もちろん、これらはある種のちょっとしたジョーク、それこそオタク的にアイロニカルな意見に過ぎないでしょう。
「ジェダイ教」の「信者」たちが『スター・ウォーズ』の熱烈なファンであること、また、ジェダイの教えに何かしらの生きる指針、道徳の基盤を見いだしていることも事実かもしれませんが、だからといって日常をジェダイ的に生きている人は少数派に留まるはずです。
「ジェダイ教」は、宗教のようなものかもしれませんが、宗教ではありません。
しかし、そう認めるとしても、単なるエンターテインメントであり、ポップカルチャーにおけるひとつのヒット作に過ぎないものが、宗教的に受け入れられている事実は興味深いものがあります。
無宗教の『スター・ウォーズ』ファンの人々は『スター・ウォーズ』のなかに自分を教え導く「宗教的なもの」を見いだしたのかもしれません。
そういうことは『スター・ウォーズ』以外の作品でもよくあることのはずです。
そしてそういった作品たちがほんとうの意味で興味深いものでありえるかどうかは、そこにチェスタトンがいうところの「ファンタジー」の精神、つまり「真の科学精神」が宿っているかで決まるでしょう。
チェスタトンがいうように、この世は魔法に満ちていて、不思議なことばかりです。
さまざまな物語たちは、わたしたちにそのことを思い出させてくれます。それが、本来、あらゆる「スピリチュアリティ」の根底にあるべき、センス・オブ・ワンダーの精神なのです。
⑥「聖なるもののデカダンス」
この章の最後に「スピリチュアルなもの」、あるいは「宗教的なるもの」が惨禍を巻き起こす忌まわしい例について触れておきたいと思います。
オウム真理教事件です。
日本中に衝撃と戦慄をもたらし、オウムの名を知らしめた地下鉄サリン事件も、すでに30年近く前のことになりました。いまの若い読者はオウムについてくわしく知らない人のほうが多数かもしれません。
この本の目的はオウムや新宗教を語ることではありませんから、この節で触れるのはその詳細ではありません。ですが、人はなぜスピリチュアリティを、あるいは「聖なるもの」を求めるのか。
そして、いったんその歯車が狂ったときどうなってしまうのか。オウム真理教がひき起こした一連の事件は、いまなお、わたしたちに多くのことを教えてくれます。
海外には同程度かそれ以上の規模の宗教テロ事件もありますが、少なくとも国内においては地下鉄サリン事件は空前の(そしてまた絶後であってほしい)大事件です。
その犠牲者はいまでも苦しんでいるにもかかわらず、オウムとは何だったのか、完全に総括されたとはいいがたいでしょう。
将来にわたってもオウムが語り尽くされることはないかもしれません。ここではオタク宗教としてのオウムの一面について触れておきたいと思います。
いまとなってはオウムとオタクがいったい何の関係があるのかと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、オウムはじっさい、オタク的な側面をあまた持ち、その布教にはアニメが使用されたりしていました。
その荒唐無稽さはオタク的には失笑ものではあるものの、それでもオウムのオタク的な濃さは「おたくの連合赤軍」と呼ばれたくらいなのです。
オウムの背景には、あきらかにオタク世代のニヒリズムがありました。その根底となっている実存的な不安感について、ここでは地下鉄サリン事件ののち、オウムを脱会した高橋英利の著書『オウムからの帰還』に典型を求めてみます。
幼い頃、高橋は自分が暮らしていた団地の外へと「ちょっとした冒険」を試みます。
ところが、その冒険は思わぬ結末にたどり着くのです。はらはらどきどきの時間の末、ようやく自宅にたどり着いたはずのかれは「べつのお母さん」と出逢ってしまうのです。
じつはかれはいつのまに自分が住んでいたのとはべつの団地に迷い込んでしまっていたのでした。
ただそれだけのことではあるのですが、このことは高橋の心のなかに深刻な問題を残します。
かれは書いています。
「 なぜ、僕はあの団地のあの女の人の子どもではなかったのか。なぜ、この団地のこの母さんの子どもだったのか。母さんが僕の母親でなければならなかった理由とはなんだろうか……。考えれば考えるほど、母さんが僕の母親である必然性がわからなくなっていった。(中略) もちろん、まだ幼かった僕がこんなふうに明確に意識していたわけではないが、自分の存在が「必然」ではなく「偶然」でしかないということを、感覚としてかかえこんでしまったのだ。自分の存在に対する漠然とした不安というものを初めて感じたのが、このときのことだったと思う。この不安感はその後もずっと消えることなく、僕の意識の奥底にこびりついてしまうのである。」
ここで高橋は、すべてが偶然でしかなく、何が起こってもおかしくないという世界の無根拠さ、つまり宮台真司がいうところの「前提を欠いた偶然性」を幼少にして戦慄とともに実感したわけです。
この世のすべてのものには「そうであらねばならない」とする根拠がない、ただの無意味な偶然の集積でしかない。人間にとってこれ以上の恐怖があるでしょうか。
たしかに「ぼくのお母さん」であるはずの人が、ひょっとしたら「べつのお母さん」であったかもしれない、それが唯一の論理的必然なのだとしたら、わたしたち人間の生もまた単なる偶然の連鎖のそのひとつ以上のものではないことになるのですから。
宮台が語るように宗教が「前提を欠いた偶然性」を社会的に馴致する装置であるとするなら、高橋がオウム真理教に惹きつけられることは必然でした。
わたしはこのエピソードから、栗本薫の短編小説「顔のない街」を思い出します(『伊集院大介の新冒険』収録)。
名探偵伊集院大介シリーズの一作で、大介がそのずっと後になってかれの助手を務めることになる滝沢稔と出逢う印象的な物語です。
この小説ではある団地にやってきた伊集院が、ひとつの殺人事件について推理します。推理小説のネタバレを行うのは禁じ手かもしれませんが、ここではあえて触れてしまいましょう(どうしてもネタバレを読みたくない人はこの節は飛ばしてほしいです)。
じつはその団地で起こったことは、まさに高橋が遭遇した「ちょっとした冒険」の顛末と同じ構造であったのです。
つまり、この事件で殺害された人物は「まったくの間違い」によって殺されてしまったのでした。
伊集院は事件について語るとともに、この「顔のない街」で、人々が「顔のない暮らし」、つまり交換可能な人生をしか送っていないことを嘆き、幼い滝沢稔に語ります。
「ぼくはね。稔くん」
伊集院大介はそっと云った。それはさながら空の向こうからきこえてくる優しい風の声のようにぼくの耳にひびいた。
「みんなに自分の顔を返してあげたいんだよ。――町にも、世界にも。人間たちにも、ね……そのためにぼくはこの町にやってきたのかなあと思っているんだ。この町で君にあえて本当によかったと思っているよ」
「ぼくはこんなとこに長いこといないよ。いるもんか」
「それはいいんだ。これは新しい町だから――だけどぼくが心配しているのは、この町だけじゃなく、世界が――」
どうでしょう、高橋の体験を踏まえれば、伊集院大介がいおうとしていたことはわたしたちにもよく伝わって来るのではないでしょうか。
途中で切り取られた「世界が――」という言葉は、「世界が顔を失おうとしている」ということに違いありません。
その「顔」という言葉からエマニュエル・レヴィナスの哲学を思い出す方もあるかもしれません。
ここでいう「顔」とは、つまり、その人を人間にしている本質そのものです。
本来、すべての人間は「顔」を持っています。さして独創的とはいえないかもしれないにせよ、その人固有の人生と苦悩とを備えていのです。
しかし、可能なかぎり画一化された人間を生み出そうとする管理社会においては、その悩みすら、その苦しみすら、オリジナルなものとはいえなくなっているかもしれないのです。
たしかに世界はそもそも「偶然性」に満ちています。しかし、それでも、ほんとうならこの世で「まったくの偶然に」出逢った人と人は絆を結ぶことができるはずです。伊集院大介と滝沢稔がそうしたように。
ですが、「顔」を持たない、あるいは奪われた人間たちにとっては、その紐帯は不可能なものなのです。
高橋は間違いなく「ぼくのお母さん」であるはずの人が「べつのお母さん」であったかもしれないという偶然の可能性に恐怖しましたが、もし、かれがその偶然に確固たる価値を見いだせていたなら「ぼくのお母さん」の「顔」が代替不可能なものであると認識していたなら、状況は変わっていたかもしれません。
すべては偶然であり、代替可能である。オタク世代のニヒリズムはそこに原因があります。
そして、しばしばオタクたちはその恐怖を、自分と他者の「顔」をしっかりと認識することで乗り越えるのではなく、ただ笑殺しようとすることでごまかそうとします。
オタクの冷笑主義の最も悪しき一面です。そのとき、オタク的な態度はまったく効果を表さないばかりか、最悪の結果につながる可能性を孕みます。
多くのオタクたちはいまなお「笑い」によってたとえばスピリチュアルを批判することを躊躇しません。
オタクの歴史を研究している吉本たいまつが「おたく文化とスピリチュアル ~「笑い」の政治性~」(『サブカル・ポップマガジンまぐまvol.16』収録)で指摘しているように、そこには権力性と暴力性がともないます。
ある意味では、かつて、オタクたち自身がそうされたことを立場を変えて行っているに過ぎないわけです。
それはひとりひとりのオタクの主観としては「権力に対する反抗」ですらあるのかもしれません。しかし、いまやそれははっきりと「権力にもとづく暴力」と化しています。弱いものいじめなのです。
わたしから見れば、そのような権力にもとづく搾取的、暴力的な行為が何ら安全弁となりえないことはいまとなっては自明に思えます。
ですが、はるかに弱くなったとはいえ、いまなおオタク文化はその種のシニカルなニヒリズムに安全性を期待している部分はあるでしょう。
先にも述べたようにオウム真理教はそういったシニシズムの限界を示しているのですが、オタクはこの事件を「他人ごと」として処理してしまいました。
しかし、たとえば竹熊健太郎が『私とハルマゲドン―おたく宗教としてのオウム真理教』で書いているように、オウムとオタクは同じ時代が生んだべつの可能性であるに過ぎません。
オウムにはオタク的な一面があり、そしてオタクのなかにもオウム的なものはひそんでいます。
聖なるものの堕落と頽廃を極限まで突き詰めるとオウム真理教が生まれます。それは、多くの人々からあたりまえの「顔」が奪われた時代の「オタク的な」ニヒリズムの結晶です。
オタクは、どのようにすればその虚無主義を乗り越えられるのでしょうか。この先の論考のテーマとして考えてゆくこととしたいところです。
第三章「異教を信じる人々」
月の影法師を
チョークで囲んだら
それは宇宙の魔法陣
風のシルフィや大地のグノメ
火のサラマンデル水のオンディーヌ
精霊を呼ぶ 松任谷由実『78』
①「世界境界とオタクの絶対倫理」
オタクは長い間「現実と虚構の区別ができない」人種として非難されてきました。
オタクの虚構に対する「アイロニカルな没入」は、「現実と虚構を混同している」証拠とみなされたのです。
現在もなお一部のフェミニストなどからその種の批判が飛んで来ることがあります。しかし、これは不当な誹謗というべきであり、じっさいにはむしろ、オタクは「一般人」よりもっと強く「現実と虚構は厳然と区別されなければならない」とする倫理を抱いています。
その倫理性を具体的に表す言葉が「中二病」です。
Wikipediaによれば、中二病とは「(日本の教育制度における)中学2年生頃の思春期に見られる、背伸びしがちな言動」を自虐する語。転じて、思春期にありがちな自己愛に満ちた空想や嗜好などを揶揄したネットスラング」を指します(https://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%AD%E4%BA%8C%E7%97%85)。
つまりはある種の「身の程知らず」を揶揄し嘲弄する表現であるわけですが、オタク的にはフィクションからの影響を現実社会において直接に態度に表すことを問題視する意味もあります。
フィクションのヒーローはかっこいい。しかし、「現実の自分」がヒーローのように振る舞うことはかっこ悪い。中二病にはそういう含意があるわけです。
それは、個々の物語を「あくまでフィクションであって、現実とは違う」ものとして処理する大切さを意味する言葉でもあります。
オタクにとって、中二病を避けることはひとつのモラルです。とはいえ、オタクである以上、どこかに中二病的嗜好とのアフィニティはあります。
たしかに中二病的な態度はいかにも幼い。自己中心的かつ自我を増大させすぎている。
一般的にいえば、そのような誇大化した自我を捨て「世界を救う」とか「この世を滅ぼす」といった誇大妄想を断念し、社会的に受け入れられるサイズの自分として成長していくことが「成熟」のルートではあるでしょう。
ですが、そもそも、そういった要素の一切を単に「幼稚」で「くだらない」ものとして切り捨てられるなら、初めからオタクなどならないのです。
大半のオタクは、たとえばあたりまえの会社員をしながら、週末には世界の命運を賭けた戦いを描くアニメに見入ったりするものでしょう。
オタクにとって、中二病的夢想はまったく無縁のものではありません。
ただ、オタクはそれらをいわば「他人ごと」として、自分とは直接に関係のないものとして切断処理することによってかろうじて社会化した「大人」のペルソナをかぶることができるのです。
オタクは中二病を冷笑します。揶揄し嘲弄します。それは一種の自罰行為ですらあるでしょう。
オタクはセックス、アルコール、ゴルフといった「大人」的なカルチャーだけでは決して生きられない人種なのであり、その意味で「永遠の思春期」を生きています。
ですが、かれらはあたかもそのはてしなくループする「中二」を卒業したかのように振る舞うのです。それがオタクにとっての常識、あるいは良識です。
熱狂的なオタクであるとはいわば「在家」の宗教者でありつづけることであり、非社会的な態度を選択することは致命的です。
だからオタクはシニカルに、アイロニカルに「中二病のタブー」を見つめ、自分自身は虚構から何ら影響を得ていないかのような態度を取ります。
「虚構をただの虚構として処理できる」ひとりの一人前の大人であるかのように装います。
しかし、それでいて内心ではあたりまえのつまらない日常を超えた物語にあこがれつづけるのです。
つまりはオタクにとって、現実と虚構という「世界の境界」を踏み越えてしまう中二病はひとつの重大な禁忌であり、蔑視するべき対象であるにもかかわらず、ただ無視するには親和的すぎる存在でもあるのです。
オタクであることは常に中二病と接しつづけることであり、それにもかかわらず決して中二病に走ってはならないとされるのです。
それがオタクが抱えるアイロニーの根源でしょう。その結果、アニメやマンガにおいて「中二病」キャラクターはさまざまにネタにされてきました。
ひとつひとつ、あるいはひとりひとりを語り切れないほど数があるのですが、その一般的な特徴は自分自身をダークサイドの人間として認識し、魔術やオカルト的な文化に耽溺するところにある。
そういった、本来であるなら虚構として処理するべきものを現実にまで持ち込んだ態度は、より年長のオタクから見れば「片腹痛い」ものであり、オタクたちはある種の微苦笑とともに中二病キャラクターを愛玩します。
もう少しわかりやすくいい換えるなら、中二病というオタクにとっての絶対倫理は、オタクが内的な美意識より現実社会に順応することを選択しつづけるための規範です。
「在家」であるオタクたちは、その規範を守りつづける限りにおいて、ひとりの、あたりまえの大人、社会人であることができます。
ですが、わたしは思います。それほどまでに「身の程をわきまえて」社会化することは大切なことなのでしょうか。
たしかに、オタクもまた一般社会で生きている以上、社会への順応は必要でしょう。オタクは現実と虚構の世界境界を越えない限りにおいてオタクでありつづけることができますが、いったんその認識を踏み越えてしまえば、社会的には一種の狂気として処理されることになります。
オタクはそのことを何よりも怖れるからこそ「現実と虚構の混同」を「未熟さ故の病」として戒めます。
とはいえ、たとえば専門のイベントで中二病的なキャラクター(たとえば『コードギアス 反逆のルルーシュ』のルルーシュ・ランペルージ)のコスチュームを着てそれらしいポーズをとることは許されます。
そう考えると、オタクたちの中二病忌避は「虚構の影響を現実に持ち込む」ことを禁じているというより「虚構の影響を一般社会に持ち込むこと」を問題にしているといったほうが正確でしょう。
オタクといえども一面ではあたりまえの社会人であり「社会の常識」をそれなりに尊重して暮らしていかなければならない。だからこそ、一種の処世術として、オタクは中二病を皮肉っぽく忌避しなければならないわけです。
わたしはそこにオタクとオタク文化のひとつの限界を見ないでもありません。それは社会の側から見れば常識的であり、順応的であるだろうが、オタクとしてはどこまでも「妥協」なのではないか。
もちろん、オタクでなくても、だれでもそうやって「妥協」することによって社会生活を送っているわけではあります。一般社会でいちいち「中二病」的に誇大妄想な態度を取っていたら社会人失格というしかありません。
ですが、そうであっても、オタクの「在家」に留まる生き方は注目に値します。オタクたちは、しばしば社会の常識に適応できない存在として「ニート」や「ひきこもり」と同一視され、嘲笑されます。
しかし、じっさいにはオタクは特異な趣味嗜好を持ちながら、あくまで社会的に生きようとする人種なのです。
もちろん、無職のオタクやひきこもりのオタクがいないわけではないでしょう。ですが、オタクにそういった一般社会と断絶しかけた人種が優位に多いと考える根拠はありません。
むしろ、オタクはその趣味を継続するために一定の資金を必要とするため、まったく社会生活を行っていなければオタクでありつづけることはむずかしいのですから、オタクとはどうしても社会との接点を必要とする人種であると考える方が合理的でしょう。
そう、オタクはある種の宗教者とは違って「出家」してしまうわけにはいかないのです。
ただ、この点に関しても注意が必要ではあります。
いうまでもなく、ひと口にオタクとはいっても、その内実は多様です。したがって、一般社会への順応を捨て去り、生活のすべてを趣味に費やしているタイプのオタクがいないわけではありません。
特にアイドルオタクなどは各地で開かれるイベントに参加しつづけるために会社員としての人生を投げうってアルバイトなどを続けている人も見受けられるようです。
そういったライフスタイルは、ある種、かぎりなく「出家」に近いといえるでしょう。
そのような「オタク出家」は、その昔、たとえば西行法師が詩心を究めるために家族をも捨て旅に生きることを選んだことと、べつだん本質的には何の変わりもありはしない。わたしはそのように信じるものです。
ただ、そのようなオタクはやはり少数派に留まりますし、「出家」しかけたオタクでも一定の社会性は備えています。
オタクはカルト的な一面をたしかに持ってはいますが、その一方で社会との距離を平穏に維持しつつ、虚構を虚構として、偶像を偶像として処理する、いってしまえば無害な人種なのです。
問題は、そのような態度がなぜあれほどの「宗教的な」熱狂と両立するのかということです。
次項以降では、オタク的なるものによく似て、しかしどこかで異なる、そのような宗教や文化を紹介しつつ、その点について考えていきましょう。
②「復活を遂げるペイガニズム」
前項では一般的にオタクにとって、虚構とはあくまで虚構として処理し、生活に持ち込まないよう配慮するべき対象であることを書きました。
前章でつらつら書いてきたように、オタクは宗教者とは違って、与えられた物語を「信じ切る」ことはできません。オタクにとって物語はあくまで虚構です。
虚構世界は虚構世界、現実世界は現実世界。その「世界境界」を越えてしまっている文化が即ち宗教やスピリチュアルであり、オタク的なものと宗教的、あるいはスピリチュアル的なものは似て非なる存在なのです。
ひとまずはそういえるでしょう。
しかし、オタクとスピリチュアルがきわめて近い関係にあることもたしかです。
もっとも、オタク文化と同じくスピリチュアル文化も多岐にわたり、その内実はさまざまではあります。
そのすべてがオタク的な一面を持っているとはいいがたいかもしれません。
そのなかでもオタク文化と共通する何かを持っているように思われるものとして、ここでは「ペイガン(異教)」と呼ばれる宗教を挙げておきましょう。
ペイガンとは何か。
それは欧州社会におけるキリスト教二千年の発展と支配のもと、その存在を抑圧され抹消されてきた古代の宗教を指します。
ペイガンは遥かな神話時代に滅び去ったものと見られがちですが、現代においてもそれらを信仰する人びとは実在します。いわばイエスという十字架の神に封じられた太古の尊大なる神々が、二千年の眠りの末に現代によみがえっているわけです。
そういった異教の神々を崇める無数の宗教を、総括してネオペイガニズム(復興異教主義)と呼びます。
その言葉の意味するところは広く、ひと言でいい表すことはむずかしいけれど、ようは土着の非キリスト教的な教理を現代に復活させようとする運動である。
その内実はネオドルイド教であったり、ゲルマン・ネオペイガニズムであったりとさまざまなようですが、とにかく一般的なキリスト教に限界を見、それ以前の宗教に回帰しようとすることが共通しています。
有名なケルト文化なども民族のアイデンティティを求めて復興運動が続いています。
それらの運動は、宗教的な運動がしばしばそうであるように、歴史学的な事実と背反する一面があるようです。
たとえばケルト復興の重要人物である天才詩人イェイツは、歴史的事実をあまり重視しませんでした。かれにとってケルトという言葉で表されるものは、歴史学的な正確さとはそれほど関係のない美しい幻想であったのです。
ケルト復興運動は、その用語的にも、オタク文化ときわめて近いものです。
もちろん、それはオタクのほうがケルトの文化を借用してきたからだし、その種の運動はいずれもごく「まじめ」なものであって、単にオタク文化との表面的な類似だけを問題にすることはできません。
ただ、ここで重要なのは、オタクたちが虚構として消費しているまさにその文化を、物語を、まさに現実として生きようとしている人々が実在することです。
あたりまえのことでしょうか。そうかもしれません。たとえばアトラスの人気テレビゲームである『女神転生』や『ペルソナ』あたりに熱中している人は、それがキリスト教や仏教の教義を「元ネタ」にしていることを知っていることでしょう。
だから、オタク的には自分が「ネタ」として消費している文化を「ベタ」に実践している人々がいることは当然の常識ではあります。
ですが、それでも、アニメやゲームなどで親しんでいる神話的な題材をきょう、フィクションとしてではなくひとつのリアルとして生きている人たちがあることは意外性があるのではないでしょうか。
たとえば、ギリシャ・ローマ神話などは日本のフィクションにおいてメジャーな題材ですが、その信仰そのものは遠い昔に途絶えてしまっています。
その一方で、やはりフィクションとして消費されつづける題材でありながら、はるかな昔に滅びてしまったわけではなく、いまなお信仰されつづける神話や伝説があるのです。
もちろん、こういった異教の伝統は、自然によみがえったというよりは、かなりのところ意図して復活させられたものです。
異教の神々は、キリスト教の伝統のなかで、長い間、邪悪な悪魔とみなされてきました。殊に豊饒の女神たちは淫猥な誘惑者として描写されました。
ネオペイガニズムはそういったキリスト教の物語から古い神々を解放しようとします。そこには、従来のキリスト教の教義に対する反感や、違和感があるのでしょう。
また、アイデンティティや民族意識の問題なども複雑に絡み合っているに違いありません。
だからこそ、信徒たちは自分たちが信じる教えの「古さ」を強調します。ネオペイガニズムの教えはキリスト教よりもっと古い太古から伝わっている伝統あるものであるというわけです。
しかし、じっさいのところ、それはどの程度、そういった「古い信仰」や「伝統」を反映しているのでしょうか。一概にはいえないものの、その実態は相当に怪しいものです。
ネオペイガニズムの信徒たちは自分たちが信奉する神々の前キリスト教的な歴史性を強調しますが、現実にはそのような歴史は作られたものであり、実在しないというのが大方の研究者の意見です。
もちろん、キリスト教に抑圧された古い宗教や神話は存在します。ですが、それらと現代のネオペイガニズムを直線的に結ぶことはできないのです。
そうにもかかわらず、ネオペイガニズムではいまなおその種の歴史が信じられています。かれらにとってその「古さ」はアイデンティティの由来であり、またプライドの根源なのです。
どんなにそれがフィクションに過ぎないと指摘されても、その信仰は揺らがない。そもそも信じるとはそういうことでしょう。
虚構を信じる。
物語を生きる。
それは「虚構を虚構として処理する」ことに、倫理と、ひょっとしたら美学すら抱くオタクとはまったく異なる、真に宗教的な姿勢です。
表層的にはオタク文化とよく似た「虚構を信じる」態度を取っているわけですが、その内実は当然ながらまったく異なっていますし、そもそもかれらは「あえて信じることを選んだ」わけではないのです。
その点はオタク的な「アイロニカルな没入」とはまるで性格が異なっています。
③「くらやみから飛び出た魔女たち」
ネオペイガニズムについて話を続けましょう。
前項で記したようにこういったオカルティックでスピリチュアルな信仰はオタク文化とは一線を画すものですが、だからこそ、オタク文化の特徴を照射してくれるように思えます。
英国にグラストンベリーという土地があります。ここはスピリチュアルな文化を信奉する人にとっての世界的な「聖地」です。そこではさまざまにスピリチュアルなカルチャーが花開き、篤い信仰を集めています。
グラストンベリーという名前を聞き慣れない人でも「アヴァロン」と呼べばああとうなずいてくれるかもしれません。
アヴァロンとはアーサー王伝説における彼岸なる妖精郷のことですが、グラストンベリーこそはそのアヴァロンであるとする説が根強くあるのです。
もちろん、アーサー王の物語は伝説、民話の類であり、かれが実在したのかどうかもわからないわけですし、「グラストンベリー=アヴァロン説」に対しても根強い異論が存在するようですが、それでも現地では自分たちの土地こそは妖精の島アヴァロンだと信じられているわけです。
このグラストンベリーにじっさいに赴いて現地のことを調査した記録に『グラストンベリーの女神たち』があります。
この本によると、かの地ではネオペイガニズムとしての「女神運動」が盛んです。
女神運動とは何か。
それは、字義通り、キリスト教によって弾圧されたとされる古の大いなる女神を現代によみがえらせようとする運動を示します。
キリスト教はいうまでもなく男性的、あるいは少なくとも男性中心的な宗教です。
歴史的に「処女マリア」への崇拝といった側面もあることはあるでしょうが、基本的には女性は「人類の始祖たるアダムを誘惑し、罪を犯した」エヴァの遠い子孫とされ、一段低い扱いを受けていることは否めません。
そこには、女性が自分自身のスピリチュアリティを抑圧される側面があります。
そこで、近代になってキリスト教の男性的な神ではなく、古い偉大な女神を崇拝しようという動きが起こりました。
女神信仰では、古代には父権的で闘争的な社会ではなく、母権的で温和な調和に満ちた社会が実在したとされます。
その背景にはJ・J・バッハオーフェンが物した『母権制』があります。
松岡正剛による紹介を引くと、このように大変な絶賛を受けた書物です。
エンゲルスは「本書はモーセ五書以来の不動の書となるだろう」と絶賛した。ニーチェは「ここに永遠回帰がある」と唸った。ベンヤミンは「これは学問的予言だ」と書いた。たんに手放しで称賛しただけではない。エンゲルスはバハオーフェンを下敷きにして『家族・私有財産及び国家の起源』に着手し、ニーチェは永遠回帰論に手を染め、ベンヤミンは「忘却」とは何だったのかを考察して、現在においてはどこをパサージュすべきかを決断した。
いかにも松岡らしい端的ないい切りかたで、正直、わたしにはどこまでほんとうのことなのか良くわかりません。
それでも、この紹介を読むだけでも『母権制』が歴史にあたえた影響の大きさと深さを感じます。
たしかに当時、男性的ではなく女性的な母権制の社会という蜃気楼のようなイメージを、歴史学的に「証明」したこの本にはインパクトがあったのでしょう。
じっさい、古代の遥かな時代にいまとはまったく異なるもうひとつの文明が存在したという考えかたは、怪しげといえば怪しげですが、大きなロマンがあります。
きょうのオカルトやスピリチュアルの業界でも人気がある発想でしょう。
そこで宇宙人などを持ち出してしまうとそれこそオカルトそのものになってしまうわけですが、バッハオーフェンの本は一見して学問的な体裁で記されています。
だからこそ当時の第一線で活躍していた人物たちをも魅了したわけです。
それにしても、はたしてこの古い母権社会は実在したのでしょうか。
残念ながら、どうもこの母権制社会概念にはバッハオーフェンの空想の翼が生み出した疑史の一面があり、母権制の実在ははっきり否定されているようです。
ニーチェやエンゲルスにまで影響を与えた母権社会は、結局は実在しなかったのです。
母権社会の存在は、しょせん歴史学的には決して受け入れられない「ファンタジー」であるに過ぎません。
しかし、それは魅力的なファンタジーであることもたしかです。
こういった幻想は、当然ながらオカルトやスピリチュアルが大好きな人にはウケます。
かれらにとってバッハオーフェンの説が歴史学的にどのように受け取られたかは重要ではありません。それが新奇で革命的な思想を抱えていることこそが重大なのです。
そこで、色々な人が色々なことを主張して母権制概念をスピリチュアル業界に持ち込んでいきました。ここで、母権制は「魔女」と組み合わされます。
魔女と女神。
一見すると対極にも思われる概念ではありますが、スピリチュアル業界ではそれらは共通の「偉大なる女性」のイメージを孕んでいて、切っても切れない関係にあるのです。
女神崇拝と魔女として生きることは一体なのです。
そもそもひと口に魔女といっても、あくまでキリスト教の弾圧によってイメージをねじ曲げられてしまったからこそ邪悪な印象がつきまとうのであって、本来の魔女たちはそのような存在ではありえなかったのだ、と現代魔女たちは主張します。
女性が女性らしくありえた古代の母権制の社会では、魔女たちはその魔法の儀式を通じ自然と語り合える存在だった。ところが、キリスト教的な社会がそういった魔女の女神と自然崇拝の宗教を弾圧し、抑圧し、禁止し、ついには封印してしまったというわけです。
じっさいには古代、あるいは中世においてそのような魔女たちが存在したという証拠はなく、むしろ現実に魔女たちが「誕生」したのは近代に至ってからというのが真相です。
もちろん、中世に「魔女狩り」と呼ばれるような「魔女弾圧」があったことは歴史的な事実ですが、それは魔女と呼ばれるような女性たちが実在した証拠にはならないのです。
中世に魔女として告発され、弾圧されたのは、じっさいには太古からの伝承を受け継いだ魔女などではなく、ごくふつうであたりまえの女性たちに過ぎなかったのですから。
つまり、ネガティヴな意味でもポジティヴな意味でも魔女は存在せず、中世から近代まで、その実在しない魔女たちに対する弾圧が延々と続いていたわけです。
驚くべきことだと思いますが、イギリスでは、1736年に制定された魔女や魔法を禁止するアンチ・ウィッチクラフト法が、じつに1951年まで生きていました。そして、この法律の廃止が、近代における魔女の歴史に重大な意味を持ちます。
この1951年の魔女禁止令廃止直後の7月29日、「すべてのカブンによびかけて」というヘッドラインがサンデー・ビクトリアル』誌に掲載されたのです。
カブンとは魔女のグループを指します。そして、この記事を発表した人物こそが現代における「魔女の父」とされるジェラルド・ガートナーでした。
この人物が実質的に魔女文化と女神崇拝を現代社会にもたらした(かれ自身のいい分を信じるなら「よみがえらせた」)功労者です。
かれは時代遅れのアンチ・ウィッチクラフト法の廃止を良いことに、英国中の「魔女」たちを集め、魔女文化を「再興」しました。じっさいには捏造というほうがふさわしいかもしれないけれど。
ガードナーは晩年の「20世紀最大の魔術師」アレイスター・クロウリーの協力を得て『影の書』なる本を創作しています。スピリチュアル文化は色々なところで絡み合っているわけです。
ここでは、河西瑛里子の論文からネオペイガニズムとしての近代魔女文化勃興を説明している個所を引用しておきましょう。
現代の女神運動の実践の歴史の転換点の一つは、1951年にイギリスで魔女禁止令が廃止されたことである。これを境に、イギリスでは1950年代半ばごろから、魔女(witch)を名乗る人々が少しずつ現れてきて、ネオペイガニズム(Neopaganism)という運動が起こる。実践者はネオペイガニズムを、魔女術(Witchcraft)やドルイド教(Druidry)といった、キリスト教が到来する前にヨーロッパに存在していた、ケルト文化などの自然崇拝的な信仰への復興運動と位置づけている。魔女の存在を世間に知らせたとして有名なのが、現代魔女術の父と呼ばれるジェラルド・ガ―ドナー(1884-1964)である。彼は、1939年、年老いたある魔女と出会い、消えかけていく魔女術の知恵を書物に残そうとした。このとき、彼のオカルト趣味と民俗学の知識が融合され、創られた新しい魔女術が現在、ウイッカ(Wicca)と呼ばれる、多数派の魔女術である。ウイッカは、現代の庭女の多数派を占めていて、実践者には都会の住人が多く、男性の姿もみられ、少人数の集団でおこなう儀式を重視する。英語圏で「魔女術」といえば一般的にはウイッカのことを指している。一方、民間療法やいわゆるおまじないに携わるヘッジウイッチと呼ばれる魔女もいる。ヘッジウイッチの大半は、田舎で暮らし、1人で活動している女性である。https://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/bitstream/2433/134780/1/98_269.pdf
また、ガードナーがそのようにして「魔女の父」として成功するまでには、幾人かの先駆者がいました。
占星術研究家の鏡リュウジによると、そのなかで主なのは古典的名著『魔女』においてキリスト教の弾圧を受けた古代の異教文化を高らかに謳い上げた著名な歴史家のミシュレ、『アラディアもしくは魔女の福音書』を物したチャールズ・リーランド、そしてマーガレット・ミューレイ(ないしマレー)の三人です。
ミシュレに始まったものがリーランド、ミューレイへと継承され、少しずつねじ曲がりながら発展していったと見ることができます。
殊にリーランドの存在は大きく、現代における魔女的な歴史観のいしづえを作ったのはかれの『アラディア』であるといいます。
このなぞめいた書物『アラディア』は、かれがマグダレーナと呼ばれる女性から教わった魔女の神秘な秘法について書かれているのですが、例によって事実としては信用できる根拠がありません。
しかし、男性であれ女性であれ、この硬直した、あるいは暴力的ですらある社会に疲れ果て、「女性的なるもの」にあこがれ、惹かれる人は少なくないでしょう。女神信仰と魔女の物語はそのような人に対し「癒やしと救いとつながり」を提供しています。
それがじっさいには歴史的に実在がたしかめられないフィクションでしかないとしても、「信じる」ことは力になるのです。
大いなる魔法の力に。
④「妖精郷グラストンベリーの女神信仰」
ここまで書いて来たように、女神信仰と魔女文化は一枚のコインの裏表に等しい関係にあります。
ガードナーが創始した「ウィッカ(魔女宗)」はネオペイガニズムのなかでも最も盛んな一派だし、欧米ではいまも魔女の文化は意外なほど広い影響力を備えているのです。
ただ、ひと口に魔女といってもその指し示す範囲は広く、その気になれば「すべての女性は魔女なのだ」くらいのことはいえないこともありません。
ここでは、近代的な魔女の歴史に絞って話を続けましょう。魔女文化が成立するまでには、幾人ものスターが登場しています。
そのなかでも有名なのがたとえばスターホークです。スターホーク、「星(スター)」と「鷹(ホーク)」を組み合わせた筆名です。
彼女はミリアム・シーモスとしてユダヤ人の家庭に生を受けた女性でしたが、夢で啓示を受けてスターホークを名乗りました。
そして、当時のフェミニズムやエコロジー活動の影響を受けて、『聖魔女術 スパイラル・ダンス 大いなる女神宗教の復活』を記します。これが欧米でベストセラーとなり、現代のネオペイガニズムの思想に大きな影響を与えました。
『聖魔女術』というタイトルは、日本語として矛盾して感じられますが、これはそもそも「魔女」という訳語に原因があります。
スターホークにしてみれば「聖なる魔女」とは矛盾でも何でもなかったはずです。
彼女が語り出す魔女の物語は古代のロマンに満ちていかにも美しい。歴史学的な考証には耐えないにしろ「女性的なるもの」中心の社会という、行き詰まった現行社会のオルタナティヴを提示しています。
少なくとも単に「トンデモ」として却下してしまうことは惜しいでしょう。
一方、オタク文化のほうも『魔法使いサリー』に始まり、『魔法少女まどか☆マギカ』に至るまで、さまざまな魅力的な魔女、魔法少女たちを生み出してきました。
最近では、狭義のオタク文化からは少しずれますが、『ハリー・ポッター』シリーズの少女ハーマイオニーがすぐに思い浮かぶところでしょう。
それらは一般に「女児向け」の作品として生み出されてきたわけですが、あえていわゆる「男性向け」の文脈に限っても、たとえば『To Heart』(1998年)の昔から「魔女っ子」を扱ってきた作品は少なくありません。
「魔女っ子」は先に述べた「中二病」と相性が良く、そのふたつの属性を併せ持つキャラクターは数多いのです。
こういったオタク的な作品において魔女はフィクションの題材として扱われてきました。ところが、ここまで見てきたように、リアルに「魔女」を生きようとしている人々があるわけです。
現実には、女神信仰の異教がキリスト教に弾圧された歴史は実在しません。それはひとつの疑史でしかないのです。
そして女神と魔女の文化はその偽りの歴史に依存しています。したがって、そういった偽書と偽史にもとづく、いわば「あったかもしれない架空の世界」を前提とした魔女文化は、オタクから見れば、一種の「女子中二病」に見えないこともありません。
その意味で、シニカルでアイロニカルなオタクにとっては「いい歳して魔女とか(笑)」と笑い飛ばしてしまう態度こそが「正解」であるかもしれません。
しかし、魔女として生きている本人たちはどこまでも真剣なのであって、その真摯さをあなどることはできません。
少なくとも「大人」たちの社会からその奇矯さを冷笑とともに嘲られてきたオタクがこういったスピリチュアルな文化を嗤笑することは、どこか天に唾する一面があります。
また、それが太古の母権社会というファンタジーに立脚していることを認めるとしても、それでもなお魔女たちの文化はきわめて魅力的です。
その魅力はいったいどこから来ているのでしょうか。
色々な答えがありえるでしょうが、何といっても連綿たる男性社会において否定的に捉えられてきた「女性的なもの」を徹底して肯定していこうとするところが大きいでしょう。
その意味で魔女文化はフェミニズムと深い関係にあります。
昨今、オタク文化とフェミニズムは微妙に対立関係にありますから、フェミニズムというと眉をしかめる向きもあるかもしれません。
しかし、じつはこういった怪しく、うさんくさい魔女の歴史は、フェミニズムの内部からも批判を受けているのです。
フェミニストの北村紗枝は、インターネット上の記事で、魔女文化の魅力を語りながら、しかし魔女にはなれないと語っています。その理由は魔女文化の「本質主義」と「科学的な問題」にあるといいます。
こういうわけで、魔女は、少なくとも私にとってはとても魅力的ですし、できることならそうなりなかったと思います。実際に女神などを信仰している人には尊敬の念を抱いています。でも、私にはどうしても魔女になることはできませんでした。理由はふたつあります。ひとつには女神信仰には本質主義的なところがあること、ふたつには私が個人的にとても大事だと思っている学問、とくに歴史学や科学と衝突することです。 ウィッカなどの女神信仰では、女性に本質的に備わる出産の力が重視されていますが、私は全ての女性には何か根本的に男性と違う精神性が備わっているというような前提には懐疑的です。個人的に、出産などを過剰に礼賛するのは子どもを産みたくない女性、子どもを産めない女性に対する偏見につながりやすいと思うところもあるので、その点でも眉に唾をつけざるを得ません。また、ウィッカの実践者は月経が女性の身体を刷新させる力の根源だと考え、サロモンセンの本には経血を魔術に使用する魔女なども登場します(p. 237)。私はアレルギー性鼻炎でしょっちゅう大量の鼻水を出していることもあって、自分の身体から何か神秘的なものが出てくるとは信じられません。経血も鼻水同様の感染性廃棄物に見えます。女性の身体の機能をやたらと神秘的に礼賛するのは、どうも自分の柄ではないのです。 さらに、女神信仰では失われた古代の母権世界をユートピア的に描いたり、中世末期から近世までに魔女狩りの対象となった人々を古代から非キリスト教的伝統を保持していた魔女と考えたりするなど、歴史学の観点からはあまり信憑性のなさそうな神話体系を持っていることもあります。これは、学問に仕える者として、お話だと割り切ってもなかなか心情的に受け入れられないところがあります。
北村の意見は理解できます。魔女の文化は歴史学や科学と矛盾すること、また、本質主義的であり、女性をある限界に縛りつけるものであること。いずれも納得のいく理由ではあります。
ただ、本質主義はともかく、宗教としての魔女文化が科学的歴史学と矛盾することは、当然といえば当然のことです。
そもそも魔女とか魔法といった言葉ほど、科学と縁遠い概念もないでしょう。科学と矛盾するから魔女にはなれないというのでは、そもそも魔女になる気がないとしか思えません。
ひっきょう、北村は魔女的なるものをそこまで好きになれなかっただけのことなのではないでしょか。
否、おそらく彼女は「魔女」という言葉の響き、そのどこか昏くロマンティックな雰囲気は好きなのでしょう。
ただ、近代において創造(スターホーク的にいうなら「リ・クリエイション」)された魔女の文化は好きになれなかったのだと思います。
『グラストンベリーの女神たち』では、女神を信じる男女(男性もいるのです)の姿が、じつに活き活きと描き出されています。
面白いのは、それが必ずしも狂熱を帯びてはおらず、過激な信仰とはいいがたいところです。
たとえば、女神の信者たちが「アヴァロン」なる異界とアクセスしようとする場面。
本章の冒頭のアヴァロンの女神に捧げる祝祭や2で描いた季節の祝祭では、女神会館という室内に非日常の世界としての「アヴァロン」を創り出した。これはグリーンウッド(Greenwood)の調査した魔女たちが信じているファンタジーとしての異界(Otherworld)に似ている。彼女は、魔女たちは想像力の中で異界に行くが、異界の存在を真剣に信じていると言う[Greenwood 2000a]。しかし、筆者は季節の祝祭の場で、積極的な参加者がアヴァロンや女神の存在を完全に信じていたかどうかは疑わしいと思った。
なぜなら、季節の祝祭の準備のときに盛んに話し合われていたのは、劇の準備でもするかのような演出効果であった。また、女神を呼び出した後、実際にその場にいるかどうかを確認する行為は行われず、呼び出しという行為自体が、女神がその場にいるという事態を成就させていた。さらに、祝祭中も真剣な面持ちではあるものの、女神からの言葉を聞いて、エクスタシーや興奮のあまり倒れるような人、そのような状態に陥っているような人は皆無であり、皆ただ淡々とその様子を静かに観ていたのである。つまり、プリーステス・トレーニングなどを通じて、儀式を要請している世界観を理解している積極的な参加者は、異界「アヴァロン」の存在を信じるというより、ともに創り出しているという意識の共有を求めていたと考えられる。そのため、パフォーマンスに参加しないという、その場の一体感をぶち壊すような行為は咎められたと理解できる。
どうでしょう、一般的な日本の新興宗教的のイメージとはだいぶ異なる女神信仰の姿が見えてこないでしょうか。
女神信仰の現場において「アヴァロン」という異界はべつだん信じられていないということ。
つまり、女神を信奉し崇拝しているはずの人たちですらも「アヴァロン」の実在を熱狂的に信仰しているわけではなく、あくまで「ともに創り出している」に留まるわけです。
もちろん、だからといって即座にすべては作りごとの虚構に過ぎないといい切るわけにはいきません。
女神信仰には、少なくとも熱心な信者にとってのキリスト教や仏教と同じくらいにはリアルな側面があるでしょう。
その熱さと冷静さ。女神運動は奇妙に魅力的です。
たしかに女神と魔女の物語には信じがたいところも多いのですが、それでも、あくまでロマンティックなものを求める心理は、ひとりのオタクとして非常に良く理解できます。
もちろん、わたしは「虚構を虚構として消費する」オタクの立場に立つから、女神を信じることも魔女(日本語にしてこそ魔「女」だが、ここでいう魔女には男性も含まれる)になることもできませんが、そのロマンそのものには大いに惹かれます。
はるか古に男性的なキリスト教によって弾圧されながら、悠久の時を越え、現代によみがえった魔女のカブン――魅力を感じるなというほうが無理なのではないでしょうか。
⑤「サイコマジックという実践」
ここで、ネオペイガニズムとまた少し違う方向性から「オタク的なるもの」を眺めてみましょう。
内実的にネオペイガニズムほど「オタク的なもの」と近いわけではありませんが、「オタク的なもの」を考えるとき、とても示唆に富むように思える分野。アレハンドロ・ホドロフスキーの「サイコマジック」です。
聞き慣れない響きかもしれません。サイコマジックとは一種の心理療法です。もっとも、フロイトを開祖とする精神分析とは決定的に異なっています。
精神分析が(かなり怪しいところはあるにせよ)科学を前提としているのに対し、サイコマジックが頼るものは芸術、それもホドロフスキー一流の血まみれのアートなのです。
カルトな映画作品で知られるアーティストであるホドロフスキーは芸術の力を信じ、それが人の心の傷を癒やすことを目指して「サイコマジック」を開拓しました。
それは一見して怪しいしろものです。「サイコマジック」は論文と実験のくり返しで検証され確立された学術的な方法論ではなく、多分にホドロフスキー個人の才覚に依存する技法(アート)だからです。
いい換えるなら、どこまでも再現性を旨とする科学(サイエンス)ではありえず、あくまでも魔術(マジック)なのです。
じっさい、「サイコマジック」はドキュメンタリー映画化され、また著作としてまとめられているのですが、その映画を見ても、著書を読んでも、かれの方法論が科学的に有効だとはとても思えません。
映画のなかにはくりかえし重い心の傷を抱えた人々が登場するのですが、それらの人物たちに対してホドロフスキーがほどこしていく「サイコマジック」は荒唐無稽にすら思えます。
それはあまりにも「アート」であり過ぎるのです。
もちろん、芸術が人の心を癒やすことは十分にありえるでしょう。ですが、ホドロフスキーがもちいる「アート」は何といっても生々しい。
エロティックでエモーショナルで、「生」の根源に触れているかのような行為の数々。
一応はあいての了解を得ているからセクシュアルハラスメントにはあたらないわけですが、それにしてもきわめて危ういものを感じさせずにはおきません。
たとえば、映画に収録されている全裸になった女性たちに自分自身の経血で絵を描かせる場面はきわめて衝撃的です。
日本なら、あるいはアメリカでも、淫祠邪教のたぐいとみなされて非難されかねないでしょう。
まさに古代の魔術を現代に再現するかのようであり、ほんとうに深刻なトラウマが治ったりするものなのか?と疑問に思わずにはいられません。
ところが、それにもかかわらず、現実に「サイコマジック」にもとづく治療を受けた人間たちはなぜかとても晴れ晴れとした表情で去っていくのです。
人生の大問題を解決できた人もいれば、崩壊寸前のところまで行っていた夫婦仲が進展したりもします。
あるいは統計的にエビデンスを取ってみればまったく効果がない人も一定数いることがあきらかになるかもしれませんが、それにしても、その効果は意外に無視できないものがあります。
いったいこれはどういうことなのだろう? 神秘的としかいいようがありません。
映像で、あるいは文章で「サイコマジック」を観ていて思わされるのは、対象と冷静な距離を置く科学的な精神療法の安全さと堅実さ、そしてその科学的であり合理的であるが故のある種の限界です。
一般的な精神療法では、人権意識もあって、患者とのあいだに一定の精神的な距離を取ります。
医者が患者の妄想に巻き込まれたりすることは許されず、患者と医者がひとつの「物語」をシェアしたりもしません。あたりまえのことです。
ところが、「サイコマジック」においては、ホドロフスキーは積極的に患者とナラティヴを共有していこうとしているように見えます。
それこそは「サイコマジック」の魔術たるゆえんであり、またそれがまゆつばに思えてならない理由でもあるのですが、とにかくホドロフスキーも患者も真剣です。
近代科学が取り組むにはあまりに危険で、淫靡で、そして魅力的なひとつの神秘学(オカルト)の奥義がそこにあるといえます。
映画のクライマックスでは、ホドロフスキーは何百、何千人もの集団で、テレビを通して大規模な「サイコマジック」を試みます。
ここでは、「サイコマジック」は心理療法であることを超えて、はっきりとオカルト、あるいは魔術の次元に足を踏み入れています(あるいはホドロフスキー本人は、もともとそれは魔術なのだ、というかもしれませんが)。
その光景はじつに圧巻です。その実際的な効果は日本の超能力番組にも似てまったく信じられませんが、それでも心を鷲づかみにするような何か異様な迫力があります。
少なくとも、魔術的なものに惹かれるタイプの人間ならそれを感じ取ることでしょう。
また、ホドロフスキーには『ホドロフスキーのDUNE』と題するドキュメンタリー映画もあります。
いまから数十年前にホドロフスキーがハリウッドで撮影を試み、そして失敗に終わった映画企画『DUNE』を巡る一連の出来事を綴った作品です。
ホドロフスキーはこの『DUNE』をもちいて世界を、人類の意識を変えようとしていたといいます。
まさに誇大妄想としか思われない話なのですが、かれはじっさいに前衛画家サルバドール・ダリや超人気ロックバンド・ピンクフロイドといった個性的な面々の協力を得るところまで行っています。
映画は諸事情のため完成しなかったようですが、もし完成していたらどのようなものになっていたのか、あるいはほんとうに世界にショックとインパクトをあたえたかもしれないと想像がふくらみます。
もちろん、ホドロフスキーの世界は一般的なエンターテインメント映画としてはあまりにもカルトです。
それは、強烈な刺激に満ち満ちてはいますが、たとえば『アベンジャーズ』がそうであるように、わかりやすく「面白い」作品ではありません。そこにはハリウッド脚本術の三幕構成も何もあったものではないのです。
その意味で、ホドロフスキー版の『DUNE』は仮に制作されていたとしても、『スター・ウォーズ』のように大ヒットしたりしなかったことでしょう。
それでも、「もしかしたら……」と思ってしまうのは、ホドロフスキーという人物の奇妙な魅力の故です。
映画もまた、ホドロフスキーにとって「サイコマジック」です。
かれはオタクたちのようにフィクションとのあいだに安全な距離を空けたりしません。どこまでも虚構に耽溺し、むしろ現実を虚構によって塗り替えようとしているように見えます。
かれのやりかたは倫理的に問題があると指摘することもできなくはないでしょう。
じっさい、ホドロフスキーの息子に対する接し方など、一歩間違えれば虐待なのではないかと思われて来るくらい。
ただ、それだけにかれのやりかたには人を惹きつける強烈な引力があります。
あと半歩でもずれてしまえば、ただのオカルトに成り下がるところなのかもしれないのだけれど、その真剣さは「ただの怪しげな新興宗教の教祖に過ぎないではないか」といって済ませることを許しません。
近年に至ってホドロフスキーの芸術的なカルト映画の評価はさらに高まり、かれは『リアリティのダンス』、『エンドレス・ポエトリー』といった自伝映画を続けざまに撮っています。
その映画もまた一種の「サイコマジック」として何か魔術的な迫力を備え、かれが紛れもなく凡人ではありえないことが伝わって来ます。単なるハッタリだけの人物ではないのです。
そういった映画やコミックなどを通してホドロフスキーがめざしているもの、それは人間たちの「意識の変容」です。
書籍版『サイコマジック』の解説によると、ホドロフスキーがめざしている境地は、ヴァン・ヴォートの『スラン』や、アーサー・C・クラークの『幼年期の終り』といった「黄金時代」のオプティミスティックなSF小説に近似しているといいます。つまり、人類の種としての進化です。
クラークについてはまた後で取り上げますが、わりあい楽天的といえる「あかるい未来」を夢見た人です。
現代SFは『ニューロマンサー』や『ブレードランナー』といったサイバーパンク作品の「汚れた未来」のヴィジョンを経て、むしろ暗い、シリアスな未来を想像するようになっていますが、ホドロフスキーはあくまでそういった未来像を拒否し、「人類は種として進歩することができる」と考えるわけです。
あるいはそれはあまりに時代遅れの信念かもしれませんが、かれがその「サイコマジック」を通じてじっさいに人類を進化させようと試みていることを思うとき、一笑して済ませることはできません。
かれはクラークやハインラインといった作家たちが描いたSFの世界を現実に生きている人なのです。
このあまりに独特の人物から、日本のオタクたちが学ぶことは何かあるでしょうか?
ホドロフスキーの生々しい豊饒な世界と、オタクたちの幼い二次元宇宙はあまりにもかけ離れています。
また、まず大半のオタクが「サイコマジック」という魔術のいかがわしさには引いてしまうことでしょう。
ただ、それでもわたしは「サイコマジック」に強烈に惹きつけられます。それはネオペイガニズムに惹かれるのと同じ理由です。
じっさい、ホドロフスキーの世界は魔女や魔術といったオカルトな文化とシンクロしています。かれは次節でいうところの「魔術の物語」を生きているわけです。
だからこそ、きわめて怪しげで、奇妙な人物ではありますが、かれには何ともスピリチュアルな魅力がある。
人がただ合理性だけで生きられない以上、かれのような生き方はこれからもたくさんの人たちを惹くことでしょう。
そして、あるいはいつかかれの「マジック」はほんとうに世界を変えていくのかもしれない。そんな夢想をしてみたくなります。
⑥「霊性の物語としてのスピリチュアル文化」
ここまで、ネオペイガニズム、サイコマジックなど、どこかでオカルトやスピリチュアルと隣接した文化を見てきました。それらは一面でオタク文化のスピリチュアリティを照射する性質を備えていると感じられます。
「虚構を虚構として処理する」オタク文化と「虚構を現実として信じる」ネオペイガニズムやサイコマジックはたしかに異質です。
オタクから見れば、こういったスピリチュアル的な文化にハマる人は愚かしく思えても不思議はありません。
しかし、じっさいには推しの「尊さ」をあがめるオタクもまた、スピリチュアルなるものを崇める素質を備えています。
ただ、オタクにとっては、虚構作品に耽溺しても、それをあくまで虚構として処理するしかないため、「アイロニカルな没入」に留まるのです。
それにしても、ネオペイガニズムやサイコマジックを見ていると、その絶対倫理が、必ずしも絶対的なものでなくても良いのではないか、と思われて来ます。
もちろん、マンガはマンガだし、アニメはアニメです。『ONE PIECE』や『NARUTO』がどれほど面白いとしても、だれもそれらを現実の出来事だと思い込んだりしません。
また、推しのアイドルや俳優や歌手がどれほど魅力的だとしても、かれらがどこまでも「遠い」存在であることを失念したりもしないでしょう。そこで良識を失ってしまったら、オタク活動はたやすく狂気に陥ります。
しかし、それでも宗教的に「物語を生きる」ことはとても魅力的です。
ひとりのオタクとして、物語と距離を保って生きて来たからこそ、「物語をダイレクトに生きている」人たちには憧憬を感じます。
もちろん、それは一歩間違えればカルト宗教に落ちていくようなルートではあるでしょう。
ネオペイガニズムはじっさいに宗教であるわけだし、ホドロフスキーなどを見ているとちょっと苦笑したくなるときもある。
それはそうなのですが、その「世界境界」を超え、物語の世界に暮らしているような生きかたに、オタクでしかない自分の限界を思うこともたしかなのです。
当然ですが、虚構を虚構として処理することは良いでしょう。しかし、はたして、わたしたちオタクはそのフィクションから何を学ぶことができるのでしょうか?
さて、先にも名前を出した佐々木俊尚の著書に『時間とテクノロジー』があります。
タイトルから内容を想像しづらい一冊で、また、要約して語ることもむずかしいのですが、あえていうなら人類史を通しどのような世界認識が試みられてきたのかを解説した一冊です。
佐々木は、この本のなかで、人間が世界を認識するためにもちいる枠組みを「物語」と呼びます。かれは歴史的に語られた「物語」を表すために、「因果の物語」、「べきの物語」、「機械の物語」といった言葉を使っています。
「因果の物語」とは原因と結果に一対一で対応する関係を見るような「物語」です。その因果関係はじっさいに実在しているかのように思われることもありますが、現実にはそれは物語、つまりフィクションであるに過ぎないというわけ。
また、「べきの物語」とは「べき乗」から取った言葉で、ある現象が当初の常識的な想像をはるかに超えて指数関数的に大きくなっていくことを指しています。
そして「機械の物語」とはAIが人類に対して示した「物語」です。それは人間には理解できないほど複雑な構造の「物語」なのですが、たしかに実在することだけはだれにでもわかります。
なぜなら、じっさいに結果をともなっているからです。AIが示すとおりに従えば、しかるべき結果が出てくるのです。
つまり、一面で人類の知性をもはるかに超越した人工知能の発達は、まさに人間には理解できず、ただただ不可解に思われるばかりの「物語」が実在することを純粋に科学的かつ実証的にあきらかにしたわけです。
科学的とはいっても、それは人間に理解できるようなロジックの形を取っていません。すべてはブラックボックスの内側です。
だから、それはある意味でかつて興り、そして亡んでいった「魔術の物語」に似ているといえます。
そこには何ともいえない不思議と神秘の感覚があるのです。「種も仕掛けもある」ことはだれにでもわかるものの、具体的にその種が、仕掛けが何であるかはだれにもわからない。それが「機械の物語」。
「機械の物語」は科学の精髄ともいうべき人工知能によって生み出されたわけですが、それにもかかわらず何とも不思議です。まるで魔法のよう。
ここで、アーサー・C・クラークの「第三法則」を思い出してしまうことは必然でしょう。即ち、十分に発達した科学は魔法と区別がつかない。
科学はその発展の末、何とも魔法めいたところにまでたどりついてしまったということでしょうか。何とも奇妙な感慨があります。
佐々木は、そういった数々の「物語」を具体的な例を挙げながら語り、そして古典的な「因果の物語」が通用しなくなった現状について説明します。
そう、シンプルな「因果の物語」は複雑怪奇な現代社会をよく説明しえないのです。そこでかれはユングのシンクロニシティ概念を持ち出し、そういった「共時の物語」が今後は重要になっていくかもしれないと説明していく。
そこまで読んで、わたしは、スピリチュアルな認識のしくみは「霊性の物語」とでも呼ぶことができるだろうかと考えます。
現代日本のスピリチュアル文化の愛好者は「因果の物語」を離れ、さりとて古めかしい「魔術の物語」に回帰することもなく、めくるめく「霊性の物語」を生きているわけです。
それはあるいは幸福なことであるのかもしれません。しかし、しつこく何度もくり返すが、オタクにとっては物語は物語であることを超えません。
いままで散々書いてきたように、オタクにとってその境界を乗り越えることは中二「病」という病であり、狂気だからです。ここに、宗教ないし霊性とオタクとの決定的な隔たりがあります。
したがってオタク文化はどれほど内容的に酷似していても宗教ではありえない。あえていうなら、宗教ないしスピリチュアルとオタク文化は双子(三つ子?)の兄弟のような関係にあるというのがわかりやすいでしょう。
スピリチュアルという「霊性の物語」もまた、人々が「因果の物語」に疲弊したところから生み出された文化のひとつであるのでしょう。それは「魔術の物語」と同じく、科学的な因果関係を説明できないものです。
なおかつ「共時の物語」のような学問的な裏付けがあるわけではない。いまなお「霊性の物語」が成立するのは、人がスピリチュアルな充実を求める性質を持っているからに過ぎません。
いったい、なぜ、これほど多くの人が霊的な物語を求めるのでしょう。思うに、その背景にあるものは、人生に意義を求める心理です。
自分がただむなしく生きて死んでいくだけの人間であるとは信じたくない。自分を世界に確固とつなぎ留めたい。そのような意識がなければ、スピリチュアルにハマったりしないでしょう。
つまりはそこにあるものは一種の実存的な飢餓感なのです。色々なものを持ち、また与えられてきたにもかかわらず、それでも何かが欠けているという感覚。
「物質的にはある程度は豊かになったのに、心の豊かさが欠けている」などといったら説教くさいし、何より陳腐です。
しかし、わたしたちがいままさに生きている新自由主義経済思想が支配する停滞したポストモダン格差社会では、人は実存的な豊かさを実感しにくい。
ただ生きていくだけならできる。しかし、胸の奥のいい知れない「飢え」が、「渇き」が消えない。
そのようなとき、人はスピリチュアルなものを求めます。それはオタクも同じ。
オタクが「推し」に対し、何ら見返りのない贈与を続けるのは、そこに、自分を癒やし、救い、そしてこの世界につなぎ留めてくれる「霊性の物語」を見るからなのではないでしょうか。
そのとき、ずっと抱えて来たのかもしれない「飢え」や「渇き」が初めて癒やされる。
前章で取り上げた『人類にとって「推し」とは何なのかイケメン俳優オタクの僕が本気出して考えてみた。』には、このような記述があります。
孤独だった。でもその孤独は、決して物理的にひとりであることじゃない。自分の内にある孤独を、誰ともシェアできないことが孤独だった。
そんな僕が、ほんのちょびっとだけ自分に対してまだいくらかマシと思えるようになったのは、好きなものを好きと素直に言えるようになったからだと思います。
「推し」は人の孤独を救い、どうしようもない「自分自身からの排除」までも癒やすのです。その不思議な魔法の力!
しかし、オタクは一般的には「推し」にスピリチュアルなものを感じ取りながら、それでもなおスピリチュアル文化に耽溺するでもなく、しばしばいささかのアイロニカルな感情とともに、ある人物や作品を推しつづけます。かれらは、わたしたちは、その「没入」の果てに何を見るのでしょう?
オタク的な文化が、ときに人を宗教のように「癒やし」、「救い」、世界からの遊離を食い止めてくれることはたしかです。
ですが、わたしたちはただ癒やされ、救われているだけなのでしょうか? 自ら推す人物や物語から何かを持ち帰ることはできないのでしょうか?
ネオペイガニズムの信者やサイコマジックの患者のように、物語から大きな果実を得てそれを喰らうことは不可能なのか?
その問題については、次章以降に考えていきたいと思います。
第四章「存在のビッグ・クエスチョン」
翻弄されているということは
状態としては美しいでしょうか
いいえ 綺麗な花は枯れ
醜い過程が嘲笑うのです
…何時の日も 椎名林檎「依存症」
①「戦場化した新自由主義社会のアミュレット」
それにしても、宗教が衰微しつづけるこの時代において、スピリチュアルという言葉に象徴される「新霊性文化」が出て来たことはあまりにも意味深い。
それはひっきょう、宗教がリアルでなくなった時代においてもなお、人が宗教的なるもの、あるいは非合理的なるものを希求する心理を持っていることを意味しているように思えます。
それらは「聖なるもの」というには、あまりに卑俗に思われるかもしれません。天使だの宇宙人だの、あまりにも荒唐無稽な物語が無限に消費される界隈であることも事実です。
その内実はさまざまに研究が進んでいますが、それらの記述を読んでいると、いかにこの分野にいんちきやでたらめが猖獗を究めているか強く実感されます。
その意味で、スピリチュアルな文化のすべてを全面的に肯定することはできそうにありません。むしろ、批判的に見ることのほうがよほど自然にすら思われます。
しかし、それでも、なお、スピリチュアルなものを求めることには意味があります。その求めるものをじっさいにいわゆるスピリチュアル文化のなかに見いだすことは困難であるにしろ。
くり返しましょう。「人はパンのみにて生きるにあらず」。他に類を見ない想像力に恵まれた動物である人間は、この世に実在しないものを希求します。そして、そのことによって救済されるのです。
たとえば仕事がうまくいかないとき、家族としっくり来ないとき、何かスピリチュアルなアイテムに頼る人は少なくないでしょう。
それは客観的にはまるで意味がないただの「モノ」かもしれませんが、なにがしかのヒエロファニーと化しているわけです。
わたしたちが生きる現代社会は、さまざまな問題を抱え、またわたしたちの生活は過酷さを増す一方です。
何らかの意味でスピリチュアルな文物は、その「戦場化」した資本主義競争社会において自分自身を苛烈な抑圧から守るアミュレット(お守り)であるのです。
そのアミュレットは聖なる力であなたを苛烈な運命から守ってくれる、ように思える。
科学的、客観的にどうであれ、重要なのはあなた自身がその「物語」を信じられることではないでしょうか。
それがじっさいには聖とも魔とも縁がない単なる物質であるに過ぎないとしても、ナラティヴの力は人の心にこそ作用するのです。アミュレットとは、つねにそのような性質のものです。
ただ、あまりにもあたりまえのことかもしれませんが、スピリチュアルな文化そのものも搾取的な一面を持ちます。
スピリチュアル的な文化は、その先駆けであるニューエイジ文化の頃から、脱近代、脱文明、脱資本主義的なるものを志向してはいたでしょう。
が、その実、結局はマネーと縁を切ることはできませんでした。
もちろん、だからといって一概にスピリチュアルを「不純」といい切ることはできません。
資本主義はいまやわたしたちの文明の隅々にまで行きわたっており、ただ宗教やスピリチュアルだけがその影響を逃れることは不可能です。
この世のあらゆるものが金で売買される現代において、霊的なものだけがその仕組みを免れることはできないとしても、非難には値しないでしょう。
もっとも、そうはいってもそういった「霊性の文化」こそがしばしば資本主義社会のなかでも最も強欲な一派に思われることも事実です。
だからこそ、カルト教団や詐欺グループによる、いわゆる「霊感商法」や「洗脳ビジネス」が問題になる。
「聖なるもの」を志向するスピリチュアルな文物は、それでいてどうしようもなく金まみれであり、しばしば搾取の口実として利用されます。
そういったスピリチュアル・ビジネスのどうしようもない実態を批判的に記述した本として『霊と金 スピリチュアル・ビジネスの構造』があります。
まさに端的なタイトルですが、「霊(スピリチュアル)」と「金(ビジネス)」のダーティーな関係を綴った本です。
この本では、スピリチュアルな価値観が現実的なリスク・マネジメントを歪め、大金を使うことをためらわなくさせるプロセスが、さまざまな実例を挙げて列挙されています。
すでに十数年前の実例なので古くなってしまっているところも多々ありますが、いまなお、スピリチュアル・ビジネスの危険性を学ぶためには読む価値のある一冊です。
スピリチュアルなマーケットで売買されている「聖なるもの」は、決して無料ではないのです。
また、オタク文化にしても、きわめて強力な資本主義的ロジックで動いていることは自明でしょう。オタクたちはあらゆる物語を金で買わなければならないのですが、それ自体は当然のことだとしても、あまりにも強欲に思えてならない仕組みもあります。
そのなかでも最もわかりやすいのが、ソーシャルゲームでしょう。
大方のソーシャルゲームは「ガチャ」とか「ガシャ」と呼ばれるなかばギャンブル的なシステムによって維持、運営されています。
「ガチャ」では、そのゲームにおいて強力なキャラクターのカードやデータが一定の確率で出るよう設定されています。そして、その「ガチャ」を回すために一定の金額が必要になるわけです。
いうまでもなく、たかが電子情報のキャラクターカード一枚であり、ゲームの内部でしか通用しないデータに過ぎません。
ところが、オタクはときにその一枚に何十万円という額を費やすことすらあります。
それはもはや「お布施」であることを超えて「献金」なのではないかと思えて来るほどです。
そのカードやデータがある種の「アミュレット」として自分を守ってくれるとしても、あまりに高額ではないでしょうか。
ここにはあまりにも露骨な矛盾があります。
われわれは競争を強いる資本主義社会から自分を守るアミュレットを必要とするのですが、そのアミュレット自体が金銭でしか贖えないということ。
つまりはすべての構造はマッチポンプに過ぎない一面があるわけです。
わたしはオタク文化やスピリチュアル文化の裏面に貼りついたこういった拝金性を無視するつもりはありません。あきらかにそこには問題があります。
そのどうしようもなく資本主義的な構造を無視して「聖なるもの」も何もないものでしょう。
ただ、このどうしようもなく戦場化した社会において、人が、いったいどこから飛来するかわからない弾丸を避けるためにアミュレットを欲する心理も理解できるのです。
そういったアミュレットがなければ、ふつうに生きていくこともむずかしいのですから。
わたしたちは「より良い生活」を行うため働き、金を稼ぐ。それ自体は古来より実施されてきたごくふつうの行為です。
しかし、ポストモダン社会の悪化した労働条件においては、そういった賃金労働はしばしばきわめてストレスフルです。
だから、わたしたちはその傷を、苦しみを癒やす宗教的な救済を求める。ある人はスピリチュアルに傾き、またある人はオタク的な文化にすがる。
しかし、その「癒やし」や「救い」を得るためにはより働くことが必要になる。資本主義特有の無限のループ。
つまり、答えはこういうことなのでしょうか。この世のすべてはしょせんは金でしかない、と。
カルト宗教やオタクビジネスの拝金性は、しょせんオタクがそこに見る「聖なるもの」など都合よく幻影に過ぎず、そこにはただビジネスがあるだけなのだと明示しているようです。
ですが、それはそれで行き過ぎた結論でしょう。
オタク文化はたしかに資本主義的な消費なくして成り立ちません。しかし、逆にいえば、そこには資本主義を回転させ、社会をより良い形にしていくエネルギーがあるということもできます。
オタクは紛れもなく経済的状況によって実存の満足度を左右されるある種のエコノミック・アニマルですが、逆にいえばオタク趣味には経済的な自立を促す作用がある。
人が働き、生きていくためのそのモチベーションになりえるのです。
先述したコスチューム・プレイを題材としたマンガ『その着せ替え人形は恋をする』では、そういった「大人」としての生き方が極めて肯定的に描かれています。
そこで描写されているような、自分の力で稼いだ金銭を好きなだけ趣味に費やして癒やされ、救われる。そして幸せになる。
そのような「オタク的な」生き方は、いま、いわゆる「リア充的な」ライフスタイルにも増して、若年層の支持を集めています。
かつて、オタクといえば、さまざまないじめや弾圧のターゲットとされかねない被差別階級でしたが、いまでは事情は異なります。オタク的に生きることは、十分魅力的に思われているのです。
くり返しますが、オタク・ビジネスの現場において行われているビジネスは、ソーシャルゲームの例のように、ある種、搾取的ですらありえます。
オタクがキャラクターやナラティヴに代替不可能なほど重要な意味を見出すとすれば、それが高値で売買されることも必然ではあるでしょう。しかし、だからといってそれがオタク業界のすべてではないはずです。
ありとあらゆるものがマネーで取り引きされる資本主義市場において「聖なる価値」もまた、金になる。そのため、強欲で搾取的なビジネスが猖獗を究める。
それ自体は問題ですが、そのことを理由にして「聖なるもの」そのものを否定してしまうことはできません。
オタク文化にハマることに危険がまったくないとはいえないでしょうが、とりあえず悪質な新興宗教団体などに騙されてしまうリスクはありません。
その意味で、オタクになることは比較的安全に「スピリチュアル・ニーズ」を満たせるルートであるように思えます。
だからといってだれもがオタクになれるとは限らないこともほんとうですが、それは他のあらゆることにもいえること。「聖なる道」の探究には、本人の資質が必要なのです。
②「信仰としての推し活」
熱烈なオタクであることはスピリチュアルな一面を持ち、推し活はどこかで信仰に漸近する。そのように書いて来ました。
オタク文化と信仰の近似性については色々なことが語られているが、アイドル文化を宗教という一面から語った本に『前田敦子はキリストを超えた』があります。
一見してあまりに大袈裟で、ちょっと失笑をすら誘うタイトルが話題になった一冊ですが、内容は真剣です。
人気アイドルグループAKB48を題材に、推し活が宗教的な行為であることを論述しています。
扱っている題材はいまとなってはいくらか古くなってしまっていますが、その本質は古びません。
そう、熱狂的なオタクであることとは一面で敬虔な信徒であることでもある。だからこそ、オタクは「布教」や「巡礼」に喜びを感じるのです。
そういった宗教的なオタク的な文化がファンにあたえてくれるものは、かぎりない救いと癒やし。そしてもうひとつ「つながり」です。
かつて、キリスト教などの宗教は単に信者に教理と「物語」を強制するだけではなく、コミュニティを提供する存在でもありました。
そして、いま、オタク文化は、ただ人を「救い」、「癒やす」のみらなず、その「つながり」の役割をも果たしています。
たとえば推しのアイドルたちのコンサートや、毎年開催されるコミックマーケットを通して、オタクは自分以外のオタクと「つながり」を持ち、孤独を癒やされます。
もちろん、ひとりで推し活動を行っているオタクがいないわけではありませんが、多くのオタクにとって、「自分はひとりではない」ことは救いと希望になっていることでしょう。
あるいはいまとなってはそういった「仲間」のコミュニティを求めてオタクになる人物すら少なくないかもしれません。
オタク文化の宗教性について語ったいまのところ唯一の学術書である『オタク文化と宗教の臨界 情報・消費・場所をめぐる宗教社会学的研究』では「オタク・コミュニティの緩やかな連帯と救済」が綴られています。
オタクたちの「つながり」は、この、危険なまでに人を孤独とする社会において、「連帯」につながる可能性を持っているのです。
そのように考えると、新自由主義思想が蔓延するこの競争資本主義現代社会で、推し文化が繁栄を究めるその理由の一端がわかるような気がします。
いくら推しを推したところで、実利的にはべつだん、何が得られるわけでもない。あえていうなら心理的な報酬があるだけです。
しかし、その心理的な報酬のためだけにときに人は膨大な資金や労力をそこにつぎ込みます。それはほとんど経済的なやり取りであることを超えて、一方的に「贈与」しているようにすら見えます。
ですが、「与えることは受け取ること」。オタクたちは推しに「贈与」することによってこそ、救われるのです。
オタクは、推しに対して金銭を使うことを「お布施」と呼びます。
またも宗教的な語彙。それはもちろん、ほんとうにお布施だと思っているというよりは、いくらかオタクらしいシニカルでアイロニカルな含意を孕んだ表現ではありますが、しかしこの表現が選ばれることには必然性があります。
ここにおいて、冷静な第三者から見れば、カルト宗教に貢ぐ信者とあまり差がわからなくなってしまいます。
じっさいのところ、そういった「お布施」とカルトへの「献金」に落差はあるのでしょうか。
もちろん、あるはずです。
オタクは自分の意思で金銭を推しに使っているだけで、べつだん、だれかに強制されているわけではありません。
とはいえ、どこかでそれが「献金」に近づいてしまう一面があることはすでに述べて来た通りです。推し活はあくまで経済的に破綻しない範囲で行われなければなりません。
また、推し活とは、一面で、単なる一個人であるに過ぎないだれかに、暴力的に期待や欲望を押しつける行為でもあります。
その「好意の暴力性」を無視し、無邪気に、無神経に推しを尊崇することもできるでしょう。
そして、それは幸せなことではあるでしょう。しかし、そのような無邪気さに甘んじることができない人も少なからずいます。
そういった人たちにとって、推し活とは葛藤に満ちた行為になります。
そしてまた、ある意味では、ただのあたりまえの人間に過ぎない推しを神として崇め神聖視する推し活とは、常に失望とうらはらの行為です。
否。
人がしょせん神ではありえない以上、推しは「いつかかならず」何らかの形でファンを裏切ります。
神が神であるためには決して信者を裏切ってはならない。しかし、人はしょせん神ではありえず、いつかどこかの時点で絶対に信者を裏切るわけです。
もちろん、いわゆる「二次元の」フィクションのキャラクターなら、より純粋に神であることができるのかもしれません。
ですが、そういったキャラクターたちですら、ときに期待を裏切ります。物語はファンが予想し期待した通りに進行していくとは限らないからです。
しかし、その「裏切りの可能性」はネガティヴにだけ捉えるべきものでしょうか。
「裏切られる」可能性があるからこそ、推しはときにファンの想像をも期待をも乗り越えたパフォーマンスを見せてくれるのであって、ネガティヴな「裏切り」とポジティヴな「乗り越え」は表裏一体なのです。
さらにいうなら、そもそも考えてみれば「推しに裏切ってほしくない」とは、かってなものではあります。ファンのほうはいつ推しを見捨てることも自由なのですから。
それなのに、推しに対してはファンを裏切るなと強制できるものでしょうか。
ここに至るまで幾たびかくり返し述べてきたように、推しもまたひとりの人間として自由意思を抱えて生きているわけであり、そこにはだれにも侵害できないひとつの人生があります。二次元のキャラクターですら、そうです。
したがって、推し活にはどうしようもなくダークサイド(暗黒面)があります。その闇の深さ、また暗さ。
オタクたちがしばしば身勝手さを露わにするのは、かれらが推しに期待を裏切られた、あるいは少なくともそう信じたときです。
その推しが作家のようなクリエイターであれ、アイドルのようなパフォーマーであれ、しばしばかれらは「自分を裏切った」推しを攻撃することを躊躇しません。
インターネットを見れば、かつては「神」として崇めていたその人を口汚く中傷し罵倒する人間が膨大にあることをたしかめることができるでしょう。
神をののしること、それは信者にとって大いなる罪悪であるはずですが、推しを攻撃する人にしてみれば、むしろ神のほうがかれらの信仰を裏切ったことになるわけです。
倒錯した心理です。かってに人間を神のように崇めておいて、神のままであってくれなかったといって嘆き、責める。
常識的に考えるなら、あまりまともな行為とはいいがたいでしょう。
推しはあらゆる意味であくまで「他者」です。それも神のごとき「絶対他者」と考える人も多いでしょう。
そのまま神であってくれれば都合は良いのですが、何かの契機で人間としての素顔を見せることがあります。
それがポジティヴに「可愛い」ものなら良いのですが、ネガティヴな意味で「人間的」な顔を見せることは、推しを神聖視する見かたからすれば罪なのです。
つまりは神である推しがたかが人間ごときに堕ちてしまうことはとほうもない裏切りと感じられるのです。三島由紀夫『英霊の聲』の有名な一節を借用するなら「などてすめろぎはひととなりたまいし」となるわけです。
くり返しますが、それはべつだん、アイドルや歌手、俳優に限ったことではありません。
いわゆる「二次元の」キャラクターにしても、しばしばファンの予想や期待を裏切る。
そのキャラクターの裏側には、生身のクリエイターがいるのだから当然ではあります。
たとえば、庵野秀明監督による天才的な演出とダークでミステリアスなストーリーによって人気を集めたアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』は、その最終回に至ってなお数多くの謎を残して終わることで数知れないファンを「裏切った」と認知されました。
裏切りも何も、初めから何ら約束をしたわけではないのですが、そのときのファンの攻撃は苛烈なものでした。
つまりは、期待を裏切られる失望と期待を超えてこられる歓喜はうらはらなのに、人はそのことを都合よく忘れてしまうのです。
オタクはたやすく推しとの自他境界線を見失い、推しを自分自身の欲望を叶えるためだけにある存在であるかのように思い込んでしまう。
その意味では、可能なかぎり推しを「他者化」していくことが必要です。それは必然的に「葛藤」を孕んだ行為となるでしょう。
なぜなら、オタクにとって推しは生身の人間であるよりも「神」であってくれたほうがはるかに都合が良いからです。
ここでいう「葛藤」とは、アイドルを神のように崇めながら一方で冷ややかに「消費」しつづけることの「後ろめたさ」にともなう感情でもあります。
なるほど、オタクは推しに対する愛情を熱く語ります。推しが好きだ。神のように愛している、と。
ですが、ただの人を神として崇めたてまつることは、じつはとほうもない抑圧なのです。
推しについて真剣に考えている人ほど、そのことがよくわかってしまいます。
だから推しを「他者化」していくこと、推しに一定の限界を認めることで、神から人間に戻すことが必要なのです。
ですが、宗教としてのオタク活動において、それは神への失望を意味します。
ここには矛盾と葛藤があります。
推し、つまりアイドルやキャラクターは「この世のありとあらゆる善きものの象徴であり集合」として捉えられていることはすでに書きました。
そこに何らかの「悪しきもの」が必然的に混ざってしまうとしたらどうでしょうか。このような原理によって、推し活はしばしばアイロニカルな信仰になるのです。
③「魔術としてのポップカルチャー」
その昔、魔術の時代がありました。人が世界を理解するために魔術的な思考が必要であった時代です。
魔術はひとつの整然とした論理体系ではあったかもしれませんが、科学的な意味で合理的な思考とはいいがたいでしょう。
近代に入ると、人々は魔術から離れ、自然科学を崇拝するようになっていきました。マックス・ウェーバーはこのプロセスを「脱魔術化」と呼びます。
ウェーバーの講演録『職業としての学問』から「脱魔術化」について触れている個所を引用してみましょう。
したがって、知性主義化と合理化との増大が意味しているのは、ひとを従わせている生活条件についての知識一般の増大ではない。それは何か別のことを意味している。つまり、次のようなことを知っていること、あるいは信じていることを意味しているのである。すなわち、そのつもりになりさえすれば、いつでもそのような知識を得ることができるはずだということ、したがって、我々の生活に関与していながら説明のつかない不思議な力など原則的に存在しないということ、むしろ、いかなる事物も原理的には計算によって支配できるということである。これが意味しているのは、しかし世界の脱魔術化にほかならない。
ウェーバーはここで「脱魔術化」概念を必ずしも肯定的に使っていないことに注意が必要です。
かれはこの言葉を魔術に代わって自然科学を信じ込むようになり、自然科学で説明できないものをあたかも存在しないかのように扱うようになった人々に対する皮肉を込めて使用していたといわれます。
魔術の時代は去りました。しかし、だからといって人々が真に合理的に行動するようになったわけではなく、単に自然科学がその地位に取って代わっただけだともいえるわけです。
そして「脱魔術化」が果たされたいまでもなお、魔術概念は魅力的です。そこにはスピリチュアルにはない暗い響きがあり、どこかでゴシック・カルチャーに一脈通じています。
ゴスについては次の章で触れますが、それはいまでは元々の意味から転じある種の「暗い美学」を指しています。
また、日本においてはゴシックロリータなるファッションスタイルが成立し、独特の地位を占めていることはご存知の通り。
魔術と、魔術に対する関心は、そういったダークな文化に近いところにあります。スピリチュアルが基本的に天使や上位自己(ハイヤーセルフ)といったあかるい響きで人を惹きつけることとは対照的です。
堀江正宗『ポップ・スピリチュアリティ』では、このような性格を持つ魔術が現代のポップカルチャー、特にアニメのなかで使用されている例を集積し、分析を加えています。
それは基本的には単に物語の設定と進行のため利用されているに過ぎないわけですが、一面でそれ自体が魔術そのものでもあります。
このようにストーリーへの信仰に不可欠なものとしての魔術への関心は、本章の冒頭で定義したようなスピリチュアリティへの関心とは相当に違う。ネットでのファンの反応で、魔術や魔的なものを文字通り信じている形跡を確認したことはない。「魔術」への関心といっても、実際に儀式をおこなう実践魔術が登場するわけではない。西洋の儀式魔術はアニメの魔術のように物理的戦闘と結びつくことはない。アニメの視聴者が歴史上の儀式魔術に興味を持ったとしても、空想上の「魔術」の元ネタとして消費しているにすぎない。
しかしリアルと非リアルの区別にこだわらなければ、これら魔術的ファンタジーを生成すること自体が、魔力あるキャラクターの生成と使役でり、一種の魔術とも言える。これは作り手だけが味わえる魔術ではない。視聴者にとって見るという行為は、戦いを見守る存在としてファンタジー世界に参入することである。見なければその世界のストーリーは進行しないのだから、『見ること』は魔力保有者を戦わせるゲームを駆動させること、すなわち魔術を駆使することである。実際、作品がゲームにもなっている場合、それをプレイすれば魔的存在を使役して戦うという「魔術」を誰もが実践できる。
ツイッターにおいて自称「―の魔術師」がアカウント名として使われていたのも、この文脈で理解できる。今日の魔術・宗教的語彙を持ったメディア作品の受容者は、単に作品を受動的に消費するだけなく、より能動的に魔的キャラクターを操作し、使役する存在――魔術師――として自らを同定しているということを意味するのである。
重要な指摘です。
つまり、アニメを見たり、ゲームをプレイしたりすることは、そのストーリーを通して魔的な存在を使役することを意味し、その意味でポップカルチャーは「魔術」であり、そのカルチャーを使いこなす作家たちは「魔術師」だというのです。
もちろん、いままで見てきたように、オタクは絶対倫理として現実と虚構を明確に区別し、べつだん、作中に登場する魔術をそのまま信じ込んでいるわけではありません。
しかし、魔的な作品を生み出し、あるいは消費する、その行為そのものが魔術的なプロセスだという指摘はうなずけます。
現代のオタクたちのポップカルチャー消費はその意味で魔術なのです。
ただ、堀江は「ネットでのファンの反応で、魔術や魔的なものを文字通り信じている形跡を確認したことはない」と書いていますが、もっと文字通りの意味でポップカルチャーを魔術として使用している例にテイラー・エルウッド『ポップカルチャーマジック』があります。
これはまさに文字通りポップカルチャーで魔術(マジック)を実践しようとする本で、女性SF作家ストーム・コンスタンティンの寄稿文が寄せられています。
コンスタンティンは日本でこそ無名ですが(邦訳は雑誌などに掲載された短編がわずか三本あるのみ)、カルトでデカダンな作風で知られる人物であり、まさに「現代の魔術」の教典に寄稿文を寄せるに書くにふさわしいといえます。
この本のなかでは、日本のオタクにとっても親しい作品、たとえば『新世紀エヴァンゲリオン』や『ファイナルファンタジー』が魔術的に読み解かれています。
つまりは二次元と三次元の「世界境界」を飛び越えてしまっているわけで、オタクにとっての倫理を侵犯しています。その意味ではシニカルなオタクからは「まさに中二病だ」と嘲笑されるかもしれません。
ですが、先の堀江の記述を踏まえれば、オタク文化と魔術とのアフィニティは強く、「魔術としてのポップカルチャー」は無意識的にせよ存在しています。その意味で、こういった本が出てくることも必然ではあるのでしょう。
ここまで、信仰としての推し活と、魔術としてのポップカルチャーを見てきました。
いずれも、オタクたちはあくまでひとつの物語として消費しているに過ぎず、じっさいに信じ込んでいるわけではないと主張するでしょう。
その通りではあります。しかし、そこにそれだけでは済まないものが秘められていることも見て来たとおりです。
次節以降は、さらにオタク文化の性質に深く入り込んでいってみましょう。
④「少女たちの輪廻転生」
オタク的にフィクションを愛好する文化と、スピリチュアルなものを愛でるもうひとつの文化とを語るとき、どうしても触れておきたいひとつの「事件」、あるいは「現象」があります。
オカルト雑誌『ムー』の誌上でくり広げられた「戦士症候群」です。
これは『ムー』の文通コーナーで「ともに戦う戦士」や「転生者の仲間」を探し求める少女たちが続出した事件で、狭い意味でのスピリチュアル文化からは外れるかもしれませんが、マンガ・アニメ文化と霊性的なるものが交錯した一例として、やはり取り上げないわけにはいきません。
Wikipediaによると、具体的にはこのような「現象」でした。
1980年代、オカルト雑誌『ムー』(学研)の文通コーナー「コンタクト・プラザ」や『トワイライトゾーン』(ワールドフォトプレス)、『マヤ』(学研)の文通コーナーに、以下に述べるパターンの投稿が多発し、やがて投稿コーナーのほとんどがそれらで埋め尽くされてしまう現象が起こった。投稿の内容は、「自分は目覚めた戦士」で「仲間の戦士を探しています」という戦士パターンと、「自分は前世の記憶を取り戻した転生者」で「前世で繋がっていた仲間を探しています」という転生者パターンの2パターンおよびそのミックスに大きく分類される。戦士に目覚めて仲間を探す戦士パターンは、平井和正と石ノ森章太郎の『幻魔大戦シリーズ』(特に1983年公開の劇場版『幻魔大戦』)の影響を強く受けており、転生者パターンはテレビアニメ 『ムーの白鯨』や冬木るりかの『アリーズ』、佐藤史生の『ワン・ゼロ』など、転生した仲間たちと共に敵と戦うといった当時流行した作品に影響を受けた設定が多い。また戦士パターンには来たるべき最終戦争(ハルマゲドン)に関して五島勉の『ノストラダムスの大予言』の影響もみられるが、転生者パターンでも戦士は登場し、これは必ずしもハルマゲドンと結びつかず、むしろ身分のひとつとされている。両パターンともオーラにより階級や身分が識別、判断されるといった内容が散見される。1986年から『花とゆめ』で連載された日渡早紀の漫画『ぼくの地球を守って』は、この戦士症候群にヒントを得ており、作中では「学嫌社」のオカルト雑誌『ブー』上で仲間を募る設定である。
この「戦士症候群」については浅羽通明『天使の王国』がくわしい。
同書によると「戦士症候群」の主人公はごくふつうの女の子たちでした。かれらは平井和正原作のオカルティックなアニメ『幻魔大戦』などに影響を受け、独自の世界観を生み出しました。
しばしば『ぼくの地球を守って』がすべての「戦士症候群」の原因であるかのように語られますが、じっさいには上記引用にあるように『ムー』本誌における「戦士症候群」の発生のほうが前であって、そういった現象をモデルに作家が『ぼくの地球を守って』の物語を紡いだというほうが正しいようです。
しかし、いずれにしろ、『ぼくの地球を守って』が少女たちの想像力に火を点けたことは事実です。
1989年には徳島県で小中学生の女子三名が解熱剤を大量に飲んで自殺を図り、救急搬送される事件が起こりました。
彼女たちは「前世は美しいお姫様のミリナやミルシャー」であるという筋書きを作っており、「前世をのぞくために一度死んで戻るつもりだった」と語ったのでした。
この年、日渡は『ぼくの地球を守って』の単行本において、この作品があくまでフィクションであることを説明し、フィクションと現実の区別をつけてほしいと語っています。
この事件は少女たちの自殺未遂という衝撃的な形で虚構と現実の「世界境界」が明確に破られた、マンガ史上でも非常にめずらしい例でしょう。
もちろん、少女漫画においてはしばしば超能力や心霊体験といったスピリチュアルなテーマが描かれます。
それはホラーとして描写されることもあるし、もっと明るいアクションものとして綴られることもあるでしょうが、半ば「現実にありえること」として受け止められています。
そういう意味では、少女マンガとオカルティックだったりスピリチュアルだったりする文化はきわめて相性が良い。マンガを描くことをやめて新興宗教教祖になってしまった作家すら存在するくらいなのです。
ですが、それにしても、マンガの内容がここまでダイレクトに読者に影響をあたえることは、ひとつの驚きです。
もちろん、ここでの主役はアイロニカルにひねくれたオタクたちというよりは、もっと純真な子供たちであるに過ぎません。
それはそうなのですが、フィクションの影響力を考えるとき、このケースは非常に重要なサンプルになります。
わたしたちが考える「世界境界」、リアルとフィクションの境い目は案外、そこまで強固なものとして認識されているものではないのかもしれないということ。
もっとも、雑誌『イマドキの神さま』収録の論考によると、彼女たちは本気で前世を信じていたというよりは、すべてわかっていて「あえて」演じていた可能性が高いともいいます。それはそれで興味深い話です。
浅羽は一連の事件を分析して、コミックマーケットで同人誌を出版して仲間を求める女の子たちとの関係を語っています。
たしかに、事件の背景に「強いきずなで結ばれた親友、あるいは仲間がほしい」という動機があるとすれば、コミケで二次創作同人誌を売買する女性たちとも無関係ではないでしょう。ようは、どこで「つながり」を手に入れるかという話だからです。
オタクはオタク文化に「癒やし」や「救い」とともに、しばしば「つながり」も求めます。そういう意味では、承認と友愛のゲームとしての「戦士症候群」はいまも形を変えて続いているのです。
浅羽はこの社会において自分の存在の凡庸さに悩み、少しでも特別な存在になろうとしたと思われる少女たちのことをかなり好意的に語っています。
「彼らがそうした逃避行の中でサブカルチャーから借りてきた修辞(レトリック)と論理(ロジック)と世界像(イデオロギー)をつぎはぎしながら、たとえ数人の間であれ言葉を共有し、もうひとつの常識をつくり出そうと不器用にじたばたしている姿に、私はある感動を覚えざるを得ない」。
同感です。
たしかにこの「戦士症候群」は思春期の未熟な精神がスピリチュアルの時代を背景として発露したものに過ぎないでしょう。しかし、切ないほど「特別な存在」になりたいというその動機はきわめて良く理解できます。
この社会においては、多くの人々が注目と承認に飢え、「もっとわたしを見て!」と叫んでいます。
きょう、インターネットでも同種の動機にもとづく承認欲求のゲームは枚挙にいとまがないほど散見されます。そういう意味では、何も古い話にはなっていないのです。
この社会に十分に適応した大人から見れば、この種の「特別な自分」を求め、承認欲求に踊らされている子供たちはいかにも幼く、愚かしく思われるかもしれません。
ですが、わたしはこのいびつな社会の形に器用にアジャストして生きている人たちより、このように不器用に失敗して幻想と物語を求める人々により強く共感します。
何より、わたし自身がそういうひとりだからです。
『ぼくの地球を守って』は優れた作品ですが、ひとつのフィクションに過ぎません。
『ムー』の投稿欄で語られていたようなムー大陸もレムリア大陸も、前世の紐帯で結ばれた戦士たちもすべてはひとつの夢物語以上のものではないのです。
ですが、そのような形で個性化したいという欲望を、いま、だれが笑えるでしょうか。
それはたとえば、涼宮ハルヒが自分の「存在の耐えられない軽さ」、空虚な凡庸さに悩んだことに通底する青春の苦しみです。
それが一足にスピリチュアルな次元に飛躍してしまったことには違和感を覚えるとしても、本質的にはより普遍的な問題なのです。
⑤「夢幻の版図」
信仰としての推し活。
魔術としてのポップカルチャー。
そして少女たちの「戦士症候群」。
このように、人にとってフィクションはときに聖なる性格を帯びます。
たかが虚構であり、オタクたち自身ですらアイロニカルに接しているはずの物語が、この世の他の何よりも神聖なものとして端的な魅力を放つことがありえるのです。
そして、ここに、オタク文化とスピリチュアル文化を混交させひとつの作品として見事に結実させた作家があります。
滝本竜彦。
その滝本の最新の成果が、かれが七年もの沈黙の末に発表した『ライト・ノベル』です。
このタイトルはちょっとしたダブルミーニングになっていて、「軽い小説」と同時に「光の小説」を意味しています。
光の小説。
大袈裟なタイトルに思われるかもしれませんが、じっさい、この小説は「光」を志向しています。
あらすじをまとめてみても要領を得ないような不明快なストーリーなのですが、それにもかかわらず、『ライト・ノベル』には人の心を打つ何かがたしかにある。
ひとつにはこの小説の世界設定が「光」と「闇」を行き来する人間の精神の構造そのものを象徴的に表していて、主人公たちは「光」の方向を志向しているからです。
この作品の世界には、より上部の「光の世界」とより下部の「闇の迷宮」が存在し、人はときに光をめざし、ときに闇に惑いつづけているのです。これは単にファンタジックな物語設定というだけではありません。作家の認識する世界の、あるいは人間心理の構造そのものです。
このようなスーパーナチュラルな設定はファンタジー作品としてはごく普通のものだと思われるでしょうか。ある意味ではその通り。
最近はあまりに「ベタ」なパターンと化してそれほど見かけなくなりましたが、その昔、よくファンタジーで描かれていた「光」と「闇」の対決とは、それ自体が人間の心のなかでのライトサイドとダークサイドの対決という側面を持ちます。
その意味で、ファンタジーとは一般に人間心理のなかの出来事を象徴的に描き出す物語だといえます。
ですが、『ライト・ノベル』の特異さは、作家の現実認識をそのままに物語の形にしていることでしょう。
そういう意味ではまさにわたしがいうところの「オタク・スピリチュアリティ」の結晶のような小説です。
この作品に「聖なるもの」を見て取ることができるかどうかは人それぞれでしょうが、これほどオタク的なるものとスピリチュアル的なるものが一体化している作品は他に類を見ません。
この快挙、もしくは怪挙は、作家自身が「ヒーラー」、「瞑想家」としてスピリチュアルな活動を熱心に続けていることと強く関係しています。
滝本は「オタク」にして「スピリチュアリスト」という稀有なルートを歩んでいる作家なのです。
もちろん、ここまでくり返し述べているように、オタクにとって「世界境界」を超えてリアルとフィクションを混ぜ合わせることは倫理に反する愚かな行為です。
しかし、滝本はその禁忌を破って、なお、オタクでありつづけているのです。驚異といって良いでしょう。
たとえば後年、宗教的な作品に走った平井和正のように、物語作家としてキャリアを始めてスピリチュアルな方向へ向かった作家の先例がないわけではありません。
また、平井のその時期の作品はじっさい『ライト・ノベル』とよく似ているところもあります。
しかし、そういった作品はあまりにスピリチュアルな側面を強調するために、エンターテインメントとしては過度に歪んだしろものになってしまうのが常でした。
ところが、『ライト・ノベル』はオタク的なライトノベルとしてごく普通に読めます。そこには通俗作家としてのバランス感覚が残っているのです。
たしかに、一面では「わけのわからない話」で、「向こう側に行ってしまった」印象が残ることもたしかなのですが、それでもこの小説はオタク的なライトノベルらしさを残しています。
その不思議な混交が『ライト・ノベル』のオリジナリティです。
それは滝本竜彦が長い長い思索や苦悩の果てにたどり着いた境地なのでしょう。
滝本は悩める作家でした。かれは元々、学生時代から長い社会的ひきこもり生活を送っていたのですが、その間にデビュー作『ネガティヴ・ハッピー・チェーンソー・エッヂ』を執筆して世に出ます。
そして、自身のひきこもり生活をモデルにした第二作『NHKにようこそ!』はマンガ化、アニメ化され、広く話題となりました。
ある意味では自分の人生経験を活かしたわけですが、「自分自身のこと」を書いてしまえばその先に書くものがなくなってしまうことは必然です。そこから先、滝本の彷徨が始まります。
その頃、滝本の小説はある意味でシンプルでした。ネガティヴな少年とかれの世界を劇的に変化させる聖少女。ボーイ・ミーツ・ガール。
傍から見ると、かれはその構造を否定してよりシビアな、よりリアルな物語世界へと向かおうとして、その痛みに耐えかねていたようにも見えました。
滝本は『NHKにようこそ!』の後、『僕のエア』を挟んで、作者自身が「悟り」をテーマにしたという『ムーの少年』からついに『ライト・ノベル』へと、スピリチュアルな文化に活路を見いだしました。
『ライト・ノベル』はほんとうに不思議な小説です。唐突に美少女の姿をした「天使」が出てきたり、世界の上部と下部を放浪する探究者が登場したりと、その世界観は奇妙でとっつきづらい。
それを作者自身がスピリチュアルな文化に傾倒して狂ってしまったのだ、とまとめてしまうことはできる。じっさい、そのようにわかりやすく理解したつもりになることは簡単です。
しかし、同時にここには狭い意味での「オタク的なるもの」があふれんばかりに満ちている。この小説はスピリチュアル的でもあり、オタク的でもあるのです。
あらすじを引用してみましょう。
「こんにちはーにゃ!」―貴重な青春を無難に過ごすだけの高校生・ふみひろの前に出現した光のゲート。そこを潜り抜け出てきたのは、猫耳やしっぽを持つ美しい女の子だった。以来ふみひろの前には、美少女という名の天使たちが次々と現れる。普通の少年に突然訪れるハーレムな日常。そこに隠された驚くべき世界の真実とは―!?
まさにオタク的というか、ライトノベル的な軽薄さ。じっさい、読んでみてもオタク的な意匠は各所に出て来ます。
それゆえに、あるいはそれにもかかわらず、この「光の小説」はじつに異様な読み味です。
オタク的な意匠を使って、現実に描き出そうとしているものはまったくべつのファンタジーなのです。初期滝本作品ともまったく異なった読後感です。
ただ作者がスピリチュアルに傾倒したからそうなっただけではないでしょう。
初期には主観的に狭い視野で描かれていたものが、客観的に広い視野で描写されている印象を受けます。
ある個人の悩みと苦しみにフォーカスするのではなく、人を悩ませ苦しめるものの正体は何なのか、その「全体像」を活写しているわけです。
海猫沢めろんはこのように書いています。
「物語は、不登校の少年「ふみひろ」が学校へ行くところから始まる。
やがて、闇の大迷宮の底にいる闇の魔術師を探すエクスプローラー「ミーニャ」と出会い、日常が非日常へと変わっていく。
そして、この小説は次第に奇妙なねじれを起こしていく。
母と性行為をしようとしている異常さに気づくふみひろ、クラスメイトたちとの部活作り、かつて闇の小説を書いていたという先生。
こうして要素を取り出すとおどろおどろしい部分もあるが、全体的にはさっぱりしたギャグに包まれており、あくまでライトな読み味だ。
ただ、初期作と同じ読み味を期待した読者は困惑するかも知れない。
ここには、かつてのネガティヴで後ろ向きな少年と、それを救ってくれる聖母のような少女は存在しない。
青春の蹉跌も存在しない。
存在するのは新しい少年と少女たち、そして新しい作品、新しい作者――だが、確かにこれは滝本竜彦の作品なのだ。」
的確な評価です。
かつてのひたすらにネガティヴで苦悩に満ちた滝本の世界と比べると、この作品は「全体的にはさっぱりしたギャグに包まれており、あくまでライトな読み味」です。
それは作家自身が青春の辛さ、ディスコミュニケーションの苦しさから一定の距離を取って観察していることを意味しています。
かつて『ムーの少年』で「悟り」をテーマにした滝本は、じっさいに悟りを開いたのでしょうか。
この小説の世界はスピリチュアルで広く、高い場所を目指していながら、一方で極度に淫猥で性的、それも近親相姦的なイメージに満ちてもいます。
いったいこれは何なのだろうと不審に思う人もいるに違いありませんが、わたしの解釈ではこの作品は、スピリチュアルの言語で描かれた人間の内的宇宙(インタースペース)、つまり「夢幻の版図」の冒険記録なのです。
この『ライト・ノベル』の後、滝本の作風はさらにライト(light)な方向に進んでいます。かれはたしかに、ここで何かを掴んだのでしょう。
光の小説とは、つまり光をめざす小説です。それはオタクとしても、スピリチュアリストとしても、ひとつの成熟を意味しているのではないでしょうか。
⑥「いったい何のために生まれてきたのか?」
最後に、より深遠な意味で「宗教的な問い」を示している名作を紹介しておきましょう。『ハチクロ』の異称で知られる羽海野チカの少女マンガ『ハチミツとクローバー』です。
ここで『ハチクロ』の名前を出すことは意外であるかもしれません。
『ハチクロ』は恋のすれ違いなどのセンチメンタルな描写はあるものの、基本的にはライトなラブコメディであり、宗教ともスピリチュアリティとも関わりがないように見えるからです。
たしかにこの物語に表層的な意味での宗教的な要素はありません。超能力や魔法といったスーパーナチュラルな要素も登場しません。
しかし、それでも、この作品のテーマはきわめて宗教的です。その個性は物語終盤、露呈します。具体的には「愛の格差」として。
この場合の「格差」とは、「愛されることの格差」を指します。
この世には「だれにでも愛される人」もいれば、「だれからも愛されない人」もいる。愛には格差があるのです。
少女マンガでは、主人公はしばしばご都合主義的にその「格差」における「勝ち組」として描写されるわけですが、『ハチクロ』では必ずしも「勝ち組」だけに焦点があたるわけではありません。
羽海野はむしろ、その「負け組」の苦しみを克明に描き出します。
そのことが最も端的にあらわれるのは、過去回想です。
昔から親友の「忍」に対して劣等感を抱えるある人物の独白として、「愛されない者」の苦悩が語られます。
「忍… 忍…オレはずっと不思議だった どうしてこの世は「持つ者」と 「持たざる者」に分かれるのか どうして「愛される者」と 「愛されない者」が在るのか 誰がそれを分けたのか どこが分かれ道だったのか ――そもそも 分かれ道などあったのか? 生まれた時にはもうすべて決まっていたのではないか? ならば ああ 神さま オレのこの人生は 何の為にあったのですか」。
「神さま」に向かって「この世の摂理の理不尽」を切々と問いかけるこの一連のセリフはきわめて宗教的です。即ち「ビッグ・クエスチョン」。
『ハチミツとクローバー』は一般にはあたりまえの恋愛マンガとして理解されているものの、その実、羽海野の天才的な洞察力は宗教的な次元にまで到達しているのです。
もちろん、物語のなかで神が直接にこの問いに答えることはありません。神は沈黙を続けるばかり。人はみずからこの問いに答えるしかないのです。
しかし、それはあまりにも深刻な問いです。
「この人生は何の為にあったのですか」とは、つまり「人生の意味」を問うているわけですが、本来、人生に所与の意味など存在しないのです。人は生まれながらにして無意味な存在としてこの世にあります。
ただ、いうまでもなく、そのような当然の答えはあらかじめ問いに組み込まれています。
その上で、それでも、なお「いったい自分の人生は何のためにあったのか」と問わなければならない切迫した心理が重要です。
ここでは、そもそも無意味な生に意味をあたえるものとして「愛」が定義されています。
愛さえあれば、だれかが愛してくれれば、どんなに無意味な生も生きていくことができる。
しかし「愛されない者」にとって、それはどんなに求めても手が届かない、高すぎる樹になった果実なのです。
それでいて、「愛される者」はあたりまえのようにその「愛」を手に入れてしまう。ただ生きているだけでまわりから愛され、尊敬される人間すら実在する。
それは「生まれたときにはもうすべて決まっていた」ことなのかもしれない。
そうだとしたら、「愛されない者」はどのように生きれば良いのか。ただひたすら虚無と無意味の闇の底へ墜ちていくことしかできないのか。
物語は強く、切なく問いかけます。
いったいこの「問い」にどのように答えたら良いのでしょう?
「愛」は選別の、差別の感情です。「万人に対する平等な愛」は神しか持ちえない。
したがって、この世に「持つ者」と「持たざる者」、「愛される者」と「愛されない者」が生まれることはどうしようもない。
仮に人類がすべての経済的な格差問題を解決できたとしても、この「愛の格差問題」は「最後の人間らしさ」として残ることでしょう。
ですが、もしそうだとしたら、人間の存在は何と不安定なのでしょうか。
生まれてすぐ十分な愛情を込めて養育されるかどうか、つまり「愛されるか否か」によって人の基本的性格がある程度決定されてしまうことは現代では広く知られています。
「親(養育者)に愛されなかった」人物はしばしば破滅的な人生を選ぶ。いわゆる「愛着障害」です。
この障害を抱えた人間は、どれほどの才能、財産、名声を獲得したとしても、あたりまえの幸せな人生を生きることができません。
たとえば、困難な人生を生き、文学的天才を開花させながらも最後には自殺を遂げた太宰治やヘミングウェイなどはその典型だとされます。
「愛されない者」の人生には孤立の宿命が刻印されています。その数何十億にもなる人に囲まれて生きていながら、あたかも無限の大宇宙にひとり投げ出されたかのような孤独。
それはつまり「虚無」の深淵をのぞき込んだことに他なりません。
人は自分の生に何らかの意味があると信じられるときこそ充実して生きられるのですが、「虚無」はその幻想を、錯覚を、粉々に打ち砕いてしまう。
そのときこそ、人は「神さま」に、問わざるを得なくなるのです。「ああ 神さま オレのこの人生は 何の為にあったのですか」と。
それはかつての実存主義文学作品、サルトルの『嘔吐』やカミュの『異邦人』で描かれた「不条理の感覚」です。
「虚無」の深淵を見るとき、人は何もかもむなしく感じざるを得ない。
それとも、「虚無」と向き合ってなお、「前を向く」ことができる生き方もあるのでしょうか。
わたしはここで宮崎駿『風の谷のナウシカ』を思い出します。
ナウシカもまた「母に愛されなかった」子供でした。ナウシカの心のなかにはやはり一種の「欠落」がありました。
そして彼女は長い冒険の末、ついに、滅亡した先史文明を代表し、人類全体を新世界、新時代へ導いていこうとするなぞめいた「墓所」と対決します。
整然とした正義の論理を掲げ、人類再生の計画で彼女を説き伏せようとする墓所の「ヒドラ」に対し、ナウシカはあくまで人間の人間らしさを擁護しようとしま
す。その言葉を「ヒドラ」は「それは虚無だ!!」と告発するが、彼女はかれに「王蟲のいたわりと友愛は虚無の深淵から生まれた」と答えるのです。
そして、その先に「いのちは闇の中のまたたく光だ!」という有名なセリフが続きます。
このとき、ナウシカは「虚無」の深淵をのぞき込み、「虚無」との対話を経て「墓所」と向き合ったからこそ「ヒドラ」の論理を打ち破ることができたのではないでしょうか。
虚無より生まれ、虚無へ還っていく。それは人間がどうしても避けられないひとつの宿命です。
人の生は、どれほど豊饒で安全な社会にあってもなお、さまざまな意味で「虚無」に面しているのですから。
それなら、人が「闇の中」で「光をまたたかせる」とはどういうことなのでしょうか?
『ハチクロ』では「光に向かって進んでいく」「世界で一番小さいロボット」が描かれ、「光をめざす」ことの大切さが綴られていました。
しかし、ほんとうに「だれからも愛されない者」にそのようなことができるのでしょうか?
そもそも「光」とは何で、「光の差す方向」とはどちらなのでしょう?
それすらわからない者に、いったい「光をめざしつづける生き方」など可能なものでしょうか?
この「問い」に対して本書が示すひとつの答えが「「推し」を見つけること」です。
つまり、「愛される」ことにこだわるのではなく、「愛すること」を選ぶこと。
とはいえ、一般的にいって、だれからも愛されず、愛着障害を抱えているような人間にとって「愛すること」はきわめて困難です。
かれ/彼女の愛着は壊れている。しかし、そういった人でも「この世のありとあらゆる善きものの象徴にして集合」としての「推し」を愛することはできる。
そのようなとき、「愛すること」はその人にとってかけがえのない癒やし、そして救いになるでしょう。
それはかつて宗教が果たしてきた役割です。しかし、時代は変わり、宗教のナラティヴは説得力を失ってきた。そこで「推し」が重要になるわけです。
ある種の人々は「推し」を見いだすことによって初めてくらやみのなかで「光差す方向」を知ることができます。
その「光の道しるべ」、それは宮台真司が「サイファ」と呼び、田口ランディが「〈神聖さ〉のイデア」と語り、藤本由香里が「わたしの北極星」と名づけたものに他なりません。
それは「愛されない者」にとって、地獄に堕ちたカンダタに垂らされた蜘蛛の糸のように自分と世界とを結びつける最後の希望となるでしょう。
大仰ないい草でしょうか? しかし、だれよりもわたし自身がそうやって物語によって救われてきました。ときにフィクションであるに過ぎないはずのナラティヴは人を救う。
オタクなら、苦しくて苦しくてたまらないとき、自分こそが推し、応援しているはずのその対象に救われたことが一度はあるのではないでしょうか?
そのヒエロファニーを通して、ボロボロの人生は「闇の中でまたたく」。
暗い夜空を可憐に舞い翔ぶ、一匹の儚いホタルのように。
次の記事に続きます。






![その着せ替え人形は恋をする 1(完全生産限定版) [Blu-ray] その着せ替え人形は恋をする 1(完全生産限定版) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51kSKRiHmxL._SL500_.jpg)






















































![コードギアス 反逆のルルーシュ 1期 コンプリート DVD-BOX (全25話, 576分) アニメ [DVD] [Import] コードギアス 反逆のルルーシュ 1期 コンプリート DVD-BOX (全25話, 576分) アニメ [DVD] [Import]](https://m.media-amazon.com/images/I/5182ci3c1rL._SL500_.jpg)
















![ホドロフスキーのサイコマジック・ストーリー [DVD] ホドロフスキーのサイコマジック・ストーリー [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51+uawAZkRL._SL500_.jpg)
![ホドロフスキーのDUNE [Blu-ray] ホドロフスキーのDUNE [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/51uq7lcVp3L._SL500_.jpg)

















![幻魔大戦 [Blu-ray] 幻魔大戦 [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/61rLpYwU-rL._SL500_.jpg)