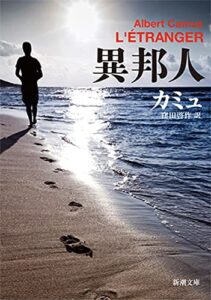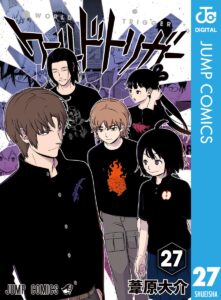アルベール・カミュの実存主義文学の傑作といわれる『異邦人』は、「今日、ママンが死んだ。もしかしすると昨日かもしれないが、私にはわからない。」というショッキングな文章で始まる。
トルストイの『アンナ・カレーニナ』などと並んで、文学史上でも指折りの「印象的な最初の一文(正確には二文だけれど)」だろう。
しかし、この文章が読者の心に一瞬でつよく刻み込まれるのはなぜだろうか。
それは、「母親が死んだ日をわからない」ということが、単なる親不孝を超えて、異常なまでの虚無と荒廃を感じさせるからだろう。
母親が死んだ。今日だと思うが、昨日かもしれない。たったこれだけのことなのだが、主人公ムルソーの内面の荒涼とした光景を想起させるものがある。
この人物の心理はいわゆる「人間的」な心の形からかけ離れているのではないかと感じさせるのである。
しかし、よくよく考えてみると、母親の死んだ日がわからないという程度のことが、なぜそれほどまでにインパクトをともなっているのかは不思議でもある。
遠く離れたところにいて連絡を受けたのなら、死んだ日が一日、二日ずれていてもわからないことはむしろ当然のことだ。
それなのに、ぼくたち(少なくともぼく)がこの一文からある種の冷淡さを感じ取ってしまうのは、この社会に「母」を重視する価値観がいかに根強くはびこっているかを表しているように思われる。
「母」は強し、といえば良いだろうか。
そういえば、きのう、漫画家・西原理恵子さんの娘で俳優の鴨志田ひよさんがアパートから飛び降りて骨折したというニュースが飛び込んできた。
彼女がいったい何を思って飛び降りたのかはわからないわけだが、背景には母親との葛藤があるといわれている。
というのも、鴨志田さんはいままで西原さんの「毒親」ぶりをさまざまに告発してきたからだ。彼女はいままずっと西原さんの「悪い親」ぶりに苦しめられてきたという。
ネットでは、例によって西原さんを批判する声が盛り上がっているようだが、ぼくはべつだん、その点に深入りしようとは思わない。
もちろん、鴨志田さんの告発の内容が事実だとすればひどい話だと思うが、あくまでよく知らない家庭のことだし、声高に責めるだけのモチベーションはぼくにはない。
ただ、あえてこのニュースを取り上げたのは、娘が母親を相対化することって、ほんとうに大変なんだなあとあらためて感じ入ったからだ。
斎藤環さんが書いているように「母は娘の人生を支配する」。
その支配から脱却し、「母殺し」を達成することはじっさい容易ではないのだろう。
なかなか「今日死んでいても、昨日死んでいてもどうでもいい」というところまでは行かないのである。
ぼくのこのような書き方を露悪的なものと見る人もいるかもしれない。
そうではない。ぼくももちろん、「まともな母」の範疇に入る人物なら、それなりに尊重するべきだと思う。
何をして「まともな母」というべきなのかはわからないが、とにかくそれなりに正常なつきあいができる母親ならば、そういった関係を維持しても良いはずだ。
しかし、いわゆる「毒親」あいてはそうはいかない。そのような「毒親」は、さっさとその支配圏から脱出し、捨てるか殺すかするしかない。
もちろん、この場合の「母殺し」とはじっさいに包丁で刺して殺してしまうということではなく、あくまで象徴的な話ではあるのだが。
とはいえ、しばしば「母殺し」は「父殺し」より遥かに困難だといわれる。
じっさい、前述の『母は娘を支配する』では、そのむずかしさがくり返し語られている。
母は娘の人生を支配して離さない、そこから抜け出すことは非常に困難なのだ、と。
そのむずかしさを物語の形で克明に思い知らせてくれるのがたとえば少女マンガである。
ある時期までの少女マンガには、「母」、あるいは「母と娘」をテーマにした作品が膨大にあった。
「母と息子」を入れればさらに多いだろう。この場合、「息子」に仮託されているのはじっさいには「娘」である作者の心理であったりするわけで、それらも広く「母と娘」の関係を描く作品として見ることができるかもしれない。
そして、そのなかでも萩尾望都の『イグアナの娘』や、よしながふみの『愛すべき娘たち』といった作品は珠玉の名作として知られている。
これらの作品が「母と娘」をどう描いているか、その点に関しては気鋭の批評家である三宅香帆さんの『母と娘の物語』という連載にくわしい。
この連載は少女マンガだけをターゲットにしたものではないが、ある種の少女マンガ論として読め、きわめて納得度が高い。
そこで取り上げられている作品を知る「少女マンガ読み」なら、「わかるわかる」とうなずく点も多いだろう。
しかし、一方でぼくはこの「母の呪縛」について書かれたテキストを読んでいて、どうにも、うまくいい表せないある違和感を抱いていた。
そのような違和感は、もし言語化できなければ単なる難癖であるに過ぎない。
著者としても「何か違う気がするんだけれど、うまくいい表せない」などといわれても困るばかりだろう(ぼくなら困る)。
それで、どうにか言語化しようとがんばってみたのだが、ようは「ほんとうに母殺しとはそこまで困難なことなのだろうか」という言葉に尽きるように思った。
どういうことか。「娘による母殺し」の困難性はこれまでさまざまな論者がくり返し語ってきたことであり、さらには『イグアナの娘』のような芸術的な作品でも強調されている。
『イグアナの娘』にせよ、『愛すべき娘たち』にせよ、娘は最終的に母の呪縛から抜け出し切れない。
「母なるもの」の恐ろしさ、おぞましさという一面がどこまでも強調されているのである。
これらを読んだ上でなおかつ「母殺しはほんとうにむずかしいのか」と問いを立てることは不見識とのそしりを免れないだろう。
だが、それでもぼくはあえていう。母殺しとは、ほんとうにそのような不可能に近い難事なのだろうか、と。
というのも、現実には「毒親育ち」であっても、それなりに「母殺し」ないし「母離れ」を成し遂げた「娘」がいるはずだからである。
もちろん、斎藤環などが書いているように、じっさい、「母殺し」は難しいのだろう。
すべての娘は母が全知にして全能の「神」のような存在であった頃の記憶を抱えている。
その「神」を「殺し」、ただのあたりまえの人間にまで相対化しようとする行為はタフな作業だ。
萩尾望都の『残酷な神が支配する』や『ローマへの道』といった作品でくり返し描かれているように、それはほんとうに神経をすり減らす作業であるに違いない。
しかし、そうはいっても何もすべての女性が母親を相対化できずにいるわけではない。
なかには、いわゆる「毒親育ち」でありながら、母親の呪縛を乗り越え、元気に、しあわせに暮らしている人だっていくらでもいるはずだ。
それなのに、作品でも批評でも「母親の影響の強大さ」ばかりが強調される傾向があることはなぜだろう。
そうなのだ、ぼくはそこに、むしろ「母を殺してはならない」という規範が作用しているのではないか、と思ってしまうのである。
娘が母を殺せないのはなぜか。そこにはさまざまな理由が関与しているだろうが、ひとつには「母を殺すこと、捨てること、ただのひとりの人間として相対化してしまうこと」が社会の母性幻想、孝子規範に背くからだろう。
この社会のすべては家庭と、その家庭を支える「母とはみな子供を愛し、育むものである」という美しい、しかし非現実的としかいいようがない前提の上に成り立っている。
その前提、その幻想を破壊することは社会そのものを崩壊させかねない「罪」とみなされうる。
だからこそ、「母殺し」の困難さは強調され、物語のなかの娘たちはいつまでもいつまでも「母の呪縛」に苦しみつづけるのではないだろうか。
何といってもフィクションはフィクションなのだ。「母なるもの」をあっさりと相対化し、自由に生きている「娘」だって出て来ても良いはずである。
それはファンタジーとしかいいようがないほど現実離れした話だろうか。そうは思わない。くり返すが、そのような「娘」は現実にたくさんいるはずなのだから。
そもそも、ぼくは人は幼少の頃の家庭環境ですべてが決まってしまうというような物言いを好きになれない。
なるほど、子供の頃の父や母の影響は大きいかもしれない。しかし、人は大人になる過程でそれを乗り越えていくことができるはずだ。
そうでなければ、人間の一生は文字通り「親ガチャ」ですべてが決まってしまうことになるではないか。
少女マンガ論も書いているアダルトビデオ監督の二村ヒトシさんは、ここら辺のことを説明するために「心の穴」という言葉を使う。
かれによれば、すべての人の心には幼少期の育ち方によって「穴」が空いていて、その「穴」がかれを、彼女を動かしているのだ、というのである。
だが、二村さんをリスペクトしてはいるものの、ぼくはこの「心の穴」理論にはどうにも違和感を感じる。
「人は幼年期にできた心の穴にもとづく行動を反復する」とは、もっともらしくはあるが、しょせん検証不可能のアイディアに過ぎない。
そのアイディアが説得力を持つのはなぜか。「人は幼年期のトラウマに縛られる」という精神分析的な観念がいまの社会で常識化しているからだ。
それは「母殺し」がむずかしいという話と一脈通じるものがある。
当然ながら、こういった理論を完全に否定することはできない。じっさい、人は生涯、母の影響から完全に脱することはできないのかもしれない。「母殺し」は不可能なのかもしれない。多くの作品と批評がそのリアリティを支持している。
しかし。しかし、だ。ぼくはここで意図して疑問を提示したい。
「母殺し」がじっさいにさまざまな困難を抱えているとしても、否、むしろそうであるからこそ、ぼくたちはその困難に苦しむ「娘」たちに希望と解放を届けなければならないのではないか、と。
そして、何がいいたいのかといえば、「母殺し」の困難性ばかりを強調する物語と批評は結局、「母は殺せない」というストーリーを支持し強化してしまっているのではないだろうかということなのだ。
「母殺し」はむずかしいと語ること、それ自体は悪くない。じっさいにむずかしいのだから。
ただ、ひたすらにむずかしさ「だけ」を強調するばかりでは、むしろ、「毒親」を利し、その支配に苦しむ「娘」たちを傷つけ、苦しめ、絶望させることにしかつながらないだろう。
つまり、たくさんの物語や批評が「母殺し」のむずかしさを強調すればするほど、読者に「ああ、やっぱり母親を捨ててしまうことはむずかしいことだし、ほんとうに恐ろしいことなんだ」という印象をあたえるように思うのである。
ぼくは天才的な名作や高度な批評に対して、とんでもないことをいってしまっているだろうか。
だが、それらの素晴らしい作品たちは、問題をあきらかにし、告発する意図を十全に満たしている一方で、いままに悩み、苦しんでいる「娘」たちをエンパワーメントする力は、必ずしも強くないようにも思うのだ。
それらが悪いわけではない。そうではなく、その一方で、もっと、「母は殺せるよ」、「殺していいよ」、「どんどん殺してしまおうよ」というストーリーを示してあげる必要があると思うのである。
その両輪があって、初めて健全な議論が展開するのではないだろうか。
「母を殺してはならない」という規範は乗り越えられるものなのだと示すこと。母親はべつに超越的な存在ではなく、ひとりのあたりまえの人間に過ぎないのだと考えても良いと許すこと。
そこにこそ、希望はある。ぼくは個人としてそのように考えるものである。
だから、いまからでも遅くない。もしあなたが「悪い母の呪縛」にとらわれているなら、その「母」を殺して、しあわせになろう。
母は殺せる。
お仕事のお願い
この記事をお読みいただきありがとうございます。
少しでも面白かったと思われましたら、![]() やTwitterでシェア
やTwitterでシェア
をしていただければ幸いです。ひとりでも多くの方に読んでいただきたいと思っています。
また、現在、記事を書くことができる媒体を求めています。
この記事や他の記事を読んでぼくに何か書かせたいと思われた方はお仕事の依頼をお願いします。いまならまだ時間があるのでお引き受けできます。
プロフィールに記載のメールアドレスか、または↑のお問い合わせフォーム、あるいはTwitterのダイレクトメッセージでご連絡ください。
簡易なポートフォリオも作ってみました。こちらも参考になさっていただければ。
自作の宣伝
この記事とは何の関係もありませんが、いま、宮崎駿監督の新作映画について解説した記事をまとめた電子書籍が発売中です。Kindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければご一読いただければ。
Kindle Unlimitedに未加入の方は良ければ下のバナーからご加入ください。これだけではなく、ぼくの電子書籍は「すべて」Kindle Unlimitedに加入すれば無料で読むことができます。初回は30日間無料です。
ちなみに、Kindle Unlimitedに登録された本はここ(
https://yoshihisamurakami.github.io/kindleunlimited-search/)から検索することができます。めちゃくちゃ便利。
よろしくお願いします。