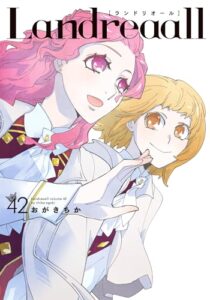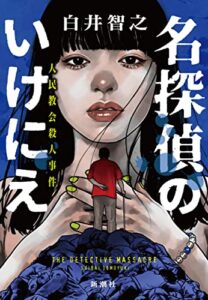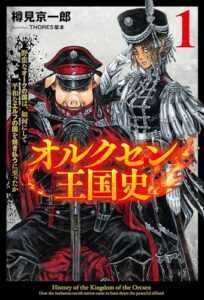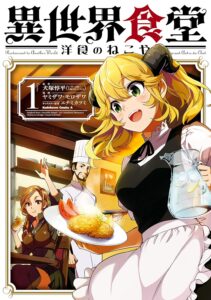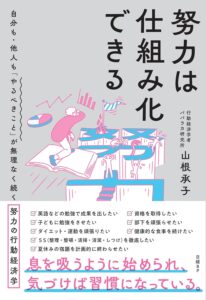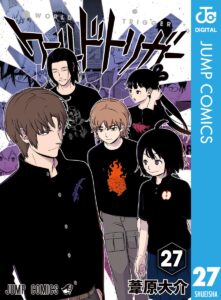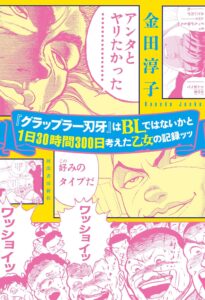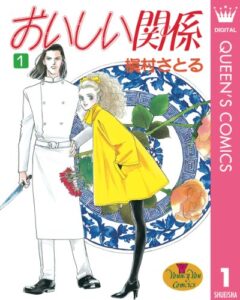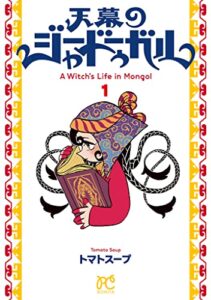先月の「新海誠と奈須きのこ」の記事に続いて、パチンコのマルハンのウェブサイト「ヲトナ基地」にておがきちか『Landreaall』の記事を公開しました。
https://www.maruhan.co.jp/east/media/new/202
もし良ければ読んでくださいまし。
この記事では主に緻密に計算された群像劇としての『Landreaall』の魅力についてふれているのですが、もちろん、この作品の面白さはただそれだけに留まるものではありません。
多角的に構築された『Landreaall』の大きなつよみとしては、他にもたとえば「ファンタジー」としての魅力があります。
一見するとライトにカジュアルにできあがっているように見える世界の途方もない「深度」。
数々の王国の長い歴史、そのエピソードのひとつひとつや、膨大な登場人物たちひとりひとりの来歴といったところに、ぼくは何ともいえない「ファンタジーらしさ」を感じ取ります。
もうひとつの代表作『エビアンワンダー』もそうですが、見た目の軽やかさと比べて異様なほど「深い」「重い」物語なんですね。
とはいえ、そもそもファンタジーとはなにかというところも議論があるところで、ひと言でファンタジーといっても、まあ色々あることは間違いない。
ぼくはそこまでたくさんファンタジーに触れてきているというほどではありませんが、でも、好きでファンタジー小説や漫画を読んで来ていることはたしかなので、やはりこの言葉には思い入れがあります。
そのぼくから見ると、たとえばいわゆる「なろう小説」はあまり「ファンタジーらしくない」。
だからといって質が低いとか、面白くないということではまったくありませんが、あれはようするにいわば「ゲーム小説」なのであって、ファンタジー独特のフレーバーみたいなものをつよく感じさせる作品はめったにないように思います。
フレーバー。
いかにもあいまいな言葉を出してしまいましたが、その作品が「ファンタジーらしさ」を感じさせるかどうかは、この「香気」によって決するのではないかと思います。
いや、わかるよ、何をめちゃくちゃ主観的で捉えどころのないことをいい出しているのだ、と指摘したくなる気持ちは。
でも、それはそういうものなんですよ。そもそも「ジャンル」という概念自体が自然発生的に出てきた作品群をあとから定義するものでしかないわけで、そうそうロジカルに定義はできない。
たとえば「ファンタジー」と似て非なる「幻想文学」というジャンルもあり、「ファンタジー」は英語から来ているもので「幻想文学」はフランス語から来た概念であるという話もどこかで聞いたことがありますが、まあ、幻想文学の最大権威である世界幻想文学賞の受賞作にはわりとポップなファンタジーもあったりしますから、あまりしゃくし定規に考える必要もないでしょう。
しょせん、この手のジャンルの定義はどこまでいってもあいまいで非論理的なものでしかないのです。
しかも、各々の論者が(いままさにぼくがしちているように)その名称に理想と思い入れを仮託して語るものだから、なおさら混乱する。
ぼくの場合は、その文章からほのかにただよい出す香りのようなものによってそれを「ファンタジーらしい」と評価するわけです。
とはいえ、その薫香の正体とはなにか。それを、ぼくは「象徴言語で書かれている」といういい方をします。
『指輪物語』でも『ゲド戦記』でも、タニス・リーでもジェイン・ヨーレンでも何でも良いですが、ぼく(たち)が優れたファンタジー小説からしばしば感じ取る神秘と魔法の気配、それがこの「象徴言語」だと思うのです。
たとえば、ファンタジーにおけるドラゴンは、ドラゴンである「と同時に」火であり、生命であり、エネルギーそのものであるわけです。
これは、あるものがじつは何かを意味しているといった隠喩(メタファー)とは違う。ドラゴンはあくまでドラゴンであり、それが同時に何かを象徴しているところに意味があるわけですから。
一般的な言語、現代の言葉で書かれているものは、それが作品として優れているかどうかとはべつに、あまり「ファンタジーらしさ」を感じさせない。
しんじつファンタジーを名乗るのなら、どこかにいにしえの時代の大気を感じさせなければならぬ、といったら、あまりにも大袈裟な話になってしまうでしょうが。
たとえば『ゲド戦記』、『闇の左手』のアーシェラ・K・ル・グィンはエッセイ集『夜の言葉』のなかで、「宰相」を「大統領補佐官」にというふうに、ちょっと用語を入れ替えると現代小説になってしまうような作品はそもそもファンタジーではないのだ、とかなり意地の悪いことをいっているのですが、そういう基準で見ていくと現代ファンタジーの大半は「とてもファンタジーとはいえない」ということになってしまうのではないかと思います。
しかし、そうかといってそういう狭い意味での「ファンタジー」のみを正統な作品として崇め、そうではないものを亜流として蔑視することは、現代においてはいかにも偏屈な見方です。
まあ、ル・グィンくらいならそのくらい偏っていても良いかもしれないけれど、より凡庸なぼく(たち)はそうはいかない。
どうしても、最も広い意味で「ファンタジー」と呼ばれている作品群もその仲間として見ないわけにはいかないのです。たとえそれがどれほど俗悪に見えたとしても。
だから、現代におけるファンタジーとはとても広い概念になっている。ただ、やっぱりぼくはそのなかでもセントラル・コアにあたるようなタイプのファンタジーがいまでも好きです。
そういった古典的な意味でのファンタジーには、大自然や宗教的共同体から追放された近代人、あるいは現代人のいわば切なる望郷にも似た憧憬、それがあえかに漂うように思います。
それはナルニアとかミドルアースといった世界への憧憬ともいえるでしょう。
で、話を『Landreaall』に戻すと、この作品にもその気高い理想世界への憧れが、ファンタジーの「香気」が仄かにただよっているように感じられるわけです。
もちろん、『Landreaall』だってゲーム的なファンタジーには違いなく、その意味でなろう小説と明確な落差があるわけではありません。
くりかえしますが、ル・グィン的な意味でオーソドックスなファンタジー小説は、いまはもうあまり受け入れられないことでしょう。
ですが、それでも、『Landreaall』を読んでいるとファンタジーがほんとうにスペシャルな「象徴言語」の文学だった時代を思い出したりします。
そういうことは「ヲトナ基地」の記事には(あまりにマニアックな話であることもあって)書けませんでしたが、べつのことを書いたので、ぜひ読んでいただければと思っています。
よろしくお願いします。
でわ。