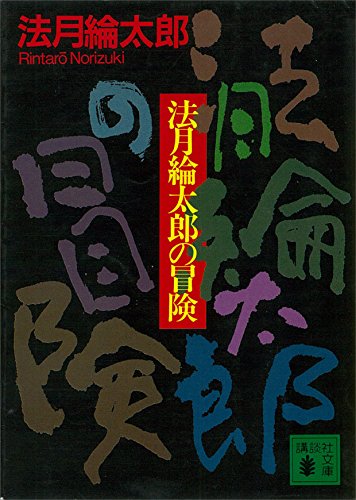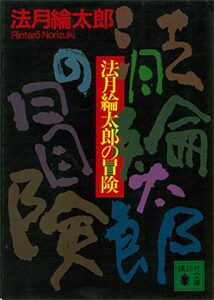- ●はじめに――ちょっと地球をひっくり返してみませんか?
- ①法月綸太郎「カニバリズム小論」
- ②麻耶雄嵩「遠くで瑠璃鳥の鳴く声が聞こえる」
- ③乙一「華歌」
- ④綾辻行人「どんどん橋、落ちた」
- ⑤連城三紀彦「親愛なるエスくんへ」
- ⑥川島誠「電話がなっている」
- ⑦森博嗣「卒業文集」
- ⑧山本周五郎「なんの花か薫る」
- ⑨栗本薫「コギト」
- ⑩鮎川哲也「達也が嗤う」
- ⑪ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア「男たちの知らない女」
- ⑫シオドア・スタージョン「輝く断片」
- ⑬クリスチアナ・ブランド「ジェミニー・クリケット事件」
- ⑭ロアルド・ダール「南から来た男」
- ⑮コニー・ウィリス「わが愛しき娘たちよ」
- ⑯ロバート・F・ヤング「ピネロピへの贈りもの」
- ⑰G・K・チェスタトン「折れた剣」
- ⑱フレドリック・ブラウン「うしろを見るな」
- ⑲アーサー・C・クラーク「太陽系最後の日」
- ⑳アーシェラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」
- 【追記――「ネタバレ」を避けるべき基準はどこにあるのか?】
- 【さいごに】
●はじめに――ちょっと地球をひっくり返してみませんか?
短編小説が好きだ。いや、何冊も何冊も連綿とつづく大長編もそれはそれで好きなのだけれど、短いなかでひとつのとじた世界を感じさせたり、読者の予想をあざやかに裏切ったりするいわゆる「珠玉の短編」の妙味はたまらない。
文学の精髄は短編にあり、とまではいわないが、やはりコンパクトにまとまった短編はあらゆる文芸の、というか物語表現の基礎にあるものだろう。
優れた物語作家は常に優れた短編作家でもあるのであって、それができなくなったときに作品は肥大化、冗長化するものなのだ。また、短編はすぐに読み終わるので何かとコスパやタイパが求められる現代にもマッチしているだろう(嘘)。
いや、なぜ嘘なのかといえば、短編小説には読者が短い単位でそのつどあたらしい世界に入り直さなければならないという問題があるからなんですけれどね。
とくにSFやファンタジーの短編集の場合、へたすると一作ごとに文字通りの別世界に飛ばされるわけで、「いちいち世界に入り直す」ためのコストは非常に大きい。
だから、ひとつ短編に限らないものの、小説の冒頭箇所の役割とは印象的な名句や格言を並べることではなく、なるべく自然に読者を物語世界へ誘い込むことだったりするのである。かならずしも劇的なインパクトはいらないのだ(本当)。
まあ、とはいえ、書くほうとしてはつい力んでしまいがちなポイントでもあるんだけれどね。
さて、ここにはぼくが読んでいろいろな意味で感動した傑作短編小説国内作品10作、海外作品10作を並べてみた。いずれも、広い意味では最後の最後でそれまでの光景が逆転し、読者を驚愕させる「どんでん返し」ものである(厳密には最後の一作だけちょっと違うかも)。
ただし、そのサプライズはいわゆる本格ミステリ的なトリックがもたらすものにかぎらない。個々の作品の結末の衝撃はそれぞれ異なる性質のものなのだ。
ただ、いずれもほんとうに面白い短編なので、ぜひ読んでみてほしい。短編がタイパが良いというのはまっかな嘘に過ぎないが、ここに挙げた作品を順番に(あるいは無作為に)読んでいけばきわめて充実した読書体験ができることは保証する。
ほんとうは国内、海外合わせて10選に絞るつもりだったのだが、どうしても絞り切れなくて20選になってしまった。どれか一作でも良いのでぜひ読んでみてくださいね。よろしく。
①法月綸太郎「カニバリズム小論」
数ある法月綸太郎の傑作短編のなかからわざわざこの一作を選ぶあたりにぼくらしさを感じてください。
法月の第一短編集『法月綸太郎の冒険』収録作で(ちなみにこれはいうまでもなく『シャーロック・ホームズの冒険』や『エラリー・クイーンの冒険』に連なる伝統のタイトル。赤川次郎の三毛猫ホームズシリーズ第一作『三毛猫ホームズの推理』もほんとうは「冒険」にしたかったらしい)、「カニバリズム(食人嗜好)」をテーマにしたブラックな作品である。
ミステリとしての完成度は他に優れたものが色々あると思うが、独特のダークな読後感は類例がないかと。
・同じ作家のオススメ短編集
②麻耶雄嵩「遠くで瑠璃鳥の鳴く声が聞こえる」
絶対に一度もないことだろうが、もし、仮に「麻耶雄嵩ってどんな作家なの? 本格ミステリはよくわからないから『魔法少女まどか☆マギカ』で喩えてくれ」といわれたら、ぼくはこう答えるだろう。「アルティメットまどかの偉大さと悪魔化ほむらの邪悪さを兼ね備えた作家さんです」。
麻耶の短編代表作のひとつであるこの「遠くで瑠璃鳥が鳴く声が聞こえる」も、神がかった巧緻と峻烈な悪意を兼ね備えた傑作(もっとも、もっとすごいのもあるのだけれど、そういうのはあまりにすごすぎて理解困難だったりする)。
「どんな事件も瞬時に解決してしまうので長編には向かない探偵」メルカトル鮎の悪辣なる天才を見よ!
・同じ作家のオススメ短編集
③乙一「華歌」
乙一の(別ペンネームの作品も含めて)数ある傑作短編のなかからどれを選ぶべきなのか迷ったが、とりあえずこの作品にしておいた。
ほんとうはぼく的にベスト・オブ・ベストの大傑作「しあわせは子猫のかたち」あたりを選びたいところだったし、あれも「最後の逆転」が印象的な小説ではあるのだけれど、「いわゆる大どんでん返し」とは少し違うよね。
まだこの頃20代前半だった若き乙一の感性はずば抜けていて、その作品にただよう清涼感というか透明感のようなものは比類ない。初期作品の完成度の異常な高さといい、まさに傑出した才能としかいいようがない作家である。
・同じ作家のオススメ短編集
④綾辻行人「どんどん橋、落ちた」
出た! 「館シリーズ」で知られる作家・綾辻行人の最凶傑作にして、一世を風靡した(気もする)いわゆる「新本格ミステリ」のなかでも極北というべきめちゃくちゃな短編である。
続編の「ぼうぼう森、燃えた」と合わせて、行き着くところまで行き着いてしまったミステリのリミットを味わえる。
ひとによってはそれこそ本を投げつけたくなるようなトンデモない話ではあるのだが、「とにかく論理の道筋は見えている」、「伏線はすべてきれいに敷かれている」わけで、いやまったくとほうもない。
べつだん、ミステリファンでなくても一読の価値はあり。凶悪です。
・同じ作家のオススメ短編集
⑤連城三紀彦「親愛なるエスくんへ」
連城三紀彦は「反転」の小説を描きつづけた。たったひとことで説明できるような「ある指摘」が入った瞬間に、目の前の光景があっというまに位相を変え、世界がくるりとひっくり返るそのカタルシス――それはまさにミステリの妙味というべきものだ。
しかし、連城がスペシャルなのは、その「反転」を可能にするためのトリックが最大限に洗練されているところである。どう考えても無理やりであるはずの「反転」が、連城においては奇跡のように「小説として」成立してしまう。そういう作家であった。
「親愛なるエスくんへ」はその連城が現実世界の食人事権を題材にした異形の傑作。幻想怪奇の世界の住人が現実世界の殺人事件に対し送ったアンサーだ。
・同じ作家のオススメ短編集
⑥川島誠「電話がなっている」
「電話がなっている」。このタイトルを見て、「ああ、あの作品か」と思いあたる人もいらっしゃるかもしれない。
そう、「あの作品」なのである。このタイトル、一部の小説マニア/オタクのあいだではそれなりに有名なのだ――凶悪きわまりない「鬱エンド」作品として。
ある種の青春小説ではあるのだけれど、まさに青春の暗黒面を煮詰めたような作品で、いやあ、素晴らしい。主人公はひとりの男の子であり、まさにかれの物語であるのだが、印象に残るのはむしろヒロインの造形のほうだ。こわいなあ、こわいこわい。
何ともスリリングでサスペンスフルな闇黒青春小説の逸品です。
・同じ作家のオススメ短編集
なし。というか読んでいません。ごめんなさい。
⑦森博嗣「卒業文集」
森博嗣は「S&Mシリーズ」や「四季」などの長編で大ヒットを飛ばした作家だが、当然ながら短編においても秀抜な作品を数多く生み出している。そのなかには何らかの形で「逆転」のサプライズを演出したものも少なくない。
で、「卒業文集」である。ある学校の卒業文集を並べた、一見するとそれだけの物語なのだが、当然ながらそこにはひとつの「しかけ」がほどこされており、それがあきらかになった瞬間、しずかな感動が立ち上がる。
これは人間の「可能性」の賛歌であるのだろう。あなたはその「しかけ」が明かされるそのまえに真実をあきらかにできるだろうか?
・同じ作家のオススメ短編集
⑧山本周五郎「なんの花か薫る」
山本周五郎は時代小説の大家である。生前、その作品できわめて高い評価を受けながらも、ありとあらゆる受賞を固辞しつづけたという人物で、まあ、かなり気むずかしい人柄だったのではないかと思う。
その山本周五郎の数ある名作短編のなかでも、ぼくはこの「なんの花か薫る」を推したい。
一読、思わずため息を吐いてしまうような、哀切なもので満ちた話である。映画化もされているようだが、原作が至上だろう。
この作家は、なんと残酷なことを考えだすのだろう、そして、なんと美しくそのさまを描き出すのだろう――その、かぎりなく哀しくやる瀬ない結末は一度読んだら忘れられない余韻を刻むことだろう。
・同じ作家のオススメ短編集
⑨栗本薫「コギト」
亡き栗本薫の名作のひとつ。デカルトの「コギト・エルゴ・スム(われ思う、ゆえにわれあり)」を参照しつつ、「唯我論の地獄」を描いた短編だ。
「自分ひとりしかいない世界」に閉じ込められ、そのなかでさまざまに思索を巡らすひとりの少女の物語なのだが、最後の最後で「その外の世界」があきらかにされたとき、あっと驚く結末が待っている。ある意味で、栗本の文学的テーマを象徴するような作品ともいえる。
ひとは決して「自分ひとりの世界」で生きているわけではなく、また、そうあるべきでもない。「自分ひとりの世界」はひっきょう、地獄でしかない。そういうテーマなのだと思う。
・同じ作家のオススメ短編集
⑩鮎川哲也「達也が嗤う」
鮎川哲也の「犯人あて」小説である。ミステリファンのあいだではきわめて有名な作品なので、知っている人は知っているかもしれない。
鮎川哲也だと、他に「薔薇荘殺人事件」あたりも逆転の傑作だが、今回は「達也が嗤う」のほうを選んだ。さて、あなたははたして作家がねらったしかけをみごとに暴き、犯人をあてることができるだろうか?
ちなみに、記憶に頼って書くのだけれど、奈須きのこが『月姫』の番外編「幻視同盟」でほぼ同じトリックを使っていた。この「幻視同盟」、かなりの傑作だと思うのだが、いまとなっては入手方法がない幻の作品である。一応、合わせてオススメしておく。
・同じ作家のオススメ短編集
⑪ジェイムズ・ティプトリー・ジュニア「男たちの知らない女」
ジェイムズ・ティプトリー・ジュニアはいわずと知れたSF小説史上屈指の(最高の、かもしれない)短編の名手である。
長期間にわたって男性の名前で活動したあと、じつは女性であることがあきらかとなって話題となった作家でもある。
今回、どの作品を選ぶか迷ったあげく、「結末の衝撃」ということでこの「男たちの知らない女」を選択することにした。一男性としてかなり重苦しい気持ちになる作品である。
ちなみに、この短編集『愛はさだめ、さだめは死』のなかでは表題作や「接続された女」が歴史に残る名作。「接続された女」のあまりに残酷な結末は忘れがたい。
・同じ作家のオススメ短編集
⑫シオドア・スタージョン「輝く断片」
スタージョンは大森望がティプトリーやラファティらと並べて「魔法の名前」と呼んだ作家のひとりである。
「魔法の名前」とは、「ジャンル小説の書き手ではあるものの、あまりに作風が独創的すぎてジャンルの枠組みに収まっているかどうか怪しい」そういうスペシャルな書き手のことだと思う。
「輝く断片」はその不世出の天才作家スタージョンの最高傑作。この世の美しいものと醜いもの、そのすべてがここにあるといいたくなるような、すさまじい一篇だ。
その結末は「失ってはならないものの喪失」の、あるいは「楽園からの追放」の語りようもない哀しみをたたえて印象深い。
一読すれば一生忘れられなくなる、そういう数少ない名作のひとつだといえよう。
・同じ作家のオススメ短編集
⑬クリスチアナ・ブランド「ジェミニー・クリケット事件」
クリスチアナ・ブランドは、その筋では名を知られた女性ミステリ作家だ。いわゆる「本格」の書き手としてはアガサ・クリスティと並んで最高の作家といって良い。
そのブランドの短編集のなかでも傑作ぞろいのショーケースとして知られているのが『招かれざる客たちのビュッフェ』で、この本のなかで最も有名な作品が「ジェミニー・クリケット事件」。
本格推理の名作中の名作というべき作品であり、いろいろなアンソロジーなどに収録されているようだ。
あるふたりの人物が過去の事件の「真相」を探ろうと推理をくり返したその果てに待つものは――読後、感嘆と戦慄のため息を吐くしかない、そういう、凄惨なまでに完成度の高い短編である。いやすごいね。
・同じ作家のオススメ短編集
思いあたらない。ごめんよー。
⑭ロアルド・ダール「南から来た男」
ロアルド・ダールから一作。あまりにもベタだが、ここは「南から来た男」を選んでおきたい。
数あるミステリのランキングやアンソロジーできわめて高い評価を得ているオールタイム・ベスト級の一作である。
じっさいのところ、狭い意味でのミステリには入らないかもしれない作品であり、ふだん、殺人事件などを扱った小説は読まないという方にもオススメしたい。
少なくとも「ギャンブル」をテーマにして、これほど背筋が凍るような恐怖を感じさせる小説はない。いやあ、ほんと、賭け事ってこわいものですね。
ダールのあの独特に意地の悪い視点を煮詰めたような一作でもあり、ギャンブルを軸にして「人間の暗黒」を暴いた小説ということもできそう。こわいです。はい。
・同じ作家のオススメ短編集
⑮コニー・ウィリス「わが愛しき娘たちよ」
コニー・ウィリスは『ドゥームズデイ・ブック』(傑作!)などの長編でヒューゴー賞、ネヴュラ賞などを取りまくっている現代SF最高のストーリーテラーであるが、「わが愛しき娘たちよ」はそのウィリスの傑作短編。
これが――これがねえ、ほんとにすごい話なんですよ。ぜひ、男性読者に読んでいただきたい。「ひええ」と背筋も凍るから。
男性への偏見があるとして大論争を呼んだという話もあるが、じっさいのところ、ウィリスはべつだんフェミニズムのテーマを背負った作家ではないわけで、そういうふうに読んだら本質を外すと思う。
あくまでこれは「悪」と「罪」について書かれた寓話なのである。とにかく結末の衝撃はSF短編史上でも指折りなのではないかと。
・同じ作家のオススメ短編集
⑯ロバート・F・ヤング「ピネロピへの贈りもの」
ロバート・F・ヤングはウェットでセンチメンタルな作風のため、日本でふしぎなくらい人気のあるSF作家だ。その優しくあたたかな作品は非常に日本人好みなのだろう。
なかでも「たんぽぽ娘」あたりは、伊藤典夫の名訳もあいまって、いまでも名作として知られている。が、今回はあえてそこは外して「ピネロピへの贈りもの」を選んでおこう。
立ち読みでも読み終えられそうな短さで、スタンダードな「どんでん返し」とはまたちょっと異なってはいるが、ヤングという作家の本領を味わえると思う。読み終えたあと、何ともほのぼのしてくるようなハッピーエンドの「いい話」なのだ。
・同じ作家のオススメ短編集
⑰G・K・チェスタトン「折れた剣」
「木をかくすなら森のなか。それでは、もし――」。チェスタトンは「逆説」の名手として知られ、本格ミステリの基礎を築いた作家である。
現代で一般的に使われているトリックの数々は、さかのぼりにさかのぼってみると大方、チェスタトンに行き着いてしまう。
この「折れた剣」もまたそういう作品のひとつなのだが、現代においてもまだ衝撃を失ってはいないと思う。アイディアとしてはシンプル、この上ないくらいシンプルな話ではあるのだが、いやはや、よくこういう話を思いつくなあという気もする。
その語りの技巧も含めて、本格ミステリ初期の名作中の名作といって良いのではないだろうか。
・同じ作家のオススメ短編集
⑱フレドリック・ブラウン「うしろを見るな」
世の中にはそのしかけによってひとつミステリファンというより、小説マニア全体の語り草になっているような作品があって、ブラウンの「うしろを見るな」もそのひとつ。
決して文学的な深みで読者を圧倒するといった作品ではないが、読後、にやりとできることは間違いない。
まあ、思いつくだけならだれかが思いついてもおかしくないアイディアではあるのかもしれないけれど、どう考えても成立しない話なので、それをどうにかして成立させるためには卓抜な技巧が必要になる。
いやあ、それにしても、よくこんな小説書くわ。読むと確実にだれかに話したくなります。
・同じ作家のオススメ短編集
⑲アーサー・C・クラーク「太陽系最後の日」
SFからまた一作。これも本格ミステリ的な「逆転の驚き」とはまた違う構造の作品だが、「結末の一行」の驚き、いわゆる「最後の一撃(フィニッシング・ストローク)」という意味では、ちょっと他にない感興を味わえる一作といって良いと思う。
太陽系が滅亡に瀕した「最後の日」、人類に救出に訪れた異星人による宇宙艦隊は「そこにだれもいない」という謎に直面する。はたして人々はどこに消えたのか――?
すでに70年以上前に書かれた作品でもあり、その人間観があまりに素朴であるという批判も成り立つことだろうが、なんだかんだいって、SFファンはみんなこういう話を好きだろう。いかにもクラークらしい小説なのである。
・同じ作家のオススメ短編集
⑳アーシェラ・K・ル・グィン「オメラスから歩み去る人々」
アーシェラ・K・ル・グィンの短編代表作。これを「どんでん返しの驚き」という文脈で持って来ることはだいぶ間違えている気もするのだが、まあいいや、せっかくだから紹介しておこう。
この小説は必ずしも「結末でそれまで見えていた光景が逆転する」というタイプの作品ではないが、最後の一行を読むと世界の見え方がまったく変わってしまうことはたしかである。
物語は問いかけてくる。「あなたならどうする?」と。
その思弁性というか、思索の深さにおいて比類ない小説といえるだろう。読者に思考を強いるある種の「オープン・エンド」のお手本のような短編だ。
・同じ作家のオススメ短編集
【追記――「ネタバレ」を避けるべき基準はどこにあるのか?】
んー、この記事に対し「この記事そのものがすでにしてネタバレである」として批判的に言及している方がわりに大勢いるようなので、ちょっとその点について記しておきます。
ぼくはふだん、自分の記事へのレスポンスにさらに返事をしたりしないんだけれど、今回は「なるほど、こういうことになるんだ」とちょっと興味深かったので、ぼくなりの考えを残しておきたいと思ったわけです(と、書いても怒る人もいるだろうけれど、まあそれはしかたない)。
第一に、ぼくはこの記事が「ネタバレ」として問題だとは思いません。具体的な結末の内容まではまったく書いていないからです。
たしかに結末を匂わせているところはある。そういう意味ではぼくの紹介を読まないで作品にふれることがベストであることは間違いないけれど、通常の紹介文で許容されるネタバレの範疇を超えてはいないと思う。
と、こう書くと「いや、そういうことじゃないだろ」という意見が出て来るかもしれません。
たとえ結末について直接に書かなくても、「結末の逆転」に魅力がある作品に対し「悲しい結末」とか「鬱エンド」とか書いている時点で結末の内容がわかってしまう。さらにいうなら、「衝撃の結末」「どんでん返し」として紹介した時点でネタバレでしかない。そういう意見はありえるはず。
それはたしかにそうですね、とぼくも思います。しかし、こういうことは、何かを紹介するときに付きまとう根本的な矛盾で、完全には避けがたいことであるとも感じる。
どういったら良いか、これはひとつの事実といっても良いだろうけれど、この手の「ネタバレ」がことさらに問われる作品って、たしかになんの情報もなく白紙の状態で読むのがいちばんではあるんですよね。
たまたまそこに置かれていた本をなにげなく読み始めたらそこにその話が掲載されていた、とかが理想。あえて「これ、衝撃的な結末だよ!」と教えてしまった時点で興をそぐ一面はある。
あるんだけれど、でも、紹介するほうとしては「そういう触れ込みで紹介しないと読まないでしょう」という気持ちがあって、わりと大々的にそういうことを書いてしまうのです。
一例を挙げましょう。たとえば、今回取り上げた「達也が嗤う」はなんと『大逆転』というアンソロジーのなかに収録されています。
もう、これは「逆転もの」であることは周知の事実としてあつかってもかまわないという判断がなされているわけです。「達也が嗤う」の結末はそのくらい有名な「どんでん返し」なのですね。
そういうことも勘案して、ぼくは今回の記事に載せる作品を選んだわけなのですけれど。
そもそも、ぼくが取り上げた作品はそれぞれ切れ味鋭い結末の名短編として有名なものが多く、べつだん、ぼくがネタバレしなくてもネット上に結末に関する情報が注意書きのひとつもなく流通しているものがほとんどです。
だから、いまになってぼくが書いた程度の情報がネタバレとして批判されるとは考えていなかったということはある。「電話がなっている」とか、その筋では伝説的な短編ですからね。
上記記事で取り上げたような作品に対し、ネットで(リアルでも)そういった、いろいろなレベルの「ネタバレ」情報が平然と流通している理由としてはふたつが考えられるでしょう。
ひとつは「達也が嗤う」のようにすでに「逆転もの」「どんでん返しもの」の名作としての声望が確立されていて、その点についてふれてもかまわないと判断されている作品であること。
ダールの「南から来た男」なんかそれですね。この記事なんか、最初から最後までぜんぶ話の筋が書かれている(以下、リンク先はそれこそほんとにどれも全面的にネタバレなので注意)。
で、もうひとつ、それがふつうは「どんでん返し」とはいわれないだろうなという作品であり、そのためにネタバレの配慮をする必要があるとは考えられていないこと。
ぼくは今回、山本周五郎の「なんの花か薫る」を取り上げたのだけれど、これは、名作としての名声こそ高くても、ふつう「どんでん返しの傑作!」みたいには評価されていないと思う。
だからネットを検索するとほとんど最後まであらすじを書いた上で「救いのない残酷な終わり方」と記してしまっている評が見つかる。
ぼくはこれをとくに問題のあるネタバレだとは思わないのだけれど、ネタバレ度でいえばぼくの記事より上でしょう。
また、クラークの「太陽系最後の日」に至ってはちょっと検索すると結末についての言及がたくさん見つかるばかりか、「結末を知っていること」を前提としたネタバレ質問が見つかったりする。
とはいえ、本編が数十年以上まえに書かれた作品であることもあって、ふつうはこういった情報は問題視されないし、じっさいされていなかったと思うのです。
ル・グィンの「オメラスから歩み去る人々」なんて、ある対談のなかではっきりと結末が言及されている。他の作品も、ちょっと調べれば結末に関する情報が見つかるものがほとんどです。
つまりはぼくが書いた程度のことはすでにネットの各所に載っているものであって、それらはとくに問題視されているようには見えないのですよ。
というか、上記の対談のように、ぼくが書いているよりずっとはっきりと結末まで書いてしまっている記事もとくべつ非難を受けているようには見えない。
それはそうでしょう。「オメラス」は文学作品ですからね。ドストエフスキーの『カラマーゾフ』がそうであるように、ネタバレを気にして語るべき対象として認識されていなくても不思議はない(この言及自体がちょっとしたネタバレだといえなくもない)。
だからこそ、ぼくもこの程度は許容範囲だと判断したわけなのだけれど、それでもある傾向の結末を20作集めて、そこに「衝撃の結末!」とか「どんでん返し」とラベルを貼ると、やっぱりネタバレだという怒られが発生するんだな、と。
何を問題のあるネタバレと判定するかのラインは人それぞれでしょうが、ぼくはこの種の「内容の匂わせ」まで一貫して避けるつもりはないので、「当然、避けるべきだ」と考える人とは価値観が違うのでしょう。
ちなみに上でふれた川島誠の「電話がなっている」は『だれかを好きになったら読む本』という児童文学アンソロジーに収録されていて、たまたまこの本を読んだ人たちはトラウマを植えつけられたとか。
それはそうでしょう、まさか『だれかを好きになったら読む本』なんてハッピーそうなタイトルの本のなかにこんな作品が紛れ込んでいるとはだれも思わない。そういう意味では、このアンソロジーは最高の作品紹介であるといえるかもしれない。
この作品はそういう偶然で出会い頭にぶつかることが最高に幸せな出逢いなんじゃないかな。まあ、それはそれで「子供にいきなりこんなものを読ませるなんて!」とか「不快な内容であるという注意書きをしてほしい」といった怒られが発生するのかもしれませんが。
結局のところ、どう書くことが正解というのではなく、どう書いたところでどこかからは批判される、ということなんだろうけれど。書くとはそういうことなんでしょうか。それにしても――あ、電話がなっている。出なくちゃ。では失礼。
【さいごに】
最後までお読みいただきありがとうございます。
オタク文化の宗教性について考える電子書籍『ヲタスピ(上)(下)』を発売しました。その他、以下すべての電子書籍はKindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければそちらでもご一読いただければと思います。
それでは、またべつの記事でお逢いしましょう。