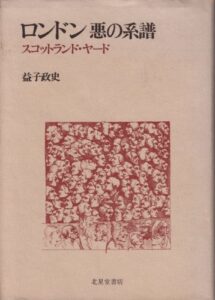いったいいつからこうなったのだろう、と思うことがあります。
何の話かというと、「ボケ」と「ツッコミ」の話。あるいは「ベタ」と「メタ」の話です。
最近――でもないでしょうが、多くの人が「批判される側」に回ることをいやがって、「批判する側」に回るため、「とにかく先に批判しよう」としているような雰囲気を感じます。
そのことが社会前提にある種の閉塞感をもたらしている。
こう書くと「そんなものを感じているのはおまえだけだ」といわれるかもしれないので急いで説明しておくと、こういうふうに考えているのはぼくだけではありません。
この「ボケ」と「ツッコミ」という表現の出典はマキタスポーツ(槙田雄司)の『一億総ツッコミ時代』なのです。
この本では、日本国民のだれもが「ボケ」ることを恐れて「ツッコミ」に回るようになったかと見える現代という時代を色々な角度から語っています。
それがかれのいう「一億総ツッコミ時代」。この時代においては、ほとんどだれもが「ボケ(批判される側)」であることをいとって「ツッコミ(批判する側)」に回ろうとします。
マキタスポーツ自身の言葉によると、こんな感じ。
バラエティ番組などでよく聞かれる「噛む」という言葉があります。これはツッコミ側の言葉で、舌がもつれてうまくセリフが言えなかったことを指摘して、笑いを起こすことです。「いま、噛んだやないか!」という具合に使います。
この「噛む」を指摘するようなことに見られる、ややサディスティックな感覚を一般の人たちも日常的によく使っています。
しかし、私にはそれを指摘しているときの彼らの「他罰的」な気分がとても気になってしまいます。相手を傷つけようというほどではないにせよ、先に攻撃することによって自分に降り掛からないように防御しているという心持ちが、端から見ていて気持ちが悪いのです。
政治家や力士など目立つ存在に対して、ネット上の匿名性のなかで貶めたり、過剰に攻撃したりする風潮もあります。「失敗していない多数側」に自分がいることで安心感を得ているというわけです。
また、他者を攻撃して「差異を楽しむ」ことで、この「何ごとに対しても諦め感の漂う毎日」をやりすごしている。そのことが閉塞感にさらなる拍車をかけています。
この感覚は、ぼくもものすごくよく理解できるんですよね。特にネットではすごく「ボケる」ことが恐れられていて、その分、「ツッコミ欲」が過剰になっているように思えてならない。
もちろん、まちがえた意見やフェイク情報に批判を加えることとてもは大切なのですが、一方で「責難は成事に非ず」、批判することは何かを成し遂げることではないともいえるわけで、ほんとうは「ベタ」に行動することと「メタ」に考えることはバランスが取れていなければならないはずなのです。
しかし、いまという時代はそのバランスがどうにも崩れていて「ツッコミ過剰」になってしまっているのではないか、とぼくは考えます。
いや、それはおまえが他人の批判から逃げ出したいから自己正当化でそういうのだろう、というふうに考える人もいるかもしれませんが、そうじゃなく、ぼくはずっと、何十年もこのテーマについて考えてきたんです。
それはこれが「オタク」という種族に関わる問題だから。オタクとは、何ごとも「メタ」に、「シニカル」に考えがちな人種です。
いまとなってはだいぶ変わって、そういう何か妙に偉そうで皮肉っぽいオタクもあまり見かけなくなったかもしれませんが、昔はたくさんいたんです、そういう人。
いわゆる「第一世代」は特にそうですね。なぜなのかよくわからないけれどやたらイヤミばかりいっているような人がいた。
ぼくはくり返しオタク第一世代の在り方を批判しているので知っている人はまたかと思うかもしれませんが、やっぱりおかしいように感じられるんですよ。
もちろん、第一世代だから全員がおかしいなんてわけはなくて、目立つ人が目立つだけなんでしょうけれどね。
オタクがなぜそういうふうにシニカルになってしまうかというと、かれらが「見る」ことに特化した人種だからだと思います。
オタクは「見る」ことに関してプライドを持っている。そして、まさにそうだからこそ「見られる」ことに嫌悪と恐怖を感じるのです。
たとえば、岡田斗司夫さんは『オタク学入門』のなかで「オタク文化の頂点は鑑賞者である」と書いています。
これ、岡田さんの野心とコンプレックスが感じ取れる気がして面白いなあとぼくなんかは思うんですけれどね。
岡田さんにいわせれば、文化を生み出しているのは決してクリエイターではなく、その道の「通」である「鑑賞者」なのです。
「実は、「作品の良さを理解して言葉にできる」という「受け手」の方が日本文化では偉い、とされているのだ」とこの本には書いています。
古来より日本の文化では鑑賞者こそがいちばん偉いのだ、と。
まあ、あきらかに「作品の良さを言葉にできるおれは偉いんだ。尊敬しろ」といっているわけなんですけれど、じっさい、かれのこのような態度を見てリスペクトしている人が何万人も何十万人もいることを考えると、人間はやっぱり自画自賛しておく必要があるのかな、と思ったりします。
ついつい自虐に走りがちなぼくは勉強になるポイントです。
とにかく岡田さんは「見る」ことに特化した人間、いい換えるならだれかの「ボケ」を見て「ツッコミ」を入れることのスペシャリストです。
まさに「一億総ツッコミ時代」を一身に体現しているような人です。
そのかれの「ツッコミ」がどのようなものであるのか、いくらでも例があるのですが、たとえば『封印』における田中公平と山本弘との三者対談を見てみましょう。
山本 やっぱヒット作飛ばす人って、そうういう不思議な感性とかそういうもんがあるちゃう? このミョーな名前とかさ、ガンダムでも。
田中 押井、富野、宮﨑、庵野っつうのは、これはやっぱりヘンやね、みんな。ヘン!
岡田 幾原君、俺会うたことないけど、きっと…
田中 幾原、ヘン! 『ウテナ』はヘンや。
山本 絶対ヘンやと思うわ。あんな番組作って、まともなヤツだたら張り倒すと思うな(笑)。
田中 あ、もう一人永野もおった。
岡田 あ、永野もおる! あいつ、ヘン!
これ、何やっているかわかりますか。まさに「先に攻撃することによって自分に降り掛からないように防御している」わけです。
会ったことも見たこともない他人を「ヘン」と規定することによって自分は「まとも」だと定義しているんですね。
それにしても山本さんはついにその作家生涯でひとつのヒット作も出すことができなかったわけですが(本人が認めている)、それで良いのだろうかと思ってしまいますね。
それはまあともかく、いい換えるなら、岡田さんのようにクリエイターとしての才能をもたない人が、その種の才能ではあきらかにかなわない人を目の前にしたときに、どこでマウンティングを取るかというと、人格で取るということなんですよ。
つまり、庵野秀明や永野護はたしかに天才かもしれないけれどヘンな奴ですよと、もっというなら子供ですよと。それに比べて自分はまともですよ、大人ですよと。
いまとなってははっきりいって岡田さんや山本さんと比べたら庵野さんや永野さんはヘンどころかずいぶんとまともな人に見えてしまうわけですが、この当時は岡田さんたちもまだそれほど化けの皮が剥がれていなかったのでこの種のいい草が通用するように感じられたのだと思います。
まあ、これもまた直接本人を知らない人間のざれ言にしか過ぎませんけれどね。
これは岡田さんがそのいい分を盗用したという竹熊健太郎さんの「オタク密教」、「オタク顕教」という概念にもかかわって来るのですが、ようは「オタク密教」とはメタであり、ツッコミです。「オタク顕教」とはベタであり、ボケです。
岡田さんというのは、ほんとうに密教的なメタ姿勢のカタマリみたいな人だと思うんですけれど、ようはものごとを正面から見ずに斜めから見ることに非常なプライドを抱いているんですね。
上記の会話とか、知らない人の人格をアニメだけ見て決めつけているわけで、ある意味で「世間知らずの痛いオタク」といえなくもないと思うのですが、岡田さんや山本さんにとってはこれが「オタクであるということ」だったと思うんですよ。
つまり、自分は信者じゃないんだと。ちゃんと裏側まで見てすべてわかった上で客観的に作品を評価しているんだということです。まさにメタ。まさにツッコミ。
こういう人はベタにボケることができません。なぜなら、ボケとは自分の「素」をそのままに露出する行為だからです。
他人のボケをあざ笑う人間は、自分がボケてツッコミを入れられることがイヤでイヤでたまらないんですね。プライドを傷つけるんです。
しかし、もちろん、公にだれかを批判するなら自分も批判を受けることになる。そういうとき、オタクはどうするか?
そう、「あえて」とかいいだすのです。「それくらいの批判は全部織り込み済みで、「わざと」言っているんだよ。だから批判するほうがバカなんだよ(笑)」みたいな態度を取る。
以前、岡田さんが女性とのキス写真がネットに流出したときに、「当たり前ですけど、ニセ写真です。初笑い、できたかな?」とごまかそうとして失敗し、大きな話題となったことがありました。
その態度の異常さに違和感を覚えた人も少なくなかったと思います。でも、ぼくは岡田さんがああいう態度になる理由がわかるような気がするんですよね。
だって、どこまでも「メタ」に「ツッコミ」を入れることを信条にしている人が、うっかり「素」を見られてしまったら、「あえて」とか「わざと」に逃げるしかないじゃないですか。そうしないとプライドを守れないじゃないですか。
ぼくは岡田さんとか唐沢俊一さんを見ていてほんとに自分の非を認めることができないんだなあと感心するんですけれど。
ちなみに山本さんという人はたぶん自分では「ツッコミ」だと思っているんだろうけれど、じつは「天然ボケ」なのではないかと思います。
かれはたぶん「あえて」じゃなく、本気で自分のいっていることは正しいと考えている。だから防衛線を張らない。そういう人だから作家になれるんですね。良くも悪くも。
それに対して岡田さんはどこまでも「あえて」の人であるわけで、やっぱり「ツッコミ」の人というか「ツッコミ」でありたい人。
こういう人が『「いいひと」戦略』みたいな本を書いているんだから面白いですよね。ほんとに本気で自分が「いいひと」に見えていると思っているんだろうか……。
で、こういう岡田さんのような「ツッコミ型オタク」に対し、徹底して「ベタ」に「ボケ」て、その結果として精神を病むほどの批判を受けたのが庵野秀明さんなのだとぼくは捉えています。
でも、どうでしょう。『新世紀エヴァンゲリオン』以降のガイナックスの崩壊を見ていると、べつに庵野さんひとりが「ヘン」で、「子供」であったわけではなく、むしろ庵野さんこそがガイナックスのなかで最も「まとも」なビジネスセンスを持った人であったように見えてきます。
そして、天才クリエイター・庵野秀明はいまとなっては日本を代表する映画監督であり、経営者としても一流のセンスを示しています。
『プロジェクト・シン・エヴァンゲリオン』とか読むとその一端がわかるわけですが、もうめちゃくちゃ「大人の才能」がある人であり、むしろそうだからこそ自分の幼稚さを直視する勇気を持てたのだとわかります。
それに対して岡田さんは庵野さんやスタジオジブリからほぼ名指しで「迷惑」と断定される始末であるわけで、まあ、ほんとうに「ヘン」なのはだれか、ということになります。
庵野さん、仕事はちゃんと成し遂げるしすごい愛妻家だし、ある意味ではめちゃくちゃ「まとも」な人なんですよね。
で、まあ、つまり、一億総ツッコミ時代は一億総オタク時代ともいえるということです。
ぼくはここら辺の岡田さんや庵野さんの言動や行動に直接間接にものすごい影響を受けている。
だから、ぼくは「あえて」に逃げることを封印して「ちゃんと傷つく」ようにしています。
何かミスを犯して指摘されると傷つくんですよね(笑)。でも、そこは「ちゃんと傷つく」、そして「ちゃんと血を流す」べきなのだと思う。
そこで先んじて自己防衛をしようとするとおかしくなる。
庵野さんふうにいうなら、ちゃんと「パンツを脱いで」書かないといけない。血で書かれたものしか人の心には響かないのですから。他人がどう思うかはわからないけれどね。
ちなみに、ぼくは『東のエデン』というアニメもこの「だれもが批判される側ではなく批判する側に、責任を追及される側ではなく追求する側にまわりたがる」問題を扱っていると思っています。
最後に主人公が「お金を払う側ではなく、お金をもらう側のほうでありたい」みたいなことをいうシーンがありましたけれど、あれを翻訳するなら「ツッコミでなくボケでなければならない」ということだと思います。ベタに生きろ、と。
この話もまた長くなるので、また、どこかで。
でわ。
【お願い】
この記事をお読みいただきありがとうございます。
少しでも面白かったと思われましたら、![]() やTwitterでシェア
やTwitterでシェア
をしていただければ幸いです。ひとりでも多くの方に読んでいただきたいと思っています。
また、現在、記事を書くことができる媒体を求めています。
この記事や他の記事を読んでぼくに何か書かせたいと思われた方はお仕事の依頼をお願いします。いまならまだ時間があるのでお引き受けできます。
プロフィールに記載のメールアドレスか、または↑のお問い合わせフォーム、あるいはTwitterのダイレクトメッセージでご連絡ください。
簡易なポートフォリオも作ってみました。こちらも参考になさっていただければ。
【電子書籍などの情報】
この記事とは何の関係もありませんが、いま、宮崎駿監督の新作映画について解説した記事をまとめた電子書籍が発売中です。Kindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければご一読いただければ。
他の電子書籍も販売ちうです。いずれもKindle Unlimitedなら無料で読めます。
『ファンタジーは女性をどう描いてきたか』はファンタジー小説や漫画において女性たちがどのように描写されてきたのかを巡る論考をはじめ、多数の記事を収録した一冊。
『「萌え」はほんとうに性差別なのか? アニメ/マンガ/ノベルのなかのセンス・オブ・ジェンダー』は一部フェミニストによる「萌え文化」批判に対抗し、それを擁護する可能性を模索した本。
『Simple is the worst』はあまりにも単純すぎる言論が左右いずれからも飛び出す現状にうんざりしている人に贈る、複雑なものごとを現実的に捉えることのススメ。
『小説家になろうの風景』はあなどられがちな超巨大サイト「小説家になろう」の「野蛮な」魅力に肉迫した内容。レビューの評価はとても高いです。