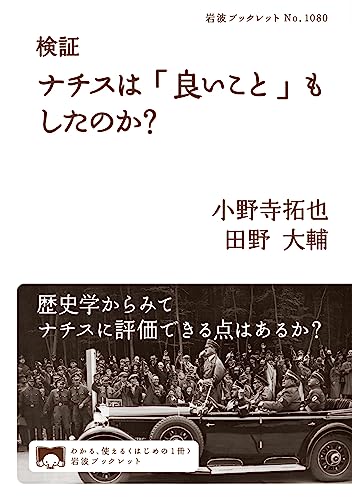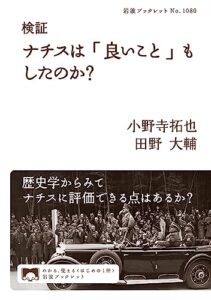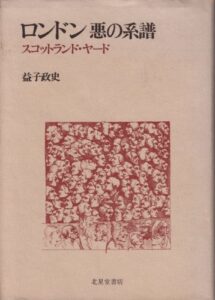話題の一冊『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』を読んでいる。
「ナチスは「良いこと」もした」という俗論を専門家の視点から批判的に検証した本で、とても面白いし、勉強になる。
本書では「ナチスは「良いこと」もした」という一種のまぜっかえし的な理屈が取り上げられ、それが歴史学的には端的に「まちがい」といってしまえることを詳細に検証していく。
そうはいってもナチスも「良いこと」もしているのではないかと漠然と考えているような人にとっては刺激的な内容といえるだろう。
歴史一般やいわゆる「歴史修正主義(リヴィジョニズム)」について知りたい方には文句なしにオススメできる一冊だ。
もっとも、「文句なし」というのは少し過言であるかもしれない。
ぼくはナチスやドイツ史について何ら専門的な知識を有していないし、著者たちの指摘に反論するつもりはさらさらないのだが、それでも、この本の論理展開にはやや危ういものを感じざるを得ない。
まず、本書の内容は単に「ナチスは良いこともした論」の誤謬を論破して歴史的事実を示すことで、ナチスが「絶対悪」であること、そのナチスの「絶対悪性」を証明することに留まらないものであると考えられる。
本書の目的はそもそもこうした「良いこともした論」一般の論理的誤謬を指摘し、それが成り立たないことを論証し、わたしたちの社会を成立させる「政治的正しさ(ポリティカル・コレクトネス)」の正当性を支持するところにあるのではないだろうか。
もし、本書がただ「ナチスの場合はこうだった」というだけの特殊論に限定される本であるのなら、たとえば「はじめに」にこのように書かれることもないだろう。
ここからもわかるように、現代社会においては、ナチスには良くも悪くも「悪の極北」のような位置付けが与えられている。ナチスは「私たちはこうあってはならない」という「絶対悪」であり、そのことを相互に確認し合うことが社会の「歯止め」として機能しているのである。「ナチス」と名指しされて、それを受け入れる人は現代社会にはほとんどいないだろう。自分はナチスとは違うと、否定する人間が大多数ではないだろうか。
こうした意味で、ナチス認識はその裏返しである「私たちの社会はこうあるべき」という、「政治的正しさ(ポリコレ=ポリティカル・コレクトネス)」と密接につながっている。
著者たちは、かれらの専門的知見からは荒唐無稽としか思われない「ナチスは良いこともした論」に危機感を覚え、それら「「中二病」的な反抗」を徹底的に批判するために本書を執筆したのだろう。
その心理はわかる。よく理解できる。
しかし、一方で仮にナチスが一切、「良いこと」をしておらず、その経済政策などがことごとく中長期的には評価に値しないとしても、「ほら、だからやっぱりナチスは絶対悪だったんだ」とはいえないと思うのである。
その理由について、以下の記事ではこのように書かれている。
まずもってナチスドイツのやった国内的な弾圧や虐殺、対外的な侵略や虐殺といったことは道徳的に否定すべき悪だという価値判断と、その経済政策がその同時代的に何らかの意味で有効であったかどうかというのは別のことです。
やや晦渋ないい回しであるかもしれないが、ようはナチスが行った「悪いこと」と、ナチスの経済政策が「良いことかどうか」とはべつの基準で判断しなければならないということだ。
これは、ごくシンプルに納得できる話だと思う。ナチスの経済政策は、たしかに俗説に反して実際には有効ではなかったのかもしれない。ぼくには判断能力はないが、おそらくそうなのだろう。
しかし、それは論理的な必然としてそうなったわけではない。「ナチスのような「絶対悪」集団は常に、必ず経済政策においても失敗するものだ」とはいえないのだ。
ナチスの経済政策にひとつも評価するべき点がなかったとして、それはいってしまえば「ナチスの場合はたまたまそうだった」というだけのことに過ぎない。
悪の集団がいつも政策的に無能だったらわかりやすいが、現実はそこまでわかりやすくはないだろう。
ようするに、このようなことがいえることになる。
①倫理的な絶対悪は絶対に「良いこと」などしないとはいえない。
これはごく素朴なレベルの話だ。
ある人物なり集団が「良いことも」しているということと、その人物、集団が「悪いこと」をしているということはべつのことであるということ。
あまりにあたりまえのことだが、「仮に」ナチスの経済政策に有効なものが見あたったとしても、だからナチスの悪逆非道が正当化されるわけではない。
ナチスが「仮に」一方で「良いこと」をしていたと認めるとしても(つまり、「ナチスは良いこともした論」を容認するとしても)、だから「ナチスはそんなに悪い奴らではなかった」とはならないのである。
いわゆる「良いこともした論」には、「良いことも悪いこともしたのだから、単純に悪い集団とはいえない」とする含みがある。
「良いこともした」とすることによって、いわば100%の「絶対悪」を50%くらいの「相対悪」にまで薄めてしまう効果を狙っているわけだ。
しかし、これはやはりまちがえている。なぜなら、「良いことも悪いこともした」とはいっても、その「良いこと」と「悪いこと」はべつに考える必要があるからだ。
「仮に」一方で良いことをしていても、他方でものすごく悪いことをしていたなら、その集団は「悪い集団」だということである。
このことを以下のようにまとめてみよう。
②「良いこと」と「悪いこと」は相殺しない。「良いこと」もした集団であっても、一方で過度に「悪いこと」をしていたら、それは「悪い集団」なのである。
ぼくたち人間は、ある人物や集団を白か黒か、善か悪かと分けて考えるようなところがある。
何か凶悪な事件を起こした人物が、取材で「ちゃんと挨拶もできる良い子だったのに」と語られたりすることはその典型的な例だ。
ぼくたちはしばしばその人物は「ほんとうは」善い人なのか、悪い人なのかというふうに考える。
じっさいには人間はそのように単純なものではなく、「善い人」であっても悪いことをするし、「悪い人」であっても善いこともする、というかそもそも「善い人」とか「悪い人」とか単純にいい切れないわけなのだが、それでもついそのように考えがちなのである。
二元論の罠、とでもいえば良いだろうか。「ナチスは良いこともした論」もこのような心理を利用しているところがある。
「良いこともした」以上、純粋な悪ではなく、つまりは「そんなに悪くなかった」と相対化してしまうのだ。
これはたしかに危険な思考である。だが、それに対して「ナチスは良いことなどしていない」と反論するのは、十分な反論になっているといえないのではないだろうか。
なぜなら、この場合、「仮に」ナチスが良いこともしていると証明されてしまったら、ナチスの倫理的悪が薄まることをも認めてしまうことにつながるからだ。
もちろん、『検証 ナチスは「良いこと」もしたのか?』の著者たちは「ナチスは良いことなどしていない」と確信を抱いており、だからそのことを示しさえすれば十分だと考えているのだろう。
だが、ぼくはそれでは十分ではないという立場に立つものである。
なぜなら、ナチスが「良いこともしていない」としても、それは「たまたま」なのであり、「悪い奴らは常に悪いことしかしない」という理屈は成り立たないからだ。
いや、悪い奴らはいつも悪いことしかしないのだ、ナチスはそのことを証明しているサンプルなのだ、と考える人もいるかもしれない。
しかし、これが誤っていることはちょっと歴史を振り返ってみればすぐにわかることだろう。歴史は「善」と「悪」の二色に分かれてなどいない。
あるいはナチスは「かぎりなく黒」の「絶対悪」かもしれないが、逆にいえばそのような存在は歴史的に見てきわめて稀有なのであって、ナチス・ドイツの例を取って「良いこともした」論一般への論破とすることはできないのである。
ぼくとしては「ナチスは良いこともした論」への反論としては、ほんとうはこのように答えなければならないと思う。
「まずナチスは良いことはしていないし、「仮に」していたとしても、それはナチスの悪行とは一切関係がないことだ」と。
これは、たしかに迂遠に感じられるいい方ではある。だから、「ナチスは良いことなどしていない」とだけいって終わらせたい誘惑を感じることもよく理解できる。
しかし、そこにはすべてを「白」と「黒」に分けて考えてしまう危険性がある。
念のためにいっておくと、ぼくはナチスが倫理的に「絶対悪」であり、なおかつその経済政策も無効であったという著者たちの主張を否定しているわけではない。
そうではなく、たとえナチスにおいてはそうであったとしても、「いつも」そうであるとは限らないし、「いつも」そうであるに違いないとシンプルに考えることは、たとえば「この団体の経済政策はまっとうだから、倫理的にもまっとうに違いない」などと考えるトラップに嵌まる危険性を秘めているといいたいのである。
そのことについて、上記引用の記事ではこのように書かれている。
悪逆非道の徒は、そのすべての政策がとんでもない無茶苦茶なものばかりを纏って登場してくるわけではありません。
まっとうな政策を(も)掲げている政治勢力であっても、その本丸が悪逆無道であれば悪逆無道に変わりはないのです。
悪逆無道の輩はその掲げる政策の全てが悪逆であるはずだ、という全面否定主義で心を武装してしまうと、その政策に少しでもまともなものがあれば、そしてそのことが確からしくなればなるほど、その本質的な悪をすら全面否定しがたくなってしまい、それこそころりと転向してしまったりしかねないのです。
至言である。そういうことなのだ。
ナチスが「絶対悪」であり、なおかつ「絶対無能」であるということと、「絶対悪」は常に「絶対無能」であるということは違う。
ここをわきまえていないと、「かれらは有能なのだから絶対悪などではない」と考えてしまいがちだということだ。それをこのようにまとめておこうか。
③政策能力と倫理的正しさは別個の概念であり、同一視してはならない。
ぼくがここで思い出すのは、よくマンガなどで見かける(ような気がする)「不良が子犬を拾うところを見かける」展開だ。
普段は「悪いこと」をしている不良が子犬を拾うという「良いこと」をしているところを見かけることで、「この人はほんとうは善い人だったのだ」と考えるようになる展開なわけだが、これはじっさいには論理的誤謬というべきだろう。
あたりまえのことだが、子犬を拾ったからといってその不良がやった「悪いこと」が免罪されるわけではない。
もう少し考えてみよう。ナチスは「絶対悪」にして「良いことなど何ひとつしていない」と認めるとして、それではアドルフ・ヒトラーという個人はどうだろうか。
いかに生粋の大悪人といえども、生まれたときからずっと延々と絶対悪だったわけはないから、「良いこと」のひとつふたつもしていても不思議はない。
たとえば、そう、雨のなか濡れた子犬を拾ったこともあるかもしれない。
しかし、たとえそのようなことがあったとしても、ヒトラーの邪悪さがいささかも減じるものではないことはあたりまえのことだ。
これは、ヒトラーがひとりの人間として純粋に「悪」の側面しか持たない人格だったということではない。その「行動」が悪行としかいいようがないということである。
「仮に」ヒトラーに「善い人」の一面があったとしても(なかったかもしれないが)、だから「ヒトラーは善いところも悪いところもある普通の人だった」などといえるはずもないのは当然のことなのだ。
ものすごく「悪いこと」をしているのなら、その人格に「善いところ」があったり、あるいは行動として「良いこと」をしていても、「悪い人」、より正確には「自分の悪行に責任を持っている人」であることは揺らがない、ということである。
あまりにもあたりまえのことに過ぎないように思われるだろうか。ぼくもそう思う。
だが、歴史の専門家であるこの本の著者たちは、目の前のトンデモ主張を手早く却下したいがために、その「あたりまえのこと」を無視しかけているように思える。
もし、ヒトラーが濡れた子犬を拾っているところを見かけたとしても、たやすくかれにだまされたりしてはならない。
これが、ぼくのこの本に対するひとつの見解であるのだが、あなたはどのように思われるだろうか。
【宣伝告知】
この記事などを読んでぼくに何か書かせても良いと思われた方はぜひお仕事の依頼をお待ちしております。いまならまだ時間があるのでお引き受けできます。よろしくお願いします! 「kenseimaxiあっとmail.goo.ne.jp」へメールを出すか(あっとを@に変換)、Twitterまでダイレクトメッセージでご連絡ください。
簡易なポートフォリオも作ってみました。こちらも参考になさっていただければ。
それから、この記事とは何の関係もありませんが、いま、宮崎駿監督の新作映画について解説した記事をまとめた電子書籍が発売中です。Kindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければご一読いただければ。
他の電子書籍も販売ちうです。いずれもKindle Unlimitedなら無料で読めます。