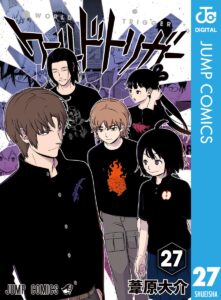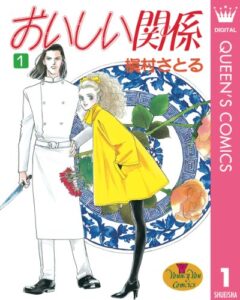この記事はこちら(![]() )からはてなブックマークに登録できます。もし面白いと思われましたら言及していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。
)からはてなブックマークに登録できます。もし面白いと思われましたら言及していただけるととても嬉しいです。よろしくお願いします。
それでは、記事へどうぞ。
- 【男らしさとタナトスのカルチャー】
- 【男らしさとは公共善への奉仕】
- 【ジェンダーは誘惑する】
- 【追加部分】
- 【『少年ジャンプ』という「男らしさ」の牙城】
- 【「父」とは何か?】
- 【現代において「父殺し」は成立しない】
- 【さいごに】
【男らしさとタナトスのカルチャー】

熊代亨さんが昭和の「ジャンプマンガ」の代表格のひとつであるところの『魁!男塾』のこのワンカットについて語った、以下の記事が面白い。
熊代さんはこのページを示しながら、このように問題を提起している。
それから32年の歳月が流れた。
この間、社会は男女の機会均等を推進し、少なくともある程度までは女性の社会進出が実現した。
男性らしさ、女性らしさ、そういったジェンダーにこだわることは愚かで、時代遅れで、無駄で、モラルのうえでも良くないと考えられるようにもなったと思う。かくして、当時からナンセンスだった「男なら しねい」から最も遠い社会に私たちはたどり着いた……はずだ。
ところが2023年においても、「男なら しねい」がインターネット上を幽霊のように徘徊しているのである。
もちろんこれを真に受けている人は少数で、良識あるほとんどの人がナンセンスなギャグとして受け取っているに違いない。だが……これはいったい何を示唆しているのだろうか。
かれはつづけてこの令和の世の中においても「男らしさ」といういわゆる「ジェンダー」が消え去っていないことを示唆していく。
そして、さまざまなデータを示しながらいうのである。「死」に近いのはやはり男だ、男たちはより「死にやすい」人生を生きている、と。
理解できる意見である。ぼくは個人的に男らしさの文化は即ち「死(タナトス)」の文化であると考えてきた。
何千年にもわたって戦争を起こし、戦場で戦ってきたのはほぼ男たちだ。
それをネガティヴに捉えるなら戦争や虐殺の責任はおおかた男性にあるといえるだろうし、ポジティヴに捉えるなら共同体を防衛し「女子供」の生命を守って来たのは男たちだったと述べることが可能だろう。
しかし、とにかく、男たちのカルチャーにはぬぐいがたく「死」の刻印が記されている。それはこの現代においてすら、いろいろな作品のなかで垣間見られる。
「男なら死ねい」は、もちろん先行作品である『男組』あたりを踏まえたいたって過剰でばかばかしいジョークではあるが、だからといってまったく無根拠でもないのである。
【男らしさとは公共善への奉仕】
そもそも、直接に生命を産み落とすことができない男たちは、その能力を持つ女性たちに対して優越感と劣等感が入り混じった複雑な感情を抱いているように思う。
男たちが「死」に魅了され、ときに戦争を起こし、ときに自殺を遂げるのは、単純に体内のテストステロンの問題というよりは、やはり男性はそうやって「だれかに奉仕する」ことでしか自分の存在意義を示せない一面があるからではないだろうか。
ただ、そういった価値観はもはや男性だけのものではない。
この『男塾』の一場面で描かれているものはつまり「公共善への身命を賭した奉仕」という価値である。
それが男性という性差と結びつけられた上で極端にデフォルメされ、「男なら死ねい!」という言葉と化しているわけだ。
しかし、『鬼滅の刃』あたりを読むと、もはや女性たちもまたそういうった「公共善への奉仕」のために死ぬことに躊躇を見せない場面が描き込まれている。
もし、その「奉仕」を至上とする価値観を「男らしさ」というなら、「男らしさ」はもはや男だけの価値観ではないのだといって良いだろう。
熊代さんはまた、このように書いている。
では、ジェンダーか生物学的な差異かを問わず、これから私たちは性別をなくすべきだろうか?
男女がいがみあい、対立するさまに着眼する限りにおいて、性別は邪魔であり、有害であり、男女平等実現の妨げのようにみえる。男女平等を突き詰めて考えるなら、ジェンダーについてごちゃごちゃと議論するのでなく、性別そのものを破壊するしかなくなるのではないだろうか。
読者のみなさんなら、どのように考えますか。
男らしさは邪魔ですか。女らしさも邪魔ですか。人間は、性別を捨てるべきですか。
かなり飛躍した話だ。そもそも「性別をなくす」とは具体的にどういうことだろうか。
身体的な意味での差違も心理的な意味での差違も一切見られないように人間を「統一」するということなのだろうか。
そうだとしたら、ぼくはそれに対し明確に反対である。たとえば、人種差別は問題だからすべての人間の肌を灰色に塗りたくろう、などといい出したら、それはやはり論外だろう。
結局のところ、「差異の統一」は差別への対抗策でも何でもなく、むしろそれじたいが最大の差別そのものなのである。
ぼくとしては、それとはまったく逆の方法論を提案したいところだ。つまり、ありとあらゆる差異を最大化していくほうが良いと思うのだ。
「男らしさ」や「女らしさ」といった差異はあって良い。しかし、それを男性や女性に対し紐づけて強制することは好ましくない。
なぜなら、じっさいに「男らしくない」男性や「女らしくない」女性はいて、「男らしさ」や「女らしさ」を特定の性別に強制することはそのような人たちに対する抑圧になるからだ。
「多様性」という言葉はいかにも手あかがついてしまった感があるが、この社会にはいろいろな人がいて良いという考えかたには賛成である。
男らしい男がいて良いのと同様、男らしくない男もいて良い。女らしい女も女らしくない女も、その人の資質を最大限に発揮できるようであるべきである。
それが、ぼくにとってのリベラルな理想だ。
【ジェンダーは誘惑する】
ただ、ある意味で「保守」的な理由からこのような素朴なリベラリズムに反対する人はいるだろう。
「男であること」、あるいは「女子供のために死ぬこと」に何らかの価値を見出している人は、そういった価値観を男性から剥ぎ取られることに反対するに違いない。
なぜなら、その価値観において、男たちは「公共善に奉仕して死ぬこと」によって「女子供」に優位に立つことができるからである。
そこにあるものは、つまり、言葉にするならこのような心理であるといえる。
「おまえたち女子供が幸せを享受していられるのはおれたちが身命を賭して守ってやっているからなのだ、感謝しろ」と。
あえていおう。非常に恩着せがましい物言いだ。
そこには「だれのおかげで喰っていけると思っているんだ」などといい出す家父長気取りオヤジのような独特の優越感と恩着せがましさがある。
男たちがやたらに「死」に魅了され、何かと死にたがるのは、ひとつには「女子供」を守って死ぬことにうっとりと自己陶酔しているからであるように思える。
それは、たとえば三島由紀夫のもっともかれらしいといわれる切腹自殺小説「憂国」などにも見られるナルシシズムであり、この社会における最後の性差別の根拠となっているものであるように思える。
「なんだかんだいってみても、戦いになったら女子供を守って死ぬのは男なのだ」。
それが、とくにネットでは、はっきりと男たちの女性への優越意識を支えているように思うのだ。
これはいわゆる「弱者男性論」にも通じる。つまり、弱者男性の苦しみとは、ひとつには男性として「女子供を守って死ぬ」アイデンティティを形成することができないところにあるということ。
弱者男性論を眺めているとつくづく思うのだが、どうも弱者男性自認の男性たちは強者男性になりたくてたまらないらしい。
生命を生み出すことができない男たちはだれかを守って死ぬことによって初めて、自分の存在価値を明確に見いだすことができるのだろうか。
いかにもばかげた話だが、「男らしさ」というタナトスの文化の背景にあるものは、そのようなことなのではないかと考えたりもする。
一方で、社会的に子供を産み落とす役割を課せられた女性たちは女性たちでそれ故の葛藤が生じるわけだが、男たちは自分自身の物語に夢中で、その苦しみに興味を示すことはまれであるように思われる。
つまりは「男らしさ」、「女らしさ」といったジェンダーは、単純に外から強制されるものというよりは、その魅力で人を自縄自縛にするものでもあるということができるだろう。
ジェンダーフリーとか男女平等などといっても、案外、人が性別に縛られるのはここらへんに理由がある。
ジェンダーはそのセイレーンの歌声でどこまでも甘く人を誘惑するのである。
【追加部分】
さて、この記事はここで終わりです。この先には独立した有料追加部分として「『少年ジャンプ』と「父殺し」」の話を述べたいと思います。300円でお読みいただくことができます。
また、月額1000円のサブスクリプション会員になるとすべての有料記事を読むことができます。良ければ、会員登録して続きをお読みください。
【『少年ジャンプ』という「男らしさ」の牙城】
そういうわけで、令和のいまになっても「男らしさ」や「女らしさ」は残りつづけ、さらには特定の性別に紐づけされて人々を魅了したり呪縛したりしている。
ジェンダーによる縛りをなくそうという男女平等の思想は立派だが、単純にジェンダーを外部的な支配や抑圧と捉えていてはその本質は見えてこない。
ジェンダーにはある種の「うまみ」があるからこそ、それらは消えやらないのだと見るべきだろう。
『男塾』ほど極端にあらわれているものはまれだが、『少年ジャンプ』は長いあいだ、その種のマッチョイズムの牙城として人気を博してきた。
じっさいには『ジャンプ』には長年、一定の女性読者がいたのだが、この雑誌はいまに至るまであくまで「少年」こそがターゲットであるという建前を崩していない。
その是非には議論があるところだろうが、『ジャンプ』が非常に「男らしさ」、あるいは「少年らしさ」というジェンダーを重視していることは間違いない。
そういった傾向に対して批判的な人もいるが、同時に、その無邪気な「少年らしさ」こそが『ジャンプ』の最大の魅力であることは論を俟たない。
最近の「『ジャンプ』にもフェミニズムマンガを連載したら」といったフェミニストたちの発言が失笑しか生まないのは、『ジャンプ』の苛烈な競争が単純にイデオロギー的な作品を許容しないというコンセンサスがあるからだろう。
『ジャンプ』はいまなお、「男の子の雑誌」でありつづけている、あるいは少なくともあろうとしつづけている。
現実に多数の女性読者や成人読者がいる以上、実態との乖離はあきらかだが、『ジャンプ』にとって「少年」こそがメインターゲットであるという看板は外せないものであるようなのである。
『ジャンプ』にはいまなお「父性的(パターナル)」なものが息づき、「母性的(マターナル)」なものは嫌われる。
【「父」とは何か?】
さて、『鬼滅の刃』からタイトルを取った『父滅の刃』という本がある。
この本のなかでは、日本マンガやハリウッド映画のなかでいかにして「父性」が軽視されるようになっていったかが縷々つづられているのだが、『ジャンプ』にはそのようなご時世でも「父」が生きている。
わかりやすいのが、「家父長相続」のストーリーだ。物語を通して「父」なるものを追いかけ、やがてその「父」を乗り越えて一人前のヒーローになるという「父殺し」の展開。
『ONE PIECE』にも『鬼滅の刃』にも『HUNTER×HUNTER』にも「偉大なる父」は見られるわけだが、そこでは「母」が登場する余地はほとんどなく、ひたすらに「どうやって父を乗り越えるか」だけがフォーカスされる。
『ジャンプ』作品ではないが、たとえば『ドラゴンクエスト3』もこの「父殺し」がテーマだったし、『シン・エヴァンゲリオン劇場版』はいくらか形を変えた「父殺しの物語」であると見ることができるだろう。
そこでは「父」なるものはいまだに生存していて、「少年」たちはその壁を乗り越えるためにさまざまに苦闘しつづける。
その姿は少女マンガがさまざまな葛藤とともに「母殺し」の困難を描いてきたこととは対照的である。
そういった『ジャンプ』の傾向を「古くさい」ものと見ることは可能だろう。じっさいのところ、現代の若者たちがつくる家庭において、家父長制が残存しているとは考えがたく、もはや『ジャンプ』的な「父殺しの物語」はある種のファンタジーと化しているとすら見える。
しかし、それでもなお、現実に『ジャンプ』のマンガがヒットしつづけていることも事実である。
つまりは、この社会においていまなお、「父」と「父殺し」のストーリーは魅力を失い切っていないのだ。
【現代において「父殺し」は成立しない】
これは、見方を変えれば不思議なことであるようにも思える。
何といっても、『ジャンプ』のマンガはすでにかつてのようなひたすらに「成長」や「上昇」を志す物語に限定されていない。
かつての『ドラゴンボール』や『SLAM DUNK』の魅力はどこまでもどこまでも猛スピードで「成長」していく主人公たちの描写にあったが、いまの『鬼滅の刃』や『呪術廻戦』、あるいは『サカモトデイズ』をそのような作品として見ることはむずかしいだろう。
そこにおいても「成長」の要素はなくなったわけではないにせよ、もはや主眼でないといって良い。
なぜなら、それらの作品における「バトル」はきわめて複雑化、複層化しており、単純に「パワーアップ」すれば良いとはいえなくなってきているからだ。
そこで描かれているものは、知的な意味でも肉体的な意味でも能力的な意味でも精神的な意味でも屈強なもののみが生き残れる「生存競争(サバイバル)」なのであって、かつてのようなひたすらに「上」をめざす戦いではない。
それなら、現在の『ジャンプ』における「父」とは何者なのか。
『HUNTER×HUNTER』を見てみよう。この長い物語は、主人公であるゴン・フリークスが父親であるジンを探し求めるところから始まった。
ジンはゴンにとってまだ見ぬ目標であり、ある種の理想そのものでもある。ゴンが「ハンター」をめざすのは、ジンがハンターであったからだ。
しかし、最新刊近くのあるエピソードにおいて、ゴンはあっさりとジンを見つけだしてしまう。
そこには、物語的な感動や盛り上がりといったものはあまり見られない。結局のところ、『HUNTER×HUNTER』はその意味では「父殺し」の物語ではなかったのである。
ここにおける「父」は、たしかに人生の先行者であり、尊敬するべき人物ではあるが、「殺す(乗り越える)」ための「壁」ではない。あくまで「自分とは別の人物」なのだ。
それでは、なぜ「父」が描かれる必要があるかというと、ひとつの見本としての役割を果たしているのだと考えられる。
ここにあるものは、人生のはじまりにおいて、まずは目標として「父」をめざす期間が必要ではあるにしても、必ずしも最後までその「父」を倒し、打ち破り、乗り越えて「家父長」を相続する必要があるわけではないという展開である。
その意味で、この作品はやはり純粋な「父殺し」の物語とはやはり少しずれている。ここでの「父」は「とりあえずめざすべき道標」ではあっても、「最終目的」ではまったくないのだ。
現在の『ジャンプ』において、「父性」をこころざすマッチョイズムがまったく死んでしまったわけではない。それはたしかだ。
しかし、だからといって「偉大なる父を乗り越えて父殺しを完結させる」というエディプス・コンプレックス的なイメージがそのままに残存していると考えることも少し違っているように思える。
現在の『ジャンプ』における「父」はあまりに複雑化し、はっきりした地図を見て取ることができなくなってしまった社会において、とりあえず志すべき目標ではあっても、人生において最後まで立ちふさがる巨大なハードルではないということ。
「父は偉大ではあるがあくまで他人、自分は自分」。その意味ではその描写は非常に成熟してきていると見ることもできる。
だが、ほんとうに現状を分析するためにはより多くのサンプルが必要だろう。『ジャンプ』の現状はどこにあるのか? ひきつづきウォッチしつづけることとしたい。
【さいごに】
最後までお読みいただきありがとうございます。
また、オタク文化の宗教性について考える電子書籍『ヲタスピ(上)(下)』を発売しました。その他、以下すべての電子書籍はKindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければそちらでもご一読いただければと思います。
それでは、またべつの記事でお逢いしましょう。









![シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME <初回限定版>(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray) [Blu-ray] シン・エヴァンゲリオン劇場版 EVANGELION:3.0+1.11 THRICE UPON A TIME <初回限定版>(Blu-ray+4K Ultra HD Blu-ray) [Blu-ray]](https://m.media-amazon.com/images/I/21pEpqe97tL._SL500_.jpg)