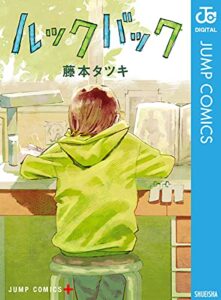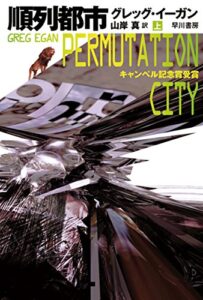初めに、退屈なほど自明の事実をひとつ。
『ファイアパンチ』、『チェンソーマン』などの長編で知られる漫画家藤本タツキが2021年に発表したマンガ『ルックバック』はまさに記憶に残すべき傑作だった。
幼くして画業に優れたあるふたりの少女が漫画家をめざし、幾たびとなく成功と挫折をくり返しながら前へ、前へ進んでゆこうとするこの物語は、発表からわずか30分(!)でTwitterにおけるトピックのランキングで2位にまで上昇するという快挙を生み、いまではなかば伝説的に語られることとなっている。
悪ふざけとリリシズムを巧みに使い分けるこの若く気ままな天才作家の現時点での代表作のひとつ、そしてこの10年のすべての中短編マンガのなかでも最高傑作のひとつといって良いだろう。
「創作」という行為の本質をえぐり出し、いまなお多くの作家たちを触発しつづけるすばらしい作品である。
その『ルックバック』が、このたび、アニメーション映画になった。人気を考えれば必然の展開ではあるものの、じっさい、そのクオリティはどうだったのか。多くの人が気になるところだと思う。
結論から書いてしまうと、これが、まあ、とほうもない傑作なのである。
原作も凄まじいインパクトがあったが、このアニメーション版『ルックバック』は、その原作の物語を繊細に再現しつつ、いかにもアニメーションらしい出色の演出を加えてその衝撃をさらに、さらに凌駕する。
ひとりの、ちょっと絵が達者なだけのあたりまえの小学生の物語として始まった作品は、わずか58分のあいだに驚くべき飛距離のホップステップジャンプをくり返し、観客を感動の結末まで連れてゆくのだ。
圧巻の傑作としかいいようがない。今年の邦画のベスト候補であるばかりか、アニメーション映画のオールタイムベストのひとつに数えたいほどの歴史的、道標的作品だといいたくなる。
ぼくは公開二日目の昨日に観に行ったのだが、劇場の席はほとんど満員だった。
これから口コミでの評価が広まっていくものと思われ、わずか全国110館での公開とはいえ、興行的にも相当な数字を記録することだろう。
が、もちろんより重要なのはこの映画の質的な達成のほうである。
何かを生み出すということの苦しさ、生きていることの切なさ、いまそこにだれかが生きてあることの愛おしさ、そのすべてがやがて失われゆくことのやるせなさ、そして、どこまでもどこまでも着実で前向きな創造のスピリット――すべてが、あまりにも高次元で達成を見ている。
その秀抜な表現のなかでもとくに驚かれたのが、圧倒的な色彩と描線のみずみずしさだ。
キャラクターたちの表情のひとつひとつ、その鋭くもどこか危うい情感の表現は原作マンガに匹敵し、あるいは上回るものがあると思う。
アニメを観ていてここまでやわらかな清新さに打ちのめされたのは、片渕須直監督の『マイマイ新子と千年の魔法』を見たとき以来である。
ここには、日々、膨大なアニメーションを「消費」してゆく日常のなかで、ほとんど忘れかけていた「絵が動く」というアニメーションの原初的な快楽を思い出させるものがある。
どうしても「絵」という言葉を使いたくなるような奇跡的な表現の達成だ。
しかし、もちろん、物語はただふたりの少女の苦悩と成長と栄光を描いてそこで終わることを良しとしない。
あたかも世界の必然の法則であるかのごとく、ふたりの道は違え、別れ別れとなり、そして、そのひとりに恐るべき悪意が降り掛かるのである。
物語終盤へ向けた強烈なカタストロフィ。世界は崩落し、二度と元には戻らないかたちで変質する。
この「悪意」の形式的とも取れる表現にはさまざまに議論が寄せられているが、じっさい、この世界において、こういったできごとは「いたって良くあること」でしかないというのも真実だろう。
もしこの世に神がいるとすれば、それは決して善意の存在ではなく、むしろぼくたち人間をありとあらゆる手段でさいなんで楽しむデミウルゴスなのではないかと思うほど、この世界には「不条理」や「理不尽」が充満している。
そう――そうなのだ、ぼくは昔から、いつも、いつも、いつも疑問に思っていた。この、不条理で理不尽でめちゃくちゃででたらめで、もうどうにも崩れかかっているとしか思えない世界で、ひとりの人間が真剣に生きることに意味はあるのか、と。
ぼくには世界も社会もまったくまともとは思えない。きょうもきょうとても日常世界ではいじめやハラスメントがつづき、人々は差別と暴力と暴言に夢中になり、ニュース番組ではどこか遠くの悲劇と近くの腐敗が伝えられている。
何だろう?
もうめちゃくちゃじゃん。
人類が何千年も何万年もかけて堆積してきた矛盾と悪徳はすでに限界にまで到達しているとしか思えない。
あるいは世界が崩れかけているというのは微温に過ぎる表現であって、ぼくたちの世界はとっくに崩れ去ってしまっているのかもしれない。そしてこのさき、あと何十年かでほんとうにすべてが終焉を迎えてしまうのかも。
そこまで壮大な話をしなくても、ひとを自殺にまで追い込んだいじめの加害者が学校の保護を得て進学していつまでも幸せに暮らしました、めでたしめでたし、なんてどす黒い話はざらにある。
『ルックバック』はフィクションだが、そこで描かれている「不条理な死」、「理不尽な現実」の描写はウソでも何でもなく、いくらでもありえるしあることなのだ。
世界は一個の腐敗した卵であるに過ぎない。
生まれてきた以上、可能なかぎり真摯に、善良に、親切に生きたい。しかし、この腐った世界でマジメに生きてみたところで、悪意の神がちょっと悪戯を行なえばそこでおしまい。すべての努力も献身も無となって消え去る。
ほんとうはおてんとうさまなんて見てはいないのだ。それなら、なぜ「それでも」真剣に生きなければならないのか? ばかばかしいかぎりではないか。
だが、いま、映画『ルックバック』を観終えて、ぼくはその問いに対する答えが初めてこたえになったように思う。バカみたいに簡単なことだ。
マンガがあるからだ。
映画があるからだ。
物語があるからだよ。
世界の本質的な狂気に必死になってみっともなく抗っているのがぼくひとりではないとわかるからなのだ。
この映画のクライマックスで、「死」の青白い手が奪ったものの大きさに打ちのめされ、主人公はついに決定的に挫折する。
この瞬間、どんなに努力し専心したところで人間は運命の気まぐれな一撃に対してまったく無力であるという「世界の虚無」が露出したといえる。
虚無(ニヒル)。
いわば、この世界の各所にはそういったどうしようもなく深い落とし穴が空いていて、そこへ落ちたら最後、二度と上がることはできないのだ。
そういったこの世の虚無にふれてあらゆる意味と価値を喪失した態度をニヒリズム(虚無主義)と呼ぶ。
この言葉は哲学者ニーチェの名とともに広く知られているが、さいしょに使い始めたのは作家のツルゲーネフだという。
が、学問的なあれこれは良い。ぼくがこの言葉を使うのは、『ルックバック』がまさにニヒリズムへの抵抗を主題とした物語だと感じたからだ。
戦後日本の社会はしばしばニヒリズムが蔓延しているといわれる。したがって、幾多のクリエイターがニヒリズムをテーマに選んできた。
典型的なのは三島由紀夫や宮崎駿だ。とくに宮﨑は一貫してニヒリスティックな発言を行いながら、それでも「子供に向けてニヒリズムを語ってはならない」との倫理を掲げ、とくにそのアニメーションにおいては希望的というか未来志向的な「子供のための」物語をつらぬいてきた。
そして、また、その宮﨑がニヒリストとしてときに過激なまでに執拗に批判するのが戦後マンガの巨匠・手塚治虫である。
手塚が真にニヒリストであったかはともかく、たしかにかれは「子供に向けても平気でニヒリズムを語る」人であった。
手塚がかいたいくつもの傑作では、しばしば無惨なまでに悲劇的な物語が綴られ、ひどく虚無が「露出」している印象を与える。これはたしかに宮崎駿のアニメーションとは対照的である。
ひっきょう、手塚のマンガには何か得体のしれない「暗いもの」が染みついていて、かれは生涯、それと格闘しつづけたと見るべきなのかもしれない。
一方で宮崎駿はごく最近の作品や「個人的」なマンガ作品である大名作『風の谷のナウシカ』を除いて、あくまで子供たちに人生の希望を見せようとこころみてきたように思える。
しかし、思うに、子供に向けてニヒリズムを語らないということは、子供に対しニヒリズムへの対処法を教えられないということでもある。
あくまでも自分のなかの虚無を隠蔽し、希望的な虚構を紡ぎ出すその姿勢がほんとうに「子供向け」のクリエイターとして誠実な態度といえるかどうかは議論があるところだろう。
あるいは、それこそが自他ともに認める宮﨑の「弟子」である庵野秀明が「宮さんはパンツを脱がない」と批判する一因ではなかったか。
いずれにしろ、手塚や宮崎といったマンガ/アニメの世界における第一人者にしてからがそうなのである。エンターテインメントとしてのマンガやアニメを突きつめると、どうしてもどこかで虚無が露出するところはあるのではないかとぼくは考える。
なぜなら、エンターテインメントとは、何らかの「意味」や「価値」より「ただ面白い」ことが優越すると捉える「遊び」の文法に他ならないからである。
命をもかけて遊ぶことは狂気の沙汰だ。しかし、「その狂気の沙汰こそおもしろい」。しばしば愛や正義といったオブラートにつつまれて提示されるこのエンターテインメントの本質が暴露されるとき、まさに世界の虚無がさらけ出される。
『ルックバック』においてもそうだ。世界はその本質においてどうしようもなく虚無を胚胎しているということが終盤になって露出する。
この世界は狂っている! ぼくたちはその出口のない牢獄のなかで右往左往して一生を終えるさだめなのだ。
なんてばかばかしい。そう思わないだろうか? ここに、ニヒリズムの誘惑はある。
しかし――そのとき、あたかも一個の世界をへだてるかのように閉じられた扉のまえで、主人公はひとつの想像に耽る。
それは、彼女たちふたりの人生がわずかにきっかけによって微妙に、しかし決定的に異なる展開をたどった「もうひとつのセカイ」の想像(イマジン)だ。
その「もうひとつのセカイ」では、悪は倒され、命は救われ、すべてがひとつの完璧なハッピーエンドへと向かう――まるでできすぎたご都合主義のマンガかアニメのように。
これは以前書いたことだが、先日亡くなったSF作家の山本弘は、かれが考える「本来あるべき理想世界」を「正義が正義である世界」と名づけた。
そのセカイでは、正義はつねに勝ち、悪はつねに滅ぼされて、悲劇は何も起こらないのだ。この概念にかんしては未完成のまま放り出している山本弘論でくわしく書いたのでここではくり返しふれることはしない。
ただ、ぼくが思うに、山本がその「正義が正義である世界」を是とし、現実世界を非としたことも、ひっきょう、ある種の暗いニヒリズムに過ぎなかったのではないだろうか。
一見すると、山本の作品はおおむねいつもハッピーエンドであり、未来に対する希望を感じさせるものと見えるかもしれない。
しかし、かれはじっさいにはこの「狂った世界」と「愚かな人間たち」をついに受け入れることができずに終わった真正のニヒリストであった。
山本のニヒリズムは、現実の世界と人間とを否定するかたちであらわれる。
『ルックバック』の「もうひとつのセカイ」もやはり山本の「正義が正義である世界」のような願望充足めいたありえない虚構に過ぎないだろうか。
おそらくは、そうであるかもしれない。だが、注目するべきなのは、『ルックバック』は決して「もうひとつのセカイ」で「正義が正義である」ところを描いて終わらないということだ。
この最終盤において、この作品ではまさに驚くべきことがある。「正義が正義である」虚構の、夢想の世界から、まったく救いのない現実の世界へ、一枚の扉を超えてひとつのメッセージがとどくのだ。
ルックバック、と。
それはあたかも、単なるつくりごとに過ぎない物語が現実と虚無に対して敢然と戦いを挑みはじめたかのようなできごとだ。
虚構が現実に対し挑む戦い。抵抗。それはしんじつ、あまりに勝ち目のないむなしい戦いだ。無謀としかいいようがない儚い抵抗だ。
だが、「それでも、なお」、その「もうひとつのセカイ」からとどいたふしぎなメッセージは、絶対的な虚無をまえに折れかけた主人公のこころにふたたび火をつける。
ルックバック(背中を見て)。
世界がどんなに深く虚無を孕んで病んでいても、「それでも」抗い、戦う者たちがいる。
それは神や運命や世界というあまり圧倒的な存在を敵にまわしたほんとうに絶望的な戦いに過ぎないかもしれない。しかし、じっさいにどうしようもなく崩れかけたこの世界を、いくつもの「それでも」が支えているのだ。
そこに物語があるから、ぼくたちは戦える。ひとりではないとわかっているから、抗いつづけることができる。そういうことではないか。
『ルックバック』。
かぎりなく繊細な描写と神がかってあざやかな演出によってひとりの少女の神への、世界への、運命への、虚無への、不条理と理不尽への果敢な抵抗を描き出したという意味で、この映画は正真正銘、稀代の大傑作というべきだろう。
万難を排して映画館で見ることをお奨めする。そこに、あなたは希望の花が咲いているところを見つけるだろう。
その花は虚無の暴風をまえにあえなく散ってゆくさだめかもしれないが、「それでも」、またあらたな種をはこび、どこかで花を咲かせるのだ。
そうやってぼくたちは物語を紡いでゆく。いつかすべてが闇黒に消え失せるとしても、「それでも」、ぼくたちは花の種をまきつづけることに倦みはしないことだろう。
ぼくは、そう信じるものである。
ルックバック。
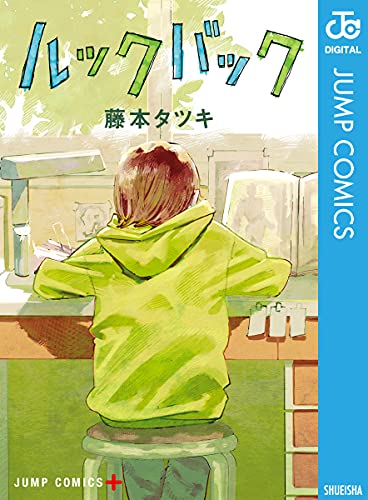



![マイマイ新子と千年の魔法 [DVD] マイマイ新子と千年の魔法 [DVD]](https://m.media-amazon.com/images/I/51p5pvtbnzL._SL500_.jpg)