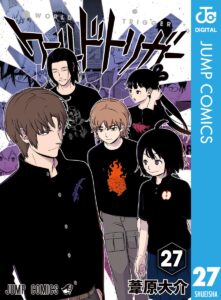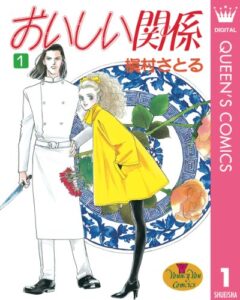どもども、今日も今日とてマンガの話をしたいと思います。いや、めちゃくちゃ凄いマンガを見つけたので、どうしてもオススメしなければと思ったしだい。
いや、これはほんとに凄い。凄まじい。故・三浦健太郎の『ベルセルク』を初めて読んだときを思わせる壮絶な面白さ。
このままいくと今年のベスト・オブ・ベストになりそう。花丸付きのオススメ作品といえると思う。
吾妻幸『血を這う亡国の王女』。きょうはこのタイトルを憶えて帰ってください。損はさせない。
「地」ではなく「血」であるところがポイントで、まさに己の血の上を這うかのような凄絶きわまりない物語が展開する。
文句なしに面白い、そしてただ面白いだけでは済まない大問題作であることはたしかだが、そのあまりに凄まじい暴力描写から万人向けとはとてもいえないだろう。
初期の『ベルセルク』を好きだった人には全面的にオススメできるものの、物語の現段階では『ベルセルク』のような魔法や奇跡の描写はなく、より純度の高いダークファンタジーといえる。
いや、これをファンタジーと呼んで良いものだろうか? これはまさに「暗黒の現実」をそのままにえぐり取って形にした一作ということもできそうだ。
あ、そこの人、「いまさら凄惨なバイオレンス描写なんて見飽きたよ」と思われましたね。
たしかにその通り。表現の自由が危ぶまれる現代日本とはいえ、陰惨だったり無惨だったりする暴力の描写が売りの作品はいくらでもある。
ぼくのような人間はその手の描写を見飽きてすっかり感覚が麻痺してしまっているくらい。
しかし、この『血を這う亡国の王女』はそういったただのウルトラバイオレンスな作品とは一風異なる。
このマンガの特徴は、無惨をきわめる性暴力を、徹底して「被害者」の側から描いている一点にあるからだ。
そう、この物語においては「国を滅ぼされ、娼婦となった」王女「プリシラ」がいかに邪悪な男たちの欲望にさらされるかが、執拗に描写され抜くのである。
その反吐が出るようなグロテスクな展開には、たぶんだれもが一定の嫌悪を感じることだろう。
ここにはしばしば英雄的に美化され糊塗される「暴力」の本質がある。
暴力の本質とは決して美しいものでも公正なものでもない。むしろ、人間の内なる醜悪さを徹底したその結晶こそが暴力なのだということが、この物語を読んでいるとわかる。
ここにあるものは、ヒロイックな「男の子の物語」の「不都合な裏側」である。
延々とつづく戦時性暴力の描きは、もちろん趣味的なものではない。これは歴史の陰に隠匿されてきた「ただの現実」であり、いくらでも例がある話なのである。
いくさで猛り狂った男たちの暴力の矛先はつねに無辜の女たちへ向かう。それは昔から変わらないことだし、いまでもそうなのだ。
その事実はウクライナ戦争を見ていればわかることだろう。暴力とレイプは一体――あるいは、同じもののべつの側面に過ぎないのだ、ということ。
もちろん、それ自体は男性向けのポルノコミックではある種、見なれた光景ではある。しかし、ここには男性を気持ちよくさせるためのエロティックな快感はまったく、これっぽっちも介在しない。
ここで描かれるものは、どこまでいっても「暴力」としての性欲なのだ。あるいはふだん、その手の本を読みなれている男性読者の多くは、ここで気まずい思いをするかもしれない。
ここでは、男の欲望というものが、いかに薄汚く女性を圧迫して来たか、その封印された歴史がひも解かれている。
おそらく、このマンガがもっと人気を得てメジャーになったなら、このあまりにも仮借ない性暴力描写に反発する人も出て来ると思う。
ここではあまりに女性ばかりが被害者として描かれ、男性がデフォルメされた「悪」としてのみ語られている、と。
しかし、これは決して「男対女」、「強者対弱者」といったシンプルでわかりやすい構図に留まる作品ではない。
第二話ではプリシラに味方する男性も登場して、物語の展開は錯綜する。そして何より、この種の性暴力や性差別が戦史上、まかり通っていたことは歴然たるファクトなのだ。
『血を這う亡国の王女』はそのだれもが「見たくない」、「ないことにしておきたい」呪われた匣をひらいてしまう。
「死んだほうがよほどラクだ」というほどの地獄の底に何があるのか、いまのところまだわからないが、注目して見なければならない。
とにかく第一巻にして堂々たる大傑作の開幕という風格を感じさせる一作である。
性と暴力の暗黒面を垣間見せるその展開は、特に女性にとってはあまり直視したくないものであるかもしれない。だから、「だれにでもオススメ」というつもりはない。
だが、これはまさに読むに足る一作だ。この種のファンタジー作品で、こういった性暴力を徹底して「女性の視点から」描いたものはちょっと類例を思いつかない。
それだけでもこのマンガには巨大な価値がある。殺戮と凌辱に満ちた暗い血のオペラ。
「だれしも見たくないもの」が描かれているという一点で、この作品を否定する向きもあるかもしれない。しかし、ほんとうに素晴らしい作品を見たいと思う人には全面的にオススメする。
ここから始まるおそらくは呪われた物語に期待が膨らむ。いったい何を見せてもらえるのだろう。世界で最も凄愴な悪夢か、それとも仄かな希望なのか。
いま最も楽しみなマンガのひとつである。第二巻が待ち遠しい。
さて、ここから先は本編のネタバレやファンタジーにおける性差別、性暴力のことを『JKハルは異世界で娼婦になった』などの類似作品のことを絡めて語ることにしたいと思います。
ここからはまたべつの記事として認識していただいてかまいません。
月1000円のメンバーシップサークル〈グリフォンウィング〉に加入していただくと、過去とこれからの有料記事がひと通り読めます。良ければご加入ください。
あと、この記事などを読んでぼくに何か書かせても良いと思われた方はぜひお仕事の依頼をお待ちしております。よろしくお願いします! でわー。
さてさて、そういうわけで有料部分である。どのような手段でここを読まれているのかわからないけれど、とりあえずありがとうございます。
先へ進もう。『血を這う亡国の王女』という作品の魅力は、徹底して「女の子の物語」であるところにある。
かつて、ヒロイックファンタジーといえば、わずかな例外を除いて「男の世界」だった。
その例外とはC・L・ムーアの『ジレル・オブ・ジョイリー(処女戦士ジレル)』のような作品のことだが、まあ、ほとんどの作品は男性中心の物語を綴っていたのである。
しかし、いつの頃からか、女性を中心に据えたファンタジーもたくさん出て来るようになった。
そして、いまではもう、女戦士や女騎士、女魔法使いといったキャラクターが主人公となったヒロイック(ヒロイニック?)ファンタジーはめずらしくもない。
とはいえ、そこで描かれる「女戦士の物語」はある種、理想化されたり性的な要素を脱色されたものであることが多いこともたしかである。
たとえば、小野不由美の傑作小説『十二国記』シリーズでは、そもそも生殖の方法そのものが違う世界という設定になっている。
これはひとつには物語世界を男女平等の状況に設定し、物語から性的な要素を排除するための方策だったのではないだろうか(それでも主人公の陽子は娼館に売られそうになったりもするのだが)。
ファンタジーでは性暴力や性差別は可能であれば触れずに済ませておきたい題材として扱われているようにも思える。
その一方で、『異世界迷宮でハーレムを』のように直接的に「男の夢」としての「奴隷ハーレム」を描いた作品も出て来る。
そこにあるものは、非常に男性にとって都合の良いファンタジーだ。
念のためにいっておくと、ぼくはそのような男性向けご都合主義ファンタジー作品を批判するつもりはない。それはそれで読んでみればそれなりに面白い。
フェミニストは怒るかもしれないが、まあ、そういうものだとわかった上で読むのならそれなりに楽しめることはたしかだろう。
大切なのは、そういった「男の夢」というものが構造的にどのようなダークサイドを抱えているのかを直視する姿勢である。
楽しい、エッチな、奴隷ハーレム。だが、「奴隷」にされたほうがどのような内面を抱えているものか想像してみる姿勢は重要だろう。ここに「女の子の物語」の可能性が胚胎している。
とはいえ、「被害者の物語」は「加害者の物語」のようにからっとはしていない。陰惨であり、暗黒である。
『ベルセルク』だって陰惨無比なダークファンタジーではあったが、少なくとも主人公は強力な戦士ではあった。
性暴力の被害者である「娼婦の王女」を主人公に据えるという企画は冒険的である。
あるいはだれも読みたくない物語ですらあるのではないか、とすら思える。
ここにあるものは、ファンタジーの装いでどこまでも「現実の歴史」を直視しようとする姿勢に他ならない。
もちろん、作中の設定がリアリズムを貫いているということではない。そうではなく、性暴力というものがいかに人間の尊厳を無視した邪悪なものかストレートに見つめる視点がそこにある、ということなのだ。
高橋準『ファンタジーとジェンダー』ではファンタジー小説におけるジェンダーの落差を分析している。
そこでは、トールキンの『指輪物語』や栗本薫の『グイン・サーガ』のような名作小説であってもなお、やはり男性中心的な性格があることがはっきりと書かれている。
やはり、この種のファンタジー小説とは多かれ少なかれ「男の子の物語」を中心として発展してきた歴史があり、そこで「女の子の物語」が描かれることも増えてきてはいるにせよ、そのとき、「女性性」の苦しい一面は軽視される傾向があるようなのである。
それはおそらく、だれも見たくない描写なのかもしれない。しかし、それこそが「暴力」というもののきれいごとでは済まない本質だということもほんとうである。
暴力とは、男と男のかよわい女子供を守る真剣勝負などというナラティヴに容易に回収できるようなクリーンな概念ではない。それはもっと薄汚く、醜く、破綻したものなのだ。
男たちはいう。「女子供を守ってやっているのはおれたちなのだから、これくらいはしかたないだろう?」。
それが暴力を正当化するための最大のロジックであり、つまり、性差別と性暴力とはどこかで一体の概念なのである。
その意味で、多くの男性読者はこの物語を読むことで「男とは何なのか」と突きつけられることになるだろう。
この問いはあまりにも重い。もちろん、ある種のフェミニストが主張するように「男であること」が即座に悪や暴力を意味するはずはない。
男であるからといって暴力的性格だとはかぎらない。それはその通りである。しかし、このマンガを読むと、同時に「堕ちることは簡単だ」ということもよくわかる。
この作品のなかには管理売春とすら呼べないような性的凌辱を「必要悪」とうそぶく男が登場する。そう、性暴力を正当化するロジックなどいくらでも生み出すことが可能なのである。
じっさい、歴史上、そのようにして性暴力は正当化されてきた。しかたないことなのだ、国を守り、弱い女子供を守るためには必要なことなのだから、と。
しかし、それでもそこにはやはり正当化し切れない「後ろめたさ」が残る。そこで、性暴力は隠蔽され、「ないもの」として扱われる。
かくして、「男の子の物語」は光り輝き、「女の子の物語」は闇のなかに閉ざされる。
たとえば、戦場における性暴力を告発してノーベル文学賞を受賞したスヴェトラーナ・アレクシエーヴィチの『戦争は女の顔をしていない』は、国の恥をさらすものとして嫌悪されたという。
また、現代でも旧日本軍に性暴力があった事実をかたくなに認めようとしない人は大勢いる。性暴力とは、ヒロイックに演出された戦争の、暴力のだれにも愛されない暗部なのだ。
しかし、現代においては、そのような「男の子の物語」のくらやみを見つめ、新たな「女の子の物語」を紡ぎ出そうとする作品もある。
たとえば、平鳥コウ『JKハルは異世界で娼婦になった』がそれである。
この作品は異世界で売春婦になった少女ハルの物語を紡いだもので、一読して「男の子の物語」の裏側にある性産業で生きる女の子のストーリーを描こうとしていることはあきらかだ。
あきらかなのだが、一部の男性読者にはそもそもそのあきらかであるはずのことが「見えない」。紛れもなくそこにあるはずのストーリーが理解できないのである。
もっとも、理解できないだけなら良い。かれらはそれを自分たちの文脈に取り込んで「理解したつもりになる」。
そしてこの作品が「男の子の物語」を告発し、その構造に隠された卑劣さを暴き立てようとすることの意味をあざ笑う。
「女の子の物語」を語る言葉をもたないかれらにしてみれば、『JKハル』は不出来な「男の子の物語」に過ぎないわけである。
そのことが端的にあきらかになったのは、いわゆる「異世界シャワー」事件である。
これは作家の山本弘が『JKハル』の「シャワー」の描写に着目して批判し、むしろ嘲弄したことに始まる騒動で、いかのこの種の読者が作品を「オヤジ的」にしか読解できないものであるか、はしなくも露呈したできごとであった。
検索すれば「山本弘 異世界シャワー」とか「JKハル 異世界シャワー」で検索すればすぐに記事が出て来るからいちいち説明はしないが、山本にとって重要なのはその世界がいかにロジカルに合理的にできているからである。
それはかれにとってあまりにも当然の認識であり、かれはそもそも「そうではないファンタジー」があることなど想像すらできない。
だが、『JKハル』という小説の面白さは、そもそもそういった「一見すると合理的に設計されたファンタジー」が性という暗黒を抱え込んでいることを徹底して告発する一点にあるのだ。
そこにあるものは性差別と性暴力こそが「男の子の物語」というイデオロギーを裏で支えてきた闇である。
『JKハル』という作品の素晴らしさは、だからといってフェミニズム的というかポリコレ的に男性に敵意を燃やすのではなく、より平等な、より面白い物語を求めようとするところにある。
とはいえ、そこに告発があることはまちがいない。それなのに、山本は「自分自身が告発されている」ことをまったく自覚できない。
かれの見当はずれでお門違いの批判は、あまりにも「オヤジ的」なのである。
そう、山本による『JKハル』批判は、かれがいかにこの物語を読めていないか自己暴露するものでしかない。
「設定が合理的にできていないじゃないか!」というかれの批判は、それ自体がこの種の人間は「男の子の物語」の暗黒面をどんなに目の前に突きつけられても決してそれを理解することができないという現実を教えてくれるものなのだった。
『血を這う亡国の王女』は『JKハル』よりさらにダークに、ダーティーに、わかりやすく、「性の暗黒」についての物語であることを示しているが、それでも、この作品を理解できない人は少なくないだろう。
物語に登場して性暴力を振るう男性たちを単に「悪役」として切り捨てることはあまりにもたやすい。そこにあるものは「善い男性」と「悪い男性」を切り分けて考える切断のロジックである。
だが、現実にはもちろんそう簡単に善悪は分けられない。当然ながら男性全体が一般に性暴力の責任を負っているといいたいのではない。そうではなく、「闇はいつもそこにある」といっているだけなのだ。
ぼくは昔からたくさんのファンタジー小説を読んで来たが、そこで描かれる女性たちの立場の弱さにはいつも違和感があった。
端的なのは『グイン・サーガ』だが、そこでは女性たちは一貫して男たちの都合に振りまわされるかよわい存在として描かれ、強く、「男らしく」あろうとする女性は「可愛げがない」ものとして描写されることが常だった。
そこにはあきらかに性差別的な視点があったといまでも思う。
もちろん、現代のファンタジーはここまであからさまに女性を冷遇したりしないものがほとんどだろう。
ある意味ではかなりのところまで時代は変わったし、「いや、ほんとうに差別されているのは男性のほうなのだ」という「弱者男性論」が登場してきていることを考えても、単純に女性のための物語が少ないとはとてもいえない。
だが、それでも、「見たくないもの」としての「性差別と性暴力の物語」はほとんどノータッチのままで温存されてきたようにも思う。
性暴力は決してフェミニストの妄想などではない。人類の歴史上、延々と続いてきたものであり、それでいて決して「男の子の物語」では直視されない「なかったこと」にされがちな現実でもある。
「異世界シャワー」問題はほんとうは「異世界にシャワーがあることは設定的に合理的かどうか」などという些末な問題ではない。
そうではなく、そもそも「設定の合理性」とは何か、一見すると「合理的」に見えるものの裏に、「合理性」を重視しているとうそぶく男性作家たちが隠蔽して見ずに済ませようとしているものがあるのではないか、ということが本質なのだ。
山本ももちろん、心から性暴力や性差別に反対する立場を取るというに違いない。そしておそらく自分でもそう信じていたと思う。
だが、それにもかかわらず、目の前に性差別と性暴力の物語を見せられたとき、かれが着目するのは「その世界にシャワーがあるかどうか」といったトリビアルなポイントでしかないのだ。
そのことが物語っているのは、かれが『JKハル』のテーマが理解できないだけではなく、そもそもそのようなテーマがありえるという想像力を持ってないということである。
『JKハル』は「合理的な」物語世界がその実、裏側から見たらいかにでたらめなしろものであるかを告発したストーリーであるのだから。
「異世界シャワー」の例はサンプルとしてあまりにも極端だが、一事が万事だ。「女の子の物語」とは、決してオヤジ的には理解できないものであることが良くわかるだろう。
いずれにせよ、『地を這う亡国の王女』は新時代を切り拓く傑作である。これこそぼくが待ち望んだ作品であるかもしれない。注目している。続刊を早くよろしくお願いします。