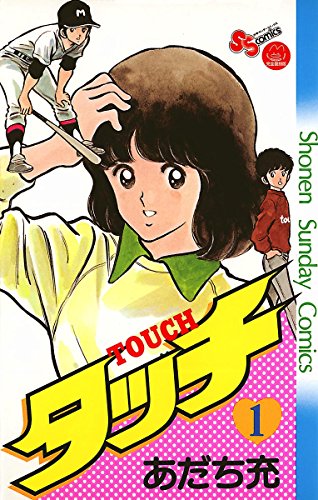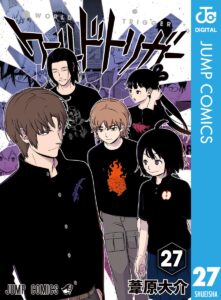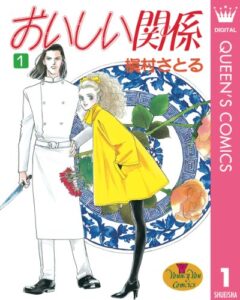浅倉南の話をしたい。
もちろん、あだち充の傑作漫画『タッチ』のヒロインである「南ちゃん」のことである。
彼女が少年漫画史上に残る重要なキャラクターであることはあきらかだが、それにしてはその評価は個人個人で分かれる。
もちろん、だれからも愛される万人向けのヒロインなど存在しようもないわけだが、浅倉南の人気とうらはらの悪評は強く印象に残る。
なぜ、南はこれほどまでに嫌われるのか。ぼくにはそれはそもそも彼女が何を考え、何を思い行動していたか広く理解されていないからだと思えてならない。
当然、作中にはっきりと南の心理が書かれていない以上、すべては解釈の問題でしかなく、自分の考え方が「正しい」などと主張することはできない。
しかし、いままで浅倉南について、さらには『タッチ』という作品について伝統的になされてきた「読み」を検証しながら、もう少し違う読解を提案していくことは可能だろう。
だから、浅倉南の話をしたい。じっさいのところ、浅倉南が何をどう考えて行動していたのか、そのほんとうのところを明らかにしたいのだ。
まず、本題に入る前に話をくりかえしておくと、ここでいう『タッチ』とはあくまであだち充によるマンガ版のことだということである。
自明のことに思われるだろうか。しかし、『タッチ』や浅倉南の評価について検索し、なぜこうも南への評価は混乱するのかと考えていて、ひとつ気づき、また推測できたことがある。
それは世紀の名作であることがあきらかな『タッチ』という作品について語るとき、多くの人が厳密にテキストを参照するというよりは自分のあいまいな「印象」で話してしまっているということである。
さらには、その「印象」は純粋に原作マンガのテキストに従ってものではなく、多くの場合、アニメーション版の要素が混ざってしまっていると思しい。
最近のアニメはかなりのところ原作のストーリーに忠実に作られるようになっているが、かつてはアニメ化といえばいくらかオリジナルエピソードを足すことがふつうだった。
『タッチ』の場合も、どうやら重大な個所でマンガとアニメの描写が異なっている場面が多数あるらしい。
そして、多くの人がアニメと原作が混じった何となくの「記憶」や「印象」で南を語ってしまっているようなのだ。
これはよくあることかもしれないが、ある作品について厳密に分析しようとするとき、致命的なことである。
よって、ここではアニメの内容は無視し、あくまで原作の内容に従って記述する。
マンガを語るとき、重要なのはあくまでマンガのテキストだ。べつだん、バルトやら何やらをひきあいに出すまでもなく、あたりまえのことだろう。そのあたりまえを忠実に実践していくことにしたい。
さて、浅倉南という興味深いキャラクターを語るまえに、まずは先行する批評を紹介したい。たとえば、CDB氏の「『タッチ』の南ちゃんは本当は何者だったのか」という記事である。
そこでは南のイメージが「人によってバラバラ」であることを踏まえた上で、このように書かれている。
早い話が、浅倉南という子はそれまでの少年漫画に出て来た応援ヒロイン、主人公を応援したり、勝負に勝った方の彼女になったりというそういうステレオタイプを逆手に取った新しい天才ヒロイン像だったわけである。「いわゆるああいうタイプのキャラだと見せて実はちがうんだよ~ん」というキャラだったはずの南ちゃんなのだが、『タッチ』1億部という異常なヒットの結果(あだち充全作品ではなく『タッチ』だけで売り上げ1億部なのだそうだ)『タッチ』以前の古いスポ根漫画が時の流れで忘れ去られ、「女子マネージャーといえば南ちゃん、いわゆるああいう南みたいな女」という誤解が生まれてしまったのは皮肉である。
もうひとつ南のイメージが混乱するのは、『タッチ』という作品が和也の死の前と後でまったく変わって行く、というかあだち充という作家が和也の死を描いたことで完全にひとつ上の次元の作家に化けていく作品なので、南ちゃん像というのが1巻と最終巻でかなり変化しているのである。最初の方の南ちゃんがわりと普通の女の子であるのに比べ、後半の浅倉南はほとんど涙を流さないハードボイルドな、そして天才性を強めたヒロイン像になっていく。これは南というキャラだけではなく、あだち充という漫画家が和也の死とそれ以降を描くことによって、「ラブコメハードボイルド」とでもいうべき、それ以降のあだち充作品に共通するあのクールでポップな文体を獲得していく。」
そう、浅倉南というキャラクターは物語を通して変化し、成長している。初期ではきわめて優秀ではあるものの、それでも「普通の女の子」の範疇に入っていたキャラクターが、後半に行くに従って傑出した天才の素顔をあらわにし始めるのである。
そこら辺のことを上記記事ではこのように綴っている。
自分で書いておいてなんだがこれもちょっと語弊があって、浅倉南という人は天才なのだが、前のめりにバリバリのキャリア志向なのかというとちょっと違うと思う(僕が書いたのだが)。かといって家庭志向なのでもない。なんというか南という人を勉強にたとえると、苦もなく東大には入れるのだがそんなことには興味がなく、世界の誰にも解けない数学の命題のことをぼんやりと考え続けているような、そういうタイプの天才なのだと思う。この「解けない命題」とは言うまでもなく、和也の死のことである。
そうなのだ。浅倉南を理解し、ひいては『タッチ』を読解するためにまずはこの補助線を理解してほしい。
①浅倉南は天才である。
いかにも「和也や達也の夢に寄生している」ようなイメージがつきまとう南だが、その実、彼女自身がすさまじいまでの才能を備えていることは明記しておく必要がある(じっさいに作中には達也が南のことを和也と比べて「おまえ以上の天才かもしれないぞ」と語るシーンがある)。
もちろん、これは原作を熟読した人間にとってはあたりまえの事実に過ぎないが、氾濫する「何となくのあいまいなイメージ」や「聞きかじりの情報」を執念深く修正していくためにはこういった事実の確認から入る必要がある、と考える。
さて、それではその天才の南がなぜ和也に対して「南を甲子園につれてって」などといい出すのだろうか。
この、いかにも他人に努力を強いて何もしないかのようにも感じられるセリフは、南に関する誤解を深めている。
そこには具体的にどのような意味があったのか。ここでちょっとした衝撃の事実をひとつ。じつは「南を甲子園につれてって」というセリフは、少なくとも原作のなかには登場しない。
たったいま全巻を読み返して確認したばかりだ。ただ、「南を」を省いた「甲子園つれてって」があるだけである。
そしてこのセリフは、達也のモチベーションを高めるために口にされる。
単行本だと第13巻から第14巻にかけてのあたりだ。どこまでもやさしく、お人好しで他人のことを気にしてばかりであった和也がなぜピッチャーとしてあれほどの力を発揮できたのか、と考える達也は、南の言葉があったからだと気づくのである。
そして達也はその「甲子園つれてって」という言葉を自分にもいってくれるよう求め、南はそれに応える。
つまり、この言葉は南自身の願望「ではなく」、むしろ達也を強く動機づけるために発せられているのだ。
そしてそれは和也に対しても同じことだっただろう。おそらく、ほんとうに幼い頃はただ何げなく「甲子園に行きたいなあ、連れてってね、カッちゃん」くらいの気持ちでいっていたのかもしれない。
だが、それはしだいに抜き差しならない真剣な感情へ変わっていった。そのプロセスにおいて、この言葉は「和也を支えるための言葉」へ変化していったのだと思われる。
つまり、一貫して南は自分が甲子園に行きたいというよりは、和也や達也を励ますためにこう語っているのだと考えるほうが自然だ。
もっとも、原作3巻には「そりゃ南の夢だから、なんとかかなえてあげたいけどサ。」と語る和也に対し、南がそのことを肯定する場面がある。
「そ、夢なの。小さいときからの―― 初めてTVでみた甲子園―― そして背番号1! カッコよかったなァ… それがサ、もし自分の高校で……… そしてその背番号1が南のーー」
「南の?」
「幼なじみだったら最高じゃない それをTVじゃなくて、甲子園のスタンドでみるの…… それが南の夢。」
しかし、この場面はよく読むと意味深なのだ。
「それが南の夢。」と語っているコマでは、南の顔は後ろ向きになっていて表情が見えなくなっている。このことを口にしたとき、彼女が考えていたのかはよくわからない。
また、あだち充の表情の描写はじつに絶妙で、物語は何ともミステリアスな印象になっている。
とはいえ、おそらく、南は自分の言葉が和也を支えていることを知っていた。初めはほんとうに甲子園へつれてってほしかったのかもしれないが、それはいつのまにか和也のモチベーションを高め、かれに実力を発揮させるための魔法の呪文へと変わっていたのだろう。
つまり、二本目の補助線はこういうことである。
②浅倉南が「甲子園つれてって」と言うのは自分の夢のため「ではなく」和也と達也の動機づけのためである。
さらに、ここで良く理解しておいてもらいたいことは、南は一貫して和也に対しものすごく気を遣っているということである。
彼女の恋愛対象は最初から一貫して和也ではなく達也だ。これは本編にはっきりと記載されている。第21巻において「南はタッちゃんが好きなのか?」「ずっとまえから?」と聞かれた彼女ははっきり「うん」と答えている。
南は双子のあいだを揺れ動いたりしていない。初めからずっと一貫して恋愛的な意味では達也のことを好きだったはずだ。
しかし、こう考えるとひとつの当然の疑問に突き当たるだろう。それなら、なぜ和也にいい寄られたとき、はっきり拒絶しなかったのかということだ。
この点こそが「浅倉南は二股をかける悪女」といった、ぼくから見るとあきらかに不当な評価につながっているポイントであろうと考える。
じつは作中でもそのような評価が存在することを示唆する場面も存在する。第20巻で噂好きらしい女子生徒が「ピーチクパーチク」と語る場面だ。
「なにいってんのよ! 浅倉さんは和也くんの恋人だったのよォ。中学のときから有名だったんだから、あの二人は! それが和也くんが亡くなったとたん、達也くんに乗りかえちゃってサ。かわいい顔してけっこう調子いいわよねェ。ま、なんたって双子だもの。うってつけのスペアだわさ。」
卑しい受け取りかたとしかいいようがないが、少なくとも原作ではこのような受け取られ方も意識されていることがわかる。
それなのに、あだち充はなぜ「一見すると三角関係に見える」描写を選択したのか? そして、なぜ南は和也に対してもっとはっきり「達也が好きだ」といわなかったのか?
これは、和也の内面を想像してみないと理解できない。というか、和也の複雑コンプレックスを理解しないと、『タッチ』という物語はそもそもまったく理解できなくなるのである。
この点について、成田美名子の名作少女マンガ『CIPHER』と比較しながら分析しているのが以下の記事だ。
これはきわめて秀逸な内容だと思う。そこではこう書かれている。
まず、上杉家の話から。
出来のいい弟としょっちゅう比べられて「出がらし」よばわりされていた達也ですが、より強烈なコンプレックスを抱いていたのって、実は和也のほうだと思うんです。
「一番は達也」「愛されるのは達也」「自分は努力しているし認められているけど、達也が本気を出したら決してかなわない」というふうに彼は思ってしまっているし、おまけにそれはかなり正しい(そこが辛い)。
あだち充作品の主人公って大体そうなんですけど、達也って飄々としてほんとうにかっこいいです。和也の抱える苦しみってのはひりついてて、読んでる側まで息苦しくなっちゃうようなところがあるんですが、達也は逆。さらっとして、きもちのいい男です。さすが主人公。そりゃ南もたっちゃんが好きだよ、と思います。和也は優等生でモテモテだけど、モテることと愛されることは違っていて、やっぱり「愛される」のは達也なんですよね。」
そう、どんなに和也が人気があってまわりからリスペクトされていても、「一番は達也」であり、「愛されるのは達也」なのだ。
これが『タッチ』を読むとき、最低限押さえておかなければならない第三の補助線である。
③和也は達也に対し複雑に折れ曲がったコンプレックスを抱いている。
なぜ、そのようなことがありえるのか? あきらかに優れているのは和也のほうであり、達也は劣った能力しか持っていない「出がらし」でしかないはずではないか。
だが、ここが『タッチ』という作品のおそろしい、ほんとうにおそろしいところなのだ。
最近、仲間内で話題になっている面白いマンガに『ダイヤモンドの功罪』という作品がある。ここでは、主人公の天才投手があまりにもかけ離れた実力によってまわりの少年たちを追い詰め、その夢を打ち砕いていくプロセスが綴られている。
じつはぼくがこの記事を書こうと思ったのは、この『ダイヤモンドの功罪』を読んで、超絶的な実力を持ちながらそれをセーブせざるを得ない孤独な主人公の姿に上杉達也を思い出したからだ。
そう、和也が亡くなるまで、作中であきらかに達也は本来の実力を抑えている。和也を抑圧しないように、和也からすべてを奪ってしまわないようにとかれは気を遣っているのである。
達也は南と同じくはっきりと天才だ。マンガならではの誇張表現ではあるだろうが、和也が亡くなったあと、達也はこの天才的であるはずの弟が幼い頃から積み上げてきた実力と実績にわずか二年で追いつき、そして追い越してしまう。
また、幼い頃から何をしても最初にできるようになるのは和也ではなく達也のほうだったという描写もある。達也が最初から本気を出して努力していたらおそらく和也は敵わないのだ。
そして、そう、愛の問題がある。南は一貫して達也を愛している。かれがまったく能力を発揮できないように見える(もちろん、ほんとうは意図して抑えている)子供の頃から、達也しか見ていない。
しょせん愛とはステータスだとかスペックだとかの問題ではないのだ。
「一切の努力も才能も関係なく、愛されるものは愛され、愛されないものは愛されない」。これほどの理不尽がこの世にあるだろうか。
しかし、それは現実にいくらでもありえることであり、「双子のテーマ」はこの「愛の問題系」を赤裸々に暴き立てる。
つまり、和也がどんなにどんなにどんなに能力を積み上げても! 甲子園へ行ったとしても。おそらくプロ野球のスター選手になってすら。南が選ぶのは達也なのである。
それがわかっているから和也は達也に劣等感を抱く。そして、また、自分は選ばれない、愛されない、「二番手」でしかない、そんな思いがどれほど和也を傷つけるか、南はもちろんわかっている。
だからこそ、彼女はどうしても和也を拒絶することができない。自分のひとことが和也のギリギリのところでバランスが保たれた自我を崩壊させてしまう危険があるとわかっているからだ。
第四巻には南と和也の印象的な会話がある。
「何年かまえ――」
「え?」
「あ、そうそう。小学校六年のときだ。アニキが海でおぼれたことがあったろ………」
「ええ。」
「そうだ。あのときだ。」
「なにが?」
「病院に運ばれたアニキを、二人して外でずっとまってたよね。 セミがやかましくてさ………」
「七月のおわりごろだったわ。」
「まってる間、ひともしゃべらなかったよ、南は…… 一生懸命アニキを心配していた…… 助かったとしってメチャクチャ泣きだすまで……… ひとこともしゃべらなかった……… あのとき…とてもアニキがうらやましく思えたのを覚えてるよ………」
「カッちゃんがそうなったって同じよ。」
「うん。たぶん…… そうなんだと思うけど……」
「あたりまえでしょ。」
「比べるようなことじゃないのはわかってるんだ……… でもね…… やっぱり……うらやましかった……」
よりあいてをうらやんでいるのは達也ではなく和也のほうなのである。
これはそれこそ『CIPHER』を読めばわかることだが、物語における双子とは単なる共通する遺伝子をもつあいてというだけに留まらず、むしろ「自分がそうであったかもしれないもうひとつの可能性」そのものである。
つまり、和也は達也を見ることで「自分だって愛されたかもしれない」という可能性を知ることになる。しかし、現実に自分は達也ではなく、南に選ばれることはない。
それがわかっているからこそ、かれはいっそう南に執着するのだ。「ぼくを選んで」、「ぼくを愛して」、「ぼくの才能でもなく成果でもなく、ぼく自身を見て」と。
もちろん、かれは人間として浅倉南を好きだったに違いない。ただ、かれが南に向ける感情はそれだけではなく、このようなきわめて錯綜した内面的感情が絡んでいる。
上記記事にも書かれている通り、和也はモテるが、それはただ幻想を見てちやほやされているだけのことである。愛されているわけではない。
それがこの上なくはっきりとわかるのはたとえば第二巻のエピソードで、和也はたまたまデートすることになった女の子から「わあ、和也さんでも転んだりするんですね?」 と驚かれたりする。
彼女が恋しているのは「完璧な少年」の虚像でしかなく、じっさいの和也ではまったくないということである。
だからこそ、だれかに「ほんとうの自分」、「完璧ではないそのままの自分」を認めてほしい、そのままで愛してほしい、和也はそう願っていたのではないだろうか。
そして、そのことを南ははっきりとわかっている。感じている。だから、かれに「甲子園つれてって」と望むのだ。わたしはあなたの努力を認めていますよ、その価値をわかっていますよ、というメッセージ。
しかし、それでも、なお、彼女は和也が最も欲しているもの――無償にして無条件の愛、それだけはあたえてあげることができない。
なぜならば。そう、彼女が愛しているのはあくまで和也ではなく達也だからである。
この三角関係の描写の深さは、ほんとうにおそろしいものがある。南はどんなに和也に対し、「あなたには価値がある。あなたは素晴らしい。あなたは愛されるだけの意味をもつ存在だ」と伝えたかったことだろう。
そのことを思うとぼくは涙が出そうになる。努力家の和也。傍から見て完璧に見える和也。そして内面のなかで、おそらくは悶え苦しんでいたであろう和也。
その和也を救えるのは、唯一、双子の閉ざされた小宇宙に干渉できる南だけなのである。それなのに、南は恋愛的な意味で和也を愛することはできなかった。
そんな南がどんなに和也のバリューを語ったところで、かれにとどかないのは当然ではないか。だからこそ、南は何もいうことができず、ただ沈黙するばかりなのだ。
そして、また、達也も和也の苦悩を、その原因が自分にあることを感じていたことだろう。第四巻には兄弟のこのような会話がある。
「きめた? 野球部入部。今日、返事するんだろ? やりなよ。おれに気を遣うことないよ。」
「なんでおれがおまえに気をつかうんだよ。比較されてみじめになるのはおれのほうじゃねえか。」
「そういう意味じゃないんだけど………」
「んじゃどういう意味だい?」
「………」
和也ははっきりと達也が自分に気を遣っていることをわかっているのだ。
それぞれ天才的な才能をもつ三人が三人とも、あいてに気を遣って遠慮しあい、本心を隠したり、力を抑えたりしている。
それでも、和也が生きていたらすべてが自然と解決に向かった可能性もあっただろう。しかし、和也は事故死し、達也も南もその死に捕らわれてしまう。
通常、少年マンガは「より上へ」とか「より強く」といった「上昇」のモチベーションに貫かれている。めざすは全国制覇であったり、海賊王であったりするわけである。
だが、『タッチ』という作品を印象的にしているのは「喪失」と「死への下降」の展開だ。達也も南も、いつもあかるく振る舞いながら、それでも和也の死から抜け出すことができない。
和也が亡くなったことで、三角関係は解決するどころかいっそう強くからまってしまった。このタナトスの描写こそが、『タッチ』以降のあだち充作品を連綿と貫いていく「死のテーマ」そのものだ。
素晴らしい。あまりにも素晴らしい。そして、なんという深い人間描写だろう。
ここまで来ればあきらかなことに、浅倉南は「完璧なヒロイン」でも「兄弟のあいだで揺れ動く悪女」でもない。だれよりも救ってやりたい幼なじみの少年をどうしても救えない宿命を抱えたひとりの切ない女の子なのである。
『CIPHER』の後半において、ヒロインのアニスはあまり存在を感じさせない(男性キャラクターのドラマが深くなるとヒロインの存在感が薄れるのは、『彼氏彼女の事情』などとも共通する少女マンガあるあるである)。
それに対し、南は最後まで物語の中心人物でありつづける。だが、はたしてその内面が十分に理解されているといえるだろうか。
そう――浅倉南をだれも知らない。
ぼくはそう思うのである。
【宣伝告知】
この記事などを読んでぼくに何か書かせても良いと思われた方はぜひお仕事の依頼をお待ちしております。よろしくお願いします! Twitterまでダイレクトメッセージでご連絡ください。
それから、この記事とは何の関係もありませんが、いま、宮崎駿監督の新作映画について解説した記事をまとめた電子書籍が発売中です。Kindle Unlimitedだと無料で読めるのでもし良ければご一読いただければ。
なお、毎月一回配信のYouTube〈アズキアライアカデミアラジオ〉でも、『きみたちはどう生きるか』を取り上げています。お聴きいただけると嬉しいです。
で、この下は独立した内容の有料記事になっています。あだち充のマンガにおける「死」の描写と、『タッチ』屈指の名ゼリフ、「きれいな顔してるだろ。」について語っています。こちらもどうぞ。
月1000円のメンバーシップサークル〈グリフォンウィング〉に加入していただくと、ここを含む過去とこれからの有料記事がすべて読めます。最初の三日はお試し無料です。良ければご加入ください。
でわ。
そういうわけで有料個所である。
ここから先は最新作『MIX』などについても触れながら、あだち充という作家の個性について振り返っていきたい。
上の記事の有料部分でCDBさんが書いている通り、あだち充は批評的に軽んじられている印象がつよい。
じつに数億冊の単行本を売っている日本有数の人気漫画家であるにもかかわらず、その作家性が批評的に分析される機会はきわめて少なかったと思う。
みな、「兄弟の対立」とか「死と喪失」といったテーマは実感していながら、それが何を意味し、どのように作用しているのか、明確に言語化する人は少なかったのではないか。
上の無料部分で書いたことは『タッチ』を一読すればわかる人にはすぐわかることを野暮に言語化しただけの内容に過ぎない。
しかし、最大の代表作に対してすら色々な誤解(あえて「誤解」といい切ってしまおう)がまかり通っているところにも、あだち充を正確に分析した批評的文章の少なさを思い知らされる気がする。
もっとも、これはあだちひとりのことではなく、小学館系というか『少年サンデー』系列の作家は一様にそうであるかもしれない。
マンガの沃野は広大であり、一部の「批評的に語りやすい」作家に注目が集まる一方で、手つかずの作家や作品もまだいくらでもある。
その意味で、この記事があだち充と『タッチ』の再評価にわずかでも寄与することがあったら幸甚である。
さて、上に書いたように、あだち充の作家としての個性は「死と喪失」にある。
べつだん、バトルマンガでもないにもかかわらず、かれの作品ではしばしば主要登場人物が死亡して物語から退場する。
『クロスゲーム』でもそうだったし『MIX』もやはりそうだった。
ある日、あるとき、いままであたりまえにとなりにいた人がいなくなる。それもあっさりと、何の「伏線」もなくそうなる。
あだちの作品では繰り返し繰り返しそういう展開が描かれる。
その最大の例が『タッチ』であり、上杉和也であるわけだが、いったいこの「死と喪失」の描写は何を意味しているのだろうか。
おそらくあだちには何らかの内的必然性があってこのおような展開を採用しつづけているのだろうが、その秘密は具体的にはわからないし、そもそも「作家が何を考えているか」など、知ってもしかたないことだ。
むしろ重要なのは、この「タナトスのテーマ」が物語にどのように影を落としているかだろう。
『タッチ』の場合はわかりやすい。上杉和也はいわば主人公である達也のシャドウだ。そして、かれは死ぬことでいわば抽象的次元の存在と化して達也や南の人生を呪縛する。
一方、『クロスゲーム』で亡くなるのは主人公の幼なじみの少女である。彼女は第一巻のラストで唐突に物語からいなくなる。そして、やはりその死が物語に大きな影響を及ぼす。
『タッチ』にしろ『クロスゲーム』にしろ、そしてのちの『MIX』にしろ、興味深いのはその死のテーマがあたりまえの日常のなかに組み込まれていることだ。
『タッチ』では「もうひとりの主人公」とも呼べそうな和也がいなくなったあとも、一見するとあかるいラブコメディの雰囲気は変わらない。
ひとりが欠けただけで元のままの物語が続いていくように見える。しかし、その実、かけがえのないものを喪ったことはあまりにも巨大な影響を登場人物たちに投げかける。
そして、その死をどう受け止め、受け入れるかが物語の大きなテーマとなるのである。
上記記事でCDBさんはあだち充を村上春樹に喩えている。これはわかる。村上春樹もまた、「喪失感の作家」だからだ。
そこには、人が喪ってはならないものを喪ってしまったとき、どのように変わらざるを得ないのかというダークなテーマが流れているように思う。
そして、あだち充は決してその「かけがえのないものの喪失」を決して大袈裟には描かない。むしろ、静かに、抑制して描写する。そのさりげなさは怖いほどだ。
それはぼくたちの平穏で安全に見える日常が、その実、つねに「死」と隣り合わせであることを思い出させる。
『タッチ』で和也の死が描かれるまでの一連の展開は、あだち充の美学の極致だ。
「最大のキャラクターが物語からいなくなる」というショッキングなイベントが、あくまで何げなく、夏の日のひとコマの光景として綴られている。
そして、そのなかでも最も印象的なのは、「綺麗な顔してるだろ。死んでるんだぜ、それで。」という達也の有名なセリフである。
このセリフは何か異様なほどのリアリティで読者の心を打つ。人が死んだときというのはこういうものなのではないか、と実感させるものがある。
しかし、なぜ、この短いセリフは極端に印象的な名ゼリフとなっているのだろう。
たとえば、「「綺麗な顔してるだろ。」あのタッチの名シーンは、なぜマンガ史に名を刻んだのか」と題する記事ではこう解説されている。
それでこの前、友だちと電話してるときに「なんであのシーンって、いまだに語り継がれてるんだろうね〜」って話になりまして。その電話ではいまいち明確な答えが出なかった。
(中略)
と、このシーンでは球場と病院を行ったり来たりしながら話が展開するんですね。全体的にセリフが少なく、過度な説明もない。いい意味で淡々と物語が進む。
説明なく、急に達也がテレビで試合を観ているシーンが出てくるので「あれ? タッちゃん家に帰ったんかな?」と思った人も多かったそうだ。
ただ、その後に「中村総合病院」と、やたらデカく看板が描かれて、病院のテレビであることが発覚。「おいコレ、もしや和也が……」みたいな空気が漂い始めるわけです。
で、和也が亡くなっていることが発覚するわけですが、「メインキャラの死を描くこと」自体は、当時他のマンガでも見られたシーンだ。じゃあなぜ、これが世間的にインパクトがあったのか。その最大の理由が「あの、ほんわかラブコメのあだち充がやったから」である。
つまり、タッチの前のあだち充のイメージは「ナイン」「みゆき」という隔週完全オリジナル作品によって「ゆったりコメディの恋愛マンガ」というものになったわけだ。熱血とかシリアスとかは無縁だったのである。
そんなあだち充のマンガで、主要キャラの和也が亡くなってしまうわけだ。こりゃ大事件ですよ。一瞬「え……?」って固まったあとに「……いやいやいやいや。どうすんのこの後!」っていう。もはや「おい、あだち充病んでんのか」事案ですよね。この世間の大騒ぎについては、後ほどご紹介しましょう。
とにかく、この「あだちマンガゆえのイメージの裏切り」こそが、このシーンをマンガ史に残る名シーンにした背景にあったのである。
また、この記事にはこのような指摘もある。
あだち充のマンガってめちゃめちゃセリフが少ないのよね〜。キャラの動きとか表情で、人物の考えていることを読者に「読ませる」っていう感じで。だから個人的には、ちょっとわかりにくくて……。俺子どものときアホだったからさ。だから、ちょっと知力が必要だった気がするのよ。
セリフが少ないのは派手な展開が少ない表れじゃない? するとテンポ良くなるじゃん? だから自ずと派手な展開は少ない。日常的なユーモアがベースだよね。だから和也が亡くなるなんて、もう考えてもみなかったよねマジで。
あのシーンだと、病院で和也の死を知った両親の顔をすごく覚えてて。セリフなくて、ぼーっとしてるだけ。「……なんで和也が!」とかないんだよね。あぁ、これがあだち充が描く「死」なんだなぁって。いま読んだら思うよね。
その頃、ふわふわしたラブコメ作家と見られていたあだち充の作品で突然に「リアルな死」が描き込まれたからショッキングだった、ということである。
これは、ひとつの納得のいくアンサーだし、事実としてこういう側面は大きいだろう。当時、この場面をリアルタイムで読んだ人たちがどれほどのショックを受けたのか、想像することもできない。
とはいえ、である。いまとなっては和也の死はマンガ読みにとってはほぼ常識である。ぼくたちは『タッチ』を読み返してその展開に衝撃を受けることはない。
それなのに、やはり和也の死の場面と「綺麗な顔してるだろ。」というセリフは名場面であり名ゼリフなのだ。なぜだろう?
ぼくはここに「世界の真実」が描かれているからだと思う。その真実とは、人はいつでもあっさり死ぬことがありえるし、一度死んでしまったら決して生き返ることはない、ということだ。
最近は少なくなったが、むかしの少年漫画ではいったん死んだように見えた人気キャラクターが読者の反響しだいで「生き返る」ことはしょっちゅうだった。
最も端的な例は車田正美の『リングにかけろ』あたりだろうが、『シティハンター』などでも飛行機爆発に巻き込まれたはずのキャラクターがあたりまえのように「生き返る」展開が描かれていた。
『タッチ』における「死」の描写は、それらとはまったく異なっている。対照的といって良いほどだ。
そこにあるものは日常のひとコマとしての「突然死」であり、だからこそ強烈なリアリティがあるのである。
そしてまた、「きれいな顔してるだろ。」という達也のいつもの冗談のような言葉は、人が「死」と向き合ったとき、必ずしもわかりやすく愁嘆場を演じるものではないことを表わしている。
そう、あだち充の世界においては「日常」と「非日常」、「生」と「死」はどこまでも連続しているのである。
ぼくたちはふだん、その両者を切断して考えたがるが、ほんとうは「喪失」はいつでもすぐ近くにある。
そして、いったん喪ってしまったなら、そのあとはその「傷」を受け入れて生きていくしかないのである。自分自身の順番が回って来る、そのときまで。
これが、あだち充が示す「世界の真実のリアリティ」だ。
もっとも、ただ単に「突然死」を描くだけでは、優れた文学作品にはなりえるかもしれないが、少年漫画としてエンターテインメントにはなりえないだろう。
『タッチ』という作品があまりにも素晴らしいのは、人がその「永遠に消えない傷」を抱えてどのように立ち上がるか、そのプロセスまで見せてくれている点だ。
あだち充の世界では死者はよみがえらず(たまに幽霊は出て来るが)、「喪失」は取り換えしようもない。
それでも、人は生きていくし、また、生きていくしかない。そのことがかれの作品ではいつもていねいに描かれている。
喪ってはならないものを永遠に喪ったとき、人は変わる。変わらざるを得ない。だが、そもそも人が生きていくとは変わるということなのだ。
人はある意味では一瞬一瞬、死につづけている。その、あたりまえでいてなかなか実感しづらい事実を、『タッチ』や『クロスゲーム』は描き切る。
素晴らしい。
近年、『進撃の巨人』のような作品でも、ほとんど伏線らしき伏線がなく重要なキャラクターが死んでしまう「突然死」の展開は描かれるようになった。
ただ、あだち充の作品は一見するとそのような過酷で残酷な世界を舞台にしているわけではないだけに、いっそう死の描写は迫真的である。
そうなのだ、ほんとうは人が死ぬとき、「伏線」なんてものが存在するはずもないのだ。
死とは人生に空いた大きな落とし穴だ。だれだって、あした生きているかどうか、ほんとうのことはわからない。
その、背筋が冷やりとするような認識の鋭さ。
そう、あだち充は死をつねに直視する「喪失感の作家」のひとりである。その肌寒いような感触は、この世の真実に支えられている。ぼくは、そういうふうに考えるものである。